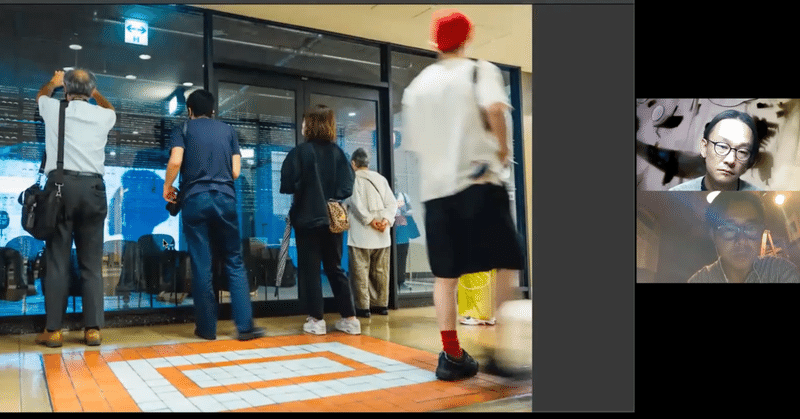
SDSノート_11東京影絵「アーティストトーク3」
こんにちは。ソーシャルダイブ・スタディーズ(以下 SDS)、コーディネーターの工藤大貴です。今回はアーティストトーク第3弾のレポートです。前回までのSDSについては下記をご覧ください▼
第11回レクチャーとなる7月28日(水)のアーティストトークでは、「東京影絵」を本芸術祭に出展されている影絵師の川村亘平斎さんに登壇いただきました。
この頃から新型コロナウイルスの感染者数も急増し、SDSとしてははじめての完全オンライン実施といたしました。

▲左:川村亘平斎さん
日本あるいは世界の各地で、フィールドワークとインタビューで伝説や歴史を調べて、「これからの伝承」ともいうべき影絵のパフォーマンスを続けるお話しを聞きました。また、出展している「東京影絵」は、19か国60名の外国ルーツの人々への取材を通じて、影絵人形などの無人展示や書籍出版を実施されています。今回も聴講されたメンバーお二人にその様子をレポートしてもらいます。それではぜひご覧ください▼
***
SDSメンバーの中島静代です。レポートを書くのは2回目なので、前回とは違った自己紹介をします。現在は私立高校のスクールカウンセラーをしていますが、これまで臨床心理士として、産婦人科、小児科、小学校〜高校での勤務経験があり、あらゆる年代の子どもと親の支援をしてきたのが、ちょっとした自慢?です。
もともとアート作品やアートプロジェクトの製作を妄想して楽しむのが好きで、SDSメンバーとなり、その妄想が実現するかもとワクワクしています。
川村亘平斎さんの影絵の魅力だけではなく、その地域の伝承話を掘り起こすという作業にも興味を持ちました。地元の人が気づかない価値に、よそ者だから気づくことや、よそ者にだからこそ語ってくれる言葉があるように思いました。
川村さんの、「ここで語られた話が、数十年後、この地域の伝承話となっていくかもしれない」という言葉に、アーティストの果たす役割の大きさを知ることができました。
「東京影絵」は、心理学的に非常に興味深い作品だと思いました。ユングの唱えた普遍的無意識の中に「ペルソナ」と「シャドウ」がありますが、その意味は「ペルソナ」が「社会に適応するために演じる役割」、「シャドウ」が「ペルソナの影で生きられなかった自分」です。「影絵」と「仮面」という作品の持つ性格から、まさにこの両者が揺さぶられ、自然に深い語りが引き出されたのではないでしょうか。
「東京影絵」は、彼らが日本で生きていくために抑圧せざるを得なかった「自分」に光を当て、生かすために必要な語りだったように思います。しかし作品が建物の制度上の問題から、ガラスを隔てたあちら側の世界で展示され、彼らのシャドウが白日の元に晒されることなく守られることになったのは、偶然が生み出した必然であるように感じました。


***
SDSメンバーの寺本さつきです。6月から都内の出版社で、広報課の契約社員として働いています。それ以前は、印刷会社の営業として15年ほど勤めていました。印刷の仕事は好きで続けていたのですが転職をすることになり、
今後の人生では、本に関わることと現代美術に関わることをやっていきたいと思いました。
けれども、本はともかく、現代美術はこれまでは見て楽しむばかりで、何の勉強も経験もしてこなかった、これでは関わりようがない!と途方に暮れていました。そのような時に運よくSDSのことを知り、参加できています。
今回のアーティストトークでは、「東京影絵クラブ」を主宰している川村亘平斎さんのお話を伺いました。
最初の川村さんのご紹介のところで気がついたのですが、私は2014年の山形ビエンナーレに行っており、川村さんがガムランを演奏していたライブにも参加していました。スマホには今も川村さんの写真があります!まさか7年経ってこのような形でお会いするとは、不思議な気持ちです。
それはともかく、今回お話しを伺って、「東京影絵クラブ」にとても興味を持ちました。展示はこれから伺うのですが、本も欲しいと思っています。
「東京に暮らす19ヶ国60名の、海外ルーツの人々のオーラルヒストリーを新しい物語に。」という内容が、今までありそうでなく、自分がやってみたかったこととピッタリ合っているような気がしました。見せていただいたPVの内容も音楽も映像も、素晴らしいと思いました。

私は以前から、海外ルーツの方には一方的に親近感と興味を持っているのですが、自分から積極的に話しかけたりはできていません。親近感や興味をもつ理由は、自分が幼い頃に海外に住んでいた時期があり、そこで感じ考えたこと、日本で感じ考えていることがいろいろとあるからだと思います。
様々な方とお話しして、東京の実際の姿を浮かび上がらせることができたら良いなと思います。トークをありがとうございました!
第11回レクチャーの記録はここまでとなります。それでは、またSDSノートにてお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
