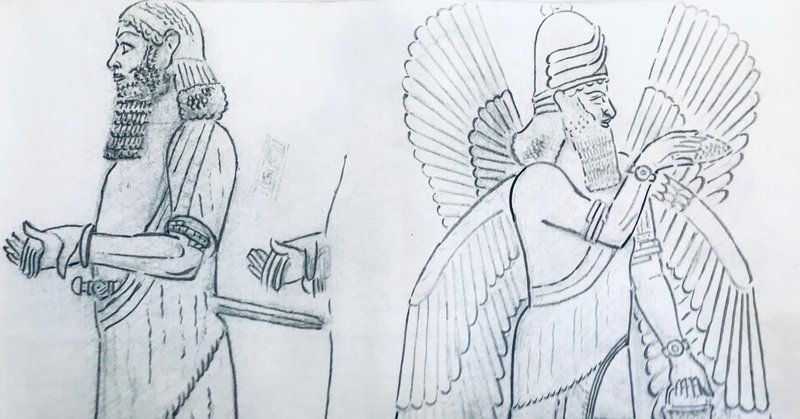
《美術人類史.Ⅰ》 美の起源(後編)
さて後編は「人の表現」について考えるところから始めます。
「表現」とは想起する意志、つまり思考を発露する事です。
例えば言葉選び一つとっても人の表現です。
ならば、他にも様々に日々膨大な表現を行っている事が分かります。
およそ瞬時に使う言葉一つも、他の動作も気付けば大変な事ですが、本来溢れんばかりの情報処理から導いているのです。
それを人は負担なく呼吸や鼓動の様な生理現象と同じ様な働きで、どうして出来るのかも気にならないほどスムーズに、さらりと行っています。
では、どうして無意識で可能なのでしょう?
それは本能的な記憶のシステムが上手く働いて、環境ある人の生活スタイルに沿って、意識は幾つかの分野に、どんどんまとめられて簡素になり、全ての負担を減らしてた記憶を蓄積し、系統化され、分野事の主張に組み込まれて行くからです。
生物遺伝や経験や学習蓄積の主張は謂わば性格となって人に現れ、いつしか人格に落ち着きます。
したがって、人の表現は人の性格から出ると思われがちですが、これが実は誤解です。
五感で何かを覚えて、脳で物事に置き換えて、感想を考え、身体で動作発露し、確かめるといった表現の成り立つシステムまで、中々関心を寄せる必要がない為なのです。
こうして、人の性格から人の表現を見ても、人格の評価にしか値しません。
人が何故に美を美に感じられるのかなど、人の面白い神秘は無意識のところに隠れています。
美術人類史では、地味ですがさらに摂理を解析したいと思います。どうぞお付き合い下さい。
さてあらためて、一番シンプルな表現は何でしょうか。
口から音を発し、首振り身振り手振り、四肢を使い、顔の表情を使います。
ただこれでは正に赤ん坊です。原始的な動作に限られ、本能的な繋がり以上の伝わり方はしません。
そこで役立つ工夫が要ります。相手により良く伝える為に幅広い表現を可能にするのもの、
すばり私達の持つ知識です。
知識の発達が伝達力の格差向上になり、洗練されると、個人、集団の円滑な生活環境の構築、繁栄と安定をもたらします。知らないままでは何も変わらず叶いません。
知識は表現の意識の中で、ある物事とある物事が掛け合い、結びつくと物理的にどんどん豊かになりますが、自然の創造ではありません。
誰しもが何かの折に「なるほど!」と閃き発見に思う瞬間には、些細でも新たなる知識が思考内に生まれています。よって知識は人工物です。
人類はこの未知を知る事、知識の構築に並々ならぬ執着と努力を繰り返して来ました。
どなたの人生でも様々な理屈が繋がる事は、無条件に喜ばしい摂理となっています。誰しもあの合点が行く時の、何かわだかまりが解けた用な心理作用は悦びではないでしょうか?
それでは何故、理屈が成る事で安心の作用をもたらすのでしょうか。これが美術の意欲の本質に関係します。
さらに美術人類史考察を進めます。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
