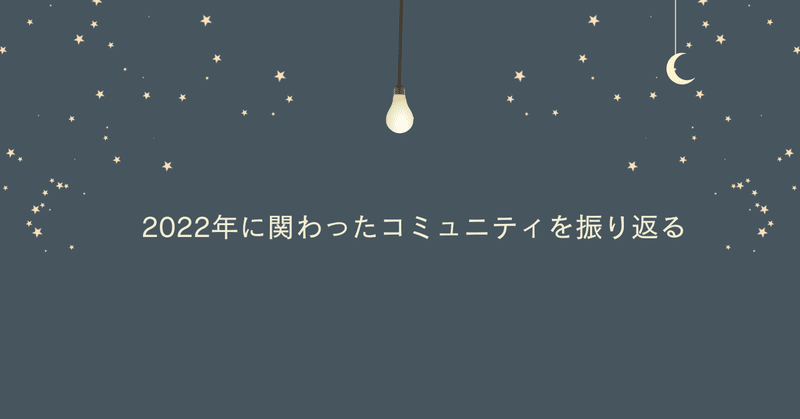
2022年に関わったコミュニティを振り返る
2022年によかったことを振り返ります。
おもにひととのつながりです。
かまくら読書会
かまくら読書会について
鎌倉で行われている読書会です。
流行病が出てからはオンラインが中心ですが、もともと鎌倉の公民館などを会場として行っており、徐々にリアルも再開されてきています。
初めて参加したのは、2019年の『中動態の世界』でした。
本当に久しぶりに読書会に参加できた。『中動態の世界』を興味深く読んでいることもあるけど、なんといっても参加している方たちの人間的な魅力を強く感じた。共感できる問題意識を持った人たちがいて、初めて会って数時間の間に様々なことを話せて。こういうのはすごく勇気が湧くんだ。
— t (@htokiwa5) July 20, 2019
最初から人がすごく良くて、今でも大好きなコミュニティです。
今年の読書会参加
仕事の都合などで頻繁に参加はできていないけれど、今年参加したのは2.2冊分くらいでした。
水木しげる『のんのんばあとオレ』
プラトン『国家』 *途中離脱。0.2冊分
小室直樹『憲法言論』
2021年は2冊だったのでちょっと増えたかな…。
自分からはあまり読まない本も読むきっかけができるのもありがたいです。
本の選定も自分に合っている気がしています。
番外編のハイキング
今年は念願の鎌倉ハイキングに行くことができました。
鎌倉の紅葉が良かったし、頼朝の像を探し当てられたし、シート敷いて食べたお昼は美味しかったし、数十年ぶりにフリスビーで遊んだり…仲間たちと読書以外の経験を共有できたことが素晴らしかったですね。

来年は、○○作り系のイベントにも参加したいです。
鎌倉山の集会所にも行ってみたい。
とまり木
話せるシェア本屋とまり木について
茅ヶ崎市矢畑にあるシェア本屋です。
シェア本屋というのは、本棚のひと区画を借りて自分が「ひと区画だけの本屋」になれるというものです。
店主のジミーさんとは昨年茅ヶ崎のコワーキングスペース・チガラボでたまたま出会ったのでした。
それも、もともとは箱根のブックカフェ・本喫茶わかばさんのクラファンから一箱古本市に参加したときに、同じ参加者さんにチガラボを紹介していただき…という、ひとのつながりで得られた縁でした。
このとまり木で、5月から本棚オーナーになりました。

参加したイベント
とまり木は多様な本棚オーナーさんたちがイベントを主催していたりします。
参加できたイベントは4つかな。
本棚オーナーミーティング(イベントか?)
お金のことを学ぶワークショップ
ワークショップのためのワークショップ
FBのカスタム性別を通してジェンダーのこととかを学ぶ
大掃除(イベントか?)
先日の大掃除の時にも新たな出会いがあり、こうしたつながりができたひとたちのイベントに参加したり、コラボしたりできたら楽しいと思います。
自分たちでイベントを主催
「本読み対話会」として、テーマとなる本を中心に対話する会を開催できました。
「読書会」としていないのは、なんとなく色々な理由があるのですが、まだ言語化が難しいのでそっとしておきます。
今年、3回実施できました。
小国士朗『笑える革命』(8月)
新井和宏・高橋博之『共感資本社会を生きる』(10月)
西村佳哲『自分をいかして生きる』(12月)
ジミーさんや本棚オーナー仲間の人柄が良くて、(物理的に)一番近いコミュニティとしてとても大切な場です。
DATASaberBridge
DATA Saber(Bridge)について
DATA Saberは「データに溺れかけている世界を その剣で守り導く救世主」「データを通して世界を理解し、それを人に正しく伝える努力を怠らず、人の心を動かし、行動を促す。これがDATA Saberである。」
Bridgeとつくのは、もともと師匠を自分で見つけて弟子入りするという教育プログラムのところ、師匠と弟子の大規模マッチング(師匠が20〜30名、弟子が200名規模)を行なって弟子入りしやすい環境をとったものです。
このための準備や運営、師匠たち(師匠sと呼ばれる)の労が全てボランティアというちょっと信じられないコミュニティです。
きっかけ
DATA Saberを目指す過程では、TableauというBIツールの習熟をねらいます。
もともと、今年の5月ごろに兄と会ってお互いの仕事の話をする中で勧められたのがTableauでした。Tableau自体は会社でも使われていたしViewerとして自部署の実績を見たりすることはありましたが、自分で作っていくというイメージはあまり持っていませんでした(権限がなかったというのもある)。
勧められたのを良いことに、社内で色々調べてみると、どうもうちの拠点ではCreatorライセンスが満足に使われていないらしい。そこで、権限を持っている偉い人(話しやすい)に「使わせてほしい」と直談判、晴れてCreatorライセンスを使えるようになりました。
社内のTableau先輩に尋ねても、残念ながら社内に勉強会のようなものはなさそうでした。
そうなると自宅でも学んでいかないと、ということで出会ったのがKTチャンネルとTableau極めるチャンネルでした。
学び始めて1ヶ月ほどした時に、DATA Saber Bridgeの構想を知り「なんと運命的なタイミングか」と歓喜したものです。
プログラムの秀逸さ
ゲーミフィケーションを意識したプログラムが秀逸です。
開会式の動画配信はオープニングからRPGぽくて、ゲーム好きはこれだけでテンションが上がります。
進め方も、力をつけてクエスト(試練)に挑む→クエストを通してレベルアップするというオーソドックスなものの中に「仲間たちとの協力」の要素が多分に含まれています。師匠やコミュニティの助けを借りながら、仲間たちと協力して試練をクリアしていくのは、昔どハマりしたMMOをリアルでやっているような錯覚すら覚えます。
もちろんひとりで挑戦してクリアして行っても良いのですが、せっかくなので協力すると楽しさが倍増します。
試練はTableauの技術的な課題だけではなく、コミュニティ活動も必須条件として課されています。
それは、DATA Saberの使命がデータドリブン文化を広めることだから。当然、広めるための動き方を体得する必要があるのです。
コミュニティ活動はパブリックな活動と所属する組織内の活動の二つがあり、どちらも規定をクリアする必要があります。どちらかひとつではダメ。
自分の場合は組織内活動がネックでした。
パブリック…クリアするだけなら出来る→これまでやってこなかったことに挑戦する好機でもある
組織内…条件が結構厳しくてクリアも危ういかも…→先人の足跡を見て踏破への道順を定めた
パブリック活動のメインはVIz(Tableauで作ったグラフ)やブログ記事をアップすることで賄えるようになっています。
実はこのことがTableauのナレッジの蓄積になっていて、Apprentice(弟子)先輩たちの記事が大いに参考になっているという、「そこまで考えてたのか…」という驚きの仕掛けが作られていました。
コミュニティの良さ
そもそも、技術試練をクリアするのも一筋縄ではいかないので、助けを求めたり協力しあったりすることは必須です。むしろそれが200名が一斉に挑戦するBridgeの醍醐味と言えるかもしれません。
そしてタイミングを図ったように楽しめるイベントが開催されました。
90日という期間の3分の1くらいのところでのMakeover企画。スタートの興奮状態からだんだんと難しさにやられてきた頃に、自分が作ったVizを神様のような方が手を加えてくれるという大変光栄なイベントです。
そして12月に行われたクリスマスイベントは、リアルで師匠や弟子仲間と交流できる素晴らしい会でした。
こうしたイベントを通して、師匠たちのスキルの高さを実感し、そんな師匠たちが気さくに相談に乗ってくれたり真剣に話を来てくれたりと、本当に素晴らしいコミュニティです。

Tableau public さだまさし ソロコンサート4500回の軌跡 #DATASaberBridge
来年のこと
2022年はプライベートでの広がりが劇的に広がった年でした。
この広がり、ひととのつながりを絶やさず、育てていくような2023年にしたいものです。
そのためにやるべきことは、DATA SaberやTableauのコミュニティに関わり続けるような準備でしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
