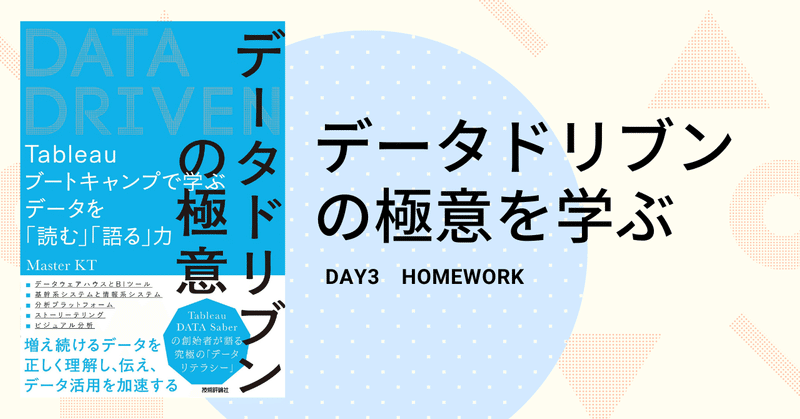
『データドリブンの極意』DAY3_HOMEWORK
①分析プラットフォームを組織に導入する意義を説明する
(1)コスト削減の観点
報告資料の作成時間
マネジメント層による情報のキャッチアップ時間
現場管理者による現場状況の把握時間
(2)データドリブン文化の観点
全マネジメント層、全現場管理者が同じデータを見て理解・判断できることの利点
合意されたデータを土台とした円滑なコミュニケーションとタスク管理の利点
施策に対する迅速な効果検証の利点
②自分の所属している組織の分析課題を整理する
・現在の自社の分析環境の状態
(分析プラットフォームは完成しているか、あるいは構築途中か)
→自社…現場レベルに浸透はしていない(プラットフォームとして完成しているか、構築途中かも不明)が、Serverは利用あり
→自拠点…完成しておらず、構築の計画中という段階
・新しい環境へシフトするにあたって、障害になる要素(人、システムなど)

→人の要素(自拠点)は上記の通り
→システム(自社)
IT部門…Server利用権限の認否を握っている。現状で各拠点での利用は想定されていない様子。
→システム(自拠点)
システム部門…Serverを利用できないとなれば、自拠点サーバ内にtwbx形式で置き更新していく形となる。移行期ではExcelとの並行利用が望ましいためサーバ容量の圧迫につながる点をどう評価されるか。
・いつを目標(具体的な年月を明記)に、どうやって変えていくかのプラン
まず、自拠点がどのような状態になるのが好ましいか移行ツリーを描いてみる。

・ツリーの読み方
基本的には下から上に向けて(矢印の方向に)「こうすると」→「こうなる」と読んでいく。
アクションにより状態に変化が起こり、その状態を前提としてまたアクションを起こし、変化が起きる。
現状(下)から始まり、理想の状態(上)までの移行ステップをアクションと状態の変化で表している。
いったんの目指すゴールは、ここでは現場管理者の「日々のタスク対応にTableauから得たインサイトが活きる」ことであり、マネジメント層の「日々のマネジメントにTableauから得たインサイトが活きる」こととした。
それぞれの前提となるのは「日常的にTableauを見る」状態を作ることとなる。
※ツリー上ではTableau「を」見ると表現しているが、正しくはTableau「で」見る
・アクション(どのように)
(1)Tableau化するレポートを選定する…Excelで作成されている既存のレポートを重要度*とTableau化のしやすさと効果の高さ**から選別し、重要度が高くTableauで作成しやすいレポート***から着手していく。
*重要度はマネジメント層と現場管理者層とに分けて評価する
**Tableauのインタラクティブ性が効果的に働くかを評価する
***Tableauではインタラクティブ性を付加価値として用意しておく
(2)スポットで分析課題を進める…スポットで取り組む・依頼を受ける分析にTableauを使う。部署内での習熟度を上げるとともに、Tableauが目に触れる機会を増やすことが目的。
(3)Tableau化を実行する…接続するデータを精査し、自動化を考慮した構成にして作成する。あわせて、Serverを利用できなくても定期更新が担保される仕組みを作る。また、将来的にライセンスが拡充した時のためにメンテナンスの容易さを考えておく。
(4)定期展開する…Tsbleauで作成したチャートをメールで定期展開する。チャートで概要を把握するのに適していると実感してもらうことが目的。またTableauが目に触れる機会を増やす効果も見込む。
(5)打合せ・報告の場でTableauを利用する…報告時*にインタラクティブな分析**ができることを示す。
*メール等ではなくTableauを画面共有しながらの直接報告が望ましいが、報告相手の時間を拘束することにもなるため、分析目的や結果のイシュー度から直接報告すべきものをある程度選定する
**インタラクティブな分析を演出するために、興味を持たれるであろう軸のデータを接続しておく必要がある。ある程度深掘りできるように事前準備が必要。また業務のドメイン知識も重要となるため現場管理者への事前打合せや同席を依頼する
(6)Excelレポートと並行利用する…全てをTableauに完全移行することでの抵抗感を軽減するため、移行期にはExcelのレポートと並行で出していく。Tableauの強みであるインタラクティブ性を報告・打合せや分析時に訴求し、移行への機運を高めていく。複製されるファイル問題については、マネジメント層に向けてサーバ容量の観点と、常に最新版を扱うことの利点を説いていく(Server利用への布石)。
(7)現場向けの分析課題を協業する…現場の課題、現場管理者の課題感、マネジメント層が現場管理者に求める課題意識
・状況
実行中*…(2)(3)(4)(7)
未着手…(1)(5)(6)
*実行中のものも全てうまくいっているわけではなく、不十分な点も課題もある
・いつを目標に
(1) 2023年2月中に既存レポートの選別を完了
(2) 継続
(3) 2023年3月中に自拠点KPIダッシュボードを作成
(4) 2023年3月中に上記自拠点KPIダッシュボードを定期展開
(5) 2023年1月中の報告時にTableauを利用
(6) 2023年3月以降順次(1で選別したレポートから)
(7) 継続
2023年度中に自拠点でのCreatorライセンスを1つ→3つに
2023年度中に自拠点でのExplorerライセンスを0→4つに
参考・利用したもの
『ゴールドラット博士の論理思考プロセス』
だいぶ前に進められて読んだ。ロジックツリーの作り方に詳しい。
miro。便利。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
