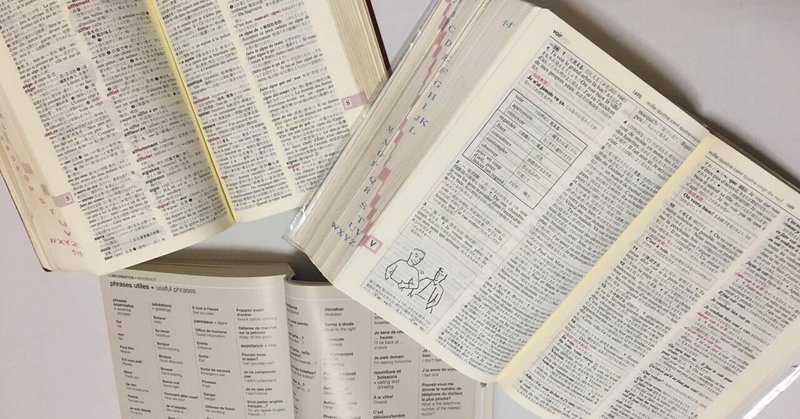
Photo by
teeth_tooth
「多様性を認めない」のは「多様性」ではない
大学の研究員?
「多様性」の定義を誤読して記事を書き巷に流布して回る人が研究室にいる大学って何を教えてるんだろうか。
ちなみにこの記事で著者は、開始数行にも渡って議論するつもりがない予防線を張っており、万が一にもこの記事を見つけられたら「うわー日本語読めない人がいる!」とか言い出しそうだから言っておくが、議論ふっかけてるんじゃなくて指摘だから。
一刻も早く、言葉の定義を間違えていたことを認め、自分の“連載”で間違いを訂正してほしい。
「多様性」は社会の不平等を改める行程で、共有されるようになった認識。
これは「What is diversity」の検索結果のスクリーンショット。

著者は「1.」の意味で社会問題の多様性を語っている。
「1.」は「種の多様性」とか物理的な意味。なので間違い。
社会問題を「なんでもあり」にしたらそりゃ「多様性を認めないのも多様性」になるだろうね。
問題はそれじゃない。
今まで権利を剥奪されてきて、社会の中でいないように扱われ、義務だけは背負わされるという搾取を受けてきた人々の声を聞き、社会のシステムを改めようという話をずっとしている。ずっと。
「多様性を認めないのも多様性」なら白人至上主義も多様性。
障害者を「意思疎通ができないから生きてる意味がない」というのも多様性。
言葉の定義は変わっていくものだし、国や地域によって違う意味で使われるということもある。
だから「日本ではそういう意味」ということにしたいのならどうぞ。
ただ多様性を「2.」の意味で使ってる人たちに「1.」の意味しかないように欺くのは、多様性を阻害する行為だから見過ごすわけにはいかない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
