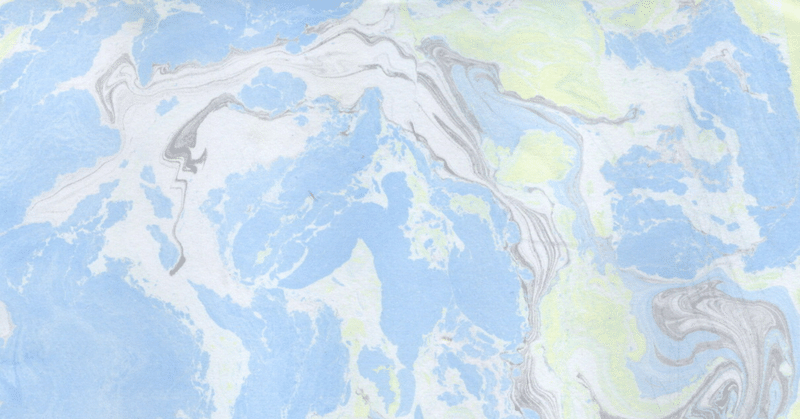
僕は道端の小石に話しかけている
ぼくには、ぼくだけに見えるおともだちがいる。
その子の名前はこいしちゃん。
どこから来たのかも、ふだんどこにいるのかもぼくは知らない。
だけど、ぼくがさびしい時にはいつもちゃんと来てくれるんだ。
*
とある一軒家の六畳間。そこにはおもちゃがたくさん並んでいる。その真ん中に座っている少年は、側にあったおもちゃを一つ取って遊び始めた。特に「これがいい!」といったものもないらしく、ある時は積木をやったり、またある時は黙々と知育玩具で音を鳴らしたり。その時によって遊ぶものは異なっていた。
そんな彼は、今日はブロックを組み合わせて形を作っていく遊びを選んだようだった。うーん、と考えながらブロックの色を選んで組み合わせていく。ああでもない、こうでもないとくっつけては外し、くっつけてはまた外し。どうやら彼なりに拘りがあるようだった。
《なーにしてるのー? 今日はブロック?》
その時、少年の背後からそんな明るい声が飛んできた。その声で、少年はパッと後ろを振り向く。そこには緑色の髪の上に黒い帽子を被り、フリルのついた可愛らしい服を着た小柄な少女が立っていた。彼女は少年の手元を覗き込みながらにこりと笑った。
「こいしちゃん! 今日も来てくれたんだ!」
《来るよー。だってわたしは海人くんのおともだちだもん》
「ねぇねぇ、ぼく二人でやってみたいおもちゃがあるんだ! いっしょに遊んでくれる?」
《いいよ~。どれどれ?》
こいしは少年の隣でしゃがみ、おもちゃの並んだ場所を見つめる。少年はそこからあるおもちゃの箱を引っ張り出し、彼女に見せた。
「これ!」
海人が見せたそれは、氷に見立てたブロックをハンマーで順番に落としていくゲームだった。彼はたまにこれを一人でやっていたが、箱の表面に写真がある通り、二人でやったら楽しそうだと思ったのだろう。顔面いっぱいにわくわくした表情を広げる彼に、こいしはまたもにっこりと笑って答える。
《うん! それやろっか!》
それを聞いてわーい、と喜びながら、彼はおもちゃの箱を開け始めた。
*
海人がこいしと出会ったのは、彼が五歳になったばかりの頃のことだった。
丁度その頃、海人には妹が生まれた。しかし「妹ができた」といってもめでたいことばかりではなく、彼女は予定日よりも数か月早く生まれた未熟児だった。暫く病院で過ごす必要があったため、海人の母は彼女にほぼ付きっ切りで世話をしなくてはならなかった。海人は祖父母の元に預けられることが多くなった。
母親のお腹が大きくなっていくのを真横で見ていたこともあって「お兄ちゃん」という自覚が多少芽生えてきていたものの、急に母親がいなくなる時間、つまり祖父母の家に預けられる時間が増え、最初は祖父母にたくさん会えて嬉しかった海人も、段々と寂しさを覚えるようになった。海人が「お母さんは?」と訊いても、毎回「海人の妹のところだよ、もう少し一緒に待とうね」という答えしか返ってこない。
――「もうすこし」っていつまで?
――「もうすこし」「もうすこし」って、ぼくずっと待ってばっかりじゃないか!
祖父母の慰めの言葉に不信感が募ってしまった海人は家にいたくなくなり、祖父母の家の周辺で一人で遊ぶことが多くなった。幸いにも祖父母宅にはボールがあったので、彼はそれでサッカーの真似事をよくしていた。テニスでいう壁打ちのようなことを一人でやっていた。
その日も、海人は壁に向かってボールを蹴っていた。壁の下側にある染みや傷を目印にし、そこに向かって蹴っていく。五歳児の遊びなので大体は外れるのだが、たまに当たることがある。その時ばかりは彼も嬉しそうだった。
しかしその嬉しさからか、次のシュートは思わず勢いよく蹴ってしまった。ボールは壁で跳ね返り、海人の後方へと転がっていく。
――取りに行かなきゃ。
海人がそう思ってボールを追いかけようとしたその時、誰かの足にコツンとボールが当たったのが見えた、ような気がした。
『ん……?』
そこでボールの勢いが落ち着いたので、確かに何かに当たりはしたのだろう。しかし、海人がその場をよくよく見てみると、そこには比較的大きめな石が出っ張った状態であるだけだった。そこに引っかかったのだろう。
じゃあ、誰かの足が見えた気がしたのは……?と海人が思っていると、
《私に気付いてくれた?》
そんな声が背後から聞こえてきたのである。
『わぁっ!!?』
彼がバッと振り向くと、そこには彼よりは年上そうだが割と幼めに見える一人の少女がいた。彼女は手を後ろで組みながら若干前傾姿勢になり、彼を覗き込むような仕草をしている。
――今さっきまでだれもいなかったのに、いつの間に!?
『だ、だれ……!?』
あまりの驚きでまともに声が出せず、海人はやっとの思いでそう問うた。すると、目の前の少女は楽しそうににっこりと笑う。
《わたしはね、こいし! きみのおともだちになりに来たんだ》
『と、ともだち……?』
《うん! きみが一人で遊んでるのを見かけたから。ねぇ、わたしといっしょに遊ばない? おにごっこしようよ! わたしのことつかまえてみて!》
『えっ、ま、まってよ!』
無邪気に笑いながら走ってゆくこいし。そんな彼女のペースにすぐのまれてしまった海人は戸惑いつつも、誰かと遊べるのが嬉しい気持ちもあり、少しして彼女のことを追いかけ始めた。
《おにさーん、こっちだよ~》
『まってよー! はやいよー!』
海人が鬼ごっこに夢中になった頃にはもう、彼女が誰なのかはどうでもよくなっていた。寂しさの海から脱出するためには「一緒に遊べる存在がいること」ただそれだけで良かったのだ。
海人とこいしは、海人が祖父母宅に預けられている日には必ず一緒に遊んでいた。
しかしある日、遊んでいる途中で雨が降ってきてしまった。最初はどうしよう、と思った海人だったが、すぐにこいしに向かって言った。
『家の中で遊ぼう! いっしょに来て!』
海人は家の入口に戻り、インターホンを鳴らす。するとすぐに海人の祖母がタオルを持ってやって来た。
『かいちゃん、すぐお風呂入っちゃいなさい! 風邪引いちゃうから』
『おばあちゃん、ぼくこの子といっしょに家の中で遊びたいんだけどいい? ずっといっしょに遊んでくれてた子なんだけど』
そう海人が指さす方向を見て、祖母は首を傾げる。
『……かいちゃん、誰のことを言ってるの?』
『えっ? ここにいるでしょ、緑色の髪の子』
海人のすぐ斜め後ろにはこいしがいた。しかし。
『緑色の髪の子? ……おばあちゃんには、かいちゃん以外誰も見えてないよ?』
祖母が怪訝そうにそう言ったことで、海人は「こいしは自分以外には見えない存在(イマジナリーフレンド)」だということを知ったのである。
しかし、それを知ったところでこいしは海人の友達。
晴れの日は家のすぐ横の空き地で、雨の日は海人がいる部屋で。こいしがふらっと現れては二人で一緒に遊ぶ。
産後数か月で妹の状態が落ち着いて退院し、母親が家にいれるようになってからも、海人が一人で遊んでいる時は必ずこいしが来てくれた。
母親が妹の世話で忙しくても、こいしがいてくれれば寂しくない。
そんな安心感が、海人の心の中にはあった。
*
「じゃーんけーんぽん!」
《あっちむいてほい!》
「あっ! また負けたー! なんで!?」
《ふふふ、わたしあっち向いてホイ強いんだよー!》
今日の海人とこいしは、あっち向いてホイをしていた。海人が幼稚園で教わってきたので、家でもこいしと一緒にやっていたのである。幼稚園ではかなりの勝率だった海人だが、こいしの前では全く勝てなかった。
「なにかズルしてない!? ようちえんではぼく強かったのに!」
《してないよー、相手の動きをよみとるのがコツ!》
「あいてのうごきを……??」
こいしの言っている意味が全く分からない海人。そんな彼の様子を見て、こいしは無邪気に笑っていた。
「……ねぇ、こいしちゃん」
そんな様子のこいしを見て、海人はふと彼女に問いかけた。
《なーに?》
「こいしちゃんって、いつもはだれと遊んでるの?」
《……え?》
その問いかけに、思わずきょとんとするこいし。
「だって、ぼくがようちえん行ってるあいだとかは、こいしちゃん別のところにいるんでしょ? そしたらだれと遊んでるのかなって」
海人がそう言うと、こいしは「あぁ!」と手をぽんと打って答えた。
《そういうことか! わたしにはね、お姉ちゃんがいるんだ~》
「お姉ちゃん?」
《そう! だからわたしは実は妹なんだよー》
こいしは海人の隣に移動し、再び座った。
《わたしはずっと、お姉ちゃんにたすけられてばっかり。わたしだけじゃ何もできないんだ》
「そんなことないじゃん! ぼくはこいしちゃんにしてもらったこと、たくさんあるよ?」
《海人くんのほうがずっと、ずーっとすごいよ? 杏奈ちゃんが生まれて、お母さんが中々海人くんにかまえなくても、海人くんはわがまま言わずに待ってる》
こいしによって急に現状が言葉に変換され、海人は思わず言葉を飲み込んだ。無意識に、意識しないようにしていたのかもしれない。感覚的にだが、海人はそんな感じのことを思っていた。
《えらいねぇ。海人くんはほんとうにいい子だよ。でもね》
こいしは海人の頭の上にぽんと手を置いて言った。
《お兄ちゃんだからって、泣くのがまんしなくたっていいんだよ? わたしがお母さんのかわりにうけとめてあげる!》
最後に見せたこいしお得意のにっこり笑顔で、海人の心は止めを刺されてしまった。というのも、ここ最近海人がずっと思っていたことだったからだ。
妹の杏奈の状態が落ち着いたとはいえ、家でも諸々注意して見ていないといけないのは事実だった。家にいられるようにはなっても、イコール海人の相手をしてあげられる時間が増える、とはならなかったのだ。
時々海人が幼稚園の出来事を楽しそうに話してみても、杏奈が泣いていたらすぐにそっちへシフトしてしまう。やっと話が再開できる頃には、もう海人はこいしと遊んでいることの方が多かった。
――本当はお母さんに色んなことを話したいし、いっしょに遊びもしたい。
――でもわがまま言ったってどうしようもないから、何も言わないでおこう。
――お兄ちゃんなんだから、さみしくても泣いちゃいけないんだ。
海人はそんな気持ちを抱えて過ごしていたのだった。
「こいし、ちゃ……」
彼が名前を呼び切る前に、溢れ出てくる涙が掻き消してしまった。まるで心の中を読んだかのような言葉だった。心を真っ直ぐに射抜いた矢の傷から、抑え込んでいた感情が一気に音を立ててこぼれ落ちてゆく。海人はこいしにしがみつくようにして泣いていた。こいしはそんな海人を優しく受け止め、背中をぽんぽんと叩いていた。
《だいじょうぶだよ》
そして、こいしは言った。
《海人くんがだいじょうぶになるまで、わたしはずっとそばにいるからね》
その時、部屋の外から走ってくるような音が聞こえた。
「海人!? どうしたの!?」
彼がパッと振り向くと、そこには焦った表情でこちらを見る母親の姿があった。そんな母の姿をよく見ると、妹の世話で忙しいこともあって髪がぼさぼさになっていた。
「あ……」
そんな姿を見てしまったものだから、海人は「自分の泣き顔を見せてはいけない」と思い、慌てて涙を拭おうとした。
しかし。
――ぱしっ
その手を、こいしが止めた。
《海人くんが今思ってること、そのまま言っちゃえばいいんだよ》
「で、でも……」
《だいじょうぶ! きみのお母さんならうけとめてくれるはずだから》
ほら、行っといで。こいしは海人の背中を押して、母親の前まで連れていった。
「……そっか、今日もこいしちゃんがいてくれてたんだね」
そんな海人の様子を見て、母親はそのことを察した。そして海人と目線の位置を合わせてしゃがみこんだ後、彼をぎゅっと引き寄せた。
「ごめんね、いつも一緒に遊べなくて、話も中々できなくて……」
こいしの時にわっと泣いたはずだったのに、母親に包まれた安心感も合わさり、再び海人の目からは大粒の涙がぽろぽろとこぼれていた。母親の背中に小さな手を回しながら、海人は叫ぶように言っていた。
「ぼく、ずっとママと話したかった」
「うん」
「ほんとはいっしょに遊びたかった……っ」
「……うん」
「ぼく、ずっとさみしかった……!」
やっと本当のことを言えた少年と、それをしっかりと受け止める母親。
そんな海人たちの様子を見届けたこいしは、音も立てずにそっと部屋から姿を消した。
*
ぼくには、ぼくだけに見えるおともだちがいる。
その子の名前はこいしちゃん。
どこから来たのかも、ふだんどこにいるのかもぼくは知らない。
だけど、ぼくがさびしい時にはいつもちゃんと来てくれるんだ。
でも、ぼくが小学生になってから、こいしちゃんはいなくなってしまった。
*
月日は流れ、海人は小学生になった。まだ大きいランドセルを背負い、学校に通っていた。
通学路を歩いていると、後ろから「海人ー!」と彼を呼ぶ声がした。海人は後ろを振り向く。
「佑真、おはよう」
「おはよ! なぁ、今日のほーかご何して遊ぶ?」
「んー、そうだなぁ」
そう、海人には一緒に遊ぶ友達ができた。出席番号が一つ違いの佑真だ。入学式の日に席が隣であり、人懐っこい佑真は海人に話しかけてくれたのだった。それから二人はよく一緒に遊ぶようになった。
佑真のお陰で一人で遊ぶことはめっきり減った海人だったが、勿論こいしのことを忘れるはずもなく。佑真という友達ができたことをこいしに伝えたかった彼は、自室にいる時や一人で外に出た時などに、何度もこいしの名前を呼んだ。
しかしあの明るい笑顔が、声が、再び海人の前に現れることは二度となかった。
元々海人にしか見えていなかったこいしだったが、彼女は本当に、名前通りの「小石」になってしまったのかもしれなかった。海人は少しずつ、そんな道端の小石に話しかけている感覚と同様のものを抱いていた。
――もう、こいしちゃんは来ないんだな。
そしてやがて、諦めにも似た気持ちでそう悟ることになったのだった。
「よし、じゃあ教室まできょーそーしようぜ! 勝った方が今日の遊びのけってーけんな! よーいどん!」
海人が遊びを考えつつこいしのことをふと思い出していると、佑真が急にかけっこを始めた。突然の展開に海人は思わず怯んでしまった。
「えっ!? ちょ、まってよー!」
佑真に一歩遅れて海人も走り出す。急に自分のペースに引き込んだり、明るく接してくれたりする佑真の姿にどこかこいしが重なる。しかし、彼は紛れもなく現実の友達である佑真だ。
――ぼくにも、ちゃんと友達ができたよ。こいしちゃん。
心の中でそう思いながら、海人は佑真のランドセルを急いで追いかけた。
*
「……本当にこれでよかったの、こいし」
そんな少年たちの様子を、学校近くの木の上から見守る存在が二人。共にフリルの服を身にまとい、体の周囲には目のついたコードのようなものが漂っている。
「うん。一番長く一緒にいたあの子に、さよならをはっきり伝えてしまうのは酷でしょう?」
横にいる姉の問いかけに対し、妹は微かに笑った顔でそう答えた。しかし、少年を見つめるその瞳はどこか寂しそうだった。
「彼には『イマジナリーフレンドという現象だった』って認識で終わってほしいから」
「……それもそうね」
姉、さとりはそう納得すると、見送っていた少年の後ろ姿から目を背けた。
……もうそろそろ、向かわなくては。
「行きましょうか」
そして、さとりはそう言いながら木から飛び降りる。こいしもそれに続いて地面に降りた。
さとりとこいしは、山奥に棲む覚の集団から追放されてしまった姉妹だった。理由は主にこいしがそもそも覚として向いていないことにあったが、最大の決め手はこいしがサードアイを自ら閉じてしまったことだった。そうすると勿論覚としては生きていけないためこいしは追放され、そんなこいしを見放せなかったさとりも集団から離脱したのであった。
自ら覚としての生を手放したこいしだったが、今更他の存在になれるはずもなかったため、最終的にはもうこの世から消えてしまう以外に選択肢がない状況になってしまっていた。その状況をどうにかしたかったさとりは、必死にこいしを救う方法を探し回った。その最中に妖怪の噂で聞いたのが「山奥にある博麗神社という神社に行けば、全てを受け入れてくれる場所へ行けるらしい」というものだった。確証のない噂ではあったが、さとりはこいしを連れ、藁にも縋る思いでそこを目指すことにした。
集団から離れてどのくらい経ったかも分からなくなった頃、こいしは外で座り込んでいる一人の子どもを見つけた。
『お姉ちゃん』
『どうしたの、こいし』
『あそこにいる子の心、読める?』
こいしはなんてことないように言ったが、さとりは思わずこいしの肩を掴んだ。
『こいし! あなた忘れたの! あなたは人間に傷付けられてその瞳を閉じたんでしょう! 今更どうして人間に――』
『寂しそうだから』
『えっ……?』
『あの子、一人ぼっちで寂しそう。だから少しだけ話し相手になってあげたいの』
さとりを真っ直ぐ見ながら迷わずにそう答えたこいし。それを見たさとりは何も言えなくなってしまった。少ししてこいしの肩から手を放し、溜息をついた。
『……分かった、あなたの要望に応えましょう。だけど、話すのは少しだけよ。いい?』
『うん、ありがとうお姉ちゃん!』
こいしの姿勢に観念したさとりは、子どもの感情を読み取ってこいしに伝える。それを聞いたこいしはその子の所に向かい、十分ほど話をした。話を終えたこいしがさとりの元に戻ってくる時、彼女の顔には明るい笑顔が広がっていた。
『お帰り、こいし。話せた?』
『うん! やっぱり私、人間の子どもは嫌いになれないみたい。それに……』
『それに?』
『一人でいる時の気持ちはよく分かるから。せめて少しの間だけでも友達になれたら、って』
この時のことをきっかけに、こいしは一人でいる子どもの「少しの間だけのお友達」を始めることとなった。しかし、見かけた全ての子どもを対応するとキリがなかったため、さとりは「博麗神社に向かうまでの道中で見かけた子だけで、その子に友達ができるまでにすること」「私が最初に心を読んで、大丈夫そうだと判断した子だけにすること」という条件を設けた。
最初はこいしの行動にあまり乗り気ではなかったさとりだったが、覚でいた時よりも楽しそうなその様子を見て「最後くらいは好きなことをさせてあげたい」と思うようになっていった。そして次第にさとり自身も協力的になっていき、さとりが子どもの心を読み、こいしが実際に対応していくという、博麗神社に着くまでの「イマジナリーフレンドとしての姉妹旅」が始まったのだった。
そこまで数多くの子どもの友達になれたわけではなかったが、その分こいしは一人ずつ丁寧に接していった。最初は悲しい顔をしていることが多かった子どもたちだったが、二人が次へ向かう時には皆笑顔になっていた。そうやって子どもたちを一人ずつ助けながら二人は神社までの道のりを少しずつ進んでゆき、最後の子どもに選ばれたのが先程の海人少年だった。
そんな最後の「友達の役目」も無事に終わり、姉妹旅は到頭終点まで辿り着いたのだった。
*
最後の少年を見送ってから二人はかなりの距離を移動し、木々が鬱蒼と茂る山の中を進んでいた。
「お姉ちゃん」
「ん?」
「……私が今までに出会った皆、これからも幸せでいられるといいな」
姉に話しかけたこいしは歩きながら空を見上げ、そう呟くように言った。さとりはそんなこいしを一度だけ見て、再び前を向く。
「そうね……きっとあの子たちは幸せになると思うわ」
「ふふ、それは心を読んだから言えること?」
「まさか。覚に未来予知の能力はないことくらい、こいしも分かっているでしょう?」
「あはは、そうだねぇ」
そうやってコロコロと笑うこいしを見て、さとりは少しだけ切なそうな笑みを浮かべる。
「……こいし」
「なーに?」
「きっと……きっと次の場所では、あなた自身も幸せになれるわよ」
瞼を縫い付けられたこいしのサードアイを見ながら、さとりは祈るかのようにそう言った。
――これから向かうは、全てを受け入れてくれる場所。きっとそこでなら、私たち自身のための幸せな日々も送れるはず。
さとりはこいしの手を取り、山道を登ってゆく。博麗神社はもうすぐそこだった。
fin.
《後書き》
感想から勝手にリクエストにさせてもらいました()、今回はこいしです。
こいしにIF(イマジナリーフレンドの略です)の印象があるのは珍しくないと思いますが、どうしてもこれで書きたかった……。タイトルもIFのことを指しています。
割と最近に解離性同一性障害のことを知った時にIFのことも知り、「これはできるだけ丁寧に書きたい」と思っていたのですが、果たしてちゃんと書けているだろうか。不安。
念のためにお伝えしますが、IF自体はフィクションでもファンタジーでもなく、この現実で起こっている現象です。
それだけはどうか正しく伝わりますように……。
*
因みに覚の集団から外された辺りのところ、かなり展開すっ飛んで(?)書いてあることに感づいた方はいらっしゃるのでしょうか。
そうです。わざとなんです。え、何故ってそれは文字すu(( というのは半分冗談で、書けたらもう1つ話を書こうか迷っているからです。こいしを1つの話に集約するのは無理でした。
とはいえまだ全く固まっていないので、どうか期待しないでお待ちください。
*
設定のご意見や感想、キャラのリクエスト等はTwitter(@asuya_novels)までお寄せいただけると幸いです!
ここまでご覧いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
