
68. 第4章「行け行け東映・積極経営推進」
第10節「東映100年に向けて 次なる事業への取り組み ④」
⑦俳優育成、マネージメント事業:東映芸能株式会社 後編
1967年8月、第9回をもって明治座での東映歌舞伎は終了しましたが、東映芸能は、1968年、前年6月に新歌舞伎座で初公演した東映劇団の3月公演という形で久留米市石橋文化センターを皮切りに16都市をめぐる18公演の劇団活動を続けます。
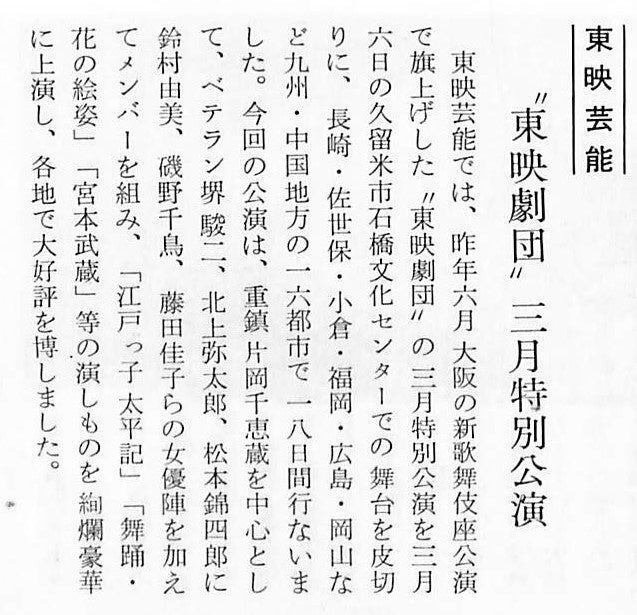
1968年の年頭あいさつで大川が語った新人スターを作るために、東映本社は5年ぶりに第12回ニュータレントオーディションと言う名で東映ニューフェイスオーディションを復活。3月に募集を開始するとおよそ8000名あまりの応募者があり、その中からオーディションを重ね、13名の入社を発表しました。



6月6日、日活に入社した1名の辞退者を除く宮内洋ら12名が入社、明日の東映スターを目指します。

9月1日の東映の全社的機構改革に伴い、8月31日、大川は東映芸能(株)会長、東映常務の今田智憲が社長、俊藤浩滋が副社長にそれぞれ就任しました。
俊藤は、大川に頼まれて巨人の名監督である水原茂の東映フライヤーズ招聘に尽力し、念願の日本シリーズ優勝に導いた陰の功労者であり、鶴田浩二を東映に導き、高倉健、藤純子、菅原文太など東映任侠映画スターを作り上げた、東映屈指の映画プロデューサーです。
俊藤がプロデュースし、娘の藤純子主演した『緋牡丹博徒』が、就任後間もなくの9月14日に公開され大ヒットしました。

大川は、10月21日に記者会見を開き、東映芸能の方針として、タレントの養成と確保、演劇公演、児童劇団の結成、音楽・ダビング請け負い、レコードの制作販売など芸能事業の拡大を目指していくことを語ります。


この方針の下、11月9日、俊藤は、東映芸能創立3周年記念イベント「スターパレード 歌の祭典」を新宿厚生年金大ホールで開催します。
鶴田浩二、高倉健、若山富三郎、梅宮辰夫、藤純子、千葉真一、里見浩太郎、菅原文太と東映任侠映画オールスターが勢ぞろいした舞台には千葉と映画『浪曲子守唄』で共演した子役時代の真田広之も出演しました。
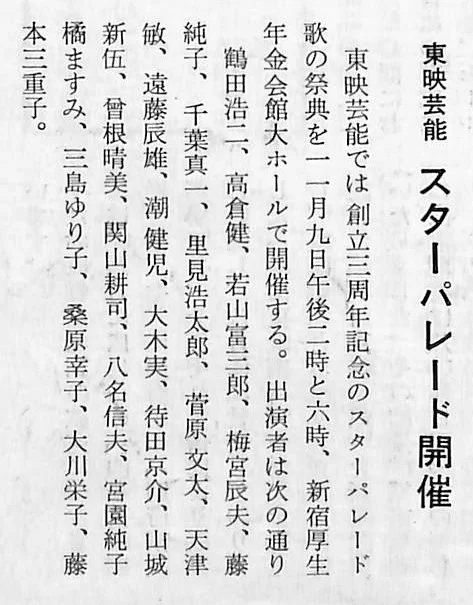


一方、来年1月には児童劇団の旗揚げ公演として新宿伊勢丹ホールにてテレビで人気の『ゲゲゲの鬼太郎』の舞台劇を開催することが決まります。
ここから東映テレビアニメを題材にしたショーがはじまりました。


1969年、大川は年頭あいさつにて芸能事業の本格的育成に向けての人事の刷新を行ったこと、タレントの需要は大きく伸びていくと考えられるためその養成と確保が大事であること、児童劇団の創設、レコード制作への取り組みの期待などについて語ります。



ジャニーズ事務所をはじめ、芸能プロダクションがこれから大きく伸びて行こうとするこの時点での俳優・タレント育成及びマネージメントの大事さ、音楽業界への進出などは現在の芸能プロ隆盛をみると非常に的を得ており、お金をかけてでも取り組む価値がありました。

1月の児童劇団旗揚げ公演『ゲゲゲの鬼太郎』も大成功した東映芸能は、4月の東映劇団の明治座公演、夏休みの鬼太郎公演の決定、大川待望の藤純子レコード収録完了、3月ビクター発売など事業の着実な進捗を述べます。
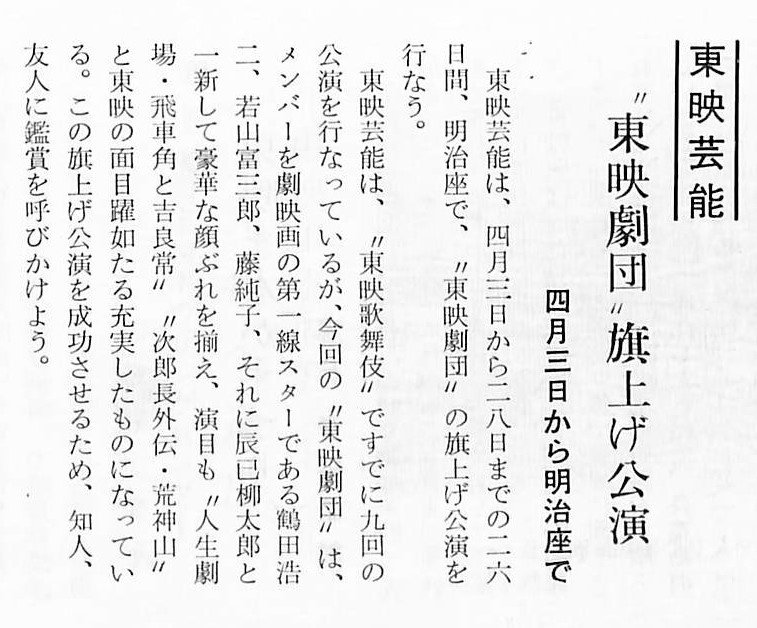

そして3月8日、東映自主製作レコード第1弾・藤純子歌う『緋牡丹博徒』が発売されました。


レコードは順調に売り上げを伸ばし、曽根晴美による第2弾の制作にとりかかります。


4月1日付けで東映芸能社長の今田が退任し再び大川が就任。4月3日には、鶴田浩二、若山富三郎、藤純子に加え、新国劇の辰巳柳太郎も参加する東映劇団による明治座公演を盛況に旗上げすることができました。



続けて、新人の発掘に向けて12月から第13回ニュータレントオーディション参加者募集を始めます。

1970年、大川は、年頭あいさつでタレントの養成と確保に向けてハッパをかけました。

それを受けて、1月20日に大川に代わって東映芸能社長に就任した俊藤博(俊藤浩滋本名)は目標の第一にタレントの養成と確保を今年度の目標に掲げ、一大タレント供給会社へと成長することを目指します。

4月には、鶴田浩二、藤純子を中心とした明治座での東映劇団第2回公演が決定しました。

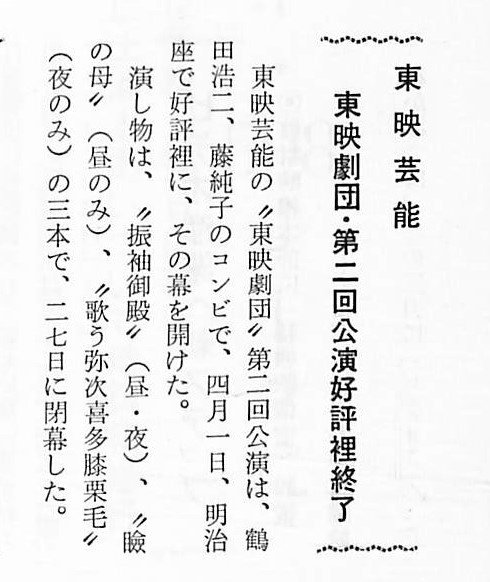
同じ4月、14名の第13回ニューフェイスが入社し、9月に半年の研修を終え卒業公演を行います。

しかし、なかなかタレントの育成は思うように進まず、この年の第13回で東映ニューフェイス募集も終了しました。
東映芸能の劇場公演も下火になり、1971年の年頭挨拶で大川の口から芸能活動の活発化について語ることはありませんでした。
1971年8月、大川博は逝去し岡田茂が東映社長に就任します。
この年4月に始まった『仮面ライダー』は大人気を博し、子供たちの間で変身ブームを巻き起こしました。
ここから、東映芸能の新たな展開が始まります。
また、東京撮影所の児童演劇研修所と演技研修所はこの後も地道に活動を続け、1994年に統合して東映アカデミーと改称。それまでに数多くの俳優を育てました。
その後の東映芸能の活動は改めてご紹介いたします。
