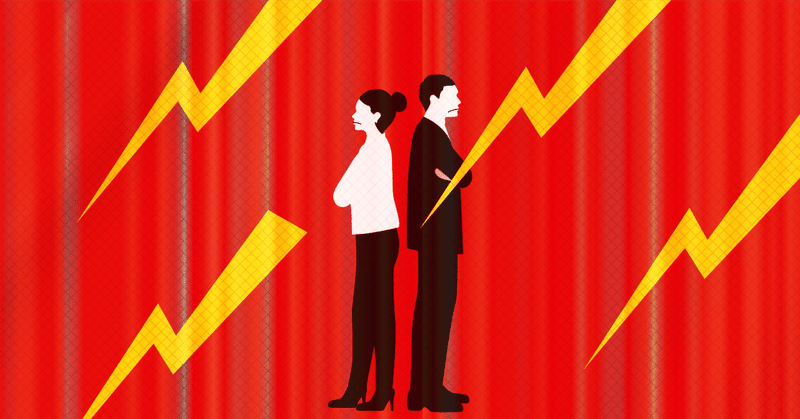
インボイスで変わることのあれこれ -2-
消費税に関わる潜在的な不正
消費税については、以前から潜在的な不正があります。
例)
内税方式の製造生産者が1000円の商品を8掛けで卸す
▽
販売者は外税で売る
この場合、納税の内訳は以下となります
消費者 1000円を1100円で購入し、100円納税
販売者 1000円を800円で購入し、200円の売上に対し20円納税
製造者 1000円を800円で卸し、800円の売上に対し73<72※>円納税
差額 100 - (20+73<72>)= 7~8円
※端数切り捨ての場合
つまり、消費者が内訳上税金分として支払いさせられた100円のうち、7~8円は納税されず、販売者の利益に置き換えられます(益税の概念)。販売者の事業上のサービスは手数料にあたる金額だけなのですが、その何倍もの(手数料料率の逆数倍)利益が何もしていないのに発生してる事になります。インボイスになると仕入れ分の納税額が免除されますので、生産製造側が内税であったり、免税事業者の場合、差額は利益計上されます。少々複雑ですが納税回避分が利益還元されると言って良いと思います。消費税分と提示した額を利益化しているので景品表示法の考えでは価格の不当表示に相当すると考えられます。
これが確定的な行為である事は明白で、販売者が内税方式で販売するケースは圧倒的に少ないのです。理由は消費者の支払った税額の一部を懐に入れられないからです。
実質、脱税は野放しになっていると言えます。
売上清算方式の販売者は税なし価格すら外税で販売している所があります。
この場合、上記の例ですと、100円の消費税のうち80円を着服している事になります。※2
―――――以上は現状の不正ですが、この仕組みはそのまま、さらに複雑に、手口を増やしてしまうのがインボイス制度です。
なお、経理に関しては仕入れに適用している全ての購入商品(水道光熱費ほか経費等も含む)に対してインボイス該当項目のある領収書の保管と業者の確認が必要となり、不可能な場合は控除(上記例では72~73円の消費税額控除)ができなくなります。現状は制約なくできています。
これが損失のイメージをかきたてるので、取引先が納税事業者登録をせよと要求してくる訳ですが、必ずしも損失とはならない事は前回記事でご説明しています。
(困るのは※2のような事業者だけ、つまり税なし価格の製造者に対する大きな不正をしている事業者が納税事業者登録して申告する場合だけです(そこだけ不正は減ります)。小さな不正は従来通りです)
簡易課税制度(みなし仕入れ率)
簡易課税制度は、あらかじめ制度を利用する事を税務署に申請する必要があります。
条件:前年(法人は前々年)課税売上高5,000万円以下
この制度は個々に消費税額控除を行うのでなく、仕入れ先の事業種別ごとに設定された一律のみなし仕入れ率を使い、計算上の利益との差額に対する消費税だけを納めるというものです。
目的は事務処理負荷の軽減(インボイスの処理の省略)です。
小売業のみなし仕入れ率は80%となっています。冒頭の例を適用すると問題はそのまま残っていますが、さらにここから不正が、しかも合法的に可能となります。
販売者が掛け率の引き下げを要求したとします。8掛けを7.5掛けにせよと言った場合、あるいは現行そうなっている場合です。
消費者 1000円を1100円で購入し、100円納税
販売者 1000円を750円で購入し、250円の売上に対し、みなし800円差額20円納税
製造者 1000円を700円で卸し、700円の売上に対し64<63※>円納税
差額 100 - (20+63<64>)= 16~17円
※端数切り捨ての場合
どうでしょう。この場合販売者は、顧客が支払った消費税相当増額からさらに11円余分に利益化し、納税額を減らす事ができる事になります。現状不正を行っている所はこういった事を行う(手数料、インボイス対応費用などと名目をつけて数パーセントの実質仕入れ価格の引き下げを図る)可能性が高いと思われます。
なお、こちらは仕入れ先がインボイス方式で消費税を納税する納税事業者である事を前提としていますが、インボイス対応経理書類の保存が免除されますので、実質的に相手が対応してるか区別はできません。厳密な区別をする場合、免税事業者に対する措置も同様にあります。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
前段は納税事業者からの仕入れに関するものでしたが、明確に免税事業者相手の取引を厳密に行った場合でも同じ事が可能になります。ただし、こちらは経過措置という事で期間があります。
多くの企業は2026年10月1日までの80%控除期間は、免税事業者もそのまま扱うという判断をしている所があるようです。
こちらは業種によらず80%ですから、販売であれば80%未満の掛け率を指定された場合は、先ほどの例と同じ事になります。
この制度に関する不正について
当局の見解は不正があったとして事業者が告発しない限りは分からない、とのこと。事業者が報告すべき(当局で対応しない)という言い方のようです。もちろんこの主張には根拠はありません。逆に仮に報告しても真面目に聞いてもらえるかどうか不安になると思います。
単純な疑問として、この制度を何のために施行したいのかよく分からない所があります。公正な納税のためではない事は確かに思えます。
-1-で述べたように徴税を事業者に代行させる、ですとか、取引の流れを監視したいといった目的であるように思います。事業継続のための補助金申請の段階で取引内容が記載された通帳の提出を求められていたそうで、抵抗のあった事業者も多かったようですが、インボイスの導入的な書類提出処理だったのではないかと思います。
まとめ
製造側・受注元では報酬を削られる恐れがある
消費側は納税額の全額が公費に利用されず、中抜きされる
利益に対して納税額が不足する事になり、消費を上げるか税額を増やすという話になる
経済偏重のモラル低下が新しい社会問題の種になったり、現在の問題を深刻化させる
以上です。ありがとうございました。
サポート頂けると嬉しいです。
