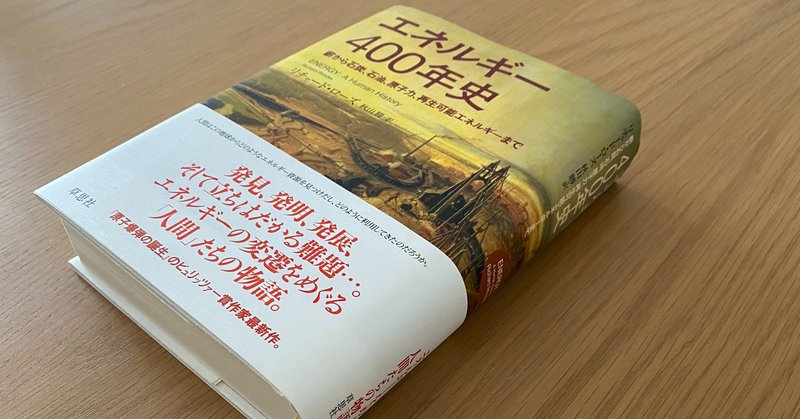
エネルギーの歴史から環境問題を考える
『エネルギー400年史』(リチャード・ローズ著 秋山勝訳 草思社)の第1部「動力」を読んでの感想です。
環境問題を考える時、我々は過去を「過ち」であると決めつけ、現在を「転換点」であるとして、終末論的な議論によって明るい未来か悲惨な未来が訪れると考えていないでしょうか?
しかし、人類が化石燃料を燃やし始めた歴史を知れば、過去は「過ち」ではなくなり「学ぶべき歴史」になるのだと思います。
化石燃料というと、18世紀の産業革命の産物のように思われますが実際にはそうではありません。「薪(まき)」として木を燃やしていては森林資源が枯渇してしまうため、16世紀ころから代替燃料として石炭を燃やすようになったのです。
すでに1500年代後半のロンドンでは近郊の森から薪が供給できなくなり、薪の価格が高騰しています。人々はやむを得ず本来工業用であった石炭を家庭で燃やし始めるようになりますが、その結果ロンドンの空気は煤と煙で汚染されていきます。
この時代、環境問題とされたものは「家庭用石炭による大気汚染」です。
一方、需要が拡大する石炭を掘り出すため、炭鉱では水を汲み出す技術が必要になります。この時ポンプの動力として発明されたのが蒸気機関です。
蒸気機関はやがて水を汲み出す以外にも石炭を運ぶ動力としても使われるようになりました。そうして鉄道が整備されるようになります。
このことは様々な効果をもたらしました。
経済の活性化と製鉄業の拡大、自由な移動と時間間隔の変化など。
製鉄によって木材から鉄への転換が行われると、木材の供給に余裕が生まれるようになりました。家庭の燃料は薪に回帰して、人々は経済の恩恵を受けながら快適な生活を送れるようになったのです。
当時の人にとって産業革命と蒸気機関が明るい未来をもたらしてくれたのは間違いないでしょう。
ここで現在に目を向けてみます。
CO2削減の観点から自然エネルギーの活用が急務であることは事実です。
しかし「自然エネルギーを活用すれば全てが解決される」というのは誤りではないでしょうか?
太陽光発電は「土壌に当たるはずの日光を遮っている」という意味で土壌の負担になりますし、風力発電は時として野鳥を切る刃となります。
もちろんそれらの問題に対する対策もされていますが、それでも「CO2削減」という大命題の前に軽視されていないでしょうか?
石炭が木材資源の削減に寄与する一方でCO2排出の増加をもたらしたように、CO2削減が達成できたとしても今度は新たな問題が出てくるはずです。
今考えられる理想的な世界像も、後世では全く別の評価となるのです。
劇薬をもって「理想の世界」を目指すより、現実的な解決策を続けて「より良い世界」を創り続けていくことが、ほんとうの意味での「持続可能な社会」ではないでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
