
改訂版2010年代ベストアルバム. 40~31位
どうも。
では、改訂版2010年代ベストアルバム、続けていきましょう。今回は40位から31位。このようになっております。

はい。まずは40位からいきましょう。
40(40).Take Care/Drake (2011)
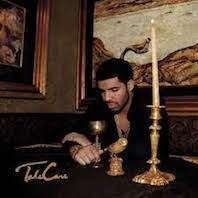
40位はドレイク。2011年の、最高傑作といって良いでしょう、「Take Care」。前回ランクつけたときはもうすでにロック・イン・リオでの傲慢騒動があった後でした。それで低めで40位になってたかと思います。今回は2023年のロラパルーザ・ブラジル当日ドタキャン騒動で僕自身が直接被害被っていて、さらに言えば、前回から年1のペースでワースト更新中の不評アルバムがリリースされまくってましたが、前回と同じ順位となりました。下げなかったのは、やはり彼が一個人としてどんなにひどいやつであろうとも、このアルバムと、そのつぎのアルバムあたりでの音楽界への貢献は否定できるものではないから。あの頃はその後みたいに安全牌のトラップに逃げたりせず、トロントの仲間たちとエレクトロにもネオソウルにも対応できそうな良質なトラックに、いち早くウィーケンドをフックアップするセンスやリアーナとの客演をキメるうまさがあり、ヴォーカルとラップの両刀使いも絶妙でした。「これからは彼のような歌もラップもでき、耳の肥えたトラック選べるスーパースターの時代になるのか」と実際感心してましたからね。そこから比べると今は随分な体たらくぶりですけど、未だにあの頃の彼に並ぶ才覚の人が現れないのも問題で。誰か脅かして、尻に火をつけてほしいんですけどね。
39(-).Pop 2/Charlie XCX (2017)

39位はチャーリーXCX。彼女が2017年の暮れに出したミックステープ。これ、僕だけじゃなく、彼女の最高傑作であげる人、多いですね。このアルバムは前回にも入れるかどうか迷ってて、そのときは映画「きっと、星のせいじゃない」に使われヒットした「Boom Clap」の入った「Sucker」(2014年)というアルバムを100位にしたんですけどね。そのアルバムから彼女、映画の曲のヒット(これがキュートでいい曲ではあったんですが)のポップなイメージを避けたかったのか、しばらくはミックステープ・リリースが続いて、よりエレクトロな方向に原点回帰したのかなと思ってて、その最中に出たのがこれでしたね。ここでの彼女はカーリー・レイ・ジェプセン、トーヴェ・ロウ、キャロライン・ポラチェック、キム・ペトラスなどと積極的にコラボ。この体験を通して、「エレクトロにしっかりベースを置いた形での彼女なりのポップ」の形が固まったか、これ以降はまた通常なアルバム制作に戻って早いペースでアルバムも三枚作ってますけど、ここが何かしらの起爆剤になったかな。曲の閃きとキレがとにかくすばらしく、リピートを重ねたくなる作品ですね。
38(50).Wasting Light/Foo Fighters (2011)
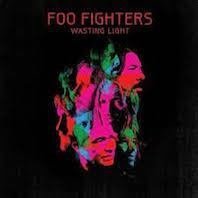
38位はフー・ファイターズ。2011年発表の「Wasting Light」。リリース当初から「久々の傑作」と話題になり、実際にかなり売れてツアーも大成功したので、イメージとして彼らがこの時代を代表するビッグ・バンドになってたことも事実だと思います。客観的に見てレッチリやグリーン・デイよりは調子良かったですからね。彼らの場合、90sの最初の3枚が評判良く、00sに入って4枚目でマンネリズムを感じたか、そのつぎの2枚がそれまでよりは激しい分ちょっと粗い方向に行きすぎた印象があって僕自身も少し離れてたんですけど、このアルバムは前2作の流れはありながらも全体がタイトで引き締まり、初期3作のソングライティングも戻り、曲調に幅もあるという、彼らの中のバランスとしてはかなり良いものが出来たと思います。その前みたいな「Best Of You」とか「Pretender」みたいな有名チューンこそ出てないものの、その代わりに全体の平均点がすごく高めでね。このときにロラパルーザ・ブラジルの最初のヘッドライナーで2時間30分もライブやってくれたのも良い思い出です。その後、3枚くらいまた試行錯誤してましたが、今年出た「But Here We Are」がテイラー・ホーキンスの急死を乗り越え、このとき以来の傑作となっております。
37(37).Golden Hour/Kacey Musgraves (2018)

37位はケイシー・マスグレイヴス。これはなんと、リリース翌年の2019年のグラミーでAOTY、最優秀アルバムにまで輝いてしまった傑作アルバムですね、「Golden Hour」。これはですね、同じカントリーの出自からのポップ化でも、テイラーの路線に違和感を感じていた僕にとっては、「ああ、こういう路線に行って欲しかったんだよ!」と痛切に思った路線そのものだったんですよ。別にエレクトロで踊って欲しいだとか、ラップして欲しいとか、そういうことじゃないんですよ。アコースティックのままでもアレンジの施しによってはすごく洒落たものにできるし、ただ単に16ビートを応用するだけで、いい感じにグルーヴィーでソウルフルなサウンドにすることは可能。しかも、それ以前から抱えて持ってるギターを捨てる必要なんかもない。僕はテイラーのポップ化に期待をかけていた分、失望も大きかった。なのですぐにケイシー派になりました。実際、インディ・ロック畑からはこのアルバム、ものすごく歓迎されたし、それはその後もそうです。テイラー、このアルバムのことに言及しないんですけど、このアルバムの1年後にLordeのファースト作ったプロデューサーと「Lover」という、ハメはずしすぎない、その後の彼女の路線を定義するようなアルバム作ったので、「Reputation」でやりすぎてしまったことは、これ意識しての反省(とりわけ、ドキュメンタリー「Miss Americana」の始まりがグラミーのノミネート漏れのシーン。この時のAOTYウィナーが先述した通りケイシー)だったんだろうと僕は思ってます。
36(9).A Seat At The Table/Solange (2016)

36位はソランジュ。前回から大幅に下がってしまいましたが、それでもこのアルバムのことはすごく愛してます。このアルバムが姉ビヨンセの「Lemonade」の数ヶ月後に出た時にはすごく快哉をあげましたよ。彼女、まだ22歳だった時に出したアルバム「Sol-Angel And The Hadly St.Dreams」はちょっとしたカルト・アルバムで60sのモータウンを始めとしたソウルへのオマージュ・アルバムだったんですね。その時から彼女のマニア性は知ってたし、ブルックリンのインディ・ロックのシーンにも出入りし、ビヨンセやジェイZ、ライブハウスに連れて行ってたような人で。ただ、メンタルヘルスに問題があって度々ブレイクダウン。そこから1枚EP挟んで待つこと8年。見事なまでの耽美派ネオ・ソウルを作ってくれました。全曲ほぼ彼女の作詞作曲で、美術のインスタレーションとか、ダンスじゃなくて「舞踊」が似合う、ストイックで厳かな雰囲気。ある意味ビヨークがエレクトロで作ってきたものをソウル・ミュージックでやった趣でした。2019年も次作「When I Get Home」では70sのスティーヴィー・ワンダーに影響を受けた初期エレクトロ・ソウル・ミュージックの現代版でこれも見事な出来でした。それなのに順位を下げたのは、まさにその孤高性ゆえです。他への波及がなく自己完結してしまってる。あと、人前でライブもやらないどころか、今、何をしているのかさえわからない。2020年代に浮上してきた魅力あふれる女性たちが外に外に働きかけてアピールする存在なので、そっちを支持したくなっちゃうんですよねえ・・。一旦動けばすぐにまたグーンと上がるとは思うんですけど、果たしてそれがいつになるのやら。その危うさは彼女からは消えません。
35(6).St.Vicent/St.Vincent (2014)

35位はセイント・ヴィンセント。2014年に発表したセルフ・タイトル・アルバムですね。このアルバムが出た時、僕、ものすごく興奮したんですよ。エレクトロを下地にトリッキーかつフリーキーなギター・サウンドで一足飛びにアルバムの評判が高まっていた頃で、このアルバムの成功で、全米アルバム・チャートで一気に12位まで飛躍。「ああ、このまま成長して、この時代を制す存在になるんじゃないか」とすごく期待しましたもの。そう思った理由の一つは、やっぱり圧倒的なライヴ・パフォーマンス。もともとがセッション・ギタリストだったんですけど、それだけにロック史上初の「プリンスばりにギターを操るロック・クイーン」にもなるわけですけど、細身の体にオートクチュールの特注ドレス着て見た目は華麗に、そして音はグイグイとパワーとセンスで押しまくる、「美の破壊力の祭典」状態で。あの時期に見た諸々のライブの中では圧倒的なライブ・パフォーマンスできてましたね。当時のツアーではトコ・ヤスダさんっていう日本人のキーボードの人とシンクロでダンスも踊ったりもして、そこも見せ場でね。このままロックシーンの頂点に立つんじゃないか、そんなことまで思ってました。ただ、その後、2枚の評判も、チャート実績もいいアルバムは出すもののインパクトとしてはこのアルバムから横ばい。アルバムは良いものの、「今回はプリンス風」とか「今度は70s半ばのボウイ風」とか、どこか「企画性」に走ってしまいがちで、「彼女の側からリスナーに伝えたいもの」というのが今ひとつ希薄な感じが続いています。その後、ラナ・デル・レイやミツキあたりのファン層見ていて、ヴィンセントがなぜそうなってしまったのかはわかる気はしています。あと、69位のとこでも書きましたが、プロデューサーとしてスリーター・キニーの分裂劇を招いたことも今回、彼女の評価をかなり落としたことの要因にはなってます。
34(15).This Is Happening/LCD Soundsystem (2010)

34位はLCDサウンドシステム。2010年のサード・アルバム「This Is Happening」。僕がブラジル越したばかりの頃にこれ出たんですよ。この時はまだ仕事見つかってなくて暇でウェブ・ニュースばっかり追ってましたけど、ロックで話題といえばこれで。LCD、2007年の「Sound Of Silver」で大絶賛されて、これで王手かけてたようなとこあったんですけど、ジェイムス・マーフィー、これで堂々のロックスターを目指すような感じの露出して、とにかく目立ちまくったんですよね。これまで「ニューヨーク一のエレクトロの才人」だとはみんな思ってましたけど、およそロックスターとは風貌がかけはなれすぎて誰も思ってなかったんですけど、ただ、応援はすごくしたくなりましたよ。だって、何度も言ってますけど、この当時のピッチフォークの推すインディ・アーティストがもう地味すぎて泣きたくなるレベルでしたから。ジェイムスが笑わせも込みで目立ってくれた方がよっぽど良かったです。サウンドの方は、聞いてすぐジェイムスとわかるパシパシ響く電子音に乗った安定のポストパンクでしたけど、やはりそういうやる気は伝わるのか一気に全米トップ10入って、フェスでもヘッドライナーになりましたからね。そういう「やる気」は僕は大歓迎でした。ただ、それはこのアルバムで引退だか活動休止するからで、そこからは7年アルバムが出ず、さらにその次も6年アルバムが出ず。このアルバムの時は「40男の勝負」な感じでしたが、50代なかばでも遅くないと思いますけどね。
33(34).Days Are Gone/HAIM (2013)

33位はHAIM。前回選んだ時も34位。2013年のこのデビュー・アルバムは浮き沈みなく、安定したポジションを築いています。このアルバムで出てきた時はとにかく曲のクオリティ、そのものに驚きましたね。三姉妹でロックバンドというのもなかなかに珍しいものでしたが、「ドン、パ、ドドン、パ」という、うねりの大きなパーカッションのリズムから、カッティング・ギターでグイグイ迫る、彼女達独自のポップなロックンロール。「Forever」「The Wire」「Don't Save Me」。しかもどの曲とっても、良い意味ですごく書き手の癖のある曲調と歌い回しがあり、作家性の強さも感じさせて。デビューの時からこれだけはっきり個性のあるバンドは強いなとその時から思ってましたね。この時にすでに英米でトップ10入り力を持ってて、その後の2枚もそこから大きく上がりこそはしないものの、インパクトの強かっったデビュー作から魅力を損なわずいまに至ってます。ただ、今年に入って10年の念願叶って初めてライブ見たんですけど、そこでの本人たちのライブでの演奏、歌唱的な実力とバンドの持つ抜群の華を見てしまったら、これ、本人たちもっと欲出さないとダメですね。時代を制しておかしくない実力があるので。良くも悪くも本人たち楽しく明るくマイペースで天性に任せてるところがあるのかなと思うし、そこも魅力ですけど、今のガールロックのブーム先駆けてるんだから、貫禄を示す側になっていきますよね。
32(20).Modern Vampire Of The City/Vampire Weenend (2013)

32位はヴァンパイア・ウィークエンド。いわゆるピッチフォークUSインディ・バンドの筆頭格ですね。2008年のデビューの時からいち早く成功。アメリカの若手のインディ・バンドじゃ有望株になりましたね。特にこのサードの頃は「イギリスはアークティック、アメリカはヴァンパイア」みたいな感じにもなってましたけど、まあ、その割に両者の差はだいぶついているような気もしないではありません。ただ、少なくとも2013年の時点では、このアルバムは彼らの一つの到達点でしたよね。ポール・サイモンの後継者的S
SWのフロントマン、エズラ・コーニグと、バンドナンバー2で類い稀なアレンジャーのロスタム・バットマングリ。この2人のぶつかり合いによるケミストリーが最も強く出たアルバムだと思います。デビュー当時のアフリカン・テイストだったり、ウェス・アンダーソンの映画のサントラを彷彿させるバロック・ポップ・テイストみたいにテイストそのものは初期から完されていたもののそこから骨太に進化した感じはしましたね。ただ、それがライブだとちょっとひ弱で、この時のツアー、ロラパルーザ・ブラジルで酷評されたりもしてたんですけど、そこから6年音沙汰ないままにロスタムが脱退。2019年の6年ぶりの新作「Father Of The Bride」はエズラのユーモアとウィットに溢れたストーリーテリングの手腕を存分に生かした作品でこれはこれで僕は好きでしたけど、デビュー3作で築き上げてきた支持層には複雑なものがあったかも。もうすぐ新作出るようですけど、そこでそれがどうなるか。エズラが、これまでの軌跡もどことなく似てるデーモン・アルバーンの域にまで到達できれば面白くなる気もするんですが。
31(44).2014 Forest Hills Drive/J Cole (2014)

31位はJコール。これまでの最大ヒット作の「2014 Forest Hills Drive」。これは9年前の12月に出たアルバムなんですけど、ビルボードでかなりのロングセラーとなっていて、Spotifyでも収録曲の「Wet Dreamz」「No Role Modelz」がかなり長きにわたりこうストリームを続けていることで定番作となっています。2010年代半ばからのヒップホップのユーフォリアで頂点のラッパーはもちろんケンドリック・ラマーで、他にタイラー・ザ・クリエイターやチャンス・ザ・ラッパー、チャイルディッシュ・ガンビーノが、とりわけインディ・ロックも聴いてる層みたいな人たちの好みで上がる感じがしてましたけど、忘れて欲しくないのはケンドリックのライバルといえばまずはJコールです。このアルバムが12月リリースだったことで年間チャートとかで盛り上がり損ねたというのもあるだろうし、サウンド的に特に目新しいいことをせず、オーソドックスなネオソウル系のヒップホップなので気づかれにくいとは思うんですが、彼の生演奏をバックにして紡がれる、社会的な意識の高い真摯なメッセージはヒップホップ・シーンにおいて信頼が置かれ続けています。例えて言うなら、140キロ程度のストレートでもキレとコントロールを生かしてエース級に活躍するピッチャーみたいなものですね。もう、安定のベストセラー・アーティストだし、浮き沈みに関係ない普遍的な表現を追求してるので、ヒップホップの売り上げも下がってきている昨今ですが、彼なら大丈夫だと思ってます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
