
沢田太陽の2010年代のベスト・アルバム 10位〜1位
どうも。
では、いよいよ2010年代ベスト・アルバム、残るはトップ10です。
こうなりました!

はい。僕ですね、今回、トップ10に関しては、ものすごく早く決まったんですよね。「もう、これしかないだろ!」くらいの勢いでパパッと。11位以下とは明確な差もあります。それくらい、迷うことなく選んだ10枚です。では、早速、10位から行きましょう。
10.Randon Access Memories/Daft Punk (2013)

10位はダフト・パンクの「Random Access Memories」。これは2013年に本当に大ヒットしましたよね。あの年のグラミー賞の最優秀アルバムも受賞しています。彼らにしてみれば7年ぶり、そして大ヒットということでいえば、あの松本零士のアニメで有名な「ディスカバリー」以来12年ぶりだったんですけど、あのマジックが干支一周りして帰ってきた感じがありましたね。ちょうど時代はEDMの真っ盛りでしたけど、このアルバムは、EDMが大嫌いだった人の溜飲を下げた側面もあったし、同時にEDMに夢中だった人も惹きつけた、みんなを包み込むような包容感があったとすごく思いますね。さらにいえば、現代のR&B代表でファレル・ウィリアムス、ロック代表でジュリアン・カサブランカス、そして70sエレクトロ・ディスコの先駆ジョルジオ・モロダーに70sにカーペンターズなどを手がけた名ソングライターのポール・ウイリアムスと、このアルバムは、ジャンルや時代さえも軽く超越している。実は最近、うちの7歳の息子もダフト・パンクにハマりつつあるんですけど、この誰もを取り込んで幸せにするオーラは、タイムレスなレジェンドのみが持ちうる特権ですよね。さらにこのアルバム、以前の彼らのアルバムでもそういうタイトルがありましたけど、どんなに未来を標榜する音楽であろうと、”結局は人間が作る音楽”なんですよね。そのことは、今作でバンド演奏を担当しているのが、この当時で50過ぎのベテラン・ミュージシャンたちということでもわかるし、そこに金光するヘルメットのロボットがほんの少しだけ未来的なタッチを加えるだけで、皆を魅了する魔法ができあがる。こういうハッピネスをもっと色々なアーティストから耳にしたいですね。
9.A Seat At The Table/Solange (2016)

9位はソランジュ。これは、フランク・オーシャンと共に、「新世代のR&B」の再定義をしたアルバムとして高いリスペクトを集めるアルバムですね。また、それを作ったのが、長年、あまりにも偉大なるエンターティナーの姉、ビヨンセの影に隠れ続けていた妹ソランジュというのも、ひとつの大きなドラマとして語られましたね。もともと彼女は、20歳そこそこだった2008年に、オールド・ソウル・テイストの隠れた名作を作っていたし、2010年代に入ったら今度はブルックリン界隈のインディ・ロックのライブに足繁く通うようになり、グリズリー・ベアやMGMTのライブにビヨンセやジェイZの足を運ばせていたりもして、その「趣味の良さ」はかねてから有名でした。ただ、彼女自身が鬱になりやすい傾向などがあり、それをなかなかアーティスト活動の中で発揮できなかったのですが、2016年、その才能がついに爆発しました。このアルバムで彼女は、ほぼすべての作詞作曲をこなすようになったんですけど、それはいうなれば、多彩なコードやハーモニーでおりなすタペストリーのような世界でしたね。1980年代くらいからどこか忘れ去られていた、R&Bのソングライティングの美学。そこにはスティーヴィー・ワンダーやマーヴィン・ゲイのような70sクラシックのみならず、ブルー・アイド・ソウルの元祖、ローラ・ニーロを彷彿とさせる瞬間もあったり。とりわけ90sのCD再発ブームの際に、そうしたソウル・ミュージックをあさり続けた僕のようなタイプの人にとっても、「ああ、それでこそソウルなんだよ!」と唸らせるものは十分にあったし。また、それを、一方でダーティ・プロジェクターズやTVオン・ザ・レディオといったブルックリン・ロックの友人たち、そしてもう一方で90sのオーガニック・ソウルのラファエル・サディークをコーディネイターに据え、ロンドンの新鋭サンファをゲストに迎えるなど、白人、黒人の人種バランスも絶妙。今後も古のエッセンスを本格的に現在に取り込んだ作品を期待しています。
8.AM/Arctic Monkeys (2013)

8位はアークティック・モンキーズの「AM」。このあるばむは、これまでイギリスにおける、おそらくオアシス以来の国民的ロックンロール・バンドが全世界規模のバンドに君臨することになった意味で極めて重要です。そして、それと同時に本作は、2000sに開花した「ロックンロール・リバイバル」の到達点でもあり、同時に今日まで。多くのロック・ファンが一斉に飛びついて共通で盛り上がることのできた、現状までだと最後のアルバムになっているような気がします。それくらいのビッグ・スケールのあるアルバムなんですけど、ほんとうにこれはブラジルでもすごくヒットしたアルバムで、「R U Mine」とか「Do I Wanna Know」「Snap Out Of It」あたりはラジオでも頻繁にかかってましたよ。これがここまでのヒットになったのは、彼っらのデビュー初期からのロックンロールが実験を重ねて強くなったことがあげられるでしょう。初期はそれほど顕著じゃなかったヘヴィなテイストが、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのジョッシュ・ホーミとの邂逅により渋みと重さが加わり、「Arabella」のような「21世紀のブラック・サバス」のような曲に発展もした。さらに、これまで以上にセクシーな彩りが自然に加わったのもいいですね。それはいうなれば、デビュー作のときに、シェフィールドの夜の退屈な町並みをさまよい歩いていたあのハイティーンの少年が20代も半ばになり、大人の恋をするようになるんだけど、それもいささか面倒な様が「Why'd You Only Call Me When You're High」みたいな曲で皮肉っぽく描かれている様も、デビューからのストーリーが続いているようで、そこも嬉しかったりもして。彼らがもしこのまま、次も似たような路線でアルバム作れば間違いなく現在のロックンロール・キングになっていたと思うのですが、やはりそこは3枚目で「Humbag」みたいなひねくれた作品作る彼らのこと。続く「Tranqility Bass Hotel & Casino」は彼らなりの「ペット・サウンズ」作って不評(僕は好きですが)だったりもして。ただ、そういうところも魅力なのですが。
7.Currents/Tame Impala (2015)

7位はテイム・インパーラの「Currents」。オーストラリアという国は現在もっともクリエイティヴな音楽を作るところで、それ故、ロックにとっても、停滞が叫ばれている中、優良な存在が相変わらず高い頻度で登場してくるわけですけど、言うまでもなく、彼らはその最高のロール・モデルですね。いきおい、サイケサイケだと言われがちな彼らですが、僕が最初に彼らに注目したのはメロディメイカーとしてです。それは2010年のデビュー作からの「Solitude Is Bliss」。90s、00sと、ロックやR&Bが重低音主体のグルーヴ志向になる中、コード進行の妙みたいなものを軽視するようになった世において、ブルー・アイド・ソウルとか甘ったるくなりすぎる前のAORに通じる70sの職人的ポップ・センスを感じさせて。2012年にサンパウロに単独ライブで来たときにはトッド・ラングレンの名作「A Wizard A True Star」の冒頭の名曲「International Feel」のカバーまでやって。そのトッドのアルバムは、それまでシンガーソングライターのイメージだった人が急にモーグ・シンセサイザー持って未来を志向したアルバムだったんですけど、その精神性はまんまケヴィン・パーカーに継承されたような、そんな感じでしたね。ただ、そのイメージだけだと2012年の「Lonerism」で止まりかねなかったかもしれなかったんですけど、その次のこの本作は、そんな次元をとうに超えてましたね。冒頭の1曲で、彼ら最高の代表曲と言って過言じゃない「Make It Happen」をはじめとして、彼らはクラブのフロアでのロング・プレイと、プログレ的な空間的広がりを取り入れることで、ビッグ・スケールのサウンドが強いグルーヴ感を持って表現できるようになりましたね。しかも、スウィートなメロディと、相変わらずのオーガニックな生のスネアドラムは残したままで。それはさしずめ、「ELOとピンク・フロイドと今日のエレクトロ・ミュージック」が融合したようなスケールの大きな趣で。これを仮に進化させ続けることができたら、彼らは間違いなくロック界の伝説として残るはずです。
6.St.Vincent/St.Vincent (2014)

6位はセイント・ヴィンセントの2014年の、セールス的にも大躍進したセルフ・タイトルのアルバムですね。いろんな2010sのオールタイム・リストを見ていると、ヴィンセントって、ランクインはしているんだけど、上位ではないことが目立ってるんですが、僕はそれが大いに不満ですね。彼女こそ、2010sのロックを象徴する大きな存在だと思っているので。だって考えても見てください。一体、これまで、いつの世の中に、「ロックにとっての最大のトレードマーク」であるエレキギターに「ヒロイン」なるものが存在しました?いつだって、ギターは「ヒーロー」たちが独占してきたじゃないですか。ついに「ギター・ヒロイン」が、10年という長い時間で見ても、ギタリストの中でトップに君臨できる時代が来た。これはもっと、声を大にしてアピールするべきポイントなんじゃないかな。この功績を持って、彼女は一生、後続の女性ギタリストたちから「扉を開けてくれた」と感謝され続けることになると思いますよ。本作は、そんなセイント・ヴィンセントことアニー・クラークが、ギタリストとしてのみならず、ヴォーカリスト、サウンド・クリエイターとしての力を絶頂に発揮した1枚です。エイドリアン・ブリューやプリンスの影響が感じられるフリーキーなトーンが、エレクトロやホーンによるファンキーなグルーヴとより濃厚に絡むようになるんですけど、そこにはセクシャルな妖艶さも、ロボティックな奇妙な近未来性も、クールな佇まいの中にふと垣間見せるユーモアのセンスもあり。そうしたことは「Digital Witness」「Rattlesnake」「Birth In Reverse」といった曲に顕著ですけど、それはこのときのツアーではよりハッキリしてましたね。オートクチュールのタイトなミニのドレスに身を包んだ彼女が、ギターを縦横無尽に弾きながら、キーボードのトコ・ヤスダと揃いのダンスをキメる、細部に渡るまでとことんモードなロック・ショウは、男性中心だったこれまでのそれに一石を投じる新しいステージのあり方さえ示していました。
5.Blonde/Frank Ocean (2016)
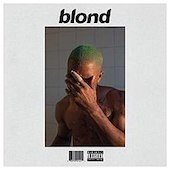
5位はフランク・オーシャンの「Blonde」。ジャケ写では「Blond」になってて、これも細かい話題になってましたけど。このアルバムは、「Channel Orange」から4年ぶりのアルバムではあるんですけど、本作の直前には、「Endless」という、オリジナル曲で構成された映像作品も出したりもして、その類まれな創造性が話題になっていましたね。この本作ですが、本当にこの人というのは独特の立ち位置のクリエイターで文章にするのが難しい人ではあるんですが、ますます独自の方向性に行きましたね。「Channel Orange」のところで僕は、「スティーヴィー・ワンダーのフォロワーかと思思ったら、次の瞬間には最新のテクノロジーで今っぽい音楽作ったりしてる人」と書きましたけど、ここでは、その2つの要素が合体した感じですね。凝り性な彼は、ファーストでの多彩なコード進行をもとに、より高度なポップ・センスを発揮した曲の数々でR&Bのソングライティングを更新(ここに関しては同年に出た前述のソランジュも同様)しているのですが、そのやり方がとことん「未完成な余白」を残してるものでもあって。アコースティック・ギターや、モーグ・シンセサイザーの使い方にあえて生々しさを残していたりもして。でも、「ロウファイ」と呼ぶには、音そのものはあまりに高度に洗練されていて、それどころか作品クレジット見れば、「どれだけ人件費かけたんだ?」と言いたくなるくらい、40〜50人規模のミュージシャンが参加していたりするし。それはあたかも、「世界一お金をかけた高級デモ・テープ」のような趣で、そんな作品は後にも先にも、これでしか聴いたことがないですね。それくらい、不思議な聴感を本作は与えてくれます。この不思議なミックス感覚、今後、真似る人が出てくるような気もしますが、これはちょっと模倣は難しいでしょうね。それよりは素直に、「ソングライティングのソフィスティケーション」の再評価を進めたような「Pink + White」「Solo」「Night」「White Ferrari」といった彼の曲作りから何かを学んだほうがいいような気もします。
4.A Brief Inquiry Into Online Relationships/The 1975 (2018)

4位はThe 1975の昨年の今頃に出たサード・アルバムです。ジャケ写が遠目だとわかりにくいの、当時から指摘されてましたけど、白地バックだと本当に見えにくいですよね。29位にあげた前作で、他のインディ・ロック・アーティストが歴史の中で見落としがちなポップ・エッセンスをもとに、独自のロックを形成しはじめた彼らでしたけど、このアルバムでは、もちろん、そこの部分はしっかり残しつつ、本作は、もう、そんな次元はとうに超越した、スケールの大きなアルバムを作ってしまいました。マティいわく「レディオヘッドでいうOKコンピューターとか、ザ・スミスでいうところのクイーン・イズ・デッドみたいなアルバムを作りたい」という発言がレコーディング中にあったんですけど、いやはや、有限実行ですね。ここでの彼らは、言うなればこれ「The 1975版のロンドン・コーリング」を作ってしまいましたね、これは。ロンドン・コーリングというクラッシュの大作が、パンクから、レゲエから、ジャズからロックンロールとジャンル横断した作品でしたけど、ここでの彼らは前作に築いたポップ・テイストのみならず、ハウス、トラップ、エレクトロ、オールド・ソウル、フォーク、スタンダード・ジャズ、そして初期レディオヘッドにまんまトライしたようなギターロックに至るまで、1時間を超える時間に、彼らがそのときに編み出しうるすべての音楽を詰め込んだアルバムを作ってしまいました。しかも、その中には、最近の世のケイオティックな動乱ぶりを描写したポリティカルな名曲「Love It If We Made It」があり、それが、今まで彼らのような存在を絶賛したことがなかったピッチフォークで「年間ベスト・トラック」に選ばれるほど評価もされたり。「多様性がある上に、社会に対してのメッセージも評価されるようなセンスでやってしまえる」ということになれば、時代をリードできる大物の座がそこまで近づいていると言っても過言ではないです。本当に、今後に目が離せないバンドになったものだなとつくづく思います。
3.Lemonade/Beyonce (2016)

3位はビヨンセの、これが最高傑作と呼んでいいでしょう。「レモネード」。32位にランクしたこれの前作「Beyonce」で彼女が「母親になったからといって終わりじゃない」と一念発起して、これまで以上に実験的で、かつ、自分の内面の本音にもっとも近い作品を作ったと書きましたが、ここでの彼女は、もうR&Bの領域を超越して、「ポップ・ミュージック全体」での視点で、自身のマックスに挑戦しようとした意欲作ですね。それはいわば、マイケル・ジャクソンがあの「スリラー」で挑戦したのとほとんど同じ地平ですね。それくらいの野望を持って作品を作る黒人アーティストが遂に30数年ぶりに現れた、ということなんだと思います。参加陣も、Mike Will Made It、ディプロ、Hit Boyと、それだけでアルバム作っても十分にかっこいいR&Bならできたメンツがいる上に、そこにプラスして、ジェイムス・ブレイクはいる、ウィーケンドはいる、ケンドリック・ラマーはいる、さらにはジャック・ホワイトはいる、その上、ファーザー・ジョン・ミスティやヴァンパイア・ウィークエンドのエズラまでいたりもする。このメンツ見ただけでもうクラッとするものがあるんですけど、そこに、2010sになっても止むことがなかった黒人への警官の暴力への怒りを込めた力強いファンキー・ナンバーの「Formation」から、ケンドリックと共に60sの「ブラック・イズ・ビューティフル」のスピリットの継承宣言を行ったような「Freedom」、家族の結束を「ブラック・カウボーイ」の再評価の意味も込めてあえてカントリー的な手法で表現した「Daddy's Lesson」、そして夫ジェイZの浮気に傷ついた気持ちを昇華させ、彼女史上、最高のラヴ・バラードとなった「Love Drought」に至るまで、楽曲の幅も、ストーリーのドラマ性もバラエティに富んでいるのだから、注文のつけようがありません。これは本当に、稀代のエンターティナーのひとつのピークだと思います。
2.Born To Die/Lana Del Rey (2012)
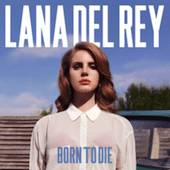
そして2位にはラナ・デル・レイの「Born To Die」。これをあげたいと思います。これはもう、まず、2010年代が起こした「最大の批評上のミステイク」。まず、これで語られますね。「サタディ・ナイト・ライヴ」で本作リリース直前にパフォーマンスを行ったら、歌唱力の低さをメディア中にn攻撃され、本作もたちまち酷評の嵐になりました。ところが、彼女のファンにとっては、そこで叩かれたことが反骨のバネとなり、彼女の歌いかける絶望感や不安感が彼らの心の隙間に入り込んで心を揺らしたことで、このアルバムはカルト評価を獲得。それは、ビルボードのアルバム・チャートにおいて、300週、6年以上にわたってトップ200にランクインし続けるという、驚異的なロングヒットになり、以後も彼女は、「世界一熱狂的な固定ファン」を国際的に集める、この時代を代表する稀有なアーティストになりました。もう、このカルト評価だけでも十分評価に値するんですけど、彼女がここで提示したメランコリックでダークな世界観。僕はこれ、今の時代の雰囲気を絶妙に暗示していたような気がするんですよね。これが出た当時って、オバマ政権の真っ只中で、リベラルな感覚が世の中心として受け入れられてはいました。ただ、なんとなく不穏な時代の空気というのはあって。警官による黒人の暴力が裁判で軽視されて大問題に発展したのはこれから間もないことだし、世界はテロへの恐れから閉鎖的な心情が世に広がり、やがてはアメリカでのトランプ政権をはじめ多くの極右政権を生み、さらにはヘイト・スピーチなるものまでが現れるようにもなって。彼女の前にも「エモ」が世に同調できない少年少女の心情を掴んでいたものでしたけど、ラナのここでの「National Anthem」などをはじめとした「古きアメリカ」への憧憬も、「保守に戻りたい」という意味ではなく、何かが失われ、決して幸せで楽観的な気分にはなれない今の世の暗示だったのかなと。その意味で、これ、今の方がさらに時代のサントラになりうるし、それはここ最近の彼女の作品を補足的な意義付でとらえるとさらに深くなるはずです。
1.To Pimp A Butterfly/Kendrick Lamar (2015)
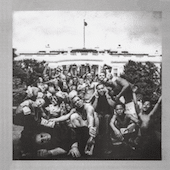
そして1位はもう、これしかないですよね。ケンドリック・ラマーの「To Pimp A Butterfly」。この10年において、これ以上のゲーム・チェンジングな作品、ないですね。12位で紹介した「Good Kid MAAD City」で、荒廃したコンプトンのような街で、正気を保ってラッパーとして生きていく決心をした自分の半生を頭から最後まで巧みにドラマ化したことで、ヒップホップが単なるマネーゲームでなく、人生や社会を語るものでもあったことに立ち返らせたことはかなりシーンそのものを動かしたようにも思うのですが、ここでのケンドリックはそれをさらに大きな次元で進め、「黒人カルチャーそのものの意識の高揚」の次元にまで高めています。それはひとつは、本作でのJAZUやソウルへの接近ですね。これによって、黒人が音楽でどういう歴史をたどって来たのかのメッセージが無言のうちに込められているし。そしてもちろん、それ以上に重要なのはリリックで。まず、冒頭でPimpという概念を使って「成功によって、白人によってたかられ利用されること」への警鐘をうながし、名曲のひとつ「King kunta」では、70sに現象的ヒットとなったTVドラマ「Roots」で有名になった18 世紀の黒人奴隷、クンタ・キンテの、高貴な反抗精神をたたえています。その後は、どこか「」やはりダメなんじゃないか」と、自身に不意に襲いかかってくるネガティヴなフィーリングとの自己葛藤の姿が描かれるんですが、この世代最大の代表曲にもなった、「過去には失敗もしたけど、大丈夫」という「Alright」、そして、アルバムのクライマックスで歌われる、自分という存在に対しての強い肯定性を歌った「i」など、「黒人」というより、「人間そのもの」のひとつの克己を歌う讃歌になってます。本作は、トレイヴォン事件以降、黒人社会内で不安と怒りが葛藤した世の絶妙なサウンドトラックにもなったのはもちろんのことなんですけど、この世代なりの新たな「ブラック・イズ・ビューティフル」を高めた一作だったと思います。そのケミストリーは僕の周囲の音楽ファンでも起きてますよね。だって、インディ・ロックしか聴いてなかったような人がたちまちヒップホップに夢中になって、本作に参加しているジャズのアーティストの活動とかまで追うようになってるんだから。そんなことを引き起こした黒人アーティストって、過去にいた記憶、ないんですよね。マイケルとも、プリンスとも、そこのところは微妙に違うというか。そう考えても異形なんですよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
