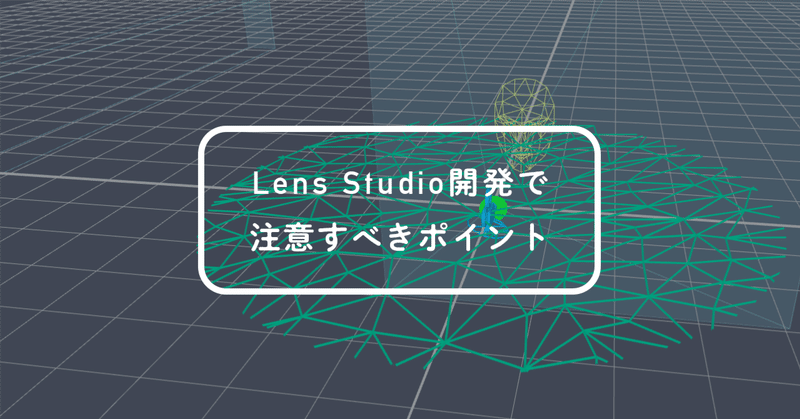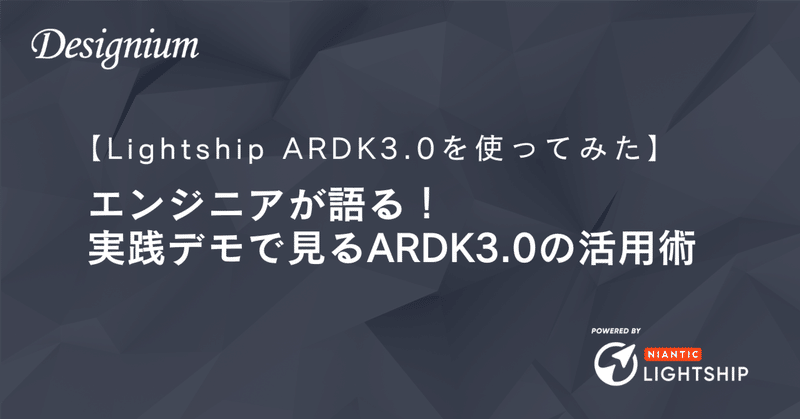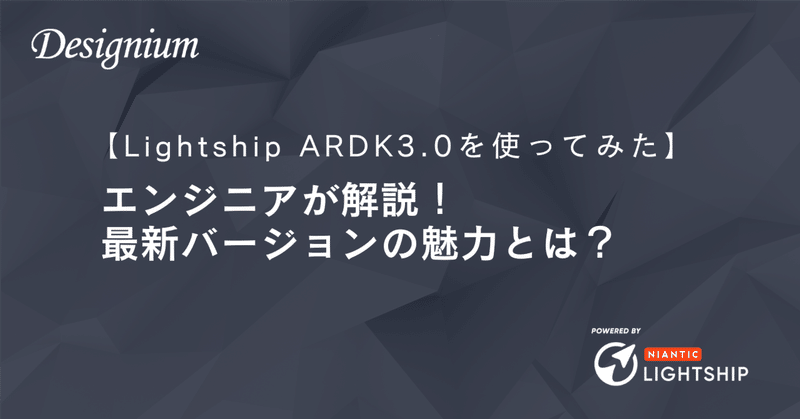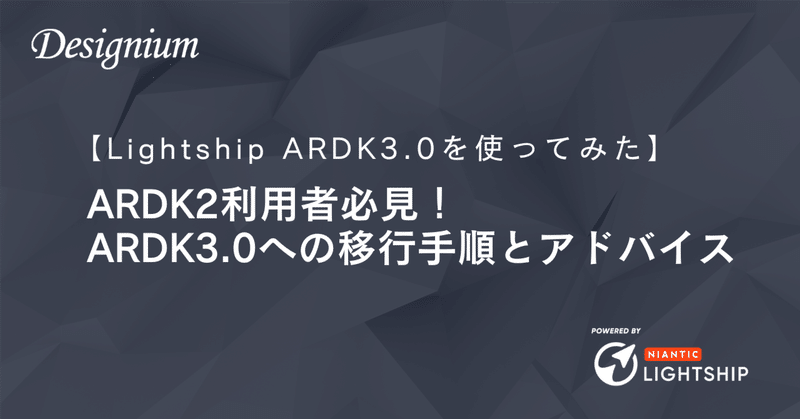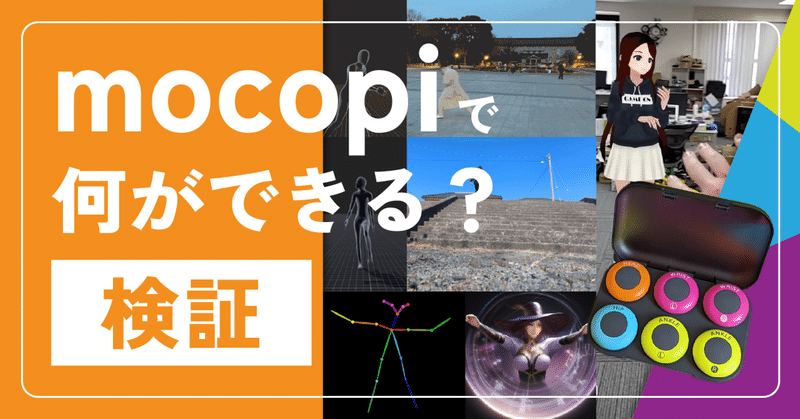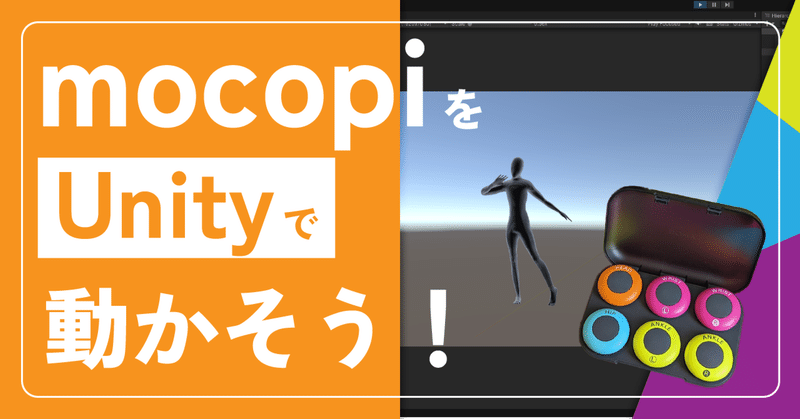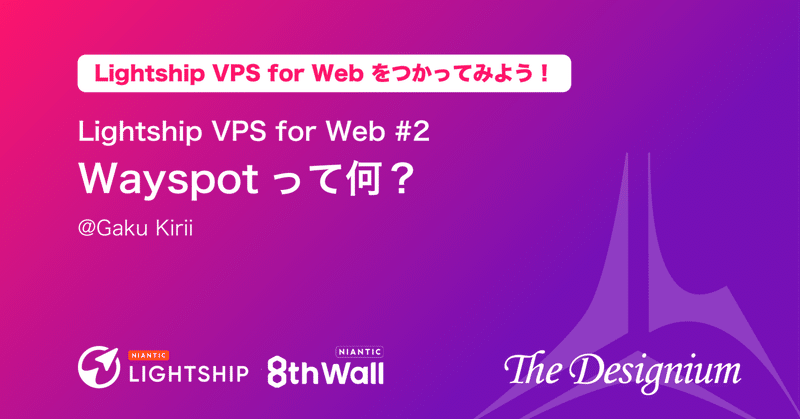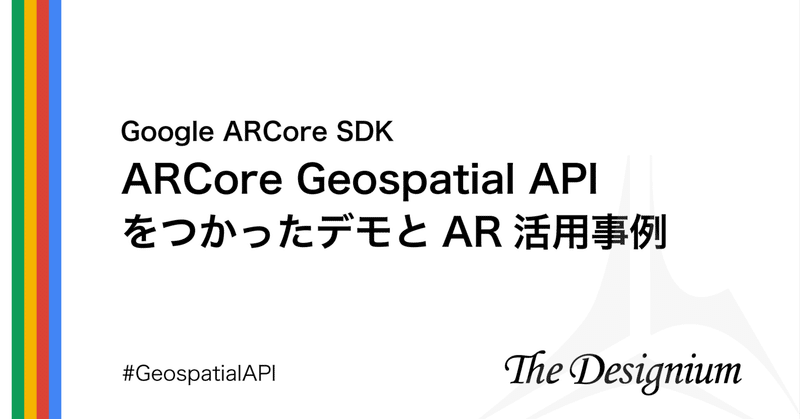#Unity
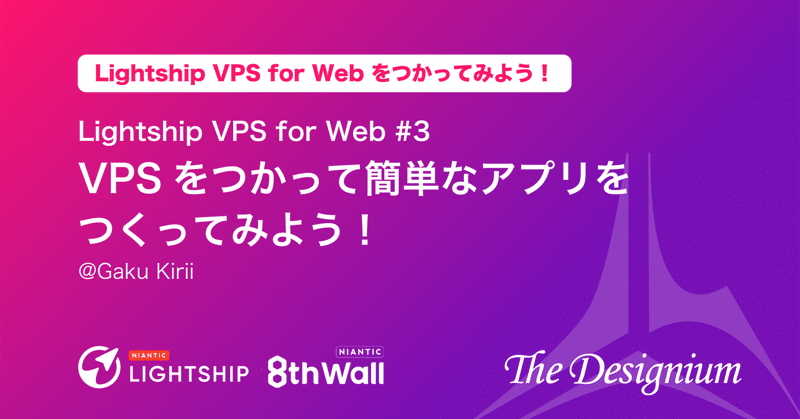
【Niantic Lightship VPS for Webをつかってみよう!#3】 VPSをつかって簡単なアプリをつくってみよう!
こんにちは、デザイニウムの桐井です。 前回の記事では、8th WallのWayspotやWayspotの追加方法、既存のExampleについて解説してきました。 今回は、実際にVPSを利用して簡単なアプリを作成してみましょう。 前回紹介した8th Wallの公式のExampleは、A-Frameを利用したものとなっています。私が使い慣れているという理由から、今回はThree.jsを利用して実装していきたいと思います。 アプリ作成の準備はじめに、以下のプロジェクトをクロー
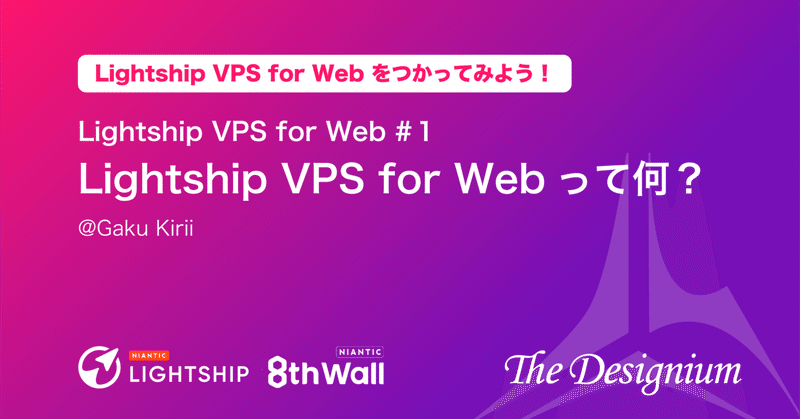
【Niantic Lightship VPS for Webをつかってみよう!#1】 Lightship VPS for Web って何?
はじめまして、デザイニウムの桐井です。 今回から3回にわたって、8th Wallに追加された新機能、『Lightship VPS for Web』についての概要や開発方法、実際のアプリ開発についてご紹介していきたいと思います。 VPSとは?VPSについては、弊社エンジニアの記事がとてもわかり易いので下記を参照していただきたいのですが、こちらでも簡単に説明させていただきます。 VPSとは、Visual Positioning System の略称で、スマホを通して得た視覚情