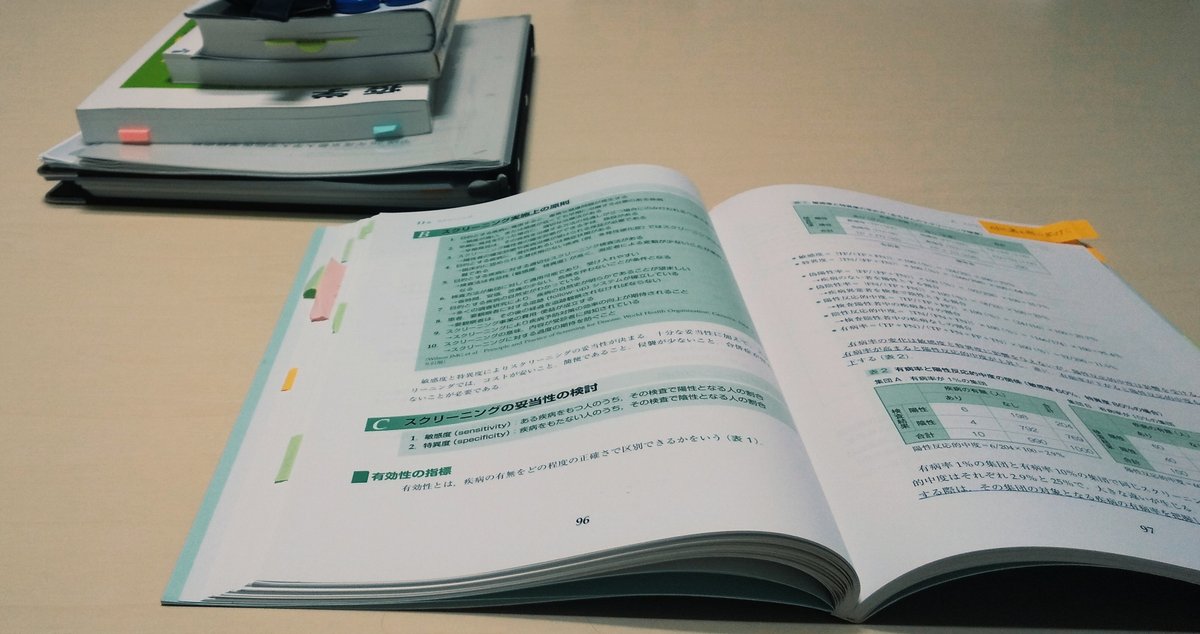
公衆衛生大学院、ことはじめ。
公衆衛生とは共同社会の組織的な努力を通じて、疾病を予防し、寿命を延長し、身体的・精神的健康と能率の増進をはかる科学・技術である。(C.E.A. Winslow; WHO)
はじめに
2020年4月より京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻専門職学位課程(MPH: Master of Public Health, SPH: School of Public Health)に社会人学生として進学することとなりました。受験が2019年9月でしたので、その後日々の業務にかまけて当時の記憶が薄れつつあるのを感じ、将来壁にぶち当たった時などに初心を思い出せるようにという個人的な側面と、同じ業界でキャリアに悩まれている方々への激励や実例の提示という側面で、本記録を文字として残そうと考えました。あくまで一例でしかなく、私の背景因子が結果に影響していることが強く予想されますので、ご参考にとどめていただければと思います。
私の背景情報について一応ぼかしておりますが、読む人が読めば筆者を特定可能かと思います。記載内容に問題があれば直接ご指摘いただけるとありがたいです。
なお、本文ではPublic Healthの訳語として、一般的な「公衆衛生学」ではなく、当該専攻の名称に倣って「社会健康医学」と表現します。
自己紹介
京都大学大学院薬学研究科修士課程修了、修士(薬科学)。現職では医薬品の市場分析や開発計画策定などに従事。統計解析ソフトRとMySQLチョットデキル(あんまりできないので勉強中)。MPHは2つめの修士課程となります。
MPH合格までのスケジュール

志望動機
そもそもなぜ当該専攻に進学しようと考えたかというところから始めたいと思います。最初のきっかけは「臨床統計家育成コース」のポスターをみかけたことでした。私は京都大学大学院薬学研究科の修士を修了後、臨床開発職としてキャリアをスタートしております。そのため、修了後も頻繁に京都大学には伺っていて医学研究科の掲示板でこのポスターを見かけ、ちょうど臨床試験の計画段階から臨床統計の専門家の重要性を実感しつつあったこともあり興味を持ち始めました。
最終的な進学先は「臨床統計家育成コース」ではありません。従ってこれからの記録は京大SPHの2年制MPHに関する一般的な内容であり、特定のプログラムの内容ではありません。
また、当時の状況として、ICH統計ガイドライン改訂の議論が進んでいたことに加え、FDAのReal World Data利活用に関するDraft Guidanceが発出されるなど、海外においてはビッグデータや日常診療データを活用した医薬品開発の基盤が議論され整備されつつあったこともあり、この枠組みによって臨床開発の位置づけは大きく変わるのではないか、また将来的な医薬品開発の方法としてRWD解析が取り入れられた際、生物統計学や疫学の知識は必須要件になるのではないかと考えました。
グローバル化によって世界がシームレスにつながることで、海外の状況がすぐに日本でも反映されるとはようになってきたとはいえ、医薬品業界は比較的規制の強い業界であり、日本の規制当局がデータの品質を重視しながらRWDを医薬品承認申請に取り入れるにはもう少し時間がかかるであろうと考えましたので、出遅れた感はあるものの、時間的余裕のまだ残っている段階でなるべく早く必要なスキルを身につけたいと考えるようになりました。
このような考えを勤務先の役員の方にご相談したところ、積極的にご支援いただき、会社からの派遣という形で大学院へ進学することができました。
MPHのある大学院の検討
会社からの支援を受けられそうだという段階では、私の興味のあるテーマについてご相談させていただくため、主として当該専攻の複数の先生方にご連絡させていただき、短期間でかなりの先生方とご面会し、ご意見を頂戴することができました。
私の場合、先生へのアプローチで躊躇することは無いのですが、どこの馬の骨ともわからない人間を好意的に受け入れてくださり、ともすれば夢見がちなことを口走ったりする私にそれぞれの専門性の観点から多角的にご意見をくださった先生方には感謝してもしきれません。この場を借りて御礼申し上げます。
いくつかある公衆衛生大学院の中から京都大学を選択したのは、ただ単に母校であるというだけではなく、統計学などの学問領域と臨床との連携を重視していると感じたからです。
製薬業界で働く以上、評価項目の選択などを議論する際に医学的な知識は必要になりますし、その他にも臨床薬理や製剤学、薬理学などの薬学的な知識に立脚して試験デザインや解析方法を議論する必要があると考えています。それぞれの学問だけに特化するのではなく、ある意味学際的に必要な知識を集約するという点で当該専攻の方針は素晴らしいと考えました。
また、当該専攻は専門職大学院ですので座学中心とされていますが、実は研究を重視している、というより研究が中心と言っても過言ではないところも強みかもしれません。実際、ある分野では修了後一定期間経った後も論文が出ていなければ除名処分になるとのことです。
MPH受験勉強
志望校も決まり、さて受験勉強をしようかと思いましたが、社会健康医学というもの自体が非常に多くの学問領域を含むため、何を勉強していいのか、何から手を付けていいのか全く分かりませんでした。とりあえず過去問を参考にしようと考え、実際には以下の通りの進め方で勉強しました。

まずはじめに、院試の過去問から傾向を読み解こうとしましたが、私にそういうセンスがないのか、10年分遡ってもあまり傾向といったものが見えてきませんでしたし、そもそもこの問題は社会健康医学なのか、完全に実務じゃないかという問題もあり、個人的には勉強の方向性に混迷を極めていました。
そうこうしているうちにオープンキャンパスがあり、その際に博士課程の先輩から教科書として「疫学 – 医学的研究と実践のサイエンス –」を勧められ、ひとまず思考停止してその教科書を体系的に勉強し始めることとしました。

さらに基本的には各研究室の先生方が自身の興味や専門性に沿った問題を作成されると予想されたので、当該専攻の先生方の書かれた論文や書籍を読み漁りました(末尾、参考書籍一覧参照)。
さて、一通り教科書を勉強したのち、過去問の回答案を作成し、理解不十分なところは再度勉強することで、出題された領域の周りについては理解を深めました。
その他、学会やセミナーにも積極的に参加しました。結果、お金が無くなりました。
当該専攻の出題は非常に多岐にわたるトピックを含み、疫学や統計学のみならず、医薬品開発に関連する問題や知的財産の問題も出題されます。しかしながら、一般入試は3問、社会人特別選抜では2問を選択して回答するため、ある程度的を絞って対策する方が良いと思います。
毎年同様の方向性の問題が出題されているものもありますが必ずしも出題されるとは限りませんし、ひねろうと思えば難しくもできるような問題も多いので、回答する問題+αで対策するのが良いのではないでしょうか。
京大MPH選考試験
試験は筆記試験(一般3問選択、社会人選抜2問、その他コースにより選択する問題が異なる)及び英語(TOEIC等の外部試験スコアを提出)、口頭試問で構成されています。
結果として、筆記2問選択のうち1問は満点、もう1問は8割程度でした。面接ではあまり難しいことは聞かれていなかったと思うのですが(詳細は開示してはいけないと思うので書きません)、なぜか8割程度だったので、どう答えれば満点だったのか未だにわかりません。なお、英語はTOEICのスコアを提出し、スコアは950点です。
受験で得たもの・学んだこと
受験を通して得られたことや学んだことは非常に幅広いものでした。実際に受験勉強を始めてみると、疫学の考え方は非常に新鮮で、薬学部時代から論文の批判的吟味には自信があったものの、臨床試験に関して様々なバイアスの種類やそれに対処するためのデザインを知ることができ、今でもプロトコール作成等の実務に直接役立っています。
参考書から学んだ知識以外にも、社内調整や根回し、自分の考えの伝え方やプレゼン・資料作成など実務でも役立つ内容を多く学ぶ機会に恵まれました。こういった経験を積めただけでも非常に有意義であったと考えています。
さらに、自分で考えることももちろん大切ですが、すでに考案されている様々な試験デザインや解析方法を知り、先人たちの巨人の方に乗ることから始めることが重要であると再認識しました。人生、常に勉強ですね。
また、業界の将来や製薬業界にとどまらない自身のキャリアや生き方について改めて考え直す良いきっかけになりましたし、それに付随して関連する政策や業界団体の動向について調べるきっかけにもなりました。受験を通して全体的にキャリアの幅は広がったように感じています。
総括
大学院進学というプロジェクトにおいて、受験や合格はマイルストーンの一つでしたが必ずしも最終目標ではありません。入学後も試験や研究、修了と様々なマイルストーンが待ち構えていますし、そもそも大学院自体も人生の大局から見るとあくまで一つのマイルストーンに過ぎないのではないでしょうか。

と、まぁそれっぽいことを書きましたが、長期的なマイルストーンを定めた上で、それを目指して一歩ずつ短期的なマイルストーンを定め、適時長期的なマイルストーンを基に軌道修正しながら進むしかないのかなと思います。この選択が良い方向に進むかはわかりませんし、自分の努力が大きな要因になるとは思いますが、少なくとも今の段階では新しい人生のスタートラインに立てたことを素直にうれしく思っています。
最後になりましたが、このような年次の浅い者の突飛な発想を受け入れご支援くださった会社関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。また、将来展望について議論させていただいた役員や上司の皆様、当該専攻の先生方、そして友人の皆様にも、心からの感謝を述べたいと思います。
参考書籍一覧
必ずしも以下のすべては必要ではないと思います。特に京大SPHでは考えさせる問題が多いので、それほど用語や数字などを覚えることもありません。こういうところが東大と違った特色でもあり、個人的にはとても好きな部分でもあります。各参考書の解説は要望があればするかもしれません。
・疫学 – 医学的研究と実践のサイエンス –
・はじめて学ぶやさしい疫学(改訂第3版)
・ロスマンの疫学
・読んでわかる!疫学入門
・公衆衛生がみえる 2018-2019
・CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛生2019
・クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説2019 vol.6 公衆衛生
・日本4.0 国家戦略の新しいリアル
・医療ビッグデータがもたらす社会変革
・ヘルスケア産業のデジタル経営革命
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
