「もしも」から運動を考えてみることがバイオメカニクスの理解につながる
普段講義をするときに、いくつか「もしも」の質問をします。例えば、
・もしも宇宙空間に自分が存在するとしたら、隣に一緒に浮かんでいるおばあさんとどちらが早く前方にあるゴールにたどり着けると思いますか
・もしもあなたがロボットを作るとしたら、目の前の段差を乗り越えるのに必要な身体機能はどういったものですか
・もしも今バスケットボールをしていて、シュートのリバウンドを取るためにジャンプ中だとしたら、今から着地地点を選べますか
こういった質問をなぜするのかというと、普段、わたしたちが自分の持っている身体をあまりにも当然のごとく動かして運動しているので、それに疑問を投げかけるため、です。
目の前の運動がどういった仕組みによって成立しているのか、そのことを理解しないと、目の前の運動を改善させることはできません。バイオメカニクスは物理の力学という分野を身体運動に応用して考える学問ですが、それはつまり、身体運動をわかる前に「物」がどうやって振る舞うか考えてみよう、ということなのです。
人間の身体も「ひとつの物体」だからです。
ひとつ考えてみましょう。
片手を、高くあげます。そこから、片手を下ろすのに、一番速い方法は何ですか。
答は、腕の力を抜く、です。
それは、なぜでしょうか。重力によって落ちるからです。
つまり、「腕を上げている」という行為は、重力に逆らって筋力を働かせる行為なのだ、ということです。腕を上げる、下げる、という単純な運動でも、重力の影響があるのだとしたら、歩く、走る、はどうでしょうか。
例えば歩くときに「足を前に出す」という運動があります。(もちろん足を前に出さなければ前進できません。)そのときに、足を前に出すために行っている運動というのはどのようなものでしょうか。
外から運動の様子を観察してみると、このとき一番大きく動くのは股関節だと思います。
股関節の伸展(下肢が身体の後方にあるように股関節を動かしている状態)から、股関節の屈曲(下肢が身体の後方に来るように股関節を動かす状態)まで、この動きが歩幅を決定しています。
では、足を前に出すときには、終始股関節を屈曲させる筋力が大きく働いているのでしょうか。
考えながら、数歩、歩いてみてください。
また、たくさん歩いたときに、股関節の屈曲筋である腸腰筋や大腿直筋が疲労するか、想像してみましょう。
実は、股関節の屈曲に働く筋は、足を振り出す最初の部分で少し活動するだけで、振り出しの後半には逆に「働かない」のです。
では、何が足を前に出しているのか?
それは、「慣性」です。慣性とは、物体の運動が「そのままの運動を続けようとする」ことをいいます。質量のある物体は、止まっているときは止まったままでいようとし、動いているときは動いたままでいようとするのです。
わたしたちの身体は質量(重さ)を持っていて、一度動き出すと止まるためにも力が必要です。
歩行中の下肢は、『直前に下肢を蹴り出した足関節を底屈する力』と、『振り出しの最初に少しだけ働く股関節の屈曲の力』で動き出し、その後は慣性で前方へ振り出されるのです。
このことを、「もしも」を使って検証してみましょう。
もしも、足関節が底屈できなかったら、歩行はどのように制限されるか。
足関節を、底屈できないようにテープや包帯で固定してみましょう。底屈させるための筋を麻痺させれば直接的な検証ができますが、それはできないので、筋力を働かせた結果起こる現象を抑えてしまおう、ということです。
さて、下肢を前に振り出すことはできましたか。
ここから先は
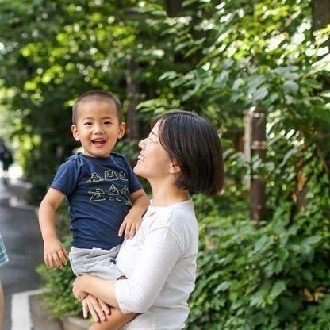
Movement Lab @ SOM IES
School of Movement®︎での講義の際に様々な質問をいただきます。質問を整理し、議論を公開し、更に感想をいただけるような場とし…
