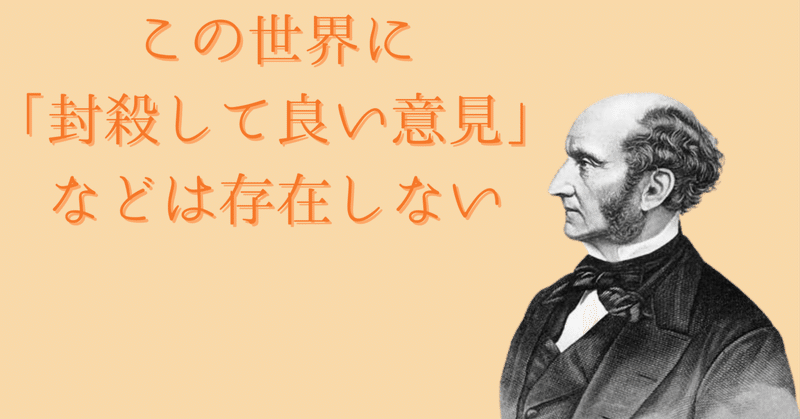
メインチャンネル『自由論』の書き出し文
◻︎提供スポンサー
◻︎本文
ジョン・スチュアート・ミルは19世紀イギリスの政治哲学者です。功利主義の創始者であるベンサムの友人であった哲学者ジェームズ・ミルの長男として生まれた彼は、父親からの英才教育によって小さな頃からメキメキと頭角を表します *1
彼の自伝によると、3歳の頃には古代ギリシア語を学んでいて、8歳の頃にはヘロドトスの著作(『歴史』)を読破したらしいです。わけがわかりません *2
ミルの生きた19世紀は激動の時代でした。
ヨーロッパでは、フランス革命の影響により自由主義とナショナリズムが広がり、ドイツ・イタリアなど、新たに統一された強力な国家が誕生します。
特筆すべきはワットによる圧縮蒸気機関の開発です。これによって石炭の産出量が爆発的に増大し、いち早く工業化に成功したイギリスは世界の覇権を握りました。アジアやアフリカにとっては苦しい時代ですね。日本においては19世紀の中頃、ペリーが浦賀に来航し江戸幕府はやむなく開国を認めました。19世紀末になると資源力に優位性があるアメリカが台頭し、イギリス一強の時代は終わり、列強同士の植民地争奪戦が勃発します。
ミルは、イギリスの隆盛とその後の混乱を経験しました。当然、社会制度や世間の常識もそれに伴って変化し「自由」に対する解釈も都度変わっていったわけです。そんな世界の中で、彼は政治哲学だけでなく、論理学や経済学にも非常に大きな影響を与える仕事をしました*3
そんなミルが著した『自由論』
この著作では「社会が個人に対して正当に行使し得る権力の本質と諸限界」が検討されます。個人にはなにかしらの”自由の領域”があり、その内側の領域を、外側の領域を検討することで浮き彫りにしていくというアプローチですね。
結論から言うと、ミルはこの”自由の領域”を
個人が個性を発揮し、他者を害さない範囲で自身の幸福を追求すること。
と定義します。
この定義の裏には功利主義的な前提があります。功利主義とは、社会全体の効用を第一とする考え方です。行為の目的や義務、善悪の基準を社会全体の「最大多数の最大幸福」をもとに判断する立場ですね。つまり、個人の自由は社会全体の功利を損なっていない範囲において絶対的に担保されるべきだ、と言っているわけです。
功利主義的なミルの自由論は、アナキズムや自由放任主義ではありません。だから、社会全体の功利のために政府が規制を行うことを全然否定しません。むしろ彼は政府における規制よりも、社会におけるそれの方を危惧しました。
もともと”自由”は、国民と政府の間で問題になっていたテーマでした。専制的な政府と、それに支配される国民。両者の利害を”自由”という観点で折衷すること。それが”自由”にとっての重要なテーマだったのです。この辺りについて論じたのがホッブズやルソーです。
しかしミルの時代には、民主主義国家が台頭し始めます。すると、国民が政府になるわけです。それによって、政府による国民に対する抑圧だけでなく国民同士による相互の抑圧が問題になってきました。ミルはこの抑圧のことを「多数者の暴虐(専制)」と呼んでいます *4
人々の自由を担保するためには、政府による権力の濫用だけでなく、多数者の暴虐に対しても何らかの対策を講じなければなりません。
もう少しわかりやすく表現すると、ミルの時代以前には「政府が定めた法による抑圧」から個人の自由をどう守るかが問題になっていたわけです。しかしミルの時代には「政府が定めた法による抑圧」にプラスして「国民同士の社会的道徳による抑圧」が問題になりました。近代民主主義国家においては、その双方の”抑圧”から個人の自由をどう守るかが課題になっていたのです。
自由は「法」と「社会的道徳」によって侵略される可能性がある。
とはいえ、「法」と「社会的道徳」が絶対悪なわけではありません。では、どんな場合において「法」と「社会的道徳」による自由の抑圧に合理性が生まれるのでしょうか。
ミルはこれに対して「危機原理」というシンプルなルールを提示します *5
ある個人の行動の自由を制限する際に、唯一可能なのは、その個人が他人に対して危害を加えることに抵抗することだけである。
つまり、ある個人が、他者やその集合である社会に対して害を与える場合のみ(政府による法や社会的道徳は)その個人の自由を制限する権利を有する
と言っているのですね。これを逆から見ると「個人は、他者や社会に危害を加えない限り、基本的になにをするのも自由である」と表現できます。
ミルはこの原理を「判断能力が成熟した大人」のみに適用できると考え *6
社会制度は「他者に対する危害」を中心に検討することができると主張しました。この原理を前提にした際に、個別の具体的な事案でどのような判断ができるのか。本書では「毒物販売」や「禁酒法」あるいは「不倫」などを例に挙げ、危機原理を前提にこれらをどう解釈できるかが論じられていますが細かい議論に関しては、ぜひ実際に本書でお確かめください。
さて、本題です。
ミルは、自由を論ずるにあたってのテーマとして表現の自由・言論の自由を採用し、それらについて詳細な検討を行いました。
その内容が非常に面白いので、紹介させていただきます。
自由を検討することにおいての表現の自由、それはすなわち「意見はどこまで許容されるべきか」というテーゼです。
まずはじめに「その意見が完全に正しい場合」について考えてみましょう。と言っても、考えるまでもありませんね。仮に完全に正しい意見というものが世の中に存在した場合、その意見を抑圧することは、文明文化の発展を阻害することであり、絶対的に悪い行為であると考えられます。
ではより一般的なケース「二つの”部分的に正しい”意見があったとき、そのどちらかを抑圧することに合理性があるか」はどうでしょうか。
ミルは、この場合においても意見を抑圧する合理性はないと言います。
意見というものは、対立する意見とぶつかり合うことで止揚するものです。対立意見を抑圧するということは、自分の意見に対する探究を辞めることと同義であり、この行為もまた、文明文化の発展を阻害するものです。
まぁ、彼の時代と我々の時代では表現の自由に対する常識が違いますから、私たちから見ると当たり前のことを主張しているように見えますね。
ではさらに進んで「完全に間違っている意見」があるとして、それを抑圧することに論理的正当性はあるでしょうか。
ミルは、この場合においても意見を抑圧する合理性はないと言います。
彼は人間社会が大きな破綻をせずに続いている事実の原因に人間の能力である「訂正する力」を挙げます *7
この力は、意見をぶつけ合わせることで磨かれていくのですが「間違っている」と判断される意見を具に抑圧していくとそのような議論の機会が失われてしまうことになります。ですから、仮に「完全に間違っている意見」があるとしても、その意見は「訂正する力を向上させる材料」として、それだけで価値を有しているのです。
こうしてみてみると、意見の抑圧という問題の根底には「対立意見が絶対に間違っている」という認識、逆にいえば「自分の意見が絶対に正しい」という確信があることがわかります。そのような前提があるからこそ「言論の自由には賛同するが、極端な言論の自由には賛同できない」という意見が現れるわけですね。その「極端かそうでないか」はどうやって判断するのか。そう判断をしている時点で、そこには自分の認識を過信した傲慢があるのです。
ミルは正しさについて以下のように述べています。
「判断が信頼できるのは、間違いを改めるという手段を常に自ら保持している場合である」
「自分の意見に反駁・反証する自由を完全に認めてあげることこそ、自分の意見が、自分の行動の指針として正しいといえるための絶対的な条件なのである。全知全能ではない人間は、これ以外のことからは、自分が正しいといえる合理的な保証を得ることができない」
「ある意見が、如何なる反論によっても論破されなかったが故に正しいとされる場合と、そもそも論破を許さないためにあらかじめ正しいと想定されている場合との間には、極めて大きな隔たりがある」
このような議論のもと、ミルは「意見は常に尊重されるべきであり、決して制限されてはいけない」と断言します。
先ほども触れたとおり、ミルのこの議論は、200年前の社会を前提にしたものです。ですから、前提条件が違う現代から見ると前時代的で古臭く、違和感を感じることも少なくありません。しかし、そこで指摘されている核となるテーゼは、今私たちが生きる現代を考える上で非常に重い価値を持ってるのではないでしょうか。
これだけ進んだ社会においても、未だ「社会的道徳による抑圧」によって抑圧されている意見があります。それどころか、人々には、より自身の意見を「完全に正しい」と確信する傾向が見られ、それが、議論とは言えない”争い”の火種になることもしばしばです。
私たちの「訂正する力」は、時代とともに磨かれているのでしょうか。
それとも、私たちは「訂正する力」を手放そうとしているのでしょうか。
ミルの『自由論』は、そんな強い問いかけを私たちの眼前に突きつけているような気がしてなりません。
□注釈と引用
*1 ジェームズ・ミルには明確に「息子を功利主義の論者として育てたい」という目的意識があったようです。また、ジェームズはアソシエーショニズムという地縁ではなく共通の目的を持つコミュニティーを重視する思想の支持者でもあり、そのような思想の代弁者になるためにミルに英才教育を施していました。結果的に、ジェームズの目的は達成されたと言って良いでしょう。
*2 ちなみに、私は38歳にていまだに『歴史』を読破できていません。すっごく苦手。
*3 ちなみに、ミルは厳密には学者ではありません。生前から名声を獲得していた彼ですが、オックスフォード大学やケンブリッジ大学からの研究の場の提供を全て断り、父親と同じく東インド会社の仕事に就職しました。そういう意味で、彼は学者という仕事を専門としていたわけではありません。
*4 『自由論』ミル (光文社古典新訳文庫)
ーさらにまた、人民の意志というのは、じっさいには人民のもっとも多数の部分の意志、あるいは、もっともアクティブな部分の意志を意味する。多数派とは、自分たちを多数派として認めさせることに成功したひとびとである。それゆえに、人民は人民の一部分を抑圧したいと欲するかもしれないので、それにたいする警戒が、ほかのあらゆる権力乱用への警戒と同様に、やはり必要なのである。したがって、権力の保持者が定期的に社会に、すなわち社会内の最強のグループに説明責任をはたすようになっても、個人にたいする政府の権力を制限することは、その重要性を少しも失わない。 こうしたものの見方は、思想家たちの知性にも、また現実であれ思い込みであれ民主主義と利害が対立するヨーロッパ社会の主要な階級の気持ちにも、ひとしく訴えるものがあったので、すぐさま常識と化した。いまでは政治について考えるとき、「多数派の専制」は一般に社会が警戒すべき害悪のひとつとされている。
*5 ミル. 自由論 (光文社古典新訳文庫)
ーその原理とは、人間が個人としてであれ集団としてであれ、ほかの人間の行動の自由に干渉するのが正当化されるのは、自衛のためである場合に限られるということである。文明社会では、相手の意に反する力の行使が正当化されるのは、ほかのひとびとに危害が及ぶのを防ぐためである場合に限られる。
*6 『自由論』においては「判断が能力が成熟した大人」以外の存在について、大人ではない子供はもとより「まだ発展していない低俗な文化を持つ民族」を想定しています。この辺りは西洋至上主義というか、彼の傲慢さが現れている箇所ですね。このような西洋至上主義的な思想は、後に構造主義者たちによって批判されます。
*7 ミル. 自由論 (光文社古典新訳文庫)
ーそれでは、なぜ合理的な意見と合理的な行為が、全体として、人類のあいだで優勢なのだろうか。 このような優勢が事実であるとすれば──というか、人間の生活は過去も現在もずっと悲惨な状態にあるわけではないのだから、それは事実であるにちがいないのだが──この優勢は人間の精神のひとつの特性のおかげである。すなわち、人間は自分の誤りを自分で改めることができる。知的で道徳的な存在である人間の、すべての美点の源泉がそこにある。
□参考文献
自由論 (岩波文庫) J.S.ミル (著), 関口 正司 (翻訳)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
