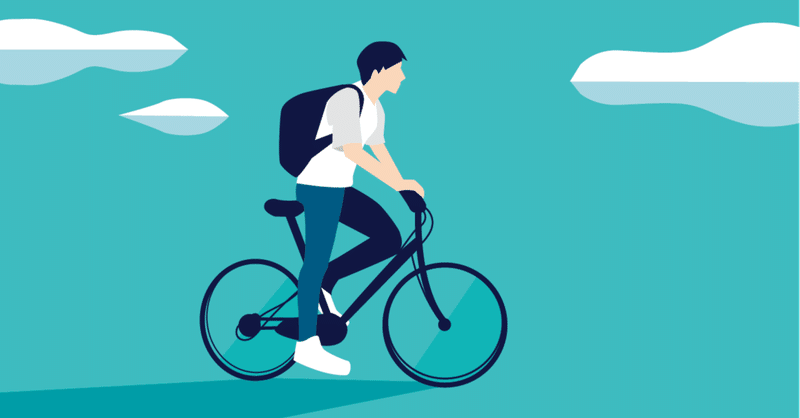
計画相談のジレンマ
私が、計画相談を行なっているなかで常に付き纏うのは、事業の継続性と相談支援の質の狭間に生じるジレンマである。自分の中での優先順位はできていても、同じ事業運営を行っている者同士でも、考え方が違うのが困る部分でもある。そもそも、「計画相談の役割」は、相談支援専門員の考え方も、法人運営の考え方も、地域特有の考え方も全く違う。どんなに厚生労働省が「ガイドライン」を出していたとしても、どこまで求められるのか?というのは、地域のそれまでの歴史的経過や福祉の力によっても違う。
例えば、基幹相談支援センターの動きによっては、計画相談が基幹相談のような動きを求められてしまうところもあるだろうし、ひとりの相談支援専門員が、自分の思いと行動力で、正に基幹相談のような動きをスタンダードとして行うこともあるだろう。特に、「相談支援」については、「終わり」「限界」がないのが直面する大きな課題であり、まだ始めたばかりの意欲の高い相談支援専門員なら、どこまでもやろうとするだろう。逆に、10年以上も相談支援をやっていると、「自分の限界ライン」や利用者ひとりひとりに対する「公平性」「平等性」まで考えて行動する。それ以上に、本質的な『エンパワメント』視点を重視できるようになり、本来の計画相談、相談支援、ソーシャルワーク、ケースワークのあり方を冷静に判断できる。まさに、ここに「相談支援のギャップ」が生じることになる。
ある意味「意欲的」、別の言い方をすると「盲目的」な支援をスタンダードとする相談支援専門員は、その時点において利用者や地域からも評価されることが多い。「そこまでやってくれる」「任せておけば安心」そういった評価は、きっと、評価される相談支援専門員自体も、役割意識や業務に対する歓びとなり悦に浸ることができると思う。やはり、私も含めて周囲から評価されることは誰にとっても嬉しいことである。しかし、それが本当に正しいかどうかは、改めて自分を客観視していく必要があるし、将来に渡り評価を継続していく必要がある。専門意識の高い相談支援専門員であれば、そういったときにこそ、自分を客観視してくれるバイザーなどにアドバイスをもらうこともあるだろう。
なぜ、そこまで言うのかといえば、計画相談の制度設計は、運営上、決して楽ではないからである。時折見られる、「ボランタリィ」な支援を行う相談支援専門員は、実際に「自分はそこまでお金は必要ない」と言い、受け入れる利用者を制限して、利用者の細かな部分まで支援を行う。そういった相談支援専門員の存在は、『福祉の鏡』と呼べるかもしれないし、そういった人たちが、地域の資源としての大きな役割を担っているところもあり、それ自体を悪くいうつもりはない。しかし、そこに例え「支援の質」の高さはあるとしても、「継続性」があるのかという点に加えて、相談支援専門員としての業務を未来に向けて成長させていく上では疑問が生じる。所謂、ボランリィな相談支援専門員の存在が、私たち計画相談の相談支援専門員の「自立」を阻害していることにもなりかねないのだ。法人内の事業所の中で、「赤字垂れ流し事業」であり、いつ切り捨てられてもおかしくない、先行きが不安定な事業のひとつが、「計画相談支援事業」だからだ。だから、計画相談と利用登録者数は、きってもきれない状況にある。
そして、そもそも論となるが、ボランタリィな対応を行う相談支援専門員が支援を行った利用者は、その方から相談支援事業所が変わり、担当が変わったときにどのようなことが生じるだろうか。その人にとって、その相談支援専門員の対応がスタンダードであり、それまでのやり方が全てになっている。しかし、全ての相談支援専門員が求められるものではない以上、必ずしもそのような形の支援を行なってもらえない可能性もある。例を出してみれば、「申請を自分でできる力があっても、相談支援専門員が代わりにしてた」相談支援専門員から、「申請を自分でできる力があるから、相談支援専門員は声かけのみをする」相談支援専門員に変わったとすれば、利用者にとってみれば「大きな違い」に感じてしまうのだ。ちなみにではあるが、そういった問題は、計画相談界隈では、常に生じている問題なのだ。
その利用者が「前の相談支援専門員はやってくれていた」「なんで、やってくれないのか?」といったことがクレームとして上がりやすくなるだけではなく、本人との信頼関係を構築していく上でマイナスからのスタートになる。また、それで関係性が拗れ、再度、新しい相談支援専門員に移行することになり、更なる負担を利用者にかけることにもつながる。しかし、もっともひどいのは、時折、以前の相談支援専門員が、次の相談支援専門員のことに対して、「あの、相談支援専門員は、何も(支援)しない」と利用者本人や行政、周辺事業所に影口を言ったりするケースも少なからず出てくる。それもまた、見当違いなことである。私たちは、相談支援を行うにあたり、本人の力を最大活用していく必要がある。その結果、ご本人自身でできることを増やしていけば、最終的には、自分で判断し行動することができるようになる。それこそが自立支援であり、エンパワメントということになる。できない利用者にやるように言うのは当然おかしい。だからこそ、本人の能力の見極めも行っていく必要があり、それまでの経過を含めたアセスメントが必要となるのだ。
ちなみに、過去に「自分は1匹狼である」ことを自慢げに話す相談支援専門員に出会ったことがあったが、そもそも、それはソーシャルワークではないことを自ら周囲に伝えているようなものである。他にも、私も以前、会ったこともない相談支援専門員からディスられているという情報を、(なんと行政機関から!)いただいたことがあった。ソーシャルワークの本質は、本人を取り巻く支援関係者との“対等な連携”であり、相手をディスることではない。もし、相手の力が及ばないならば、フォローしていくのが相談支援専門員の役割である。ちなみに、そういった傾向が強い相談支援専門員に多いのは、「私は経験をしているから」「私は、この人との付き合いが皆さんよりも長いから」「私は、専門家なので」という枕詞をいつも耳にする。そのこと自体が、周囲に迷惑をかけていることに、自ら気づくどころか、悦に浸っているのだから、、、。
『一方的な経験や専門知識は、その人の周囲を見えなくしてしまう理由でしかないのか?』
『精神保健福祉士として、精神科医療・障がい福祉・児童福祉の相談支援を中心に19年目に突入した中堅クラスと呼べる私が出した結論である』(←あえて書いてみたが、みなさんはどう思うだろうか?これが、あらゆる発言の頭につくことによって、周囲に有無を言わせなくする=“スピーチロック”と呼ばないだろうか?)。そのに足りないのは、相手に対する「敬意」であり、自らの「謙虚さ」である。想像しただけで、私が逆の立場であれば恥ずかしくて死にたくなる理由である。
よろしければ、サポートをお願いします!いただいたサポートは、大好きなコーヒー代にして、次の記事を書く時間にしたいと思います!
