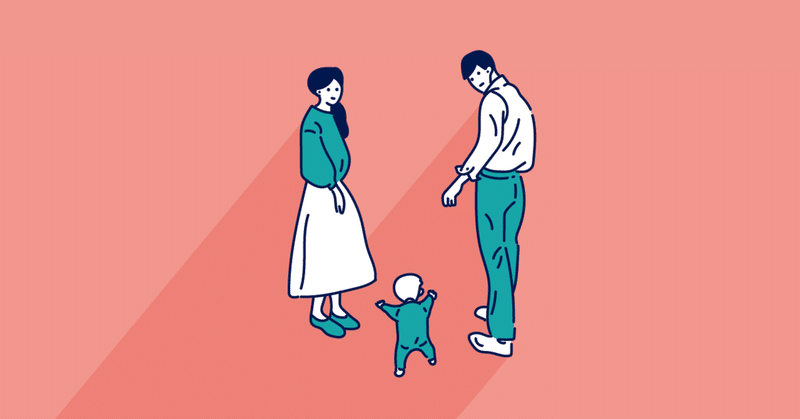
丁寧なアセスメントがもたらす支援現場での劇的な変化
先日、所属法人の運営する児童通所支援施設の「アセスメントシート」の内容について大幅な変更を行った。特に『生活歴の聞き取り』に対して、より詳細な聞き取りを行うように、一本の研修動画をつくり、職員研修を行なっている。もちろん、利用契約時にアセスメントの聞き取りを行うのは、管理者や児童発達支援管理責任者といった役職者だと思うが、普段から利用児童にまつわる(言うまでもなく利用者も同じ)情報は、すべての職員が常にアンテナを張っておく必要があるので、全職員で研修を行なっている。今回、アセスメントシートを変えたことで、特に管理クラスが保護者面談を改めて行い、これまで聞き取りをしてきた内容よりもより深い内容の生活歴を聞き取るようにしてもらった。本来であれば、利用開始時の最初の面談だからこそ、正直にいろんなことについて尋ねることができるのであり、すでに数年経過している保護者に対して、改めて様々な個人的な状況を尋ねるのには、とても神経を使うことになる。こういったところは、普段の保護者との関係性がいかに構築できているかが問われるところだ。
利用開始時だからこそ、こどもに影響する様々な要因、例えば経済状況や離婚や別離といったプライベートなことを根掘り葉掘り聞けるのであって、すでに関わりを持ち始めて尋ねるには、相手に不信感を抱かせることにもつながる。ましてや、プライベートな側面もあるので、今更話したい人はいないのが通常である。
①生まれた市 例:○○市生まれ
②同胞○名の第○子(長男) 例:同胞3名の第2子(長女)
③在胎期間(○週○日) 例:在胎期間は40週と2日
④出生児体重 例:出生時体重は2730g
⑤出生時の状況 例:出生時にダウン症の可能性を指摘され検査を行い、後日、ダウン症と診断される。また、出生時より心臓の異常がわかり、○○大学病院に搬送され手術を行う。
⑥障害等に気がついたとき(1歳半検診、3歳時検診等)
例1:3歳時検診時に、発語の遅れを指摘され、保健師より療育センターに相談にいくように勧められる。
例2:3歳時検診前から、母はことばのおくれや、呼んでも振り向かない状況に気がついて、2歳頃には市役所に相談をしていたが、様子をみるように言われていた。
⑦その後の流れ 例:○○療育センターを紹介され、OTとSTの療育のために週2回母子通園を開始。
⑧幼稚園・保育園・小学校等の入学・入園 例:3歳より「□□保育園」に入園を行う。
⑨離婚等のライフイベントの時期・詳細等 例:本人が3歳時に両親が離婚。その後、実家のある○○市に転居し二人暮らしを開始。
⑩サービス利用のきっかけ 例:小学校入学に合わせて、発語を促すことを目的に放課後等デイサービスの利用を開始。
上記はあくまで一例であり、生まれてから現在までのお子様や周囲で支えるご家族のことをひとつひとつ尋ねていくと、思わぬ内容の返答を耳にすることがある。それは、耳を疑うような、私たちの想像をはるかに超える過酷な人生の巡り合わせだったり、思いもよらぬ突然の大切な人との別れであったり、「まるでドラマをみているような」ということはこのことを指すのであり、その方のひととなりに触れることは、その人の人生を聞かせていただくことになる。実際に、登録者30数名の利用児童の保護者全員に改めてアセスメントを取ったひとりの管理者は、これまで「ここは保護者がね〜」などといった、安易な保護者への責任をなすりつけるような発言がみられていたが、全くなくなった。むしろ、「生活歴を聞いて、もっとできることがあるのではないかと考えるようになった」と話をするようになった。『人生は児童だけではなく、保護者にも平等にあるのだ』ということが、聞き取りを行うなかでようやく理解できたからだと思う。
多くの支援者は、「〜はできる」「〜はできない」といった現在の評価で支援内容を決定する傾向がある。それは、「できていないから、そこを伸ばすための支援」という考え方だ。しかし、それだけだと、支援を行うに連れて、「自宅で保護者がこの部分を見てくれたら、きっとできるようになるのに」といったことを、安易に支援者同士で口にするようになってしまう。特に、専門職と呼ばれる人たちに圧倒的に多い。それは、専門職だからこそ見える、問題の原因がそこにあるからであり、そのこと自体を否定するわけではない。しかし、いくらできない理由がわかったとしても、それを改善する手段がわかったとしても、それをご家庭でできるかどうかは、これは全く別の問題であり、保護者のこれまでの児童との関わりのなかでの関係性や、子育ての負担感、子育てに対するモチベーションといった評価は、ほとんどなされていない。その結果、「我が子を面倒みれない」「誰かに預けたい」とすら口にする保護者に対して、平気で「お子様のために〜するようにしてください」と口にしてしまうのが、今の支援者なのだ。『影でコソコソ言っているだけだから問題ない』というのも違う。
そのこどもとその子を見守る保護者の生きてきた道のりに、是非、丁寧に触れるようにしてほしい。その情報に触れた時に、あなたはきっと、保護者を責めることができなくなる場面に出くわすことがあるはずだ。アセスメントを行うのは、今、その子にできる最善の支援を、専門職である私たちが考えるために行うことなのだから。だから、一番最初に行うアセスメント時に、教えていただきたいとそっと願うように、ひとつひとつ丁寧に尋ねるようにしてほしい。
よろしければ、サポートをお願いします!いただいたサポートは、大好きなコーヒー代にして、次の記事を書く時間にしたいと思います!
