
植物状態のひととの会話 エイドリアン・オーウェン『生存する意識』 【a late care-worker's DRAFT 04】
意識なんて言う語がタイトルにあると、意識とは何ぞやみたいな哲学的、往々にして衒学的な味わいの本と思われがちですが、本書は、実に明快な科学的エビダンスに基づいた研究報告の過程とその研究過程での著者に関わる人生でのできごとが平行的に書かれた、研究報告及びそれに関わる自伝です。
自伝の部分が、この本の読後感をだれもが心の底にもつ形にはならない深い思いへと導きます。
著者は、脳医学研究者で、いわゆる植物状態にあるひとに意識があるかどうかについての研究をある偶然から始め、本書はその研究過程の報告書です。
研究初っ端では、同じ脳医学者の女性と出会い、彼女との新しい恋が新しい研究をはじめた情熱とあいまっていた青春時代から語られます。
植物状態にあるひとに、言葉を投げかけると、脳スキャン画像の一部に変化のあるひとがあり、それが研究のきっかけとなります。
したがって、本書での「意識がある」とは、他者とのあいだで自分の意志を伝えられる最低限のコミュニケーション(YES NO回答)が可能である状態という認識です。
著者は、植物状態にある人へのことば掛けでの脳スキャン画像にあらわれた変化をもとにYES NOの簡単な会話を試みようとします。
YES NOの答えは、脳内であることをイメージしてもらい、それにより脳のある箇所が反応することを明確にすることにより、判定することにしました。
YES NOの回答(脳内でイメージをつくる)により、脳の違う箇所が反応しなければ、回答は不明になります。また、重なりあった箇所が反応しては回答は混乱します。
そこで、いろいろなイメージとそれに反応する脳の部位を研究してゆきます。
最終的には、投げかけられた質問について、YESの場合は、「テニスをしている自分をイメージする」、NOの場合は、「自宅屋内を歩きまわる自分をイメージする」ように呼びかけ促します。
著者は、英国人であり、ヨーロッパには、サッカーなどもっと一般的なスポーツがあるのに、なぜテニスか?と思います。例えば、サッカーでは、フォワードやGKなどのポジションにより、脳の反応する部位がまちまちであり、テニスは個人スポーツでしかも全身運動ということで脳内でイメージする部位が限られるということです。
植物状態のひとに、著者が質問してゆくと、脳内の該当箇所が反応する回答があり、会話ができるひとがいることが判明してきます。そして、このYES/NOの会話を続けるうちに、症状が回復してきて、実際の会話ができるまで回復するひとまであらわれてきます。
初期は、CTスキャンで脳内観察をおこなったために、対象者の放射能の被曝量が大きくなる問題があり、継続的に行うことは難しかったようです。
また、スキャン画像から意識があるかどうかの判定は、熟練さが必要で、誰にでもすぐにできることではない、とのことです。
そうこうしているうちに、著者にある知らせが入ります。
この研究の糟糠の恋人でその後別れてしまっていた、あの彼女が事故により、植物状態になってしまった、と。
これが、本書のバイストーリーです。
植物状態の彼女に会うのか、脳内スキャンを行うのか、意識があるかどうかの画像判断だけでも行うのか、果たして、彼女に意識はあるのか?
この元恋人の存在が、著者の心から離れず、著者を静かに揺さぶりつづけ、本書に奥行きをつくりだしてゆきます。
この件での、著者の人間らしい葛藤と、その苦いながら、そうなるよなという結論はここには記しません。本書を読みながら著者によりそい体験することをおすすめします。
さて、それにしても、二者択一の質問は難しいです。
著者たちは、まず、「痛みがあるか、どうか」ということを聞くところから入ってゆき、そこから相手によって、踏み込んだ質問に移ってゆきます。
著者が、聞かねばならないのかもしれないが、どうしても聞けなかった質問があります。
「あなたは、死にたいと思ってますか?」
これは、難しすぎです。YESと言われ、どうすればよいのか。
また、二者択一の限界でもありますが、答えた後に答えとは違う自分の真意に気づいた時にはどうすればよいのでしょう?
私も、植物状態に近い方を介護することがあります。いつも感じるのは、植物状態になっても、その方の醸し出す人格はあるということです。これをまったく感じられない方はいません。したがって、植物状態になっても、かなりの確率で意識のある人はいるんじゃないかと常々思ってきました。
「生存する意識」は、植物状態と言われているひととのコミュニケーション、交流、触れ合いについて試みた報告書であり、その内容により、私たちは、人間のコミュニケーションについて、人が出会い別れることについてあらためて考えざるをえません。
夏目漱石は、「明暗」という小説で、人間は自分の世界でしか生きられず、他者との触れ合いは不可能ではないのか、という恐ろしく大きい主題を取り上げ、ついに未完のまま亡くなり、「明暗」は、遺作となりました。
人間の知覚する領域を定義したカントを持ち出すまでもなく、私たちが自らの五感を通じてしか、世界と接することができない以上は、厳密な意味では、漱石の問いへの素っ気ない回答は明解です。
漱石の大きな問いを思い出しながら、本書のような、科学的なエビダンスに基づいた素朴なコミュニケーション研究を読むと密かにかつささやかにほっとするのも事実です。
◎『生存する意識 植物状態の患者と対話する』 エイドリアン・オ-ウェン みすず書房
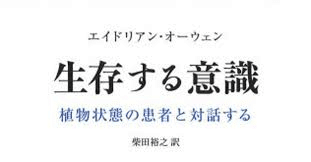
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
