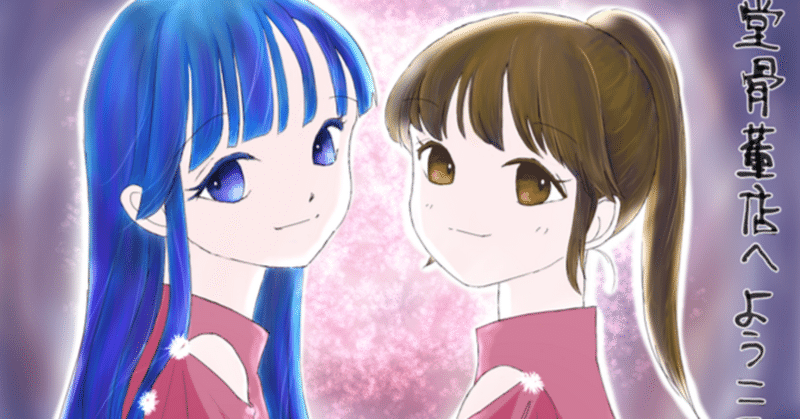
樹堂骨董店へようこそ30
神社の前の大通りにはいつもは整備されていない「竹の柵」がガードレールのように設置されていた。
これは神社周辺から民家のあるふもとまで毎年大晦日から一月三日まで期間限定で設置される。街路樹には点々と提灯も提げられている。
表向きは「神社へのわかりやすい誘導」ということになっているが、本来の目的は「人が異界へ迷い込まないため」だ。
七緒はその理由を知っている。
他に知っているのは七緒の祖母だけだった。祖母は母屋でひっそりと暮らしている。こういった話は「継ぐ者」にしか伝承されない。
表向き神社を継ぐ者は七緒の父や兄たちだ。彼らは神主などの職を日々こつこつと勤めている。でも、目に見えない話は知らされない。知らない方が、人の世界の中でうまく生きて行けるからだ。そして彼らはそのことに気付いているが、介入しようとはしなかった。介入したくても「すべ」を持たなかったから。
こうして異界を支えるモノ、異界と人の世界を繋ぎ、調整する役割を担う者、継ぐ者を支える者、他にもいろいろ存在し、すべてがバランスよく存在し合うことによって「桜杜の今」が成り立っていた。
「んーそろそろかなぁ」
七緒は巫女の正装をして神社の前の大通りを登った登山道入り口前に立っている。そこは展望台になっており、下界を一望できる。
冷たい風が容赦なく吹き抜けてゆく。海に近いとはいえ、標高が千メートルくらいあるので低地よりも寒いのだ。
つい先ほど、社務所の今日の出納簿をつけて収支がピッタリ合ったので心の中がすっきりしていた。
(父さんも、マミちゃんもやればできるじゃん)
こつこつと日々の指導の成果が大晦日にでたことに七緒は素直にうれしかった。収支の狂いつづけた悪夢の日々はもう終わったのだ。
(よかったあああ)
夜空を仰いで深呼吸した。長い髪が風になびく。
その時遠くからかすかに鈴の音が聞こえた。
「沙那ってママの事?」
「…そうだ」
「ここにいるの?」
「…これ以上は言えない。那胡が自分で見つけるのは自由だが、教えることはできない」
「…」
イツキは桜の木の下の誰かと話しているようだった。それ以上は見えないし、ふたりも風に流されてあっという間に見えなくなった。
(やっぱり夢なのかもしれない)
那胡はそう思った。
「…前を見て。出口だ」
流がそう言うと、前方のみんなの姿が雲のようなもくもくとした煙の中に吸い込まれてゆく。
「?」
すーっと二人も吸い込まれたが、その直後とんでもない突風に包まれた。あちらこちらから息もできないくらいの風が吹き付けて上も下もわからなくなる。
「ひゃあああ…」
那胡は思わず目を閉じた。
次の瞬間にピタッと風が止んだ。そして冷たい風が肌をなでてゆくのを感じた。こわごわ目を開けてみると
「帰って来た…」
眼下には桜杜高原が広がっていた。那胡たちははるか山の頂上あたりから下降していた。闇の中に街明かりが見えた。日常からは想像できない景色に
(やっぱ夢なんじゃないかなぁ…)
と那胡は冷たい風を感じながらもぼんやりと眺めている。
前方の着物のひとたちは賑やかに音楽を奏でたり歌ったりしながら風に乗って下界を目指し下降し、流と那胡もそれに続く。
その時、登山道入り口の展望台に七緒が立っているのが月明かりに映し出された。
「七緒ちゃんだ!」
七緒はこちらを見上げている。
「…ん?…那胡?」
七緒は那胡の気配を敏感にキャッチした。
(那胡の気配がする…)
その時、下から何か大きなものがスゴイ勢いで上がってくるのが那胡にはわかった。なにかとんでもなく大きなものが来る。
「ぶつかる?…でも何が?」
那胡には大きなまぶしい光の塊が、那胡たちをめがけて跳ね上がってくるように見えた。直径が十メートルはありそうだ。
「おお、巫女じゃ」
「あちらが持ち場じゃの…」
「巫女はいつの時代もかわらんのう」
「ひゃひゃひゃ」
すぐ後ろにいる那胡にはみんながそう話しているのが聞こえた。
「ミコ?」
地表に近づくにつれスピードがぐんぐん上がる。
「ひっ…」
前方からは光の塊がこちらに飛んでくる。
「ひぃぃ…」
悲鳴をあげかけて、ふと止まる。
前方の光に向かってみんなが手を振っていた。そして、光の中には同じように手を振る人々が微かに見えた。
七緒がお辞儀をすると、その目の前で那胡たちと大きな光がすれ違った。その瞬間、光の中にはこちらと同じような人々が見えた。そして列の後方に流が見えた。
「流?」
那胡はすぐとなりにいる流と見比べてしまった。同じ人に見えた。
「流がふたり?」
那胡の隣の流は何も言わないまままっすぐに麓を見つめていた。
突風が収まると、お辞儀をしていた七緒は顔を上げ
「ふーっ、お迎え完了だ…なんか那胡の気配したな…」
大きな光の塊が麓をめがけて下降してゆくのを見つめた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
