
2023年1月きいたものよんだもの
2023年1月にきいたり、よんだりしたうちで、印象に残っている作品です。きいたものは14作、よんだものは2作です。感想があるのと、ないのがあるのは、思いついたか、そうでないかです。作品が気に入ったかどうかではありません。
順不同です。
きいたもの

Drum – Paul Motian
Guitar – Bill Frisell
Tenor Saxophone – Joe Lovano
Paul Motianの音源をきいたことがなかったので、どれがいいのか調べて、これをききました。繊細というか、かなり独特な在り方をしているジャズという印象です。ベースがいない、ドラムもシンバルの音が前にきており、タムやスネアは後ろのほうにきこえる、ということが繊細さを感じさせるのかもしれません。
Bill Frisellのギターソロがどの曲もよいです。Bill Frisellだけでなく、ソロの演奏があるということが、このアルバムがジャズであることを保たせていることの一つであると思います。
ビートは強くないのですが、スウィングしているのも不思議です。

Bass – Maarten van Regteren Altena
Cello – Tristan Honsinger
Design – Karen Brookman
Drums, Viola, Banjo, Performer [Etc.] – Han Bennink
Electric Guitar, Acoustic Guitar – Derek Bailey
Soprano Saxophone – Lol Coxhill
Soprano Saxophone, Alto Saxophone, Flute, Clarinet – Anthony Braxton
Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Evan Parker
Trumpet, Flute – Leo Smith
オリジナルは1978年に発表されています。これはCompany6と7から抜粋してコンピレーションしたアルバムです。
Steve Lacyが参加している曲が、個人的には印象に残りました。やはり鳴らす、吹く音が独特というか全体の演奏の中でも突出していて、一聴してわかります。
あと6曲目の最初のほうに声が入っているのですが、唐突にはじまるので驚きます。声はHan Beninnkでしょうか。
5曲目のAnthony BraxtonとEvan Parkerのデュオがよかったです。テンションが張りつつも、それぞれに呼応して演奏しているようです。



Bass – Joe Shulman (曲: B1 to B3), Ray Brown (曲: A1 to A4)
Drums – Bill Clark (曲: B1 to B3), J.C. Heard (曲: A1 to A4)
Guitar – Barney Kessel (曲: A1 to A4)
Piano – John Lewis (2) (曲: B1 to B3), Oscar Peterson (曲: A1 to A4)
Tenor Saxophone – Lester Young
サックスという楽器は、音を吐いて鳴るのだということがよくわかる演奏です。唇の震えや息遣いがすごく前にあって、人が鳴らして演奏しているだということがわかります。
速いテンポよりも、ゆっくりしたテンポの曲のほうが、そういったことがわかりやすくきこえます。
調べる限りCDは出ておらず、LPのみのようです。
『The President』とは、Lester Youngの愛称Presの元です。そのためPresやPresidentといった言葉が入る、アルバムタイトルがよくあります。
そのせいか、サブスクなどで調べてもこのアルバムはうまく出てきません。
もしかしたら、ないのかもしれません。

オルガンによるドローン作品なのですが、ドローンの音の持続性よりもメロディがききやすいところが、良いなと思いました。ゆっくりなテンポではありますが、耳馴染みのいいメロディがミニマルに続くので、ぼーっとしていても気持ちを委ねられるような気がします。
ドローンではあると思いますが、教会音楽というかオルガンの音楽であると思います。

Angelic Process『Weighing Souls With Sand』2007
メタルとして語られている文脈から見つけましたが、きいてみるとメタルよりもシューゲイザーの要素が濃いと思いました。
ドラムやボーカルよりも、轟音のギターがなによりも一番前にきています。ギターの音も、ギターのが鳴っている時とそうでないときのメリハリがあって、よいです。ギターの音が長く続くと、耳が慣れてしまい轟音と感じなくなることがあるのですが、そこはうまく計算されて曲が作られているのか、欲しい時に轟音がくるなと思いました。
また他の近いアーティストだと、曲時間が長くなりがちなタイプの音楽かなと思うのですが、5分くらいの曲も多く、そういう点でも聞き飽きしない、間延びしないアルバムだと思います。

コンセプトがあって、作られた作品ではなく、病後に楽器などをさわって録音したものから抜粋して作品とした、とのことのようです。
曲目は基本的にはすべて8桁の日付で名づけられています。
ぱっときいた感じも、煮詰めて計算して作られたというよりも、いい意味でラフさがあり、音として書き留めておいたもメモのような印象です。
元のタイトルは『12 sketches』というタイトルだったそうで、そこからsketchesをとって12となったそうです。元のタイトルどおりスケッチという言葉が似あう作品だと思います。
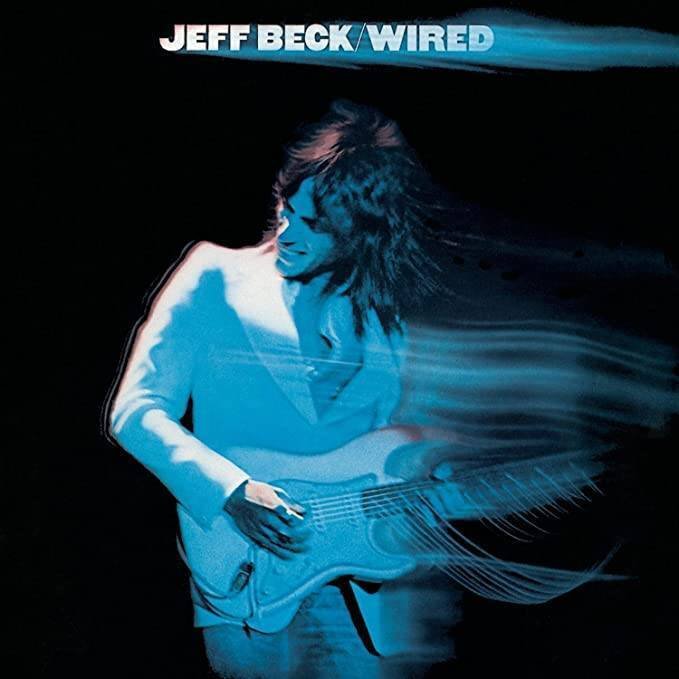
Jeff Beckは『Blow by Blow』と 『Beck, Bogert & Appice』くらいしかきいたことがなく、あまり強く興味をひかれていなかったのですが、亡くなったこともあり、こちらの作品をきいてみました。
なぜか同時期のFrank Zappaの作品を思い起こしたのは、普段フュージョンという音楽をそこまできいてないからかもしれません。
グッドバイ・ポーク・パイ・ハットが入っていたのが意外でしたが、Joni Mitchellもカバーしていますし、同時期のフュージョンに寄ったロックの人には、Mingusの作品に惹かれる何かがあったのでしょうか。
インスト作品ですが、アルバムを通して、だれることないのは、リズムがかっちりしているからかなと思いました。

Bass – Ian Kenselaar
Drums – Nic Cacioppo
Tenor Saxophone – JD Allen
アルバム全体的にコルトレーンを感じます。JD Allenのサックスだけでなく、ドラムやベースの雰囲気もどことなく60年代以降からフリーに転向するまでのコルトレーンに似ています。
それもでJD Allenの持ついぶし銀の演奏はよいです。
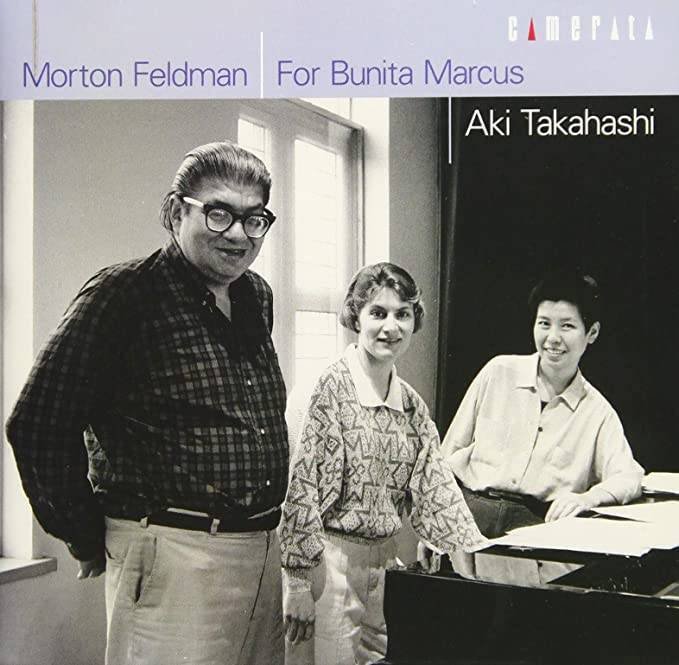
Morton Feldmanの作品は初めてききました。ピアノの弱音の残響や他の音との反響、時折出てくる短音の反復が良いと思います。Morton Feldmanの作品は、起伏がなく常に弱音(ピアノ)で演奏されるような曲が多いとのことなので、この作品も同様です。晩年の作品ですが、Bunita Marcusというのは弟子のことだそうです。
一聴すると「静謐」といった印象ですが、響きの不安定さや不穏さ、どこに向かっているのかわからない様子なども感じられます。時折出てくるミニマルな反復したフレーズも執拗さというか微かな狂気じみたものを感じます。
録音年については、初演らしいのですが、きちんとした根拠が見つかりませんでした。Feldmanの作品は気になっていたのですが、何からきいていいのかわからず放置していたのですが、とても気にいったのでRothko Chapelもききましたが、これもよかったです。少しづつ他の作品もきいてみたいです。

Bass – Wilbur Little
Drums – Elvin Jones
Piano – Billy Greene, Larry Young (曲: 1-2)
Tenor Saxophone, Flute – Joe Farrell
発掘された音源とのことですが、こんなにもかっこいいエルヴィン・ジョーンズの演奏がまだでてくるとは驚きました。個人的には9、1、3曲目あたりが良かったです。

Alto Saxophone – Johnny Hodges, Russell Procope
Bass – Richard Davis (2)
Cornet – Ray Nance
Drums – Gus Johnson
Piano – Jimmy Jones (3)
Tenor Saxophone – Harold Ashby, Paul Gonsalves
Trombone – Buster Cooper, Lawrence Brown
Trumpet – Cat Anderson
CDはなくLPのみできけるようです。
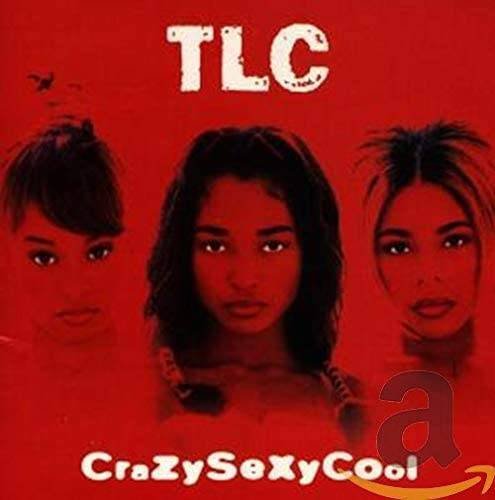
90年代R&Bサウンドです。いつまでもきいていられます。
よんだもの

先月から1か月くらいかけて少しづつ読みました。全15巻ですが、1巻ごとの内容が濃いので、読むのに時間がかかりました。
日本や海外の神話とか宗教的な寓話のようなものが混じりつつ、オリジナルの神話世界を描いています。
話は複雑だったなという印象です。最初は敵、味方というような立場がそれなりにはっきりしているのですが、途中から敵だった者が味方になったり、味方だったものが敵になったり、そもそもの敵・味方というようなものが曖昧というか最初からなかったのかもしれない、と思わせるような話の筋でした。
登場人物が年をとって、子どもだった者が大きくなったりして、成長することで性格や雰囲気が変わったりするのが、面白かったのでこの部分ももう少し描いてあるとよかったです。
正直に言うと後半は少しだれました。自分が飽きてしまっただけかもしれません。「ままな(漢字があるのですが変換できません)」という半人半獣がでてくる、というか途中で登場人物がそれであるとわかるのですが、その辺から自分は入り込めなくなったような気がします。
神話はハマれば読んでいて面白いのですが、うまくハマれないと読んでいて苦痛な部分があります。神話も含めてSFなどの超現実のお話がそこまで得意ではないのですが、水木しげるさんとかはとても好きなので、この差はなんであろうかと考えてしまいます。
おそらくその要因は一つではなく、漫画を成り立たせている様々な要素(絵のうまさであったり、話しの構成であったり)から違ってくるのだと思います。
あまりよくないことを多く書いてしまいましたが、物語としてはしっかりしたものなので、ハマる人は楽しめ作品であると思います。

WEBラジオで知って読んだのですが、相当にくだらなくてよかったです。
八世紀から九世紀あたりのイスラム圏の詩人の作品から抜粋したものですが、一篇ごとが短く、適切に解説もあり入ってきやすかったです。でもお酒を飲まない人は、何が面白いんだかわからないかもしれません。
簡単にいうと、ほとんどアル中状態の作者が、ただひたすらお酒や酔いを礼賛しているだけなのですが、かなりのダメっぷりが伺えます。
例えば、朝から酒を飲もうだの、酒がなくなったら酒屋を起こしてでも飲もう、ということが書かれています。
他にも恋愛や中傷などの詩もあるのですが、メインは飲酒に関わる詩です。
読んだ後にこれといった詩を覚えているわけではないのですが、まあこんな人もいて、くだらないことを書き残したんだな、というのがざっくりした感想です。1000年以上の前の外国の詩が日本語に訳されて読むことができる、というだけでもすごいことなのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
