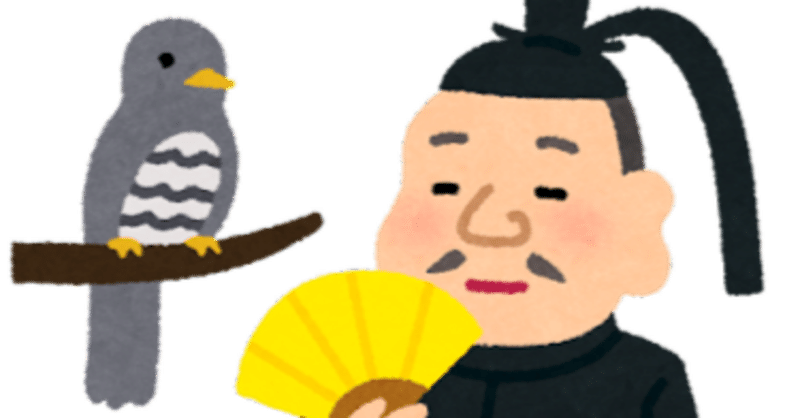
「どうする家康」第45回「二人のプリンス」 絶望の家康を救う二人のプリンスとは誰か
はじめに
「二人のプリンス」…予告編でこのタイトルが流れたときから、「秀忠と秀頼」(名家の二代目)、「家康と氏真」(今川の王子たち)、「家康と秀忠」(かつてのプリンスと現在のプリンス)、とさまざまなダブルミーニングを考えられた視聴者の方々も多かったのではないでしょうか?
蓋を開けてみれば、それらは全て正しかったわけですが、一方で際立つのは「二人」という対比ではなく、関ヶ原から10年以上を経て、70歳になった家康の細やかな心境のほうではなかったでしょうか?
史実の家康は最晩年まで精力的に鷹狩、暇さえあれば論語の講義を受けるなど、死にそうにないほど頑健ですが、「どうする家康」の家康は侘しさ、空しさ、憂い…そうした後悔や慚愧の念が強調されています。
このことは、さまざまな「二人のプリンス」は、老境の家康の心情を紐解くものとして機能しているということを意味しています。
そこで今回は家康と新旧プリンスとの関わり、家康の次世代への眼差しから、人生の終わりが見えた家康が自身の人生をどう振り返り、落とし処を見出だそうとするのか、その諦めと憂い、そして救いとは何かを考えてみましょう。
1.徳川家と豊臣家の駆け引きの始まり
(1)戦を夢想する茶々と戦しか思い返せない家康
冒頭は前回の幕引き「時が来た」が何かを説明する振り返りになっています。「後十年もすれば太閤殿下に追いつこう…」「それまでの間、秀頼の代わりを(代わりを)頼みまする」という茶々の台詞が挿入されたのは、天下の政の治める家はどこになるかを改めて決める「時が来た」ということを強調しています。ここで確認しておかなければいけないのは、両家の置かれた状況です。
家康は豊臣家から徳川家が天下を担う政治形態になるよう細心の注意を払ってきました。まず、関ヶ原の戦いにおける論功行賞です。この論功行賞は、実は事実上、親徳川勢力への豊臣直轄地の割譲でした。それにより222万石あった豊臣家の直轄地を65万石にまで削り、豊臣家の経済力を削ぐことに成功しています。対する徳川家の加増の結果は440万石です。
また、征夷大将軍として政務の実権について朝廷のお墨付きを受け、更には秀忠にその将軍職を譲ることで天下を担うのは徳川家であることを強調しています。
ただし、それでも徳川家は主家筋である豊臣家を他大名のように配下におけてはいません。徳川家の実質的な支配を決定づけた関ヶ原の戦いと将軍就任ですが、それでも完全な移行とはならなかったのです。例えば、しかし、加増・安堵を受けた諸大名は家康と知行充行状を介した直接の主従関係を結ぶことまではできず、また加増の上で西国に追いやった豊臣恩顧の大名らもいます。
領地の加増・改易の実質的な権利を得ることはできましたが、関ヶ原の戦いが豊臣政権内の内部抗争である以上、主家の力を完全に奪い切るにまでには至らなかったのです。
また徳川家は、征夷大将軍就任後も官位叙任権を独占できず、豊臣家が秀頼の名で恩顧の家臣たちに官位叙任を行うことは阻止できませんでした。豊臣秀吉という稀代の天才が成した既得権益と権威、そして経済力は厳然たる権威として、家康たちを圧迫しているのです。
ですから、茶々は家康の権威は、あくまで秀頼に親政が行えない幼少期であるこの「10年」のことであると高を括っているのです。秀頼の親政が始まれば、諸国の大名も豊臣に再びなびくと。そう思えばこそ、彼女ら大阪方が家康の行為を黙認してきたに過ぎません。
今、秀頼は成人してしばらく経ちました。家康が桶狭間の戦いを生き延び、独立したのが18歳。その頃の家康と変わらぬ年齢になった秀頼は、政を行うに早すぎる年齢ではありません。ですから、豊臣家の雌伏の時期は終わりを告げ、改めてこの問題が頭をもたげることになるのです。
大阪城、蘭陵王を舞う秀頼から始まります。見目麗しいその姿は、豊臣家の希望そのもの。それを惚れ惚れと眺める茶々の笑顔は満足げです。
そして、笑顔を絶やすことなく隣の千姫に「この天下を艱難辛苦の末一つにまとめられたのはどなたじゃ?」と問いかけます。「今は亡き太閤殿下」と慎重に答える千姫に「そなたのおじいさまは殿下の御家臣としてその代わりを任されていただけ…秀頼が成長した暁には天下をお返しくださる約束じゃ」と、さも当然のように語ります。
この茶々の台詞の文言は一見、全うですが、趣旨はかなり辛辣です。要は家康のこの10年の政の功績を豊臣に帰属するものに過ぎないと貶めた上で、後継者問題を蒸し返しているのです。家康を貶めた上で挑発する茶々の言葉に、うつむき加減に「はい」と頷く千姫の戸惑いは当然でしょう。
従順な嫁に「そなたのお爺さまは盗人ではあるまい」と、暗に「家康は今や簒奪者である」と意地悪な指摘をします。その言葉に両家をつなぐ役割を心得る千姫は「お爺さまは約束を守る方と存じます」と応じますが、応える前に二人の会話を背中で聞く大野修理をちらりと窺うのが意味深です。
彼の監視するような雰囲気を常々、意識しているのでしょう。そして、それは大野修理が、家老の片桐且元を差し置いて、事実上、茶々と一心同体の家臣団首座となっていることを匂わせます。
「なれど、もしその約束をお破りなるなら、そのときは戦になっても仕方のないこと…」と千姫の予想通りの答えを受け流す茶々のその目の先には既に秀頼もありません。更に遠くを見つめ、どことなくうっとりとした夢見心地のその表情は「仕方がない」という言葉は方便で、心から戦を望んでいることが窺えます。
母の艶然として放つ物騒な言葉に驚きを隠せない千姫に対し、茶々はギロリ横目をくれると「欲しいものは…力で手に入れる!」とその本性を表し「それが武士の世の習わしなのだから」とうっとりとし、戦を思い浮かべます。
かつて彼女の母、お市は、乱世を男ならば「力があればなんでも出来る面白き世」だと言いました。その言葉は、何もにも縛られず生きられる自由を求める心が言わせたものでした。
しかし、欲しいものは力で手に入れるのが武士の世の習わしとする茶々の言葉は似て非なるものです。茶々の少女期は力ある者たちに翻弄されるものでした。最初の城と共に実父が、二番目の城と共に母と養父が、そして自身の純血も全て力ある者に奪われました。
謂わば、奪われる悔しさ、恨み、哀しさをもって、逆説的に戦国の弱肉強食を受け入れたのが茶々です。その彼女、今や秀頼の生母として、豊臣の富と権威を使える立場になりました。今度は自分がそれを使い、受けた屈辱を晴らし、野心を叶える番です。
戦によって全てを奪われたのであれば、戦によって奪い返せばよいのです。戦場に直接出ない茶々にとって、戦とはものを手に入れるための儀式、プロセスにしか過ぎないのでしょう。
戦場の悲惨な実態を知らない彼女は、戦場に勝利の美酒に酔うことを想像するのみです。茶々の恍惚とした表情には権力を振るう喜びを味わう者の傲りがあるように思われます。
茶々が夢想する戦場のイメージが挿入された後、ぼんやりとした家康の表情のアップに切り替わります。つまり、挿入された戦場のイメージは茶々の夢想だけではなく、それを別の角度から思い返す家康のものでもあるのです。
果たして、家康は薄く開いた目の茫漠とした表情からは物思いに耽る様子以外はわかりません。ただ、それが戦場である以上、喜ばしいものではないでしょう。
カメラはそんな家康を、アップの次は斜め後方からのロングショットで捉え、独り佇む彼の孤独感を強めます。
遠くからは阿茶の呼びかけが聞こえますが、それに反応しない家康を今度は反対方向の真横からミドルショットで捉えます。呼びかけに微動だにしない老いた姿は、呆けてしまったかと錯覚させます。彼の最晩年の老いさらばえた様子が強調されます。
阿茶の何度目かの呼びかけにようやく答えた家康ですが「江戸より秀忠お着きでございます」との言葉への反応は鈍く、阿茶は察したように「憂いごとでございますか?」と気遣います。
家康は「昔のことばかり思い出す」と愚痴りますが、その内容を詳しく語ることはしません。未来や将来ではなく昔にやたらに囚われるようになった自分について「わしも…そろそろかのう…」と諦めたように呟くと、また一人、遠い目をします。この横顔はアップで映されますが、この際、瞬きを一つして、その自身の人生に思いを馳せる彼の心境を強調する芝居が効果的ですね。
それにしても、戦嫌いな彼が自分の人生を思い返すと戦ばかりというのは、乱世に生き残った結果とはいえ哀しいことですね。これまでは戦で感じた喜びや哀しみを共有できる友垣のような家臣たちがいました。しかし、家康が長生きゆえに彼らはその天命によって先に逝き、今や家康は一人でその思いを抱えるしかありません。一人だからこそ、余計に思いに囚われるのかもしれません。
そして彼は戦によって多くのものを失ったことを思い返します。戦に栄光など落ちていないことを彼は知っています。戦を知らない茶々とは正反対ですね。
(2)豊臣との共存をギリギリまで図る家康の思惑
1610年の頃は、将軍を譲り駿府に隠居し大御所になった家康が現将軍秀忠の権威を損ねないよう配慮しながら重要案件については差配する二元政治を行っていました。主に東国支配や軍制などは、秀忠のいる江戸政権が、西国政策(朝廷や豊臣家、西国大名との対応)については家康のいる駿府政権が担っていました。したがって、秀忠がわざわざ江戸から駿府へお伺を立てるのは、豊臣関係の問題だと察しがつきます。
江戸で関東総奉行の一人として秀忠を補佐している本多正信から、豊臣家のいる大阪の現状が報告されます。それは前回でも既に言及されていた豊臣家が関ヶ原の戦いによって仕官先を失った浪人らを集めて匿っていること、武具を揃え戦支度に余念がないことですが、加えて「世間は徳川と豊臣がぶつかるとの噂でもちきり」という世情不安も伝えられます。
「この十年、天下の政務を執ってきたのは我ら徳川。父上のもと、政をしかと進めていくことこそが世の安寧の根本」と言う秀忠の言葉は、最早、徳川への警戒と敵意を隠そうともしない様子に次の一手が必要ではないかという不安の表れです。「父上のもと」という言葉からも、実権は秀忠にはなく、彼自身も未だ家康に実務も精神面も頼るところが大きいことが透けて見えますね。将軍就任前に家康に言われた「上に立つものの役目は、いかに理不尽なことがあっても、結果において責めを追う」という言葉は、5年ほど経った今もなお、秀忠には重すぎるもののようです。
おそらく、この度の駿府下向もその不安を伝えてものらりくらりとかわす正信では埒があかないと考えたからでしょう。
その秀忠の言葉を引き受け、仰せのとおり。もうはっきりさせるべきでござる。今や徳川が上、豊臣が下であると」と言葉を継いだのは、正信とは逆に駿府で家康の側近として働く本多正純です。切れ者である正純ですが、物事を直線的に捉えてしまうのは秀忠同様、若さというものでしょう。彼からしてみれば、豊臣家との問題が解決させせて、もっと建設的なことに力を割きたいのだと思われます(中盤、按針と金時計を前に談笑している場面からしても、彼の関心はこれからのことと察せられます)。
父正信が、秀忠に対してのらりくらりとかわしているだろうと察したのか、正純は早々に解決を図る策を献じます。それは、後水尾天皇の即位に合わせて家康が4年ぶりに上洛することに合わせて、二条城に秀頼を招き、家康へ臣下の礼を取らせるというものでした。
自信満々の正純に乗って意見をしようと秀忠がアクションしかけた瞬間に「おとなしくお出でくださると思えんが…」と割って入ったのは阿茶です。彼女は関ヶ原の戦いの折、大阪城で茶々と一対一でやりあっていますから、彼女の恐ろしさを十二分にしっていますから、あの「おっそろしいおなご」がこちらの要求に激昂して突っぱねてくるのは見えています。
加えて、以前の秀忠の将軍就任に対する挨拶要求のときも「秀頼を行かせるくらいなら秀頼を殺して、私も死ぬ」と豪語していますからね(苦笑)
阿茶の言葉にも、現状に焦れる正純は「従わぬなら、そのときは力をもって」と言いかけますが、「ならん。それは避けたい」とそれまで静観していた家康が穏やかに制します。家康は「太閤秀吉の名は今も多くの心に生きている…その遺児に、秀頼どのに下手な仕打ちをすれば…万民の怒りが我らに向く」と言います。大阪・京都といった上方は秀吉によって経済的に立て直されていますから、上方庶民の豊臣人気も絶大です。
また、大阪城には莫大な金銀が蓄財され、その財力は侮れません。そして、先にも言ったとおり、豊臣家の権威は完全に封じられてはいません。寧ろ、独自路線を貫いています。
だからこそ、家康によって貧苦にあえぐ浪人たちが、それを頼みに集まり、戦支度も整えられるわけで、逆に言えば、正純が躍起になって秀頼を屈服させようと画策するのです。家康の「万民の怒りが我らに向く」という危惧は、もっともなことなのです。背景にあるのは、初期の徳川幕府は不安定な政権であるという問題と言えるでしょう。
秀忠が「よもや天下をお返しするつもりでは?」との問いに「上手くやらんといかんともうしておる」と家康は慎重さが肝要と応えるやり取りの中、報告後、縁側でだらかで日向ぼっこしていた正信がのっそりと立ち上がり、座敷にあがってきます。そして「力で跪かせては危のうございましょうなあ」と家康に追随する阿茶の呟きの後、正信は「秀頼さまには二条城にお出で願い大御所さまとお会いしていただく。ただしその際、上段にお座りいただいて、しかとあがめ奉る」と、正純の献策を捻り、家康が秀頼を立てれば来ると提案します。
徳川が上であるとすべきとする正純は「豊臣を上にするのですか?!」と驚愕しますが、振り返る正信は「徳川は武家の棟梁、その将軍家が敬うべき者とは何だあ?」とのんびりと返します。
聡い阿茶はあっさり悟り「公家!」と答えます。正信はつけ加えて「さよう。豊臣は公家ってことにしちまう。公家ならば城だの武力だの持つべきではありませんな」とこれによって、現在、豊臣家が着々と進める戦支度そのものも封じる一石二鳥にしようと言います。
正純は「父はこんな屁理屈ばかり才がある」と呆れ果てますが、実はこの策、家康の真意をよくよく理解したものです。前回、正信から征夷大将軍就任を勧められたとき、家康は「徳川は武家の棟梁、豊臣はあくまで公家…住み分けられるかもしれんな」と活路を見出したような独り言をつぶやいています。正信は、家康の住み分けという発想を取り入れ、豊臣と争うことなく政権を安定させたいという家康の意向を叶えようとしているのです。
こうした主君の内心を汲んだ上での深謀遠慮の献策は、正攻法で物事を勧めようとする正純の及ぶところではありません。呆れた正純の言葉に「お褒めにあずかりまして」といけしゃあしゃあと返す煽り方に、騙り者の本領発揮ですね。当然、我が意を得たりの家康は「「寧々さまに間に立っていただこう!」と早速、行動に出ます。
(3)豊臣家が抱える問題
徳川家と豊臣家が一体となって、天下を治めてくれることを願う寧々(落飾し高台院)に否応はなく、二条城へ秀頼を招く仲介のために大阪城を訪れます。徳川の意向に敵意がないことを伝えると同時に、頑な大阪方を理解し秀頼と茶々の顔を立てるように「私は悪くない申し出と思うがいかがかの?」と判断を委ねる言い方をしています。流石ですね。
しかし、茶々は静かに怒りを滲ませ「つまり天下は返さん。正々堂々戦もせぬ…頭を撫でてやるから大人しくしておれと言うことでございますな」と挑発、侮辱としか受け取りません。ここで安易に「正々堂々戦もせぬ」と戦をほのめかすところに彼女の戦を望む心情が端的に表れていますね。彼女が戦というものを命のやり取りをする悲惨さを理解することもなく、単なる政治の手段、いや、もっとも美しく天下を取る方法としか考えていないことがわかります。
家康が戦を回避しようとするのは、戦嫌いだからではありません。勝とうが負けようが、戦の本質は多くの無駄な犠牲を生むだけの悲惨なものであることを実感しているからです。戦争では本来、普通に生きていくべき人の命が奪われるのですから、本質的にはその犠牲は全て無意味です。残された者が無駄死にの辛さから逃れるために、その犠牲に意味づけをしようとするだけなのです。
戦を無くそうとするには、まず戦争による死が無意味であることを重く受け止め、そうした犠牲をこれ以上出さないようにしようとすることにあります。
家康は戦の本質を知るからこそ、戦を起こすことには慎重になり、戦に怯え、そして嫌うのです。この慎重さと臆病さこそが、戦乱の申し子家康という怪物の本性であり、生き残る術だったのです。ですから、茶々に追随して「情けない盗人よ」という大野修理の言葉は言い得て妙ですが、戦場を経験していながらこんな発言しかできない彼は武将としては三流と言えます。寧々の「そのような言い方は控えよ」という嗜める言葉はもっともです。
徳川と豊臣の不穏な空気を察した千姫は責任を感じ、その場を収めようと謝罪をします。彼女にはこんなことしかできませんからね。すると、それまで口を挟まなかった秀頼はさっと立ち上がり、千姫の元へ進むと「そなたが謝ることではない」と真摯に慰めます。ただし、徳川方の二条城への招きに対して、彼自身は何の意見も言いません。
茶々ら大阪方首脳部の頑迷さに呆れる寧々は「今、天下を治めているのは徳川どの。豊臣家は徳川どのの庇護のもとにあることを忘れてはなりませぬよ」と諭します。彼女は実質的に政治は徳川家に移っているという現実を見て、体面を保って生き残る道を模索すべきだというのです。
先ほど徳川家が豊臣家を支配下におけない弱さがあることに触れましたが、豊臣にしても徳川家を完全に圧倒する力があるわけではありません。まず関ヶ原の戦いによって、220万石から65万石になったことは収入の激減ですから大打撃です。また、諸国に設置されていた蔵入地は江戸幕府成立後解体され、そこからの年貢米も入りません。つまり、豊臣家は秀吉が蓄財した圧倒的な金銀があるものの、それは結果的に目減りしてく傾向にあります。
そしてなにより、関ヶ原の戦いによって、領地の加増、転封、改易を行う権利を徳川家に奪われています。中世における主従関係の基本は領地を与え、それを安堵することにあります。しかし、残念ながら65万石になった今の豊臣家には分け与える領地もなければ、加増などを行う権利も有していません。長期的に見れば、豊臣家は諸国の大名をつなぎとめておく最も重要な要素を持っていないのです。
また、多くの加増を受けた豊臣恩顧の大名に対しても、江戸城や名古屋城の天下普請を各大名に課すことでその経済力を削ぎ、戦を容易には起こせないようにしています。つまり、家康が10年かけて打った数々の手は確実に豊臣の力を削いでいるのです。しかし、自分たちの権威に酔う茶々たちには、将来的なジリ貧の可能性への自覚はありません。
ですから、寧々の説得にも修理は「出ていけば何をされるかわかりませぬ」と不審の念を上から目線で主張するだけです。
このままでは交渉決裂すると見た加藤清正が「おそれながら秀頼さま。お出ましにならぬならお心の弱い君と思われるやもしれませぬ!」と首脳部のプライドを煽ることで事態の打開を図ります。揶揄する修理の言葉など意に介さず「この加藤清正、秀頼さまの側を片時も離れずお守りいたします」と申し出、万が一の場合はどんな大軍であろうと打ち倒して大阪城へ秀頼を送り届けると豪語します。
彼の豊臣への忠誠心は疑うべくもありません。先に述べた蔵入地にしても、彼の所領では解体することなく彼が死ぬまで、年貢米を豊臣家へ送っています。しかし、一方で時代が徳川家に流れて言っているという現実も見えています。長女は榊原康政の嫡男に嫁がせましたし、次女は家康の十男・頼宜(後の紀州初代藩主)と婚約が決まっています。
実際、必ず秀頼を守ると言った、この二条城会見でも彼は豊臣方ではなく、この頼宜の護衛、徳川の家臣として参加しているのです。
彼の両家に対する対応のバランス感覚からは、徳川家が天下を治める世の中で豊臣家がその威光を維持しながら生き残る術を模索し、この会見を積極的に仲介したことが見えてきますね。
寧々と茶々の真顔の駆け引きに不安そうな千姫は、秀頼に目を向けます。思案気な秀頼ですが、忠義者である清正にここまで言われて引き下がるのは自身の権威を貶めることになります。状況の冷静な判断から、茶々の顔を見て大丈夫だろうと肯きます。あくまで最終決断は自身ではなく、母である茶々に委ねます。秀頼自身がどうしたいのかは、最後まで語ることはありません。
そして、秀頼の頷きを受け、茶々も秀頼の才に任せようと腹を括ると「そろそろ世に御披露目するかのう、そなたを」と自信満々に艶然と微笑みます。秀頼の養育に余程の自身があるのだと見えます。
2.二条城会見で弾ける秀頼の才覚の光と影
(1)秀頼の闊達さと柔軟さに出し抜かれる家康たち
伏見城から大阪城に移って以来、秀頼は初めてその姿を民の前に姿を表します。神秘のヴェールがいよいよ剝がされるときが来たとあって、民衆の期待は高まります。冒頭の蘭陵王の舞の見目麗しさから、今回の秀頼が眉目秀麗であることは保証されていますから、期待を上回るその美丈夫ぶりに京の民衆たちは、あれこそが自分たちにとっての天下人だと沸き立ちます。京の人々にとっては、秀頼の美しさに比べたら、家康などは老齢の田舎者にしか過ぎません。
町中に響き渡る歓声に正純は「やはり上方の豊臣人気は凄まじい…」と眉をひそめますが、家康はまだ見ぬ彼を見極めようとする目つきになっています。一説には、家康は秀頼自身の才覚よりもその人気を恐れ、豊臣家を滅ぼす決意をしたという逸話もあります。もしそれが本当であったなら、京の人々が結果的に秀頼を死なせたことになってしまいますね(笑)
さて堂々と物怖じすることもなく表れた若きカリスマは、「ようこそ…」と平伏しかけた家康が言い終わる前に家康に走り寄ります。呆気に取られた清正の様子からは、この言動は、少なくとも豊臣方で打ち合わせたものではなく、秀頼自身の計算かアドリブであると察せられます。前者であれば権謀術数に長けていますし、後者であれば優れた状況判断と柔軟性があることになります。どちらにせよ、ただ者ではありません。
ペースに巻き込まれぬよう家康はそのまま「お出でください…」と言葉を続けますが、秀頼はその手を取ると「大御所さま、わざわざのお出迎え、恐悦至極に存じます、秀頼にございます」と爽やかに微笑みます。一気に人の心を引き込む、そういう力を持っています。ここに来るまでに京の人々が湧いたのも、この笑顔なのでしょう。
しかし、ここは老獪な家康、人の虚を突く若者の言動を油断なく値踏みするように見返します。家康は、若い頃、信長や家康や信玄から虚を突かれて、狼狽えるというのを何度も繰り返していますからね。流石に用心深いですね。
目的は秀頼を上座に座らせることです。ですから、どうぞお先にお入りくださいと勧めますが、秀頼も「大御所さまからどうぞ」と慇懃に返します。なおも家康が先に行くよう勧めると「大御所さま我が妻のお爺さま。何故私が先に入れましょう」と殊勝なことをやんわりと申し出ます。その殊勝さに裏はないかと訝しむ家康ですが、秀頼は表情を崩しません。
ともあれ、孝行を出されては、受けないわけにもいかず、この場は「では、案内させていただきます」とあくまで秀頼を奉じる姿勢だけは維持しながら先に入っていきます。まず第一ラウンドは、秀頼優勢で引き分けというところです。
そして会見の場では寧々が立会人として寧々が既に控えており「秀頼どの、上段へどうぞ」と当然のように勧めます。辞去する秀頼に家康は「いえ、そういう取り決めでございます」としきたりを持ち出し、寧々もまた「取り決めどおりになさいませ、秀頼どの」と角が立たないように仲介者として発言します。彼女は、ただただ両家の関係を強くしたいというだけです。
ここまで自分のペースで淀みなく状況をリードしてきた秀頼ですが、年長者二人の言葉に、初めて思案顔になります。それを見た家康は「豊臣は関白に任じられる高貴な家柄、武家の棟梁である徳川は及びませぬ」という、とっておきの言葉を持ち出すと、さっさと下座に座ってしまいます。ここが攻めどころと家康は見たのでしょう。座り込んでしまえば、こちらのものと家康は薄っすらとニヤリとすると「さあ」と秀頼を促します。
それでも逡巡する秀頼を見て、二人の緊張した雰囲気を察した寧々は「ほんならお二人とも上段にお座りになっては?こう向かいおう」と口を挟みかけますが、家康はそれを遮って「誠に恐れおおいこと、秀頼さまこそ上段に!」と固辞します。ここで動く羽目になっては元も子もないからです。しかし、それを梃子に秀頼は再び気安く、家康の手を取ると「意地を張るのも大人げのうございますので横並びにいたしましょう」と寧々の妥協案を飲むことを提案します。
家康にしても、脇でその申し出に一礼する寧々を見ては、この度の仲介を買って出てくれた彼女の顔を立てるしかありません。秀頼に手を引かれ、足元に注意しながら共に上座に向かいます。並んだ二人の姿で家康の衰えが強調されているのが印象的ですね。老人を支える若者という孝行イメージを世間に見せつける秀頼の演出であり、また、足元がややおぼつかない家康が秀頼の立ち振る舞いの巧みさに圧倒されてしまっていることの視覚的な保証にもなっています。
そして、秀頼の手を借りながら上段に着座した瞬間、秀頼は颯爽と下座へ降ります。その鮮やかさに家康は「しまった…」という表情をしますが、時すでに遅し、秀頼が下座へ着座していしまいます。秀頼が座るとき、一瞬だけ、その斜め後ろにいる寧々の呆気に取られた顔に焦点が合うのが上手いですね。秀頼は家康を見事に出し抜き、徳川家の真意を潰し、この駆け引きに勝利します。しかし、それは同時に仲介役を兼ね、「共に向かいあうように上段に座っては」と提案した豊臣家の年長者、寧々の顔も潰したことになるのです。寧々は自らの発言で、家康に恥をかかせたことになりますから、尚更いけません。
つまり、秀頼の一連の言動は卒がなく、鮮やかな一方で、どこかで配慮に欠けた行為であるということを一瞬のカメラのフォーカスで説明しているのでしょう。
さて、駆け引きに勝った秀頼ですが、慇懃な態度を崩すことなく「大御所さま、長らくの無沙汰大変ご無礼いたしました。秀頼、心からお詫び申し上げます。何とぞお許しくださいますようお願い申し上げます」と騙したことを悪びれることもなく、深々と平伏します。絵に描いた慇懃無礼ですが、孝行を盾にしたその行為には一寸の落ち度もありませんから、家康はただただ呆気に取られてしまいます。脇に控える寧々は、家康に恥をかかせた秀頼の行為に困ったように目を伏せるしかありません。
そして、完全に場の主導権を握った秀頼は「武家として徳川どのと共に手を携えて、共に世を支えて参りましょう」とトドメの一言を爽やかに述べ、徳川方の豊臣完全公家化作戦を粉砕します。多くの場数を踏み老獪さを身に着けた家康が、こちらの意向を見抜かれた上にぐうの音も出ない形で砕かれたことは衝撃です。
据えた目つきで、乗り出すように本気で彼を値踏みする家康の様子には、してやられたという苦々しさが浮かんでいます。
秀頼は完勝しましたが、才覚を見せつけたことにより、徳川方に警戒と不審を与えたのも事実。つまり、寧々が願った協調路線が瓦解したのです。相手を騙すつもりであれば、ここは才覚の角を隠すほうが良かった面もあります。ですから、この行為が果たして長い目で見て、豊臣にとって吉と出るか凶と出るのかは別問題でしょう。秀吉のようにバカのふりができなかったのは、状況もあったでしょうが、見せつけたがる茶々の性格が反映されているかもしれません。
一般には和やかに終わったとされる二条城会見は、その裏では徳川家と豊臣家の緊張関係をより強めることになってしまいました。これを額面どおり喜んでいるのは、単純な秀忠だけです。真に受けて喜ぶ彼に、姉の狡猾さを知る江は「良かったのでございましょうか?」とかえって不安げです。正信の「えらいことじゃ…」という絶望的な呟きに「へ?」と答えた秀忠は、まだこの事態の問題が見えていません。というか、江のほうがものが見えているというのは、流石にいけませんね(笑)
正信が危惧したとおり、「徳川さまが秀頼さまを跪かせたそうやで」という噂は市中を駆け巡り、豊臣びいきの京の人々を驚かせますが、この噂に「徳川何様ぞ!」「天下の主は秀頼さまじゃ!」「我らも大阪に参るぞ!」といきり立っているのは、浪人たちです。こういう不満分子を炙り出し、世論を操作し、彼らを糾合することも豊臣方の目論見通りなのでしょう。それを眺める山伏姿の真田信繁が何を思うのでしょうか。
当然、こうした世論と緊張感が高まる情勢は徳川家にも入ってきています。「してやられました」と悔しがる正純ですが、最早どうにもなりません。これをしてのけたのは、秀頼という才覚ある一人の若者、豊臣家の嫡男です。それだけに阿茶は、家康がこの人物をどう見たか、人物評を問います。家康は「涼やかで様子もいい…秀吉じゃ」と危険視するように断じます。あえてみっともない真似をしていた秀吉とやり方は違うが、人の虚を突き、懐に飛び込み、相手の心を操る…その本質が豊臣家のそれであるというのです。
様子の良さは明らかに茶々、つまり織田家の血統です。つまり、織田家の容姿を持った狡猾な秀吉というハイブリットが秀頼であるというのです。ここに来て、恐るべき強敵として秀頼が育ったことを認識せざるを得ません。信長一人でも圧倒され、秀頼一人にも手を焼いたのに、今更、合体悪魔が生まれたようなものだからです。
場所は変わり大阪城。大阪城の濡れ縁で、秀頼が抱く猫を絵に描く千姫と秀頼が仲睦まじそうに談笑しています。茶々は、それを眺めながら、家康を出し抜き、世論を味方につけられた事の顛末にほくそ笑みます。
しかし、千姫の前で笑う秀頼の様子は、二条城で見せた狡猾さとは印象を異にします。元より人は多面的ですから、どちらも本性であるということは多分にあるのですが、わざわざここで印象の違う秀頼を入れたことに意図があるように思われます。これについては、後述しましょう。
さて、秀頼の人心掌握術にたけた聡明さは、家康・秀忠父子を悩ませます。
まず秀忠は、眠ることができません。頭によぎることは「人の上に立つ者の役割は責めを負うこと」という家康から伝えられた君主論、そして正信の「全てが人並み偉大なる凡庸」の二つです。自分のような凡庸な人間に家康のように上に立つ者として責めを負うことができるのか…そのことではないでしょうか。家康を偉大な父と信じる秀忠には、家康の言葉と正信の言葉がどうしても一致せず、落としどころが見出せません。自分はどうしたら良いのか、その方向性に悩むのです。そして、その答えが出せないことには、全てに優れた秀頼にはとても後継者として勝てないと思い悩むのです。
一方、家康は贈られてきた金時計がどういうものかを説明させるために三浦按針と改名したウィリアム・アダムスを呼び出します。当然、それは口実で真の目的は、イギリスから大筒、カルバリン砲を調達することでした。戦争ではなく貿易で国を富ませることを信念とする按針は流石に逡巡します。しかし、家康はその思いは自分も同じだと伝え、「戦を防ぐためのものじゃ。大いなる力を見せつければ攻めてくる者はおらんじゃろ」と伝えます。あくまで「戦無き世」を維持するためのものでしかなく、使う気は毛頭ないと言うのです。なおも逡巡する按針に、家康は無理にねじ込み、不承不承、承知させます。
家康のこの言葉が詭弁であることは、大坂の陣で輸入した4門のカルバリン砲が使われることが証明しています。秀忠は秀頼一人について悩んでいますが、家康はもう少し視野が広く、秀頼が反徳川を糾合するカリスマとして機能することを恐れています。戦が避けられない事態だと見ているのですね。しかし、10年かけてかりそめとはいえ「戦無き世」を維持してきた戦嫌いの家康が、秀頼を恐れ、それを始末する結果となる大筒を輸入することは、本末転倒です。三成が言う通り、自分こそが乱世を望む者だと言っているようなものです。その事実は、結局、家康を苦しめます。
(2)過去の家康の優しさが、老境の家康の絶望を救うまで
時を刻む金時計の音を聞き、それを見やりながら物思いに耽る家康の脳裏に浮かぶのは、秀吉との「」という誓いと決意、収めきれずに起きた大乱、関ヶ原の戦いに際して三成から浴びせられた「」との言葉です。結局、家康は「戦無き世」を志向しながら、未だその実現に至ってはいません。また三成の「家康こそが乱世を求める申し子」という断罪の言葉への答え、反証も得ていません。
それどころか、日々、豊臣家との緊張関係は高まり、迫りくる自分の老いと死に焦り、秀頼を恐れるあまり、戦の備えをしようとすらしています。按針に無理矢理にカルバリン砲の手配をねじ込んだことは、その焦りを象徴しています。
武装強化と軍備増強とは、古今東西、仮想敵に対する怯えから来るものです。安保条約も防衛費増額も、その根にあるのは勇気ではなく怯えです。自分の弱さを知る家康ですから、按針に言った建前が詭弁に過ぎないことを自覚しているのではないでしょうか。
「戦無き世」の実現も、三成への答えもあまりに遠く、理想と現実のギャップを埋めていくには問題は山積みです。にもかかわらず、家康に残された時間はあまりにも少ない。彼の絶望的な思いを引き立てるように時計の音は無情に刻まれます。家康は自然といらつき、そして暗くならざるを得ません。
そこへ出家し、今は今川宗誾と名乗る氏真がやってきます。ナレーションでも家康の庇護の元にあったとされましたが、家康が江戸にいる頃は氏真があまりにも頻繁に家康の元を訪れるため、品川に屋敷を与えたと言われます。一説にはうざがったとも。ともあれ、互いを知る者がいなくなった今となっては旧交を温めるのみでしょう。
因みに秀忠の上臈(女性家老)は氏真の妹、乳母も今川の遺臣です。秀忠もまた今川の薫陶を受けています。
仕組みを知りたくて時計を弄っているとの家康の言葉に「子どもの頃からそういうことが好きであったな。木彫りで生き物や人形を夢中で作っておった」と氏真は懐かしむように微笑みます。第1回あたりが自然と思い出されますが、あの頃の家康は無邪気に屈託なく笑う人形遊びの好きな少年でした。本来、戦を好まない優しい人柄だったのです。
その言葉に家康は「ふ…ははは」と自嘲気味に「は…あの頃のわしを知っておるのは今や貴方だけじゃ」と応じます。そこには、誰からも恐れられ怪物、大御所家康の正体を知る者が少なくなった侘しさと寂しさがあります。家康は日々、天下人の孤独を抱えているからです。
そんな二人を前に金時計は変わらず、時を刻む音を立てます。
家康の「奥方とは歌を詠む日々か」との問いかけに氏真は直接答えず「歌とはつくづく奥が深いものよ。技やしきたりに果てがなく、どこまでやっても極められん」と歌の奥義について語ります。これ、糸(早川殿)との楽しい会話が尽きないという惚気なんですよね(笑)
今回は家康と氏真、かつての今川のプリンス二人の対峙を強調する意味あいもあり、氏真の正室、糸(早川殿)は出てきません。しかし、台詞で晩年まで仲睦まじく過ごしたことがフォローされるのは心憎い演出です。
だから、家康は思わず微笑みます。しかし、すぐに表情を暗くし、深くため息をつくと「羨ましい限りじゃ」と言います。この言葉は深い意味を持ちます。第12回のnote記事で、家康と氏真が互いに鏡合わせの関係であることは触れましたが、それは今も同じです。
あのとき、家康は戦国大名を降りた氏真を羨みます。つまり、氏真のその後は、家康が歩みたかったifの人生そのものなのです。氏真は家康の元を去る際に、足の悪い糸に歩調を合わせます。これにより、二人が共に歩むことが示唆されたわけですが、実際に二人は共白髪となるまで過ごせました。
この夫婦像は、瀬名の願い「二人でどこかにこっそり落ち延び、誰も知らない土地で小さな畑をこさえて暮らしたい」と通ずるものであり、それは家康自身の願いでもありました。しかし戦国大名として今日まで生き延びた家康は、その過程で瀬名を失いました。ある意味では瀬名の命と引き換えに彼女から託された夢を叶える天下人の地位につきました。
叶えられなかった生き方を目の前にした家康の「羨ましいかぎりじゃ」は字面以上の重みと深い自虐と後悔が込められています。
分相応の残りの人生を歩めた氏真は逆に穏やかな顔で、そんな家康を見つめ「わしはかつてお主に「まだ降りるな」と言った…だがまさか、これほどまで長く降りられぬことになろうとはな…」と素直に労ります。降りるなどころか「そこでまだまだ苦しめ」とまで言いましたが、父、義元の夢を託さざるを得なかった彼の無念と家康への彼なりの激励でした。
だから、その労いにうつむき加減に横を向いてしまう家康に対し、満足げに微笑むと「だが後少しじゃな。戦無き世を作り、我が父の目指した王道の治世…お主が成してくれ」と、家康のこれまでの活躍に素直な賛辞と感謝を送るのです。
しかし、家康はその実現が遠いという現実と、家康自身が乱世の象徴であるという論理的問題にぶち当たり、袋小路に入っています。
氏真の言葉が真心と分かっていても皮肉にしか聞こえないことでしょう。彼の顔もまともに見られず、目を反らし続け「わしには無理かもしれん…」とぽそりと本音を漏らします。いや、兄と慕った氏真を前に、漏らしてしまったのでしょう。今の家康に他にこの弱さを漏らせる相手はいませんから。
やや驚いた氏真は「お主は見違えるほど成長した。立派になった。誰も…」と言いますが、家康は「成長などしておらん!」と強く否定し遮ると、訴えかけるように「平気で人を殺せるようになっただけじゃ」と自らの血塗られた人生を思い返します。この台詞は、冒頭の茫漠とした表情とつながりますし、また赤子の秀頼に触れられなかった晩年の秀吉とも少し重なりますね。
「戦無き世が来ると思うか」との台詞は、残虐になった自分に「戦無き世」を作る資格があるのかという意味ですが、それを見て憐れむ氏真の顔が印象的です。
ここで家康の表情は横からクローズアップされ、彼の言葉と共にその苦悩が映し出されます。
「一つ戦が終わっても…」と呟くと、かっと目を開き「新たな戦を求め、集まる者がいる…」と言います。まさに戦を仕掛けんとしている豊臣がそれです。その現実に、首をわずかに振るようにしながら「戦はなくならん…」と自分の夢は無駄なものでしかなかったとしか言えません。
「戦無き世」を目指し、そのために尽くした手がことごとく覆り、多くの犠牲と重ねた努力が無駄になっていく…家康の申し訳なさと無力感は絶望的な思いとなり、その目にはどんどん涙が滲み、表情が歪みます。中を見る彼の目には空しさしか映っていないでしょう。
この絶望感は彼の人生全体の否定ですが、それでも目の前の戦は迫り、主君として天下人として戦い続けることが求められます。責めを追うのが主君だからです。その業深さに「わしの生涯は…ずっと…死ぬまで…」と言いかけ、がっくりと畳に手をついてしまいます。
この一連の流れにおける細やかな表情の変化は、松本潤くんの上手さと同時に二年近くかけて家康と同化してきた歳月の積み重ねが見せた奇跡ですね。
さて、なおも「死ぬまで…死ぬまで戦をし続けて…」と終わらぬ無間地獄に追い詰められる家康を、すかさず抱きすくめる氏真が良いですね。そして、万感の思いを込め、幼き頃から彼へ向けた愛憎を「家康よ…弟よ、弱音を吐きたいときは、この兄が全て聞いてやる。そのためにきた。お主に助けられた命もあることを忘れるな」の台詞と共に昇華していきます。
氏真が、世を恨まぬという辞世の句詠むほどに満ち足りた人生を歩めたのは家康のおかげです。「助けられた命」とは、単純に命や生活を救われた領民や家臣という意味だけではなく、人間らしく生きられた人々がたくさんいるということではないでしょうか?家康は、羨ましく感じる氏真の存在こそが、自分の進んだ道は間違っていなかったということを知らされるのです。
若いときの氏真を殺さず逃した優しさが、こうやって家康の迷いと絶望を救うことになるとは巧い構成でしたね。結局、家康はこれまで信じてきた道を信じるしかないのです。
氏真の言葉とハグに慰められ、家康も憑物が落ち、涙ぐみます。泣き虫弱虫洟垂れの家康に少し戻ります。同じく涙ぐむ氏真は「本当のお主に戻れる日もきっと来る」と「戦無き世」は来ると信じていると伝えます。言葉の真意がわかる家康はまだ虚ろな瞳を返すしかできませんが、氏真は大丈夫と頷きます。
ようやく深く息をついた家康も微笑みます…が、それでもその目の先にある金時計の針は確実に時を刻みます。残された時間はない…その中で何をすべきか。再び家康は考え、決断することになります。
3.次代に想いを託し、つなぐこと
(1)弱きプリンス秀忠に救われる家康
家康たちに一杯食わせた秀頼は、自信をつけたのはその行動は、大胆で活発なものになっていきます。彼は京の寺社の再建に着手します。これは、譜代の家臣を持たず、後ろ盾を持たない秀吉が、自身の力を維持するため、朝廷とのつながりを強化しようとした政策の一環です。つまり、秀頼は正しく、豊臣家の嫡男として秀吉の生前の政策を引き継ぎ、実行しているのですね。
その中で特に悲願として、「豊臣の偉業を復活させる大事業」を進めます。それが、東大寺の毘盧遮那仏を上回る京大仏の建立です。因みに劇中で方広寺の名が出ないのは、当時、その寺名がついていなかったからです。因みにこの建立には徳川家も大工を派遣し、人材的な協力をしています。そして、いよいよ秀吉の十七回忌に開眼供養の運びとなります。父親が喜ぶだろう大事業の完成に流石の秀頼も素直な喜びの表情をします。
片桐且元は、その一大イベントで諸国の大名、公家、商人、上下に関係なく招くと言います。勿論、徳川家もです。当然、それは豊臣の家臣として呼びつけるというニュアンスがあるのでしょう。
ですから、大野修理は満足気に「これからますます輝きを増していく旭日の若君と齢七十を超えた老木。時が否応なく勝負をつけましょう」と言い放ちます。二条城会見の二人の姿は、秀頼の眉目秀麗な美丈夫を噂として世間に印象づけたのでしょう。その家康を貶める物言いに茶々も薄く笑います。修理は「老木さえ朽ち果てれば、後に残るは凡庸なる二代目…(一瞬入るお人好しの秀忠のカット)ふん!…比べるべくもない」と言います。つまりは、待っていれば徳川のカリスマ家康は死に、自然と次のカリスマ秀頼の元に天下が転がり込むというのです。相手に戦う気が無ければ、待てばよいのです。
しかし、この修理の発言は、天下は一人の天才の元で統べられるものであるという考えがあるようですね。この点は、前回示された、人の和を尊ぶ善良な君主の元に多くの才ある者が集まって、「戦無き世」を作っていこうとする徳川家の指向する天下とは相容れない、古い考え方だといえます。豊臣家は戦国の世の弱肉強食を集約していると言えるでしょう。
それだけに、ただ座して待てば天下が転がり込むという修理の言葉に茶々は不満げな顔をします。
さて、比べるべくもないと言われた凡庸な二代目、秀忠は駿府にて「開眼供養はどうにかしてください」と家康に懇願しています。何事にも優秀な秀頼を恐れる秀忠は、彼の手によってこれ以上、豊臣家の偉業が世間に喧伝されることを危惧します。このままでは手がつけられなくなるのではないか、自分の手には負えないのではないかと思っているのです。この裏にあるのは、自分自身の凡庸さゆえの自信の無さです。
秀忠の具申に正信は「立派な大仏を作っるだけですからな」と気のない返事です。先にも述べたように、この事業は徳川方も大工などを派遣しています。つまり、徳川にとっても都合が良いことだから手を貸したのです。大仏建立は莫大な資金が必要なことは言うまでもありません。徳川家にとって必要なことは、戦をすることなく豊臣の力を削ぐことです。となれば、豊臣の蓄財を浪費する大仏建立は願ったりかなったりなのですね。ですから、放置しておけばよいと正信は考えているのです。これもまた、家康が本来考えている豊臣との共存策に添うものです。
秀忠の言葉に焦りを察したの阿茶です。彼女は於愛が亡くなって後、彼の養育を担当していましたから、母代わりの面があります。ですから、穏やかに「迂闊に動けばかえって徳川の評判を落とすのでは?」と諭し、「自信をお持ちになって堂々としているのがよろしいかと」と苦言を呈します。彼女の言葉に追随するように、諸国の大名が誓詞を出しているから大丈夫だと言います。
この誓詞は、二条城会見に最初は在京の大名22名に、後に東国の大名65名に出させた誓詞を指していると思われますが、こうしたものを欲することが、徳川の豊臣への恐れですね。秀忠はそんなものがなんの役に立つかと激昂します。不安の原因は、結局のところ、自分自身にあるからです。
秀忠は情けない顔をしながら世間で流行る「御所柿は一人熟して落ちにけり、木の下にいて拾う秀頼」という歌について伝えます。「家康が死ぬのを待てば、秀頼が自然と天下をものにする」という修理の言葉とほぼ同じ内容です。
秀忠は「この歌に私は出てきてもいない。取るに足らぬ者と思われておるのです。父上が死んだら…私と秀頼の戦いになったら…私は負けます。負ける自信がある!」と言います。「負ける自信がある」は、ある種のパワーワードですね。負けるということについて、自分に揺らがない信頼があるということは、自分自身をよく知っているということに他なりません。人間、自分のことほどよく知りませんが、それは自身の醜い部分を直視することが耐え難いからです。それができる秀忠は、実はとんでもなくタフなものを精神的に持っているのです。
とはいえ、これを語る秀忠の心情は「秀頼は織田と豊臣の血を引く者…私は凡庸なる者です」との言葉に表れるように悲壮感が漂っています。聞く正信もかける言葉がなく、阿茶は痛々しい表情で彼を見ます。「父上の優れた才も受け継いでおりませぬ」との言葉には、彼を内心小馬鹿にしている正純は何も言えず、視線を横に泳がせています。そして、「父上がいつ死ぬのかと思うと夜も眠れませぬ」と連夜の不眠の原因を正直に打ち明けます。
この間、家康は一言も発しません。老境を迎えてからの家康は静かに人の話に耳を傾ける傾向がありますが、この度の息子の自身の不甲斐なさに対する言葉も批判をすることなくずっと聞いています。
そして、秀忠が話し終え、たっぷり間を取ってから、「秀忠。そなたはな…わしの才をよく受け継いでおる」と断じます。信じられないと言う秀忠に「弱いところじゃ。そして、その弱さをそうやって素直に認められるところじゃ」と言います。その言葉に「よりよってそれか、そんなの何の役にもたたない」と思ったのか、秀忠はぷいっと横を向いてしまうのが、また素直ですね(笑)
納得しかねる秀忠に「わしもかつてはそうであった…だが、戦乱の中でそれを捨てざるを得なかった。捨てずに持っていた頃のほうが…」と途中から自分に言い聞かせるような言い方になって自嘲すると「多くの者に慕われ、幸せであった気がする」と、その弱さの価値を語ります。
家康は今、こうして秀忠に語る中で、今更に瀬名の遺言「いいですか、兎は強うございます。狼よりずっとずっと強うございます」(第25回)の意味がわかったのかもしれません。弱いはずの兎が何故、強いのか。弱いからこそ、皆で集まり協力するからです。考えてみれば単純なことです。
家康はその弱さと優しさを周りに愛され、それゆえに彼を支えよう、叱咤しようと多くの人が集まり、そういう中でここまで来たのです。いざ、皆が怖がられる怪物になってみたら、皆、周りからいなくなってしまいましたが。
今、秀忠の周りには彼を支えるために多くの次代を担う家臣が集まっています。弱い彼を支えるはずです。だからこそ家康はかつての自分を懐かしむように「わしはそなたが眩しい。それを大事にせよ」と心からの助言をすると秀忠へと歩みよります。
そして「よいか。戦を求める者たちに天下を渡すな」と豊臣の現状を鑑み、改めて言い渡すと「王道と覇道とは?」と問います。秀忠、反射的に「徳をもって治めるが王道!武をもって治めるが覇道!」と答えます。これは、第1回の義元と家康のやり取りですね。
思い返せば、あのとき、無邪気にその理想を信じていた家康は、それを戦国の世で実現することの難しさを痛感し、それを目指しながら、結局は覇道に突き進んでしまいました。彼が思い出すのは、戦のことばかりです。ですから、氏真に自分のしたこと、人生は無駄ではなかったのかと絶望を告白したのです。
ただ、王道を目指した家康の思いは確かに秀忠に伝わっていることが、今確認されました。勿論、秀忠が王道の理念を理解するには、まだまだ多くの経験と失敗が必要でしょう。しかし、自分と同じ弱く優しい兎の心を秀忠が持ち続けるならば、自分とは違う未来、「戦無き世」が築けるはずです。
この想いは救いです。彼はずっと「自分が「戦無き世」を実現しなければならない」という使命感に生きてきました。しかし、ここにきてようやく、それが傲慢であることに気づいたのかもしれません。
今川義元はかつて「天下の主は民」と言い、「民に見放された時こそ、我らは死ぬ」とも君主の在り様を解きました。これは言い換えるなら「戦無き世」を実現するのは、優れた主君ではなく名もなき民たちが集まって成すものということでしょう。主君は彼らがそれを実現できるようレールを引いてやるぐらいのことなのです。長い道のりを歩きながら、義元や瀬名といった家康の原点に帰ってきたのではないでしょうか。
だとすれば、家康にできることは一つ。グッと顔を秀忠に寄せると「そなたこそがそれをなす者と信じておる。わしの志を受け継いでくれ」と願いを託します。秀忠に将軍を譲ったことはシステムを譲っただけに過ぎませんが、今回は志と願いを次代に任せるのです。家康の優しい期待に秀忠は泣きそうです。
そんな自分と同じ泣き虫の秀忠の顔を両手で慈しみながら、ぺしぺしと叩く家康の仕草には今までにない穏やかで深い愛情が窺えますね。次代に想いを託すことで彼は、自身の絶望から解放され、救われます。言い換えれば、秀忠の弱さが最初に救った人間は、尊敬する父親なのです。因果なものですね(笑)
言うべきことを伝え満足気な家康ですが、その時間は確実に進み、終わりが近づいていることを金時計の音が再び示唆します。この東照宮所蔵の家康が愛でた洋式金時計は、家康の好奇心の表れですが、本作では家康の寿命、最晩年のタイムリミットを刻むアイテムとしたのはなかなか興味深い演出ですね。
(2)才あるプリンス秀忠が引き受けるもの
弱い親子が対話によって、想いを引き継ぐのとは対照的に秀頼は武芸の猛稽古に励んでいます。その圧倒的な強さに大野修理も弾き飛ばされます。「手加減してはおらぬだろうな?」との言葉には、茶々が秀頼の養育に手を抜いたことがなく英才教育を施したことが窺えます。いかなることでも誰よりも優秀な人材…ああ、これ信長が施された養育と同じですね。まさに織田家のごとき教育で育て上げたのですね。ただ、この教育が信長を孤独にしたことも忘れられませんね。
さて、茶々の問いかけに「残念ながら槍も囲碁ももう敵いませぬ」と修理は答えます。武芸においても知性においても、大阪城内で彼に勝てる者はないのですね。修理はしみじみと「まこと逸材を育てられましたな」と言います。「今は亡き乱世の名将を思わせまする」との言葉は、茶々にとって最大の讃辞でしょう。信長、信玄、謙信などと秀頼が並んだのですから。
しかし、その讃辞が虚しいのは、それを発揮する場がないことです。ですから、「惜しいのう。柿が落ちるのをただ待つのが。家康を倒して手に入れてこそ真の天下であろう」と、改めて戦を望みます。流石に言葉に詰まる修理です。茶々の言葉は、力を持てばそれを使いたくなるという人間の心理を端的に表していますが、同時にそこには今もなお心の底に家康への逆恨みの炎が燻っているようにも思われますね。
そこに来たのは京大仏と共に作られた鐘に刻む鐘銘文の案の意見伺いに来た片桐且元です。そして、その案を見ながら茶々は自らの中に燃える戦への情熱を解き放つ方法を思いつきます。「面白い…面白いのう…」とほくそ笑む彼女の笑顔は悪魔の笑みと言えます。自身の個人的な感情だけで、全国を再び騒乱に巻き込もうとするのですから。
しかし、茶々にその気を抱かせるのは、相手が乱世を生き延びた天下人の家康だからです。家康はどこまでも戦国武将としての人生を全うせざるを得なくなります。
こうして、有名な方広寺鐘銘事件が起きます。鐘銘文のうちの「国家安康」「君臣豊楽」の2句、前者は家康の諱を「家」と「康」に分断して家康を呪詛しているのではないかとされ、後者は豊臣を君主として楽しむという底意が隠されているとされたあれです。通説では、徳川家の言いがかり説が取られますが、近年議論になっている豊臣方の挑発がここでは採用されたようです。「真田丸」では豊臣方の不注意でしたが、今回は茶々の無謀な暴走です。どちらの解釈でも豊臣家に救いがありませんね。
しかも、この描き方ですと、この事件には茶々の意向はあっても、そこに秀頼の意思が感じられません。そこで、先に話した二条城会見での狡猾な印象と千姫の前で見せた優しい顔との落差を再度考えてみましょう。
確かに秀頼は、麗しき見映え、腹芸も出来る聡明さ、武芸も一流と全てに才豊かな秀頼です。しかし、その一方で、実は彼自身が天下をどうしたいのか、そのビジョンや意志はほぼ描かれていません。何を考えているのかわからないと言ってよいでしょう。彼が自分の意思で動いたのは、謝る千姫を慰めたときだけかもしれません。勿論、武芸の稽古も京大仏建立に対する悦びも嘘ではないでしょう。しかし、それは茶々の教育であること、秀吉の生前の政策を受け継いだ結果であり、根っこの部分に彼の意思が介在していません。
こう考えていくと、秀頼に一つの可能性が見えてきます。それは、茶々や家臣らが望む役割を演じているということです。もしそうだとすれば、それはとても孤独で寂しいことですね。
また彼に天下のビジョンがないことも宜なるかなです。何故なら、茶々は天下を力で奪うことが目的化していて、その先のビジョンはないからです。彼女の教育は、そこまでは行き届かなかったのではないでしょうか。
茶々の念願は叶い、徳川家中でも寝耳に水のごとく大問題になります。金地院崇伝、林羅山が呼び寄せられた時点で大事です。二人を連れてきた正信は「とんでもない一手を打たれたようで…上手に少しずつ力を削ぐということは最早できませんな…」と残念そうに言います。この言葉は、これまで彼が戦を避けたい家康の意向を受けて、やってきた様々な策を講じてきたことが窺えますね。先の大仏建立の放置もその一つであることが、この台詞からも伝わりますね。
そうした努力で陰ながら家康の思いを支えた謀臣が「おそらく…避けられません」と囁くのは覚悟を促しているのです。
家康にも正信の意図はわかります「とうとう…戦か」と呟くとふぅーと深いため息をつき、瞠目します。秀忠に想いを託した今、彼はなすべきことをなすしかありません。
おわりに
多くの親しき者を失い孤独になった最晩年の家康の心境にあるのは、人生のタイムリミットに対して何もできていないことへの焦りと不安でした。更に圧迫する豊臣家という現実に、家康は、自身の目指す「戦無き世」への想いまでも揺るがされ、自身のこれまでの戦ばかりの結局は覇道だった人生、その犠牲を持ってすら実現し得ない夢を思い返し、自身の無力さと無駄な人生に絶望しました。老いは否応なしに、人を追い詰めるということ、その弱さを描かれたのが第45回でしょう。
その一方で、その弱さにも慈しみと救いを施すのが「どうする家康」です。本作は弱くても懸命に生きる人々を淡々と見つめながらも、それをないがしろにはしません。それは主人公である家康も同様です。結局、家康の絶望を救ったのは二人の人物でした。一人はかつて自分が命を救い、兄と慕った氏真です。彼は家康のおかげで救われ、家康が羨む満ち足りた人生を妻と共に送ることができました。そんな彼の存在が、家康の生きたこと、してきたことに意味があったということをささやかに知らせてくれます。そして、そんな彼が家康の哀しみを引き取ろうとします。家康の優しさは、回り回って彼自身を救います。
そして、氏真との邂逅は家康に遠い日の記憶を呼び覚まします。弱い白兎だったあの頃です。自身の弱さを認め、それを語る息子、秀忠にかつての自分と同じものを見ます。また、自身の志を受け継ぐ優しい人間性が息づいていることも見届けます。そのとき、彼は「戦無き世」とは、個人の力ではなく多くの平凡な人々の力によってなせること、そしてそれは一代で築けるものではなく、受け継いでいく中で完成されるものではないのか。そうした真実の一端に辿り着けたように思われます。それは、瀬名の願い、義元の教えを真に理解した瞬間にもなっているのが、シナリオ的には巧妙ですね。
今、自分のできることをして自分の代に「戦無き世」をなせずとも、その志を次代に託し、任せられることで十分なのだということです。ずっと自分が「戦無き世」をなさねばと思ってがむしゃらになり、それゆえに実現できないことに絶望した彼にとって、それは救いとなる気づきだったことでしょう。秀忠に夢を託す、その表情の穏やかな笑顔にその全てがあります。
つまり、「二人のプリンス」とは、家康を救った、かつて家康が救ったプリンス氏真と、将来を担い家康の志を受け継ぐ秀忠のことを指すのではないでしょうか?
こうして、家康がその天下人の孤独から思わぬ形で救われていくことで、「戦無き世」とは何なのか、誰が天下を治めるのか、その主役は誰なのか、「どうする家康」のテーマが表れてきたように思われます。
次回からはいよいよ大坂の陣です。家康がいかなる人生を全うするのか、静かに見届けたいものですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
