
太宰治『十二月八日』を読んで
掌編小説といってもいいくらいの分量しかないけど、
改めて読んでみてびっくりした。
太宰の妻の視点を奪取して、妻から見た自分、そして太平洋戦争開戦日であるその日の日本を描写しているのだが、まず最初に「この日記が”紀元二千七百年に見つかった時”によく思われるようなものとして」という話が出てくるのである。ある意味まだ今の時点でも皇紀2682年である事を考えても、その着想と、今日に通じる先取性を感じる。
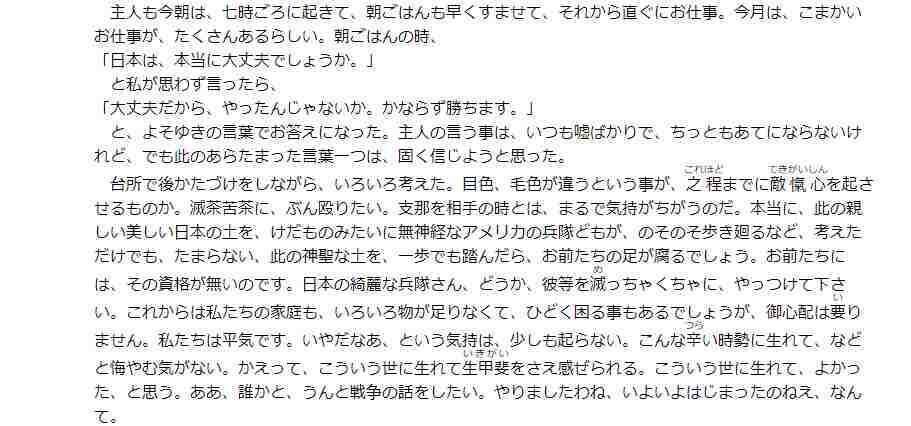
そして、切り抜いた画像の部分である。
この小説において、作者である太宰は「ダメ主人」というキャラを背負い、そのダメっぷりがこれでもかとてんこ盛りになっている。
しかし、その主人の口から「大丈夫だから、やったんじゃないか。かならず勝ちます」と言わせている。字面だけなら戦意高揚を通り越してもう戦争に勝った気分にさえなるが、そんなダメ主人が押す太鼓判、どう見ても逆説である。
さらに、戦況は恐ろしいほど日本有利、とても日本が負けると思えないような時期に、日本に米兵が上陸するなんてことを、たとえ有り得ない仮想としてでさえ着想して”恐ろしい・たまらない”と表現している。つまり、太宰は何かで「この戦争は負ける。そして日本は占領されるのだ」という予感を持っていたのだろう。
この作品の初出は、wikipediaによると1942年2月の『婦人公論』だという。日本中がハワイ奇襲・東南アジア進出・本当に大東亜共栄圏が出来るかも知れないという期待に溢れていた時期に、こんな文章が書かれていたのだ。読んだ人間は凡百の戦意高揚小説だと思ったのだろうか。多分もっと高揚した文章がこういう文芸雑誌にも勇ましく並んでいたのだろう。そう考えるとむしろ控えめな事が非難されてさえしまいそうなきもする。が、何しろ一般の雑誌ではなく、婦人誌である。そして女性の視点から描かれているわけだから、これぐらいの表現なら及第点は取れるのだろう。
例えばこれが「ハワイやカリフォルニアで苦しんでいる日系人を、日本の兵隊さんは解放してあげて下さい」等と書いてあれば、おお、まさにこの戦争を聖戦と思い込みたい当局や時流に乗りたがりの国民に対するウケが格段によくなっただろう。しかし、太宰はそんな世論の尻馬に乗るようなことはせず、とはいっても戦争反対を表明して獄に投ぜられ自らはともかく折角生まれた娘とその母親が露頭に迷うようなことを防ぐためにも”雲泥の差”であっても主人然として稼ぐ事を選択した。そうして、その場に置かれた状況の中で最大限のレトリックを使いながら、それこそ皇紀2700年にこの文章が見つかっても「世間に阿り筆を枉げた」と言わせないだけの作品を残したのだなと。
さて、今日本だけは何とか戦争はしていない。
しかし、隣国は、日本と反対側で戦争を仕掛けている。
日本でも、そんな隣国や、その隣国にシンパシーを持っているという複数の隣国に脅威を感じて、好戦的な言説や、それに対する”正面からの”反戦的言辞がそこここに見られる。
けれども、この時の太宰のような、確かな目をもちながら、しなやかな文章を書ける人はどれほどいるものだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
