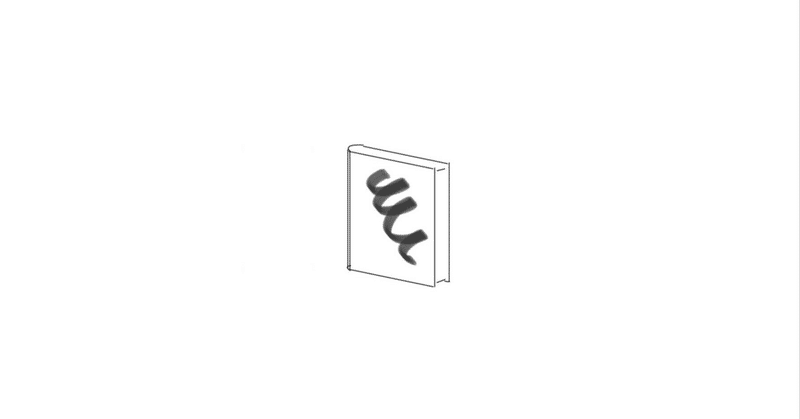
【読書記録】「竜馬がゆく」司馬遼太郎
歴史に疎く、坂本龍馬というと薩長同盟の立役者という知識しかなかった。船中八策、脱藩、新婚旅行、ピストルといった断片的なキーワードだけは知っているが、それぞれが繋がることはなく、大河ドラマも遙か忘却の彼方にある。幕末史の中でなぜかくも人気を占めているか、計りかねていた。
このような人間は一にも二にも歴史の教科書を読むべきなのだが、柄にもないなどと虚栄が抜けず、長いこと無知に蓋をし続けている。こういうものにとって歴史に忠実に沿いつつも読みやすい小説はありがたい。
殊に司馬遼太郎作品は、前途多難で万策尽きた状況にあってさえ筆致明るく、理由のない希望を抱かせてくれる。読んでいて一切の苦悶がない。船中八策のあたりでは興奮冷めやらず、日が昇ろうというのに布団の中で冴えた頭が鎮まらなかった。
司馬史観がクソミソに叩かれる時勢にあって、不勉強な人間が読んでいい本なのかは疑問が残るが、文学作品としてより一層司馬遼太郎に引き込まれることになった。以降も時代遅れの愛読書として本棚に置き続けることになると思う。
これを機に知人の勧めによりかつて尋ねた東山山麓の竜馬の墓の写真を見返してみた。

後書によれば、今の墓構えは時代が下って龍馬が再評価された頃、日露戦争時に昭憲皇太后の夢枕に立って以来のものだという。
最上に位置する木戸孝允の巨大な石碑と比べると、明治政府の立役者でありながら実現を見なかった維新志士の括りの一人にすぎない処遇を感じる。長州藩勤王体制を主導し、官職にあっても日本近代化を先頭で引っ張った男を讃えるには十分の大きさだが、他の墓と比較をするとどうしても判官贔屓を引き起こしてしまう。

坂本、中岡両人の墓と像は産寧坂からやや北方、維新成立のため足繁く行き来していた河原町を眺めている。木々が覆う霊山墓所の中でも、この区画は広く切り拓かれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
