
起業→会社員→起業と経て気付いた現代を生きる術
多かれ少なかれ、人は不安を抱えながら生きています。
主な原因は現状や将来に対する不確実性でしょうか。
健康やプライベート等、いろんな側面があると思いますが、とりわけ僕の場合は「社会で活躍できるのだろうか」という不安が大きかったです。
いつしかそんな仕事に関連する悩みもなくなったわけですが、それはなぜなのかと考えた時にひとつの結論に至ったので、久しぶりに記事を書いてみようと思った次第です。
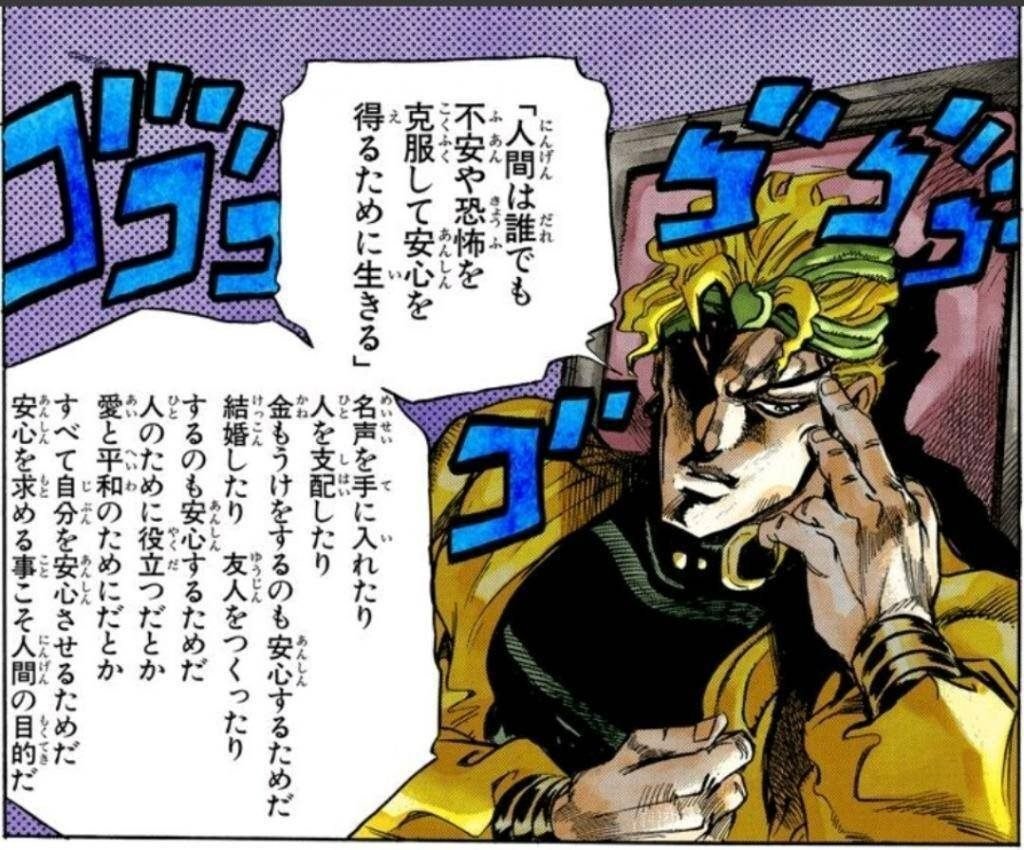
結論、社会で活躍する人はふたパターン存在する
「組織の一部として活躍できる人」と「どこでも活躍できる人」です。
それぞれの特色は以下の通りとなります。
①組織の一部として活躍できる人
自社に対する理解が深く、自社から高く評価されている
ニッチ領域のスキル、業務知識に長けている
社内SE、受託、自社開発企業に多い
②どこでも活躍できる人
市場に対する理解が深く、転職市場で引く手あまた
汎用性の高いスキル、業務知識を有している
SESエンジニアに多い
①と②は相反するものではないので両方兼ね備えている人もおり、弊社においても大活躍しています。
具体的には②であることを前提に、テクニケーションの仕組みを理解して部長ないし課長職に就いている方々となります。
※以下動画の0:45~から部長が登場
(伊藤)Bは現在7名体制で参画しているJava開発案件のチームリーダーとして活躍しており、さらには部と課に所属するメンバーのトラブル対応やキャリア面談もこなしています。
そんな人はめったにいない
「無理ゲーじゃん」と思われたかもしれませんが、ご安心ください。
そんなことができる人はごくわずかで、社会の9割以上が①②のいずれか or 両方満たしていない方です。
なので、多くの社会人は不安を抱えているのだと思います。
どこまでいけば安心感を得られるかは人それぞれですが、僕は②を目指すのが良いと思っています。
なぜなら不確実性が低いからです。
①は会社の文化や制度、人間関係にも左右されるため、答えらしい答えがなく、どうしても精神論に寄ってしまいます(それはそれで大事なのですが)。
「どこでも活躍できる人」になるためには
僕の思うSESの良いところは汎用性の高いスキルを身に着けやすいところ。これに尽きると思っています。
特定のクライアントや業種、システムに依存することなく、市場に出回っている案件(+自社が独自のパスで獲得している案件)から取捨選択し、技術者としての市場価値を高めて②をクリアすることができます。
以前、Qiita ConferenceでSESの仕組みを活かす方法について語っていますので、よろしければぜひw
自分自身と照らし合わせてみると…
学校卒業後、無職→フリーター→起業(失敗)→会社員→起業(イマココ)という遍歴を経て現在に至りますが、僕自身の不安が解消されたタイミングは会社員時代でした。
SES企業で営業や採用を経験し、半年経過したタイミングで「もう一人でも会社を回せるな」と。
今思うと非常に甘い考えではあるものの、いろんな方々のサポートを経て再度起業し、社員数276名、売上は月の売掛金ベースだと1億7千万円くらいにまでスケールさせることができました。
やってもいないので大きなことは言えないですが、これまでの実績をベースに、SESに限らず人材や採用領域であれば、別会社を設立したとしても自分が食っていける程度には成果を出せる自信があります。
特定の会社に依存するのではなく、様々な会社や社会から求められる人材になることで、将来への不安感は薄まっていきます。
んで、どうすりゃえーねん
今現在、SES企業で働くエンジニアなら以下がひとつの指針になると思います。
最初のふたつは②、最後は①に繋がります。
汎用性の高い技術で基本設計からリリースまで一貫した対応経験がある
リーダーとして、チームメンバーの進捗管理やフォロー経験がある
自社の評価制度に則った行動ができる
何も複雑なことはなく、例えば現在Strutsを用いたJava開発案件で詳細設計以降の経験を有しているなら、次のステップはSpring Bootを用いた基本設計以降に携われる案件を狙うであったり、オンプレのLinux環境の運用案件に携わっているなら、設計構築から携われる案件を狙うイメージです。
SEとして一通りの経験を積んだあとは、他の方をフォローすることでチーム全体の生産性に寄与できると、より②に近付くでしょう。
最後は出世を見越した要素なので好みが分かれると思いますが、SESと言えど会社組織として動いていることから、自社の方向性を理解して行動できる社員が評価されるのは至極当然のことです。
こうしてシンプルに考えると分かりやすいと思いませんか?
決して簡単なことではありませんが、かといって不可能なハードルではないはずです。
弊社は元々、なるべくリーダークラスとメンバークラスのエンジニアで体制を作り、現場業務を通じてスキルの底上げを狙っていましたが、今期からは組織体制を確立し、現場の垣根を超えてフォローする体制を整えました。
これにより、今まで以上に多くの方が①②を満たした人材となり、仕事のみならずプライベートも充実してくれれば良いなと期待しています。
やる?やらない?
こればかりは本人次第なので強要することはできません。
が、弊社内でポジティブなモチベーションを持った人が増えた結果、資格取得という形で影響が出始めて、気付けばJavaひとつ取ってもSilver持ちが51名、Gold持ちが15名と、スキルアップのため能動的にアクションを起こす人が後を絶ちません。
インフラも同様でAWS SAAとLPIC1がそれぞれ31名、IPAも基本情報が56名、応用情報が21名と、毎月資格保有者が増えている状況です。
実務と並行して資格取得するのは容易ではなく、本当に素晴らしいことだと思っています。
一人でも多く、「やる」側の人が増えることを願って。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
