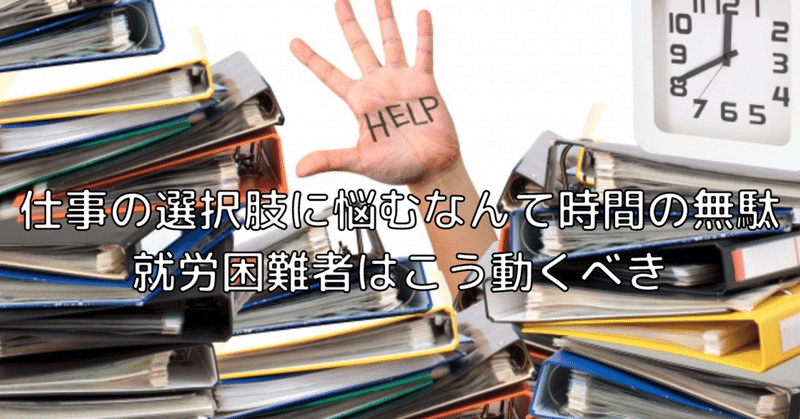
仕事の選択肢に悩むなんて時間の無駄 就労困難者はこう動くべき
ひと言に仕事と言ってもその業種や業態から、雇用形態に至るまで様々だ。
当然、どの仕事を選ぶか決めるのはあなた自身だ。
勿論、やりたい仕事、就きたい業種、希望する会社に入れるかは不透明だといえる。
今、仕事で悩んでいるあなたは一度立ち止まって大きく深呼吸しよう。
そして、何を考え、どう動き、どのような生活を手にすべきかという、ごく当たり前のことを冷静に決断して欲しい。
仕事の選択とは誰もが抱えるテーマである
仕事の選択と聞いてすぐに思いつくのは勤務体系や給与だろう。
一番の理想は自分や家族との時間が確実に取れる、それでいて自身の希望する報酬であることだと想像するが、これに異論を唱える方は多く無いだろう。
その大前提の中で、その会社の将来性であるとか、勤務地は何処か、転勤はあるのかといった外部要因と、自身のこれまでのキャリアで戦えるフィールドであるのかといった分析を開始する。
日々英会話に励み、異業種交流に精を出す。さらには週末には必ず3冊のビジネス書を読破するという目標を己に課し常にキャリアハイを目指す。
そのような方向けの指南書は世の中に溢れている為、ここでは就労困難者に向けたメッセージとなるような記事にしたいと思う。
就労困難者とはどのような人たちをいうのか
就労困難者とはどのような人、どのような状態の人を意味するのか、先ずはそこから考えて行こう。
一般的に定義されている就労困難者とは「就労に際して何かしらの課題や障害を抱えている人」ということになる。
そして結果としてその方々の現状として見られる傾向としては以下の2点だ。
1・無職である
2・低賃金である
就労困難者の定義からしてこの結論は当然であり、ここで重要な事はその対策と言える。
就労困難者に対する支援や対策とは
就労困難な方は仕方ないので我慢してください。
というほどこの国は冷たくない。
就労に関する相談から、訓練、出来る仕事の選択といった具合にそれぞれに応じた窓口や脱就労困難に向けた取り組みも多く存在する。
ここでは先ず、自身が国や自治体の定義する就職困難者に該当しているか、該当しているとしてどこに分類されるかを知ることから始めよう。
就職困難者に該当するのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者等となっている。
自身の現在地を把握する、もしくは現状で受けることの可能な支援やアドバイスを得ることが最優先であり、以下で詳しく確認できる。
就労に向けた具体的なアクションを起こす
自治体の相談窓口で自身の置かれた現状を包み隠さず相談することが大事だ。
・自身の身体、精神の状態(もちろん身内の方の相談も可能)
・現状の生活困窮程度や将来における不安
・早急に対応すべき課題
相談するだけですべてが解決するわけではないが、ひと時の安心に繋がるし、次に何をするべきかという方向性が明確になる。
ここからは支援員との相談内容に左右されるが、以下のような選択肢が考えられる。
・就労準備支援事業
これまでに挙げた“今すぐに社会に出ることに不安がある”“他人とのコミュニケーションに自信が無い”といった理由で直ちに就労するという選択肢を持てない方には、6か月から1年を上限とする一般就労に向けたサポートや就労機会の提供を行ってくれる。
・就労訓練事業
これは就労準備支援事業による支援だけでは不十分だと見込まれる、または自身が望むことにより、当人に相応しいであろう支援付き就労の場を提供するものだ。
こちらには中・長期的な支援を通じて一般就労を可能にする中間的就労といわれる就労訓練事業も準備されている。
就労に向けた相談から支援の流れ
1・先ずは相談窓口へ
各自治体が設けた相談窓口で相談しよう。
諸事情により窓口へ向かうことが困難な場合は、支援員が自宅に訪問して相談を聞いてくれることもある。
2・現状の把握
就労に関する事柄以外にも現状の生活における不安や課題をすべて支援員に相談することが大切だ。
そうすることで、問題解決に向けた課題を明確にして自立に向けた寄り添いを受けることが可能となり、一人で悩むという不安から解消される。
3・自身に最適なプランを組み立てる
現状を把握したなら次は問題解決に向けた具体的なアクションに移る必要がある。
そのアクションに必要となるプランを一緒に考えてくれるのが支援員だ。
支援員はあなたの意思を尊重しながら、支援プランといわれる自立に向けた目標や支援内容を一緒に考えてくれる。
4・支援決定
支援員と共に考えた支援プランは各自治体を通して正式決定される。
自治体の会議で正式決定された支援プランなので安心できるのはもちろん、確実に必要なサービスの提供が開始される。
5・定期的な見守り・寄り添い
自身に適したプランの為の各種サービスの提供が始まればその先はあなた一人で頑張りましょう。という訳ではないので安心して欲しい。
支援員による定期的な状況確認が行われ、その結果プランの見直し等も検討してもらえるため、さらなる不安やストレスを抱え込まないよう、無理をしないことが大切だ。
6・生活の安定へ
基本的にあなたの課題や困りごとが解決すれば支援の終了となる。
おわりに
今回の就労困難者向けのレポートは、生活困窮者自立支援法に基づく包括的な支援制度に沿った流れを紹介した。
次回は就労支援を目的とした就労継続支援事業所など、より現実的な就労困難者の現場について紹介したいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
