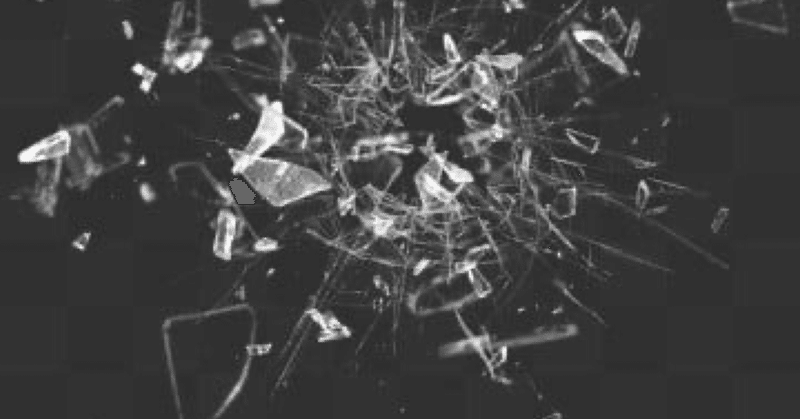
【小説】三面鏡
作:沫雪
「今までで一番印象的なお客さんっていますかぁ?」
薄暗い照明が照らすバーカウンター。会話の邪魔にならない程度にかかっている洋楽が耳に心地よい。そんな満ち足りた空間は、目の前に座っている女性の問いかけによって終わりを告げた。どうやら隣にいる常連さんとこの店の客について会話していたようだ。
「印象的、ですか…」
正直毎日のように来る常連を除けば、それなりに繁盛しているこの店に来た客のことなんてよっぽど強烈な印象がある人以外いちいち覚えちゃいない。いつものように適当な愛想笑いをしてすみません、話題にできるようなお客さんにお会いしたことなくて、と当たり障りなく流そうとした瞬間。ある一人の人物のことが脳裏によぎった。少し不思議な、3つの顔。面白いかどうかは分からないですけど、と保険をかけて口を開く。
「一人だけ、いますよ。印象に残ってるお客様」
一番最初にあの人が来店したのは確か2か月ほど前だったように思う。同い年であろう男性と一緒に仲睦まじい様子でカウンターに腰かけていたのを覚えている。
「あの、すみません」
少し控えめに声をかけてきたのは、隣に座っていた男性の方だった。お伺いします、と返事をして伝票をひったくる。
「テネシー・クーラーを二つで」
「かしこまりました」
若いのによく知っているな、と思った。テネシー・クーラー。ウイスキーベースのカクテルだが、使用できるのはテネシーウイスキーのみ。それにミントリキュールとレモンジュースなどを加えた見た目も涼しげなカクテルで、出ないことはないが最初がそれというのも珍しい。
「お待たせいたしました、テネシー・クーラーです」
“ウイスキーやカクテル、お好きなんですか?”という言葉がするりと口から出たのはバーテンダーとしては許して欲しいところである。2人は顔を見合わせた後、少し恥ずかしそうにはにかんだ。
「実は、俺も彼もお酒を飲むの初めてなんです」
「えっ、そうなんですか?」
ますますテネシー・クーラーなのが謎だ。もっと飲みやすい酒なんて腐るほどあるだろうに…
あまりにも考えていることが顔に出ていたのだろう。気恥ずかしそうに、彼は言葉を続けた。
「二人とも、人生で初めて酒を飲むときはお互いに同じものにしようと決めていて。調べているうちに見つけたのが、このカクテルなんです」
どうしてそこでテネシー・クーラーに決めたのかは、並んで座る二人の様子を見ればすぐに分かった。くすぐったいような、見ているこちらが恥ずかしくなるような初々しさをカウンター越しに漂わせながら、それでも二人はこれ以上ないほど幸せそうだった。蜂蜜をとろりと溶かし込んだような甘さと花が咲いたような幸福感が、あたりを満たしている。
どうかこの二人がこれからも上手くいきますように。そう思いながら、他のテーブルにオーダーを取りに行った。
彼が再び訪れたのは、それからわずか2日後のことだった。
その日は朝からずっとひどい雨が降り続いていた。悪天候のせいで客足もまばらで、さっきまで飲んでいたテーブル客が帰ってからは無音でプロジェクターに映し出される映画をぼんやりと眺める以外にすることはなく、暇を持て余していた。彼が来店したのはそんな時だった。
カランカラン、というドアベルの音と共に入ってきた彼は、二日前に隣の男性と静かに、だが幸せそうに笑っていたその人だった。年の割にやけに子供じみた、まるで幼児が持っているような傘を片手に立ちすくんでいる。
「いらっしゃいませ。―あの、大丈夫ですか…?」
後ろから入ってくる人物がいないのを見ると、今日は一人のようだ。いつまでも玄関に客を立たせておくわけにはいかない、と声をかけたその時。
「ぼくがこの前来たお店って、ここであってた?」
目の前の人物はうつむいていた顔を上げたかと思うと、こてんとあざとらしく首をかしげた。…本当に彼は自分が覚えている彼であっているだろうか。そんな一抹の不安を抱きつつ「えぇ、確か少し前にお連れ様とご来店していただいたと記憶しておりますが」と口を開いた。
「―そう、連れと、ね」
今までの表情が削げ落ちたような顔を見た瞬間、ひゅっと息がつまった。たった二日前まで一緒にいた彼と何かあったのだろうか。
「ねぇ、ぼくはこのまえどこに座ってたのかな?」
「…こちらの席です」
コロッと表情を変えて問いかけてくる彼に戸惑いを隠せないまま、以前座っていた席に案内する。何か言いしれない気持ち悪さがこみあげてくるようだった。
「どうしようかなぁ~」
差し出したメニュー表をぺらぺらとめくる様子はまるで珍しいものを見つけた幼子のように無邪気で、さっきの恐ろしい顔は嘘だったのではないかとさえ思えてくる。
正直、以前はあまりしゃべらず隣の男性を愛おしそうに眺めていたばかりで、その男性の連れという印象だった。しかし、今の彼は以前の彼とは少し違っているように感じる。そもそもずっと静かに酒を嗜んでいたのだから、あまりしゃべる方ではないのだろう。しかし目の前の彼は目が合った瞬間に
「あ、お兄さん、XYZお願い」
なんていってニコニコしている。どっちが本当の彼か、なんて一介のバーテンダーが考えるだけ無駄だ。前回は初めての酒ということもあって猫をかぶっていたんだろう、と思うことにして注文の品を作る。
「お待たせいたしました、XYZです」
「ふふ、ありがとう」
出来立てのカクテルを受け取った彼は一口飲んだ後、うっそりとした笑みを浮かべた。
―恐怖。それが彼に対して抱いた鮮烈な感情だった。
「ふふふ。まっててよ。もう少し、だからさー」
それから二か月ほど経って、彼は再び店を訪れた。
夏の終わりを感じさせる日差しが照り付けていたと思ったら夕方あたりから雲行きが怪しくなってきて、夜の帳が落ち店の看板に光が灯る頃にはしとしとと絹のような細い糸が空から降り注いでいる。きれいな雨、とでもいうのだろうか。店内のBGMとやけに相性のいい雨音を聞きながらグラスを拭いていた時に、彼はやってきた。
「…いらっしゃいませ。どうぞお好きな席へ」
そう声をかけると彼はカウンターに座り、少し困ったような、今まで見たことのない微笑みのようなものを浮かべ口を開いた。
「この前は随分と彼がー、いや、私が怖がらせてしまったようだね。すまなかった」
どうやら内心おびえていたのがばれていたらしい。これではバーテンダー失格である。少しどころかかなり気まずい空気を何とかしようと曖昧に返事をしながらメニュー表を出して、彼の注意が自分からそれたことを確認してほっと息を吐く。
―心臓がいくつあっても足りやしない。ちらりと盗み見た顔は確かに以前来店した人物と全く一緒だ。しかし、一番最初に出会った彼と、薄気味悪い笑みを浮かべていた彼と、今目の前に座っている彼が同一人物だとはどうしても思えなかった。
瓜二つのそっくりさんか?はたまた三つ子や兄弟だったりするのだろうか。しかし、彼はさっきわざわざ「私が」と言い直さなかったか?一体どうなっているんだ…と訳の分からなくなってきた思考回路は「すみません」という彼の呼びかけによって現実に引き戻された。
「ブルドッグをお願いします」
目の前の挙動不審なバーテンダーに苦笑をしつつ、彼はハッキリとカクテルの名を口にした。まるでなにか大切なことを伝えるかのように、しっかりと。
「―大切な人が、いらっしゃるんですか?」
カクテルを渡すと当時にこぼれ落ちた言葉は無意識だった。彼の目が真ん丸に見開かれているのを見て、自分はなんてことを口走ったんだと自分をぶん殴りたくなった。
すみません、忘れてください。そう言おうと口を開くより先に
「えぇ。一人だけ。」という彼の声が耳に届いた。
「一人だけ、いるんです。私にとって、これ以上ないほどに大切な人が」
その人を思い浮かべているのだろう、愛おしいものを見るような優しい表情をして彼は言った。それは以前となりにいた男性に向けていた恋愛感情の類ではない、いうなれば慈愛のようなものだった。
「だから私が守ってあげなくてはいけない。何に変えても」
なんて、少し格好つけすぎですね。と笑う彼から、なぜか目を離せなかった。
「ふうん?なんかよくわかんない人ですねぇ~」
少し怪しくなってきた滑舌で感想を述べた目の前の女性はぱちくりと瞬きをした後それだけかという失望感を隠しもせず、グラスに余っていた酒を飲み干した。
「だから言ったじゃないですか、面白いかは分からないですけどって。―お詫びと言っては何ですが、一杯サービスしますよ。何になさいますか?」
そう適当にご機嫌取りをしつつ、脳内を占めているのは先ほどまで話題にしていた彼のことだった。あの日以来、彼は店に来ていない。1人目の彼はあの恋人と上手くやれているだろうか。2人目の彼は少し怖かったけれど、話してみたら面白くていい人だったかもしれない。あの傘、なんだか似合ってたし。3人目の彼にあんなに想われている大切な人とは一体どんな人なんだろう。そう物思いにふける思考を呼び戻すのは、カランと鳴ったドアのベル。
「いらっしゃいませ」
長い夜は、まだ終わる気配はなさそうだ。
3つの顔の、ひとりの話
テネシー・クーラー:あの日の約束
XYZ:永遠に貴方のもの
ブルドッグ:守りたい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
