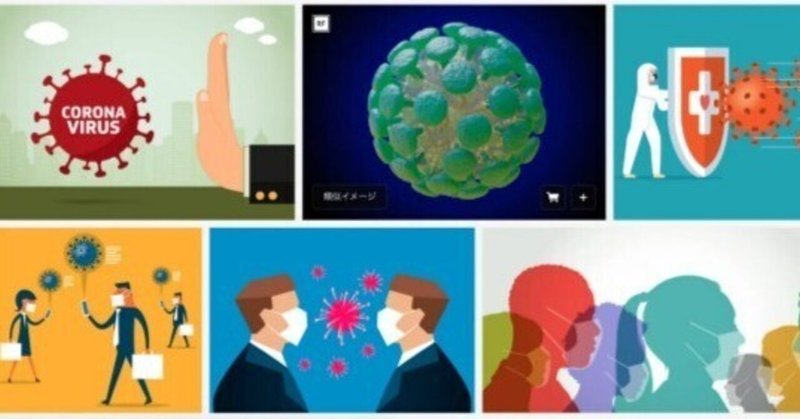
中小・民間病院のコロナ診療における役割
私が勤務する青燈会小豆畑病院は、新型コロナウイルス感染症拡大第5波の時(2021年9月)に、新型コロナウイルス専門病床10床を造って入院診療を行って参りました。42床の急性期病床のうちの21床を潰して10床のコロナ病棟を造りました。2022年の3月現在まで(第5波の終わりから第6波)コロナ診療を行ってきましたので、少し、私たちのような小さな民間病院がコロナ診療を行う意味を考えてみたいと思います。


令和3年の厚生労働白書を読むと、新型コロナウイルス感染症の入院患者受け入れ可能医療機関の現状がよくわかります。受け入れ可能医療機関は2558施設で、日本の全病院の34%と報告されています。日本の全病院の1/3が新型コロナの入院診療を行うことが可能ということです。(しかし、実際に受け入れ実績がある病院は2231施設であり327病院(全体の4.3%)が受け入れ実績がないことも報告がされています。その理由は記載されていませんから、この報告書からはわかりません。)では、受け入れ可能病院の特徴を見てみたいと思います。同報告書では、公立病院(国立病院や、市立病院、国立大学附属病院など)、公的等病院(日赤病院や済生会病院、私立大学附属病院など)、民間病院(公立、公的等以外の病院)にわけて検討しています。日本に医療の特徴は、病院の80%が民間病院であることなのですが、それはこの報告書からもわかります。そして公立病院の56%が、公的等病院の75%が新型コロナ感染症患者の入院を受け入れているのに対して、民間病院においては受け入れるのは17%と非常に低いことがわかります。(以上、背景2-1)
また、同報告書は、病院規模別で受け入れ医療機関の占める割合を検討しています。そこからわかることは、300床以上の病院では受け入れ病院の割合は90%以上であり、200床以上病院では71%、そして、100床以上199床未満で42%・100床未満で20%と、200床未満で急に低下することが示されています。(以上、背景2-2)。日本では200床以上の病院を大規模病院・199床を中小規模病院と定義され、制度の適応も変わってきます。
同報告書をまとめますと、日本の新型コロナ感染症の入院医療は、公立病院・公的等病院でかつ大規模病院が対応しているということになります。

上記画像を見て頂きたいと思います。□は一つの市(または区)と考えて頂いて良いと思います。医療は、2次医療圏という複数の市区を一つのまとめた圏域を1単位として考えます。保健所もこの2次医療圏を1単位として活動しています。この厚生労働白書からわかる日本のコロナ入院診療は、向かって左図のようになっていると言えます。2次医療圏内にある保健所(2022年3月現在は、行政の中にコロナ専門の調整本部が設けられていることが多くなっています)が、新型コロナ患者の診療依頼を、公立病院・公的等病院でかつ大規模病院に依頼しているイメージです。このなかには、軽症から重症までのすべての患者さんが含まれます。この場合、どうしても一つの医療機関に患者さんが集中します。同時に診療しなくてはいけない患者さんが増えますので、コロナ病棟の病床利用率は上がりますし、場合によっては入院できない患者さんも出てしまいます。これが、新型コロナ第5波の時に起きた、入院が必要な患者さんが入院できない社会状況を生んだ一因と思われます。
では、我々のような中小・民間病院がコロナ診療を行う意義は何なのでしょうか?上の図の向かって右側を見てください。新型コロナウイルス感染症は、軽症、中等症Ⅰ・Ⅱ、重症の4段階にその重症度を分けて治療されています。中等症Ⅰまではいわゆる酸素投与が必要のない病態で、ICUがない病院でも診療が可能です。中小・民間病院の役割は、この軽症・中等症Ⅰの患者さんの入院治療を行うことなのです。中小・民間病院は数多くありますから、これらの病院が入院診療に参加すれば、右図のように一気に病院数は増えます。また、今までの検討で、新型コロナウイルス感染症のうち47%
は軽症患者でありますから、大規模病院の患者さんは半分に減り、重症患者に注力できることになります。中小・民間病院が新型コロナ入院診療に参加することが、患者さんの受診アクセスを改善し、病院は重症度別診療に特化できるのです。

中小・民間病院が新型コロナ入院診療に参加する意味がもう一つあります。それは、中小病院特有の機動力を生かすことによる、発症から治療開始までの時間を短縮する効果です。
新型コロナウイルス感染症は、保健所がその診療の調整を行う感染症法第2類相当として扱われる病気です。従って、治療の初動から入院まで保健所が調整しています(現在は、調整本部が行っていることも多い)。その流れを簡単に説明しますと上図の左側のようになります。
患者さんが医療機関を受診して(多くはPCR検査を行っている中小医療機関)し、PCR陽性となると、医療機関から保健所に報告が行く
保健所がその患者をmedical check(入院が必要かどうかを判断するための検査。多くの場合、肺炎がないかのCT検査が行われる)のできる医療機関に、medical checkを依頼して、患者さんが受診
medical checkの結果が保健所の報告される。
medical checkの結果、入院が必要な患者さんに対して、保健所は入院可能医療機関(多くは大規模公的病院)に入院依頼をする。
このような流れを一つ一つ行っているうちに、少なくとも3日、患者さんが増えると対応病院を探すのに時間がかかりますので、5日ほどかかってしまうことがあります。それを我々の病院(のような中小・民間病院が参加することで)では2-3日に短縮できると考えています。なぜなら、今までの日本の新型コロナ診療の大まかな形として、中小病院がPCR検査やmedical checkを担当し、大規模病院が入院を請け負うスタイルでした。いわゆるPCR検査・medical checkを行う医療機関と、入院治療を行う医療が分かれていると言えると思います。それをPCRから入院診療までを中小・民間病院で行えるようにすれば、中小病院で治療できる軽症・中等症Ⅰまでの患者さんに関しては、一つの医療機関で完結できるのです。これが時間短縮の理由です。中等症Ⅱ・重症の患者さんはPCRまたはmedical checkで受診した時に、速やかに、重症が診れる大規模病院への入院を保健所に指示することもできます。

実際に半年間(新型コロナ第5波から第6波)、新型コロナ入院診療を行ってきた我々の病院の現状を知らせします。実際にmedical checkを行って入院必要と判断した患者の全員が当日、または翌日に入院していました。軽症から重症まで全員です。軽症から中等症1までは全員、当院に入院しました。中等症2の患者さんもmedical check当日に当院に入院し治療経過以後退院した人が2名、大規模病院に翌日転院した人が1名ありました。しかし、medical checkまでの時間が課題であることがわかりました。当院でPCRを担当した患者さんは当院ですぐにmedical checkを行えるのですが、medical checkの時点や入院となって初めて紹介される患者さんもありました。その場合、最大発症から7日たってからの入院となる方もありました。新型コロナ治療薬のなかには、発症から5日以上たってからの使用ではその効果が認められない薬もあり、これは大きな問題です。
今日は2022年3月20日です。私が働く茨城県ではつい2日前に1800名を超える今までの最大の新規患者感染報告がありました。まだ、気は許せませんが、これからも頑張って参ります。皆さんの健康をお祈りしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
