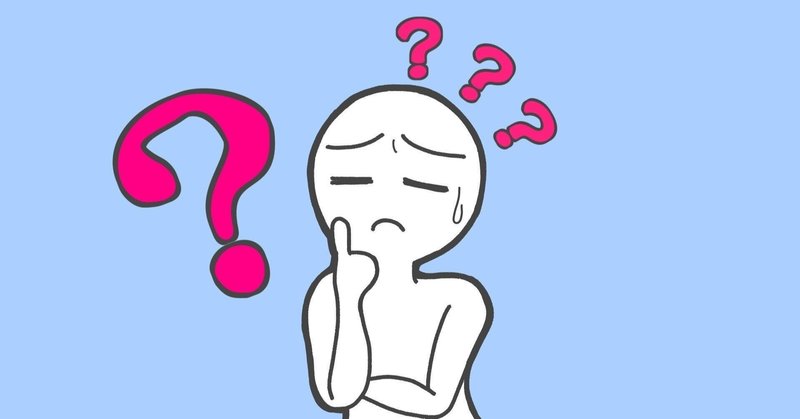
自作ドローンの飛行時によくあるトラブル
ドローンを自作して完成して、飛ばすことができた!でもちょっと変!?
この記事では、自作ドローンの飛行中のトラブルとして代表的なものを 7 つご紹介します。
主にマルチコプターを想定して記載しますが、飛行機やローバーでも共通点は多いかと思います。
1. モーターや ESC 関連の問題
モーターと ESC、どちらが破損したとしてもプロペラの回転が止まってしまいます。それまできれいに飛んでいたにも関わらず、機体の姿勢が突然崩れた場合にはモーターや ESC を確認してみてください。プロペラの破損や脱調、プロペラが外れたなどの可能性もあります。初めて飛ばす際に姿勢を崩す場合には、ESC キャリブレーションを正しく実施したかどうかも確認します。
2. PID チューニング
機体を飛ばしている際に、操縦に対して制御の反応が鈍かったり、舵を入れた瞬間に機体が揺れる(ハンチングする)場合には PID の調整が必要です。PID がかなりずれている場合、常にハンチングしてしまうこともあります。初めて飛行させる際には、同じような構成の機体(特にプロペラサイズ)の PID を参考に設定をしてください。
ArduPilot では以下のサイトが参考になります。
3. 振動
振動が高いと、加速度計の値に誤差が含まれるようになります。
加速度計は高度(垂直位置)や水平位置の推定に使われるため、振動が大きい機体の場合、高度や位置を維持できなくなる可能性があります。
対策としては、IMU に防振対策を行うことです。フライトコントローラに搭載されている IMU を使用している場合には、フライトコントローラに防振対策を実施します。振動吸収性の高い両面テープを使用したり、ダンパーを使う方法があります。
4. コンパスの干渉
鉄や電子機器などからの干渉により、コンパスから正しく方位を算出できなくなる場合があります。その場合、まっすぐ進もうと思っても曲がってしまったり、ホバリング(同じ位置で飛行)させているときに機首が勝手に動きだし、旋回し始めたりします。
問題が発生した時には、内的要因か外的要因か、静的要因か動的要因かに意識して切り分けていくとよいでしょう。
・内的要因
分電盤、モーター、バッテリー、ESC などドローンに搭載している装置からの影響
・外的要因
高圧線、高電流な電気配線付近や鉄の建造物付近など周辺環境からの影響
・静的要因
常に一定量の影響を受けている(例:コンパスの近くに磁石付の GPS アンテナを置いている)
・動的要因
状況や状態により影響度合いが変化する(例:スロットルを上げて急上昇するときに方位が勝手に変化する)
過去の記事でもコンパスに関する内容を取り扱っていますので、リンクを貼っておきます。
どうしてもコンパスの干渉を解消できない場合には、コンパスを使用しないという手もあります。
5. 電源関連
何らかの理由で高負荷となることで電圧低下が発生することや、断線により各センサーやデバイスに電源が供給されなくなる場合があります。空中で電圧低下が発生してフライトコントローラやモーターが一斉に停止してしまうと機体はそのまま自由落下します。
フライトコントローラに残されたログを確認できる場合には、ログが空中で突然途切れているのか、墜落した時のログが残されているのかを確認します。前者の場合には、空中で電源供給が失われたと考えてよいでしょう。後者の場合には電圧のログを確認して、電圧降下が発生していないかを確認しましょう。
6. GPS 関連
GPS を使用するモードで飛ばしている際に、衛星の捕捉数が足りない、またはマルチパスなどの影響などの理由から位置の誤差が発生して、勝手に機体が流れていく現象が発生します。
GPS といえば、アメリカで開発された位置測位システムですが、最近は GPS だけでなく、ロシアの GLONASS やヨーロッパの Galileoなど他の衛星からも情報を取得できる GNSS モジュールが使われるようになってきました。
そのため、衛星の捕捉数が足りなくなることはずいぶんと減ったように思うので、GNSS 関連のトラブルは減ってきているように思います。(願望?)
7. フェイルセーフ
多くのオートパイロットのソフトウェアではフェイルセーフの機能を備えています。
代表的なものを書けば以下のようなときにフェイルセーフ機能が働きます。
・バッテリー残量が少ないとき
・プロポの通信が途絶えたとき
そして、フェイルセーフが発生すると自動的にホーム(飛行開始した場所)に戻るなどのアクションが勝手に実行されます。
フェイルセーフの機能を正しく認識していなかったり、設定を間違えるなどのトラブルもあるため、事前に把握するようにしましょう。
例えば、屋内で飛行している時にフェイルセーフが発生し、機体が勝手に上昇することで天井にぶつかるというトラブルが挙げられます。
最後に
よく発生するトラブルを7つご紹介しました。
何かトラブルが発生した際には是非参考にしてください。
どのフライトコントローラ、オートパイロットのソフトウェアを使ったとしてもログ解析はできるかと思います。
ログを確認して、原因を把握することができるようになると、学びが増えて楽しさも倍増します。
ArduPilot の場合には、搭載するハードウェアによってはかなり細かく分析することもできます。慣れるまでは時間がかかって大変ですが、ログを見る習慣を身に付けておけば後々トラブルシューティングの時間を減らせたり、原因不明で諦めるといったことも少なくなります。
Wiki の資料も充実してきていますので、困ったときにはご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
