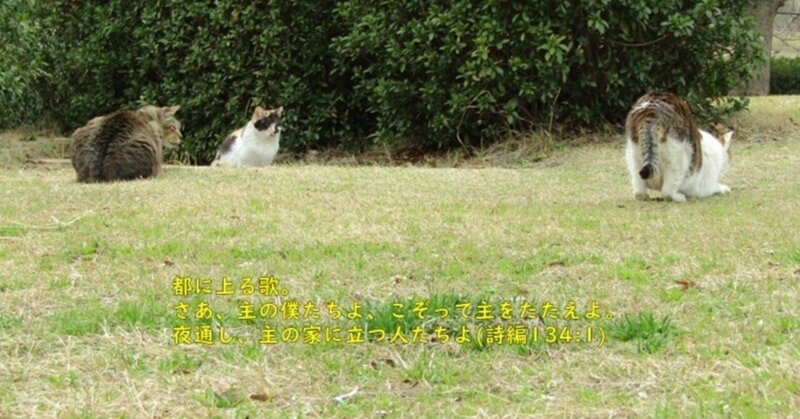
熱意ある詩人
詩編134:1-3
エルサレムの神殿へ詣でるということは、信仰篤い人々にとり、大きな喜びであったことでしょう。一年に一度の楽しみであったかもしれません。中には一生に一度という人がいたことも予想できます。日本にも、伊勢参りというものがありましたし、旅もままならぬ時代、旅が危険だった人々にとり、一大イベントであったに違いありません。
そのときに声を合わせて歌ったのか、そのために作られたのか、都上りの歌が旧約の詩編に取り入れられています。この130編の周辺には、特に短くきらめく歌が集められています。呼びかけている相手は、主の僕たちです。「主の家に立つ人たち」だと言っています。神殿に務める人々のことでしょうか。稀に来る人でなく、そこが居場所である人々です。
一年中とはいかずとも、神殿で、いわばビジネスライクに主に仕える人々です。給金もそこから出ているのでしょう。自ら信仰なしでは務まらないかもしれませんが、信仰熱心であるかどうか、は不問にされている、と言われてもおかしくないでしょう。キリスト教系学校の職員だと、必ずしもキリスト者でなくてもよいようになり、むしろ多数派かも。
観光地としての教会の経営に携わる職員も比較できるでしょうか。こうした人々に向かって「聖所に向かって手を上げ、主をたたえよ」と呼びかけるのは、一生に一度の喜びだとして神殿へやってくるような者、そういう設定であると想像してみましょう。このとき、私もまた、この詩を我が事として迎え入れることができました。
私たちの教会の指導者についても、それが生温ければ、このように対処してもよいのではないかと思うのです。組織の運営しか気にかけないような、キリスト教界の大物に対しても、この詩をぶつけてよいのではないでしょうか。天地を造られた方が、あなたを祝福してくださるように、と祈る必要が、そういうところにあるような気がしてなりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
