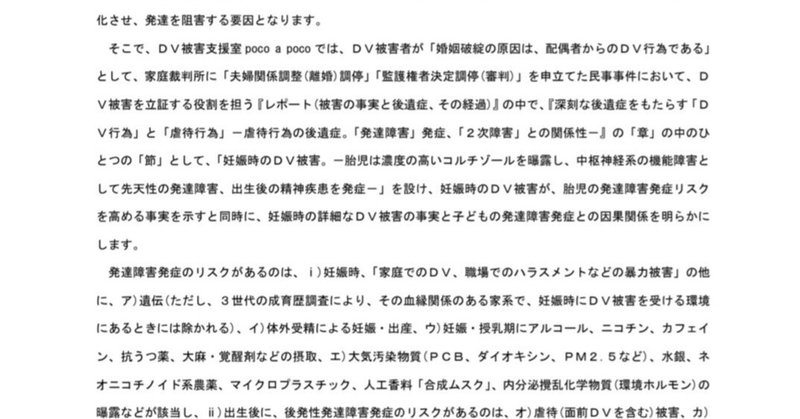
妊娠時のDV被害。-胎児は濃度の高いコルチゾールを曝露し、中枢神経系の機能障害として先天性の発達障害、出生後の精神疾患を発症-
* 子どものいるDV離婚事案で、子どもがADHD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)などの発達障害と診断されているときには、発達障害発症の要因と考えられるのが、妊娠しているときのDV被害(胎児虐待)です。
そのDV行為の加害者である配偶者(夫)が、子どもの監護権者になったり、離婚後(調停・裁判期間を含む)、その加害者である父親と発達障害の子どもとの面会交流を実施したりすることは、発達障害の子どもの症状を悪化させ、発達を阻害する要因となります。
そこで、DV被害支援室poco a pocoでは、DV被害者が「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」として、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」「監護権者決定調停(審判)」を申立てた民事事件において、DV被害を立証する役割を担う『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』の中で、『深刻な後遺症をもたらす「DV行為」と「虐待行為」-虐待行為の後遺症。「発達障害」発症、「2次障害」との関係性-』の「章」の中のひとつの「節」として、「妊娠時のDV被害。-胎児は濃度の高いコルチゾールを曝露し、中枢神経系の機能障害として先天性の発達障害、出生後の精神疾患を発症-」を設け、妊娠時のDV被害が、胎児の発達障害発症リスクを高める事実を示すと同時に、妊娠時の詳細なDV被害の事実と子どもの発達障害発症との因果関係を明らかにします。
発達障害発症のリスクがあるのは、ⅰ)妊娠時、「家庭でのDV、職場でのハラスメントなどの暴力被害」の他に、ア)遺伝(ただし、3世代の成育歴調査により、その血縁関係のある家系で、妊娠時にDV被害を受ける環境にあるときには除かれる)、イ)体外受精による妊娠・出産、ウ)妊娠・授乳期にアルコール、ニコチン、カフェイン、抗うつ薬、大麻・覚醒剤などの摂取、エ)大気汚染物質(PCB、ダイオキシン、PM2.5など)、水銀、ネオニコチノイド系農薬、マイクロプラスチック、人工香料「合成ムスク」、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の曝露などが該当し、ⅱ)出生後に、後発性発達障害発症のリスクがあるのは、オ)虐待(面前DVを含む)被害、カ)面前DV下での睡眠欠乏(中途覚醒による断眠)、キ)幼児期にスマートフォンやテレビゲームの長時間使用(視聴)、ⅲ)発達障害の症状と類似するとして、ク)低血糖症(ペットボトル症候群)をもたらす食生活などがあげられます。
また、発達障害の子どもが、ⅱ)-オ)カ)キ)の状況にあるとき、2次加害として、その症状や傾向は重篤化し、さまざまな併発症を伴うリスクが高まる。
したがって、「子どもの発達障害発症の主要因が妊娠時のDV被害である」と因果関係を示すには、ⅰ)-ア)イ)ウ)エ)、ⅱ)-オ)カ)キ)、ⅲ)-ク)などの正確な情報(知識)が必要となり、それらを含めた要因分析と検証(消去法、比較法など)のもとで、前者が主となる要因である主張することが可能となります。
また、この分析・検証には、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)』に準じ、女性センター長、あるいは、警察署長が一時保護を決定し、「母子生活支援施設(母子寮と呼ばれる行政機関のシェルター)」に入居し、その後、DV行為に及んだ加害者の交際相手や配偶者に居所を知られない土地で生活の再建をはかる中で、ADHD、自閉スペクトラム症などの発達障害と診断されていた「子どもの睡眠が改善し、生活の質が向上し、発達指数が大きく改善されたのか」なども含まれます。
なぜなら、この分析・検証の結果は、離婚後(調停などの期間を含む)、DV加害者であり、虐待加害者である父親が監護権者となるリスク、面会交流の実施するリスクを主張する重要な意味を持つからです。
なお、この章『深刻な後遺症をもたらす「DV行為」と「虐待行為」-虐待行為の後遺症。「発達障害」発症、「2次障害」との関係性-』のひとつの「節(妊娠時のDV被害。-胎児は濃度の高いコルチゾールを曝露し、中枢神経系の機能障害として先天性の発達障害、出生後の精神疾患を発症-)」をリライトするにあたり、『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』に記述されていたDV事案として、エビデンスにもとづく事実の立証にかかわる記述はすべて消し込み、一方で、調停などで不利になる可能性があること記述していない重要なテーマなどについて、一部加筆しました。
このリライトにあたり、DV事案としての事実の立証という文脈で説明している部分を消し込んだことで、多少、文脈に違和感を覚える可能性があります。
ご容赦ください。
1. 先天的(胎児)に、中枢神経系の機能障害をもたらす2つの要因
(1) 胎児が、濃度の高いコルチゾールの曝露すると
① コルチゾールの暴露。妊娠5週以降「中枢神経系の機能障害」をもたらす
② 女児に限り表れる「扁桃体」の異常
(2) 胎児期・小児期に、ネオニコチノイド系農薬など環境化学物質に曝露すると
・ キーワードは、「胎児関門」「血液脳間門」を通過できる物質
(3) 体外受精で妊娠、生まれた子どもの高い発達障害発症リスク
2.胎児期、乳幼児期のDV被害。胎児期・乳幼児期の脳形成への影響
(1) 「胎児虐待」という捉え方
(2) 乳幼児期の面前DV=心理的虐待
(3) 面前DV・虐待行為、高い発達障害発症率
① 乳幼児期の睡眠障害と発達障害の発症
② セロトニンの減少と発達障害の発症の関係性
③ 腸内細菌環境の劣化がセロトニン形成に影響
④ ADHD、精神疾患と間違われやすい「低血糖症(ペットボトル症候群)」
⑤ 消化器系の問題を抱える自閉スペクトラム症。腸内細菌との関係
3.発達障害の発症原因となる大気汚染、ネオニコチノイド系農薬
(1) 喫煙・受動喫煙(ニコチン)
(2) ダイオキシン、PCB、PM2.5
(3) ネオニコチノイド系農薬
(4) 子宮内で、内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)に曝露した胎児
(5) マイクロプラスチックと内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)
(6) 人工香料「合成ムスク」
(7) 週数別胎児の成長と薬の影響
4.長時間のテレビゲームなど、前頭前野の発達不全に
(1) 乳幼児期にテレビ・スマートフォンなどの長時間の使用、高いADHDの発症率
(2) ゲーム依存(ゲーム脳)
(3) VR(仮想現実)
(4) ネット利用
(5) アレキシサイミア
(6) スマートフォン
① 睡眠障害など
② 浅い本読みで、深い思考不全に
③ メンタル統合(前頭前野統合)と文章理解
DV事案で見落とされてきたのは、夫婦間にDV行為があり、子どもがADHD、自閉スペクトラム症、学習障害(LD)などの発達障害と診断されているとき、その発症が、「胎児期に受けた母親のDV被害」、「出生後の乳児期に、母親に対するDV被害(面前DV=心理的虐待被害)」、「出生後の乳幼児期に受けた虐待被害」であるという視点である。
『別紙2』の「3-(14)反応性愛着障害(RAD)」で述べているように、虐待の後遺症として生じる「(反応性)愛着障害」の諸症状には、発達障害(ADHDなど)の示す臨床像に極似する。
発達障害といわざるを得ない臨床像を呈し、虐待を受け、発達障害と診断されている子どもの30-40%は愛着障害であり、ADHDの子どもの養育歴をていねいに聴き、行動特性について時間をかけて観察すると、その70%は「発達性トラウマ」の問題を抱えていると指摘されている。
そのため、『別紙2』の「2-(1)虐待は、子どもの脳を委縮させる」では、子どもの脳を萎縮させるなど、脳の器質的機能的異常を生じさせるのは、出生後の虐待行為にもとづいている。
そこで、この“節(妊娠時のDV被害。-胎児は濃度の高いコルチゾールを曝露し、中枢神経系の機能障害として先天性の発達障害、出生後の精神疾患を発症-)”では、発達障害の原因である「先天性の中枢神経系の機能障害」をもたらす主要因は、母体がストレスにさらされ、胎児が、濃度の高いコルチゾールなどの曝露することにフォーカスする。
つまり、妊娠期の女性に対する交際相手や配偶者のDV行為は、子どもの胎児期の脳の中枢神経系の機能障害をもたらす。
この“節(妊娠時のDV被害。-胎児は濃度の高いコルチゾールを曝露し、中枢神経系の機能障害として先天性の発達障害、出生後の精神疾患を発症-)”では触れないが、「小児型ADHD」と「遅発型ADHD」は発症経路が異なる。
遅発型ADHDは、出生した子どもが、暴力のある家庭環境で暮らし、育つという“環境要因”により動的に変化、つまり、出生後の脳の発達に強い影響を受けて発症する。
遅発型ADHD=自己正当化型ADHDではないが、その特徴は、機能障害や他の精神疾患を示すなど、注意欠如、活動過剰、衝動的行動などの症状が、子どもで見られるよりも重度の症状を示すことが多く、不安神経症、うつ病、薬物やアルコールの依存症などの罹患率が高くなり、交通事故や犯罪行動などの増加を伴う傾向が見られる。
そういった意味で、反応性愛着障害、行為障害と酷似する。
脳の発達という視点で重要な意味を持つ乳幼児期に面前DV(=心理的虐待)被害を受けると、いうまでもなく、直接、濃度の高いコルチゾールに曝露する。
つまり、胎児期と乳幼児期の脳の発達という視点に立つと、子ども後発性ADHD、反応性愛着障害、行為障害の発症と児童虐待・面前DVは、密接に関係する。
繰り返しになるが、子どもの脳の発達に影響を与える時期は、出生後の生活環境だけでなく、「出生前の妊娠期」、つまり、「胎児期の母体環境」からはじまる。
そのため、喫煙・受動喫煙(ニコチン)、大気汚染(PM2.5など)、水銀、ネオニコチノイド系農薬などの化学物質が胎児期の脳に与える影響と同様に、妊娠している女性が受けた暴力被害によるストレスは、母体を通じて胎児が曝露し、ADHDなどの発達障害、行為障害(破壊的行動障害)、うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患の発症リスクとなり得る“環境因子”と捉える必要がある。
『別紙2』の「2-(1)虐待は、子どもの脳を委縮させる」で述べているように、近年、MRI画像診断などを使った研究により、被虐待体験者の脳の特定の部位に萎縮(器質的な損傷)が確認できる(視覚化できる)ようになり、脳科学は飛躍的に発展したことで、さまざまな研究報告がなされ、「発達障害、精神疾患などの多くが、遺伝因子にもとづくものではなく、後天的な環境因子にもとづくものである」ことが裏づけられてきた。
父親から暴力を受ける母親のストレスは、胎児期の脳の器質的発達に影響を及ぼし、このことが、発達障害や精神疾患の発症原因となり、加えて、出生後の乳幼児期に暴力のある家庭環境で暮らし、育つ、つまり、子どもが被虐待体験(逆境的小児期体験)をして育つことも後発性の発達障害、愛着障害、行為障害、人格障害(妄想性、自己愛性、サイコパス、ボーダーラインなど)、パラフィリア、PTSD、その併発症としてのうつ病、パニック障害、解離性障害、統合失調症など、さまざまな精神疾患を発症原因となっている。
また、このことが、暴力の連鎖、貧困の連鎖の要因のひとつとなっている。
このように、この節(妊娠時のDV被害。-胎児は濃度の高いコルチゾールを曝露し、中枢神経系の機能障害として先天性の発達障害、出生後の精神疾患を発症-)は、ADHD、自閉スペクトラム症、学習障害(LD)などの発達障害と診断された子どもがいるDV事案として欠くことのできない視点である。
この“環境要因”として、妊婦がDV被害によるストレスにさらされ、胎児が濃度の高いコルチゾールなどの曝露による要因の他に、ADHD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)などの発達障害の発症リスクを高めているのが、ネオニコチノイド系農薬など環境化学物質汚染である。
① 先天的(胎児)に、中枢神経系の機能障害をもたらす2つの要因
虐待を受け、児童養護施設に保護された児童の多くに、「反応性愛着障害」、「情緒障害」だけでなく、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」や「LD(学習障害)」、「軽い知的障害」が見られることはよく知られている。
児童養護施設に保護され、その時点で、「反応性愛着障害」、「情緒障害」、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」、「LD(学習障害)」、「軽い知的障害」を発症している児童は、通常、出生後に、親から虐待行為を受けてきた事実だけに注目される。
しかし、『脳科学辞典(理化学研究所の脳科学総合研究センターのメンバーらが中心となって運営しているオンライン百科事典)』では、「発達障害とは、主に、乳幼児期、あるいは、小児期にかけてその特性が顕在化する発達の遅れまたは偏りであり、主に、先天性の中枢神経系の機能障害を原因とする。広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)、学習障害、注意欠如/多動性障害、知的障害などが含まれる。」と記述されている。
つまり、発達障害の発症は、“先天性(先天的)”なもの、つまり、“生まれつき”と規定されている。
そこで、この“先天性(先天的)”を“胎児期”にと置き換えると、「胎児期に、中枢神経系の機能障害を生じた疾患」と読み替えることである。
胎児になる前は、精子、卵子の遺伝子情報となる。
つまり、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」、「LD(学習障害)」、「軽い知的障害」された子どもは、「胎児期に、中枢神経系の機能障害を生じた」と考えることができれば、「胎児の母体である母親が、DV被害にあっていた」、「その結果、胎児は、中神経系の機能障害を負った」と理解できると思う。
では、妊娠している女性が、DV被害にあうと、その子どもが発達障害を発症するリスクが高くなるのかを説明する。
a) 胎児が、濃度の高いコルチゾールの曝露すると
胎児の母体である女性が、交際相手や配偶者からDV行為などの暴力被害を受けると、『別紙2』の「1.PTSDの症状(解説)」の冒頭で述べているように、女性は強烈なストレスを覚え、緊張状態となり、アドレナリン、コルチゾールなどのストレスホルモンを分泌しながら戦闘態勢として身を守ろうとする。
このとき、胎児の母体の血液は、脅威(外敵)と戦うために心臓、脳などに優先的に送り込まれ、胃、腸などの消化器、子宮は後回しとなる。
母体の子宮に流れてくる血液量が減ると、胎盤から栄養をとり込む胎児は、栄養不足に陥り、こうした状況が慢性反復的(常態的)に繰り返されると、胎児の発育に影響が及ぶ。
さらに、母体が慢性反復的(常態的)にストレスにさらされ、胎盤が未熟な時期の胎児がコルチゾールの曝露により、胎児の胎動や心拍数は減少し、中枢神経系の発達に影響を及ぼす。
また、胎児期の高濃度コルチゾール曝露により生じた高血圧遺伝子の活性化が、エピジェネティク(遺伝暗号を超えた要因)により、胎児の脳に記録され、出生し成長すると「食塩感受性高血圧」を発症させる。
そして、母体がストレスを受け、コルチゾールが分泌されると、血管収縮作用により流産、早産をもたらす。
ア) コルチゾールの暴露。妊娠5週以降「中枢神経系の機能障害」をもたらす
コルチゾールの曝露により、胎児が影響を受ける「中枢神経系」とは、神経系の中で多数の神経細胞が集まり、大きなまとまりになっている領域のことで、「脳」と「脊髄」からなる。
脳は、大きく大脳、小脳、脳幹の3つに分けられ、人では、特に大脳が発達し、その重量は、脳全体の約80%を占め、思考や判断し行動する機能などを司る「前頭葉」、知覚や感覚などを司る「頭頂葉」、視覚を司る「後頭葉」、聴覚や記憶などを司る「側頭葉」の4つの領域がある。
「前頭葉」の大部分を占めるのが「前頭前野」で、「考える」「記憶する」「アイデアをだす」「判断する」「応用する」「行動や感情をコントロールする」「コミュニケーションをする」「集中する」「やる気をだす」など、人にとって重要な働きを担っている。
この「前頭前野」が発達不全であったり、衰えたりすると、物忘れをしたり(増えたり)、考えることができなかったり(できなくなったり)、感情的であったり(になったり)、やる気がなかったり(低下したり)する。
脊髄は、脳につながっており、脊椎(背骨)の中央を上下に貫く脊柱管の中に入っていて、脊髄は、脳とからだの各部の間に起こる刺激(知覚)や命令(運動)を伝えなど反射中枢としての役割を担う。
では、この「中枢神経系」は、胎児期のいつ発達するのだろうか?
それは、妊娠5週以降である。
妊娠5週になると、脳と脊髄のもとである神経管が膨らみはじめ、妊娠7週までに、脳や脊髄の神経細胞の約80%がつくられ、目の視神経、耳の聴神経など、感覚器官の神経細胞も発達しはじめる。
妊娠第1、第2、第3三半期における大脳皮質発生の概略は、以下のようになる。
a)第1三半期(妊娠0週0日-13週6日):神経幹細胞の発生・分裂、神経発生・移動、シナプス結合形成開始
b)第2三半期(妊娠14週0日-27週6日):神経発生・移動、軸索・樹状突起の形成やシナプス結合形成、髄鞘形成開始
c)第3三半期(妊娠28週0日以降):軸索伸長・樹状突起の分枝やシナプス形成促進、グリア増生および髄鞘形成
「妊娠第1三半期」は、胎児の形成に大変重要な時期であり、流産・奇形の発症と大きく関連する。
「統合失調症」の発症の感受性の高い時期は、この「妊娠第1三半期」と生後の「思春期後期(12-15歳)」「青年期前期(15-18歳)」で、妊娠第1三半期に母体がストレスにさらされると、胎児の大脳皮質の発生や機能構築に影響を及ぼし、統合失調症発症のリスクを高める。
「大脳皮質」は、脳の表層を覆うシワシワの部分で、前頭葉(前頭前野)、頭頂葉、側頭葉などと呼ばれる部位の総称で、大脳皮質の厚さは、(脳の外側を覆うシワシワの層)」の厚さは、2歳頃にピークを迎え、知覚、言語、意識などのプロセスに関与している。
つまり、人の高次認知機能は、大脳皮質(前頭葉(前頭前野)、頭頂葉、側頭葉など)の神経回路が担っている。
妊娠期に受けるストレスは、統合失調症と同様に、子どもの発達障害発症のリスクを増大させるが、その事実が示されたのは、1980年-1995年(昭和55年-同平成7年)の16年間に、アメリカのルイジアナ州で、サイクロンによる災害にみまわれた妊婦から生まれた子どもの自閉症発症のリスクが増大したことである。
同様に、妊娠中の離婚、転居などによるストレス、妊婦の妊娠中の重度の不安状態は、生まれてくる子どものADHDの発症リスクを増大させたり、脳の炎症性反応を惹起しやすくしたりする。
脳の炎症性反応が発症原因となる疾患は、「慢性疲労症候群」「過敏性腸症候群」などである。
母体がストレスにさらされると、「視床下部-下垂体-副腎系」が活性化する。
慢性的な妊娠期のストレスは、血中コルチゾール、および、胎盤からの副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン分泌を増加させ、胎児の神経前駆細胞の分裂、神経分化の抑制、HPA軸の発達異常をひき起こす。
「HPA軸(HPA機能)」とは、『別紙2』の「1.PTSDの症状(解説)」の冒頭で述べているように、PTSDの発症に大きくかかわる「ストレス応答や免疫、摂食、睡眠、情動、繁殖性行動、エネルギー代謝などを含む多くの体内活動に関して、視床下部、下垂体、副腎の間でフィードバックのある相互作用を行い制御している神経内分泌系」のことである。
このようなメカニズムにより、妊娠期のストレスは、胎児のストレス応答系、脳の発生に影響を及ぼし、生後のうつ病、不安障害、統合失調症などの精神疾患、発達障害の発症リスクを増加させる。
つまり、胎児は「血液脳関門」の未発達な時期(生後6ヶ月まで)で、特に、第1三半期(妊娠0週0日-13週6日)の「妊娠5-8週(器官形成期)」「9-12週(手足などの形成期)」に、妊婦がDV被害などの強烈なストレスにさらされると、胎児は濃度の高いコルチゾールなどの曝露により、胎児の「中枢神経系」の発達が損なわれ、出生後、ADHD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)などの発達障害、さまざまな精神疾患を発症する高いリスクを負う。
イ) 女児に限り表れる「扁桃体」の異常
特に、胎児が女児であるときに限り、母体のコルチゾールの濃度が高いと、古代脳(古皮質)の「扁桃体」が絡む神経ネットワークの結びつきが強くなり、また、出生後、抑うつ的な行動が増えるという結果がでている。
この事実は、特に重要で、胎児期に濃度の高いコルチゾールに曝露した女児は、同じ状況で生まれた男児に比べ、生まれながらにして、強い不安、恐怖を覚えやすく、将来、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、うつ病、不安障害、パニック障害などの精神疾患に発症しやすくなる。
PTSDやうつ病の有病率は、女性が男性の2倍高いといわれる。
平成23年(2011年)3月11日に発生した「東日本大震災」では、震災から2年半後、心的外傷後ストレス症状が、女性の31.0%、男性の19.4%に認められ、1.6倍の男女差が確認されるなど、PTSDの発症には、明確な男女差が認められる。
過去にうつ病、不安障害、パニック障害などの精神疾患、心身症を発症していたり、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしたりしていると、地震や水害などの自然災害、事故、火災などに遭遇したときには、PTSDを発症しやすく、PTSDを発症したときには重症化し、併発症としてうつ病を発症しやすく、しかも、そのうつ病の症状も重症化しやすい。
PTSDを発症しやすい人に共通しているのは、不安・緊張を覚えやすかったり、不安・緊張に陥りやすい状況になったりすることである。
この「不安・緊張」と深くかかわるのが、胎児期、濃度の高いコルチゾールに被爆した女児だけに認められた古代脳(古皮質)の「扁桃体」が絡む神経ネットワークの結びつきが強くなった」ことである。
強い不安を示す人は、そうでない人と比べて、「扁桃体」と「海馬」との結合が強いことがわかっている。
物事を記憶する能力の他に、興奮したり、恐怖を覚えたりする能力に深く関連している「扁桃体」と「海馬」が機能不全に陥ると、恐怖を覚えやすくなったり、逆に、興奮し難くなったりする。
では、PTSD、うつ病、不安障害、パニック障害の発症と深くかかわる「扁桃体」の理解は、特に重要であることから、『別紙2』の「1.PTSDの症状(解説)」の記述を引用すると、大脳辺縁系の「扁桃体」は、恐怖感、不安、悲しみ、喜び、直観力、痛み、記憶、価値判断、情動の処理、交感神経に関与している(24文)。
「扁桃体」は神経細胞の集まりで、情動反応の処理と短期的記憶において主要な役割を持ち、情動・感情の処理(好悪、快不快を起こす)、直観力、恐怖、記憶形成、痛み、ストレス反応、特に、不安や緊張、恐怖反応において重要な役割を担う(25文)。
味覚、嗅覚、内臓感覚、聴覚、視覚、体性感覚など外的な刺激を「嗅球」や「脳幹」から直接的に受け、「視床核(視覚、聴覚など)」を介して間接的に受け、「大脳皮質」で処理された情報、および、「海馬」からも受けとる(26文)。
また、扁桃体は、「記憶固定」の調節にかかわる(27文)。
学習したできごとのあとに、そのできごとの長期記憶が即座に形成されるわけではなく、そのできごとに関する情報は、「記憶固定」と呼ばれる処理によって長期的な貯蔵庫にゆっくりと同化され、半永久的な状態へと変化し、生涯にわたり保たれる(28文)。
衝撃的なできごとが起こる(トラウマとなり得る体験をする)と、そのできごとは、「海馬」を通して大脳に記憶として生涯的に残る(29文)。
この衝撃的な記憶を反復して思いだす(トラウマを追体験する)ことにより、「扁桃体」が過剰に働く(30文)。
つまり、強い不安や恐怖、緊張が長く続くと「扁桃体」が過剰に働き、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が長く続くことから神経細胞が萎縮し、他の脳神経細胞との情報伝達に影響し、「うつ病」の症状が発現する(31文)。
では、人が危機にあったとき、「扁桃体」の働きとPTSD発症するメカニズムについても、『別紙2』の「1.PTSDの症状(解説)」の記述を引用すると、トラウマ(心的外傷)体験となる危機に遭遇すると、脳のⅰ)「視床」は、危険の情報をキャッチし、ⅱ)「扁桃体」が危険信号をだす(10文)。
そして、ⅲ)「視床下部」で、「CRFホルモン」が「脳下垂体」を刺激し、ⅳ)「脳下垂体」は、「副腎」を刺激し、緊張ホルモン「コルチゾール」「アドレナリン」を分泌させる(11文)。
その結果、ⅴ)「脳幹」が血圧を上げ、心拍を早くし、血糖値を上げる(12文)。
「CRF(corticotropin releasing factor:副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)」は、視床下部から分泌されるペプチドホルモンのひとつで、「ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)」の放出を刺激する(13文)。
CRFが分泌され、前頭連合分野に伝達されると「不安」が生じる(14文)。
その不安を抑えるために、抑制性の神経伝達物質「セロトニン」の分泌を亢進させ、抑制性の神経伝達を亢進させることで、「前頭連合野」の興奮を抑制することができると不安が解消される(15文)。
慢性的なストレス刺激は、「扁桃体」を異常に興奮させるので、CRFの分泌が異常に促進し、不安が強まる(16文)。
「セロトニン」がその不安を抑制することができないと、理由のわからない不安感に苛まれることになる(17文)。
「コルチゾール」や「アドレナリン」などの緊張ホルモンが、脳や体内に回って、危険と立ち向かう超人的な力をださせたり、物凄い勢いで逃げたり、気絶したりするなどの反応をおこさせる(18文)。
このことを「HPA機能」という(19文)。
この結果、ⅵ)「前頭葉」とことばをだす「ブローカー野」は機能を停止する(20文)。
この「HPA機能」により、「ⅵ)「前頭葉」とことばをだす「ブローカー野」は機能を停止する。」ことを“フリーズ”という(21文)。
レイプされたり、殴られたりしたときに、「助けて!」が声にならなかったり、茫然と佇んだり、からだが動かずに逃げられなかったりする(22文)。
そして、予期できないできごとは、恐怖が拡大し、「扁桃体」の興奮が続くと「ストレス障害」になり(23文)、「急性ストレス障害(ASD)」が示す症状が4週間以上継続するか(診断は、3ヶ月程度を目途にする場合が多い)、なにかがきっかけとなりあとに表れるのが「PTSD」である。
なにかのきっかけで、突然、ASDの症状を示し、その症状が長期化するPTSDは「後発性/遅延性PTSD」と呼ばれ、この“後発性”は、PTSDの特徴のひとつである。
このように、PTSDとうつ病の発症には「扁桃体」が深くかかわり、その「扁桃体」は、胎児期に、女児に限り、濃度の高いコルチゾールに曝露することで影響を受ける。
つまり、胎児期に、母親がDV被害を受け、慢性反復的(常態的)に濃度の高いコルチゾールに曝露した女児は、先天的に(生まれながらにして)、PTSD、うつ病、不安障害、パニック障害など発症しやすく、同時に、「固定記憶」の調節にも影響が及ぶ。
胎児が、濃度の高いコルチゾールに曝露し、中枢神経系の発達に影響が及ぶ前の妊娠期の初期、つまり、妊娠5週以降であることから、胎児が出生後、発達障害やさまざまな性疾患発症リスクを少なくするには、妊娠しているDV被害女性(胎児の母親)が、暴力のある環境から離れ、DV被害を受けない必要がある。
胎児の母体である母親が、そのタイミングを逸すると、胎児は男女ともに、生まれながらにして、中枢神経系の機能障害を抱えるリスクがあり、しかも、女児に限っては、「扁桃体」に顕著な変異が認められることになる。
生まれながらして、中枢神経系の機能障害に加え、「扁桃体」の障害を抱えた女児は、出生後、暴力のある家庭環境で暮らし、育つ(面前DV=心理的虐待被害)ことにより、同じ被虐待体験(逆境的小児期体験)者であっても、男児よりも「分離不安」、「見捨てられ不安」を抱えやすく、『別紙2 性暴力、DVと面前DVの影響、後遺症としてのPTSD』の全体を通して示している2次・3次障害ともいえるさまざまな問題を生じやすい。
b) 胎児期・小児期に、ネオニコチノイド系農薬など環境化学物質に曝露すると
胎児期、小児期における多種類の環境化学物質(内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン))の曝露は、脳発達に重要な神経情報伝達系を直接撹乱させるだけではなく、脳発達に重要なホルモン系、免疫系の撹乱、新規(de novo)のDNA突然変異を介し、特定の高次脳機能に対応する機能神経回路の異常と考えられ、どの神経回路(シナプス)形成に異常が生じたかにより、症状が決まる。
機能神経回路の異常をもたらす要因として、1950年(昭和25年)ころから急増加した農薬、PCBなど有害な環境化学物質の曝露が疑われ、ネオニコチノイド系農薬を含め、アセチルコリン情報伝達系を撹乱する農薬の高次脳機能発達に対する毒性と発達障害との因果関係を示されている。
脳の機能には、「一次機能」と「高次脳機能」がある。
「一次機能」は、目や耳で感じた光や音を脳に伝える知覚機能、脳からの命令に従い、手足を動かす運動機能などが該当し、一方の「高次脳機能」は、一次機能により得た情報をより高等な命令に変換する機能である。
つまり、「高次脳機能」は、一次機能を連合することにより、これまで経験した知識、記憶、言語を関連づけて理解する「認知」、それをことばで説明する「言語」、新たに記憶する「記憶」、あるいは、目的を持って行動に移す「行為・遂行」、社会的な行動ができる「情動・人格」などの能力である。
つまり、胎児期・小児期の内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)、ネオニコチノイド系農薬などの曝露は、「認知」「言語」「行為・遂行」「情動・人格」などの能力が阻害されるリスクがある。
ア) キーワードは、「胎児関門」「血液脳間門」を通過できる物質
脳の発達期の胎児・小児が、ネオニコチノイド系農薬などに曝露すると、脳神経系に興奮性/抑制性の撹乱作用をおこし、神経回路形成が正常に行われないだけでなく、ミトコンドリア機能障害、酸化ストレス産生、免疫毒性、甲状腺ホルモン低下などをおこす。
こうしたネオニコチノイド系農薬などの環境化学物質曝露の危険性について、いまから10年前の2012年(平成24年)、アメリカ小児科学会は、「子どもへの農薬曝露による発達障害や脳腫瘍のリスク」を警告している(令和4年(2022年)4月現在)。
重要なことは、「ニコチンに似た化学構造」を有する各種薬剤の総称であるネオニコチノイド系農薬は、環境化学物質の中で、直接、脳神経系を標的にしていることである。
この「ニコチンに似た化学構造を有する」ことは、ネオニコチノイド系農薬が、「血液脳関門」で守られた脳の血管、「胎盤関門」で守られた胎盤の血管を通過することを意味する。
つまり、胎児が曝露する。
「血液脳関門」は、ア)脳に必要な酸素や栄養素を血管から送り届ける輸送機能、エ)脳の中の不要な物質を血管にだす排出機能、ウ)血管から有害物質が脳に入るのを防ぐバリア機能で、脳の中の環境を保つ。
しかし、母親の脳にはほとんど影響を及ぼさなかった量の有機水銀が、胎児の脳には侵入して「胎児性水俣病」を起こしたように、胎児期・乳幼児期(生後6ヶ月まで)は「血液脳関門」が未発達であることから、コルチゾールと同様に、有害な化学物質が侵入し、ダメージを受けやすい。
「水俣病」とは、熊本県八代海沿岸、および、新潟県阿賀野川流域において、メチル水銀が工場排水に混じって環境中に排泄され、人が、これらを多くとり込んだ魚や貝を摂取したことで発生した公害病で、高度経済成長期の昭和31年(1956年)5月に公式発見されたが、メチル水銀が原因だと判明し、環境に配慮した対策がとられたのは、12年後の昭和43年(1968)年である。
ネオニコチノイド系農薬などの有害な化学物質は、大人の脳にはほとんど影響を及ぼさない摂取量であっても、「血液脳関門」の未発達な胎児・乳幼児期(生後6ヶ月まで)の脳では深刻で、発達環境を危険にさらす。
そこで、重要となるのは、この脳を守ったり、胎児を守ったりする役割を果たす「血液脳関門」「胎児関門」を通過できる物質を正確に知ることである。
胎盤関門、血液脳関門を通過できる物質は、低分子、しかも脂溶性で電荷のない物質、脳の活動源となるブドウ糖やアミノ酸に加え、アルコール、カフェイン、ニコチン、大麻、覚醒剤、抗うつ薬、白砂糖などの薬品物質に加え、ネオニコチノイド系農薬」の他に、「ポリ塩化ビフェニール(PCBs)」、「ダイオキシン」、殺虫剤、除草剤、殺菌剤などに使われる「有機ヒ素化合物」、香料に使われる「リナロール」、香料・保存料に使われる「フェネチルアルコール」などのさまざまな化学物質である。
そして、これらの薬品・化学物質の“分子構造”に近い物質は、「血液脳関門」「胎盤関門」を通過できる。
例えば、頭痛薬の主成分がカフェインであるように、「胎盤関門」「血液脳関門」を通過できる抗うつ薬(精神治療薬)の大半は覚醒剤の一種である。
つまり、精神治療薬は、覚醒剤の“分子構造”と類似したものが使われる。
依存性や習慣性などがある危険な薬物として指定されている向精神薬「リタリン(中枢神経興奮剤)」は、化学構造や薬理作用が覚醒剤に類似していることから、受験生などが「集中できる」「勉強がはかどる」「眠気が覚める」と、合法覚醒剤として大人気となった。
また、「脱法ハーブ(脱法ドラッグ・危険ドラッグ)」は、覚醒剤や大麻などの成分の“分子構造”と類似したものをハーブに沁み込ませたものである。
そのため、「周産期うつ病」の妊娠期に、妊婦が「抗うつ薬」を使用すると、「胎盤関門」「血液脳関門」を通過し、胎児が「抗うつ薬」に曝露する。
いまから17年前の2005年(平成17年)に、アメリカのFDAとカナダ保健省は、妊娠中のパロキセチン服用に伴う胎児への催奇形性、特に先天性心疾患について警告したが、妊娠中の抗うつ薬SSRI曝露は、流産、早産、新生児合併症、先天異常(特に先天性心疾患)、小児期における神経発達障害(とくに自閉スペクトラム症)と関連することがわかっている(令和4年(2022年)4月現在)。
2016年(平成28年)に発表されたBrownらの研究では、「妊娠中に抗うつ薬を服用したうつ病やSSRIを使用する他の精神疾患と診断されている母親から生まれた子どもにおいて、妊娠中に抗うつ薬を未服薬で、同精神疾患と診断された母親から生まれた子どもと比べて、会話、および、言語の発達障害のリスクが高い。」と示された。
個々のSSRIの効果に関する研究では、「妊娠中のFluoxetimeやパロキセチン使用による先天異常リスクは、他のSSRIよりは小さいが、一般的な薬剤よりリスクが高い」ことが示されている。
一方で、妊娠前にうつ病を発症し、抗うつ薬を服薬しているとき、妊娠中に抗うつ薬を中止すると、うつ病再発は高リスクとなる。
したがって、うつ病を発症し、抗うつ剤を服用している女性が妊娠したとき、出産までの期間の抗うつ剤の服用については、産婦人科の医師と十分に話し合い、出産計画(バースプラン)を決めていくことになる。
問題は、日本では、生まれてきた子どもが、ADHD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)などの発達障害と診断されたとき、「発達障害は、先天性の中枢神経系の機能障害で、その原因は、遺伝的な要因が高い」と説明され、上記のような「いまでは、遺伝因子にもとづくものではなく、後天的な(胎児期・乳幼児期の)環境因子にもとづくものである」と言及しないことである。
冒頭の『脳科学辞典』など、日本で知り得る医学情報(専門医、行政機関、支援機関のHP(ホームページ)を含む)には、いまだに、発達障害発症の原因として「多くの症例で遺伝的要因が病因と考えられている」と記述され、この『レポート』で指摘している環境要因、つまり、胎児期に、ストレスホルモンのコルチゾールに曝露したり、「胎児関門」「血液脳関門」を通過する薬物・化学物質に曝露したりすることで、中枢神経系がダメージを受けるなどの環境要因が主原因であることは、それぞれ専門分野の論文にあたらない限り、ほとんど知ることができない。
つまり、「胎児、コルチゾールに暴露、発達障害」、「胎児、ネオニコチノイド系農薬、内分泌攪乱化学物質に曝露、血液脳関門、発達障害」といった専門的なキーワードを知らなければ、検索をかけて、論文などにあたることすらできない。
では、各論として、個々の問題を見ていく。
② 体外受精で妊娠、生まれた子どもの高い発達障害発症リスク
不妊治療のひとつとして実施される体外受精は、発達障害を発症する高いリスクを伴う。
2015年(平成27年)、アメリカのコロンビア大学教授のピーター・ベアマン氏らは、「不妊治療で使われる医療技術の約80%を占める顕微授精に代表される生殖補助医療で生まれた子どもは、自然に妊娠して誕生した子どもに比べ、自閉症スペクトラム障害(社会性、コミュニケーション、行動面の困難を伴う発達障害の総称)であるリスクが2倍である。」という調査結果を『American Journal of Public Health』に掲載した。
これは、カリフォルニア州で、1997年-2007年(平成9年-平成19年)に出生した590万例の小児データをもとに分析した(長期大規模疫学調査)ものである。
「顕微授精」とは、体外にとりだした卵子に、顕微鏡を使い極細のガラス針で人為的に1匹の精子を穿刺注入し、受精させてから子宮に戻す方法である。
平成29年(2017年)、日本で、不妊治療の体外受精により誕生した子どもの数は5万6617人で、16人に1人が体外受精で妊娠し、生まれた子どもとなる。
2年後の平成31年/令和元年(2019年)総出生数は86万5239人のうち6万598人、14.3人に1人が体外受精で妊娠し、生まれた子どもとなり、昭和58年(1983年)、東北大学で、国内初の体外受精児が生まれてから合計で71万931人になった。
この総数は、人口数、47都道府県中45位の高知県の人口69万7674人(2019年10月)を超え、14.3人に1人という割合は、1クラス30人の小学校では、1クラスに2人、体外受精で生まれた子どもがいることになる。
総出生数に占める体外受精で生まれた子どもの割合が年々増加したことと、発達障害の子どもが増加傾向にあることには、一定の相関関係が認められる。
③ 胎児期、乳幼児期のDV被害。胎児期・乳幼児期の脳形成への影響
a)「胎児虐待」という捉え方
妊娠中のDV被害は、母体の被害だけでなく、早産や胎児仮死、児の出産時低体重をもたらし、「セロトニン」、「アドレナリン」、「ドーパミン」などの神経伝達物質の分泌に影響を及ぼすなど、胎児の初期の脳形成に重大な影響を及ぼす。
アメリカのサウスダコタ州やウィスコンシン州では、胎児を人として捉え、胎児虐待を「児童虐待」に含み、刑事罰の対象としている。
この日本では馴染みのない「胎児虐待」は、胎児の生命を脅かしたり、深刻な健康被害をもたらしたりする怖れのある行為をいう。
日本では、妊娠中のDV被害などの「胎児虐待」が確認されても、妊婦に適切な対応やサポートは行われず、胎児への深刻な影響が放置されている。
日本において「胎児虐待」に対する対応の論議が進まない理由は、日本の刑法(判例)では、「人の始期」は、胎児のからだの一部が母体から体外にでた段階で、刑法の対象の「人」となる一部露出説を採用していることも影響している。
つまり、刑法では、胎児は人と扱わない。
一方で、民法3条1項は「私権の享有は、出生にはじまる」と規定し、原則として、胎児はまだ出生しておらず、権利能力が認められないが、民法886条1項で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と胎児は相続権が認められている(ただし、同条2項で、「胎児が死体で生まれたときは適用しない」と規定)。
つまり、民法においても、胎児は、相続を除き、人として扱われない。
そのため、児童(人)と扱われない胎児は、『児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法)』などの法律の対象外となる。
日本では、「胎児虐待」の法的な“定義”がないことが、行政機関や臨床現場で議論されてこなかった要因となっている。
平成28年(2016年)10月、『児童福祉法』が一部改正され(平成28年法律第63号)、「支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。」と明記された(第21条の10の5)。
これを受けて、医療機関から自治体の保健・福祉に情報提供することが努力義務となり、本人の同意がなくても特定妊婦や産後に養育不全や児童虐待が懸念される場合には市町村の情報提供が可能であるとされた(雇児総発1216第2号・雇児母発1216第2号)。
しかし、「胎児虐待」との表現はなく、養育不全や児童虐待が懸念されるのは「産後に」と限定している。
一方で、日本周産期メンタルヘルス学会の診療ガイド『周産期メンタルヘルス コンセンサスガイド2017』の「CQ6.メンタルヘルス不調で支援を要する妊産褥婦についての、医療・保健・福祉の情報共有及び同意取得・虐待や養育不全の場合の連絡の仕方は?」のAnswerには、「児童虐待・胎児虐待が疑われた場合は、医療機関から保健・福祉機関に情報提供を行い、医療・保健・福祉機関が連携して、母子の支援を行う。」と「胎児虐待」が明記された。
『児童福祉法』では踏み込んでいない「胎児虐待への対応」に言及した『診療ガイド』の記載は、受診した妊婦に胎児虐待やその疑いがあるとき、関係機関と連携して、妊婦をサポートし、胎児を守っていくための母子保健における胎児虐待対応を整備することを目的にしている。
しかし、その後も妊婦に適切な対応やサポートは行われず、胎児への深刻な影響が放置された。
『診療ガイド』で「胎児虐待への対応」に言及してから5年後の令和4年(2022年)6月25日、一般社団法人「日本乳幼児精神保健学会」は、離婚後の子どもの養育のあり方について声明を発表した。
その冒頭で、ユニセフの提言を引用し、「人間の脳は、乳幼児期・児童・思春期にもっとも発達し、とりわけ、受胎という命の誕生から最初の数年の間に、急激な回路の発達を遂げる。この時期に形成された人としての土台が人生全体へ強く影響を及ぼすことは、いまや発達科学の常識として良く知られたことである(ユニセフは、発達阻害を防ぐには、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの3年間-人生の最初の約1000日-への関心を高め、集中的に取り組む必要があることを強調している。)」と記し、最後で「以下、当学会は、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点から、子どもの権利を最大限尊重するという理念を基本に、最新の科学的研究および豊富な臨床現場の知見に基づき、離婚後の子どもの養育に関して声明を発する‥」と記し、その“声明”は、ⅰ)離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること、ⅱ)子どもには意思がある、ⅲ)面会交流の悪影響、ⅳ)同居親へのサポート、ⅴ)離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがあるとしている。
そして、「離婚後の子どもの養育に関する法制度の改正には、子どもの視点に立った慎重な議論を求めるものである。」と締めくくった。
「日本乳幼児精神保健学会」は、離婚後の子どもの養育のあり方として、「ⅲ)面会交流の悪影響、ⅴ)離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある」と“声明”をだすほど、この問題は軽視されている。
発達期の脳に対する強い精神的衝撃は、脳の神経伝達物質の分泌に影響を与える。
ストレスを調節するホルモンである「コルチゾール」、重要な神経伝達物質である「エピネフィリン」、「ドーパミン」、「セロトニン」等に変化が生じる。
これら神経伝達物質のバランスに問題が生じると、障害が起きる。
神経発達症(発達障害)には、「自閉症」、「双極性障害」、「統合失調症」、「学習障害(LD)」、「脳性麻痺」など、脳や神経系の発達に関連する疾患が該当する。
b) 乳幼児期の面前DV=心理的虐待
子どもが、両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりする状況は、面前DVであり、『児童虐待防止法』では、子どもに対する「心理的虐待」となる。
『別紙2』の「2-(1)虐待は、子どもの脳を委縮させる」、「同-(2)-②多くの語彙数の獲得は、考える能力を高める」で詳述しているように、そのDVを目撃している子ども(心理的虐待を受けている子ども)は、年少ほど、家庭内の暴力が非常に大きな情緒的ストレスとなり、脳の発達を阻害し、認識や感覚の発達を損なう可能性が高くなる。
長期間、慢性反復的なストレスにさらされる(曝露する)と、神経系、神経内分泌系、免疫系、遺伝子システムなどを変化させる。
ストレスを受けると脳の底部にある「視床下部」が反応して、「脳下垂体」と「副腎」からのホルモン分泌が促進され、心拍数の増加、血圧の上昇、食欲の低下などが生じる。
これらの変化は、脳に生じる原始的な反応である。
ストレスは、感情や衝動を抑制している「前頭前野」の支配力を弱めるため、「視床下部」などの古い脳領域の支配が強まった状態になり、不安を感じたり、普段は抑え込んでいる衝動、例えば、欲望にまかせた暴飲暴食、アルコールや薬物の乱用、金の浪費などに負けたりする。
「前頭前野」は、他の脳部位よりゆっくりと成熟し、20歳代で完成する。
「前頭前野」は、精神の制御装置としての役割を担っており、状況にそぐわない思考や行動を抑制している。
この働きにより、集中、計画、意思決定、洞察、判断、想起などができる。
この神経の高次中枢、つまり、神経細胞同士が接続した大規模なネットワークを介して働く「錐体細胞」は、感情や欲求、習慣を制御する脳領域とも接続している。
問題は、このネットワーク内の回路が、日々遭遇する不安や心配に対して敏感に反応し、非常に脆弱であることである。
ストレスがかかると、脳全体に突起を伸ばしている神経から「ノルアドレナリン」や「ドーパミン」などの神経伝達物質が放出される。
これらの濃度が、「前頭前野」で高まると、神経細胞間の活動が弱まり、やがて止まってしまう。
ネットワークの活動が弱まると、行動を調節する能力も低下する。
「視床下部」から「脳下垂体」に指令が届き、副腎がストレスホルモンであるコルチゾールを血液中に放出して、これが脳に届くと事態はさらに悪化する。
その結果、自制心はバランスを崩していく。
ドーパミンが、古い脳領域である「大脳基底核」に到達する。
「大脳基底核」は、「線条体」などから構成され、欲求や情動、運動の調節や運動の記憶にかかわっている一連の深部脳構造である。
「扁桃体」は、「ノルアドレナリン」と「コルチゾール」の濃度が高まると、危険に備えるよう他の神経系に警告を発したり、恐怖などの情動に関わる記憶を強めたりする。
「ドーパミン」と「ノルアドレナリン」により高次認知に必要な「前頭前野」の回路が停止しても、通常はこれら神経伝達物質の分解酵素が働く。
機能停止は長くは続かず、ストレスが軽減すると元の状態に戻る。
遺伝的にこれらの酵素の力が弱い人はストレスに弱い。
さらに、慢性的なストレスにさらされると、「扁桃体」の樹状突起(神経細胞から枝状に伸びて信号を受け取っている突起)が拡大する一方、「前頭前野」の樹状突起は萎縮する。
ストレスがなくなると、「前頭前野」の樹状突起は再生するが、ストレスが非常に強い場合には回復能力が失われる。
「前頭前野」の萎縮は、過去のストレス体験と関連している。
ストレスによる脳内変化が生じると、以後のストレスに対してさらに脆弱になり、『別紙2』の「1.PTSDの症状(解説)」で詳述しているように、うつ病や双極性障害(躁うつ病)などの気分障害、依存症、PTSDなどの不安障害につながる。
脳が傷ついた子どもは、学習意欲の低下、無気力が見られ、非行に至ったり、うつ病を発症したりすることが少なくない。
また、他人に共感する能力を失い、社会性が損なわれる。
『別紙2』の「3-(14)反応性愛着障害(RAD)」で述べているように、衝動的で、キレやすく、対人関係でトラブルを招いたり、集団行動がとれなかったり、同「4-(5)-⑥2次障害。自傷行為としての「過食嘔吐」」などで述べているように、リストカットや過食嘔吐などの自傷行為に走ったり、同「3-(15)問題行動としての“依存”」で述べているように、アルコールや薬物に依存したりするなど多くの問題を抱えやすい。
「いじめなど攻撃的行動やけんかにかかわる可能性が3倍にのぼる」、「薬物に依存したり、自殺未遂に至ったりするのは10倍以上」、「虚血性心疾患に2倍、癌に2倍、脳卒中に2-2.5倍、慢性肺疾患に4倍、糖尿病に1.5倍なりやすい」、「高校中退に2-2.5倍なりやすく、失業に2-2.5倍、貧困に1.5倍なりやすい」との報告がある。
「いじめなど攻撃的行動やけんかにかかわる」のは、反応性愛着障害に起因するだけではなく、『別紙2』の「3-(6)-②-b)子ども同士の遊びの大切さ(4歳)」の302文「虐待を受けた(暴力のある家庭環境で暮らし、育った)人は、攻撃性と関係のある「MOMA遺伝子」の“スイッチ”を入れることなど、遺伝子レベルでひき継がれることがわかっている。」ことと関係している。
「MOMA遺伝子」に“スイッチ”が入ることと暴力のある家庭環境で暮らし、育つことの関係性については、同303文-306文で述べている。
『別紙2』の「1-(5)-①後発性の発達障害、被虐待児の高い発症率」の中で、『 子どもが、両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりする状況は、面前DVであり、『児童虐待防止法』では、「心理的虐待」となる。
そのDVを目撃している子ども(心理的虐待を受けている子ども)たちは、年少ほど、家庭内の暴力が非常に大きな情緒的ストレスとなり、脳の発達を阻害し、認識や感覚の発達を損なう可能性が高くなる。
そして、この面前DV(=心理的虐待)を含む、ネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心理的(情緒的)虐待を受けた(受けている)子どもの多くに、AHDHなどの発達障害の診断がされ、その多くが2次障害を抱えている。
ADHDと診断されている一定数は、実は、「(反応性)愛着障害」である。
ADHDと「(反応性)愛着障害」の診断は、専門医でも難しく、しかも、診断時に、子どもが暮らす家庭環境に暴力のあることが伏せられることから、「(反応性)愛着障害」であってもADHDと診断されることが少なくない。
④ 面前DV・虐待行為、高い発達障害発症率
虐待を受け、児童養護施設に保護された児童の多くに、「反応性愛着障害」、「情緒障害」だけでなく、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」や「LD(学習障害)」、「軽い知的障害」が見られることはよく知られている。
『別紙2』の「1-(5)-①後発性の発達障害、被虐待児の高い発症率」24文で、「平成20年-21年度『子ども虐待問題と被虐待児の自立過程における複合的困難の構造と社会的支援のあり方に関する実証的研究(厚生労働省)』では、「A県の児童相談所で虐待受理ケース119事例の中で、71事例(59.67%)が障害を持つ子どもを養育している、つまり、56例が当該児童に障害があり、48例にきょうだいに障害があり、33例に当該児童ときょうだいの両方に障害があり、15例は、きょうだいのみに障害がある。」と報告している。」、同25文「発症率は、ADHDが10%、アスペルガー症候群が3-7%とされていることから、この59.67%という数字は、異常に高い。」と述べているように異常に高いが、ASD(アスペルガー症候群/自閉スペクトラム症)は、乳幼児期から症状が見られることがあり、「3歳児健診」後に診断を受けることが多く、一方、ADHDは、「就学後」の小学校2年-4年生(8-10歳)に診断を受けることが多いことから、虐待受理年齢が3歳以下の子どもを除くと、発症率はもっと上がると考えられる*1。
「落ち着きがない」「待てない」などを特徴とするADHDの子どもは、「がまんを強いられる課題」にとり組んだとき、脳の前頭前野がうまく働かないと考えられている。
うつ病の診断として保険適用がはじまった「光トポグラフィー検査」において、ADHDと診断された子ども30人とそうでない子ども30人(いずれも平均年齢8歳)に対して、指定された画像が現れたときだけスイッチを押すゲームをしてもらい脳の血流におきる変化を測定した結果、「ADHDではない子どもの脳は、ゲームをすると右側の前頭前野(6と10の部分)の血流が増えるのに対し、ADHDの子どもでは、ほとんど変化がなかった。」という研究報告がある。
ADHDなどの発達障害を発症させるひとつの要因が、神経伝達物質をバランスよく分配できなくなることである。
*1 DV離婚事案では、平成25年(2013年)4月-平成27年(2015年)7月の2年3ヶ月(27ヶ月)で、「33件」の離婚調停・裁判での離婚の成立、一時保護の決定、保護命令の発令、傷害事件の立件に向けて、交際相手や配偶者からのDV行為を立証するためのサポートをし、そのうちの「17件(51.52%)」で、『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』を作成し、主業務再開後の令和2年(2020年)4月-令和4年(2022年)6月の2年2ヶ月(26ヶ月)では、「6件」のサポートのうち「4件」、併せて、「39件」のサポート、「21件」の『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』を作成しました。
サポートした「39件」のうち、子どものいる事案が「28件(71.80%)」で、「61人」の子どもがいました。
この61人の子どものうち53人(86.89%)が未成年(20歳以下)で、その53人のうち32人(60.38%)が、既に、アスペルガー症候群、ADHDと診断されていました。
一般的に、ASD(アスペルガー症候群/自閉スペクトラム症)は、乳幼児期から症状が見られることがあり、「3歳児健診」後に診断を受けることが多く、一方、ADHDは、「就学後」の小学校2年-4年生(8-10歳)に診断を受けることが多いことから、未成年者53人から「3歳未満の子ども17人(32.08%/27.87%)」を除くと36人で88.88%です。
この60.38%という高い数字は、「児童相談所で虐待受理ケース119事例の中で、障害を持つ子どもを養育している71事例(59.67%)」とほぼ同じで、88.88%はそれ以上の高い数値です。
3歳以上の未成年者41人で、アスペルガー症候群、ADHDと診断されていない子ども9人には、リストカット、過食嘔吐、OD(大量服薬)などの自傷行為のある子ども4人、家出を繰り返し、性的自傷のある子ども2人が含まれます。
DV被害者である母親からの情報(ワークシートの記載とメールのやり取りなど)で、3歳以上の未成年者41人のうち、上記の症状や傾向を示していない子どもはわずか3人(7.32%)でした。
また、既に、成人(20歳以上)していた子ども8人(13.11%)のうち4人(50.0%)が、中高校生時に非行で補導経験があり、そのうちの2名が傷害事件・薬物使用で逮捕・服役を経験していました。
a) 乳幼児期の睡眠障害と発達障害の発症
ADHDなどの発達障害を発症させる要因となる神経伝達物質をバランスよく分配できなくなる要因のひとつが、乳幼児期の面前DV被害を起因とする「睡眠障害」である。
それは、日々繰り返される暴力などの大きな物音に神経が研ぎ澄まされ、神経が高ぶり(中途覚醒)、しばしば目が覚めてしまい睡眠が分断され(断眠:睡眠のコマ切れ状態)、睡眠欠乏になることでもたらされる。
睡眠の役割は、ⅰ)日中使った神経伝達物質をもとにシナプス小胞に返還することによって、神経伝達物質の補充と再利用する、ⅱ)活動時に神経突起で働くミトコンドリア(エネルギー(ATP)をつくる役割を果たす)が細胞内に戻り、複製を行って数を増やす(休養する)、ⅲ)脳が統合的に機能できるように、脳幹調節機構とその他の部位で、神経伝達物質をバランスよく再分配することである。
つまり、睡眠は、日中に生じた生体内のアンバランスを、本来のバランスへと整える重要な役割を果たす。
ところが、日々繰り返される両親間のDV行為による大きな物音に神経が研ぎ澄まされ、神経が高ぶり(中途覚醒)、睡眠が分断され(断眠)、睡眠欠乏になることで、神経伝達物質をバランスよく分配できなくなる。
このことが、発達障害を発症させる要因になる。
一方で、子どもが、面前DV=心理的虐待被害を受けない安全な環境で生活し、睡眠の時間を本来のものに修正できると、発達指数(DQ)が改善することもわかっている。
例えば、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、配偶者暴力防止法)』に準じ、女性センター長、あるいは、警察署長が一時保護を決定し、母子生活支援施設(母子寮と呼ばれる行政機関のシェルター)に入居し、その後、DV行為に及んだ加害者である交際相手や配偶者に居所を知られない土地で生活の再建をはかる中で、ADHD、自閉スペクトラム症などの発達障害と診断されていた子どもの睡眠が改善すると、生活の質が向上し、発達指数が大きく改善される。
一方で、離婚後(夫婦関係調整(離婚)調停、監護権者決定調停(審判)で離婚に至ったり、監護権者が決定したりするまでの期間を含む)の監護権者でないDV加害者の親と子どもとの面会交流を実施すると、安定していた子どもの睡眠状況が、再び、中途覚醒、断眠を繰り返すようになり、改善されていた発達指数が悪化したり、停滞したりすることも知られている。
こうした事実が、③-a)で触れた「日本乳幼児精神保健学会」の、離婚後の子どもの養育のあり方として、「ⅲ)面会交流の悪影響、ⅴ)離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある」と“声明”につながっている。
睡眠時間の絶対的な不足、つまり、「睡眠欠乏」を起因として発症するのが「睡眠不足症候群(ISS)」である。
一般的に、睡眠不足が慢性化すると「睡眠不足症候群」をもたらし、さらに重症化すると、逆に「過眠型睡眠障害」となり日常生活が壊されてしまい、学校どころではなくなり、不登校状態に至ることがある。
慢性的な睡眠欠乏状態は、「日中の眠気が強い」、「集中力が低下してきた」、「友人間などのコミュニケーションがうまくいかなくなる(イライラ感や集中力低下により)」、「作業能率が落ちる(勉強が手につかない)」、「自律神経機能にも障害が出現し、頭痛・腹痛をはじめとした不定愁訴が出現する」、「交通事故に遭いやすくなる」など、“ボンヤリしてしまう”ために問題を生じさせる。
つまり、子どもの不登校には、中枢神経の疲労状態が関係していることが少なくない。
b) セロトニンの減少と発達障害の発症の関係性
発達障害は、脳機能の障害が主な原因と考えられ、15番染色体の遺伝情報に変異のある例が知られている。
理化学研究所脳科学総合研究センターの内匠透シニア・チームリーダーらは、染色体に人と同様の変異を生じさせたマウスを使った実験により、「鳴き声で、母親と意思疎通するのが苦手であるなどの行動が表れ、その原因が、脳幹にある縫線核の働きが低下し、縫線核でつくられる神経伝達物質のセロトニンの量が減っている」こと突き止め、さえに、「この染色体に変異を生じさせたマウスに対し、不安な気持ちを落ち着かせるなどの作用があるセロトニンを投与すると、自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害に似た特徴が改善した。」と発表した。
そして、自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害の人の遺伝子分析などにより、「脳内で神経細胞をつなぐシナプスがうまく形成されなくなり、脳神経の情報伝達に支障がでることが発症に関与する可能性がある。」と発表した。
c) 腸内細菌環境の劣化がセロトニン形成に影響
人は脅威にさらされると、不安を抑えるために、抑制性の神経伝達物質「セロトニン」の分泌を亢進させ、抑制性の神経伝達を亢進させることで、「前頭連合野」の興奮を抑制することができると不安が解消されるように、セロトニンは、脳(心)の安定に欠かせない。
このセロトニンが不足すると「うつ病」を誘発し、副交感神経の働き(リラックスする)を損ない、交感神経と副交感神経(以上、自律神経)のバランスを崩す。
自律神経の不調は、呼吸、消化、体温調節、ホルモン分泌などさまざまな機能に影響を及ぼし、体調不調を招く。
恐怖や不安のコントロールが効かなくなり、混乱を招き、動悸や呼吸困難などの身体症状をみせる「パニック障害」をひきおこす。
注意力散漫で多動、感情をコントロールし難いなどの症状をみせる「ADHD(注意欠陥多動性障害)」も、脳幹形成期のセロトニンの分泌に影響がでたことが発症原因のひとつとされている。
このセロトニンが欠乏すると、うつ病、パニック障害を誘発する、
このストレス下で精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の約90%は、腸に存在する。
脳にあるのは2%で、血小板に8%である。
セロトニンは、トリプトファンという必須アミノ酸から5-ヒドロキシトリプトファン(5-HTP)を経て合成される。
このとき、「腸内細菌」がトリプトファの代謝にかかわっている。
例えば、うつ病を発症した人はセロトニンの分泌が少ないが、このとき、腸内細菌叢の異常により、セロトニン合成不全が生じている。
腸内細菌が産生する酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸が、交感神経節を介して、脳に送られる情報に影響を与えている。
さらに、腸管には、迷走神経や脊髄神経などの脳・中枢に向かう神経(求心性神経)が多数分布し、これらが腸管内部の情報を脳に伝達している。
腸内細菌がトリプトファンの代謝を促してセロトニンをつくり、そのセロトニンが、迷走神経などのセロトニンリセプターに作用し、脳へ情報を伝えていく。
つまり、神経系が介在して脳と腸管が互いに連絡し合い、それぞれの機能に影響し合っている。
脳を健全に保つには、子どものときの食生活がとても大切である。
d) ADHD、精神疾患と間違われやすい「低血糖症(ペットボトル症候群)」
「アドレナリン」は怒りのホルモン、攻撃のホルモンで、毒性は、毒蛇の毒の2-3倍といわれる。
この猛毒のアドレナリンは、「あっ敵だ!」「あっ殴られる。怖い!」と感じた瞬間、副腎で生成され、一瞬で血液に乗って全身を駆け巡り、血中で酸化し、アドレノクロムになる。
「アドレノクロム」は、人によって幻覚をも誘発する物質である。
そして、猛毒のアドレナリンは、怒りを感じたときだけでなく、血糖を脳や筋肉のエネルギー源として活動させるときにも分泌される。
白砂糖たっぷりのジュース、炭酸飲料を大量に飲み、ジャムをたっぷりつけたパン、生クリームたっぷりのケーキ(以上、浸透性が高くいち早く血液にとり込まれる)を食べたりすると、対外に存在するはずの“外的”が体内にいると見間違い、アドレナリンを分泌する。
本来外に向かうエネルギーが体内に向かい、内在化されてしまうと、からだはイライラ、ムカムカしたり、怒鳴りたくなったりする。
人のからだは、血糖値が上昇(浸透性が高いと急上昇)すると、インスリンを分泌し、血糖値を下げる。
しかし、上記のような浸透性の高く、血糖値を急上昇させる食品を多く摂取し、血糖値が下がると甘いものが欲しくなり食べ、そして、血糖値が急上昇することを繰り返すうちに、インスリンは出っ放し状態となり、甘いものを大量に摂るのに血糖値は低めのまま(インスリンの過剰分泌)の低血糖状態をひき起こす。
つまり、「低血糖症」を発症する。
「ペットボトル症候群」は、「低血糖症」を表す総称で、インスリンを投与したり、治療薬を服薬したりしている糖尿病患者がひき起こす深刻な(命の危険のある)「低血糖」とは異なる。
白砂糖の燃焼時には、カルシウム、ビタミンB群を大量に消費する。
カルシウム、ビタミンB群が欠乏すると、ますますイライラ、ムカムカを募らせることになり、<キレやすい奴>と煙たがれる。
キレやすい子どもの心の病を解く鍵のひとつが、「低血糖症(ペットボトル症候群)」である。
「低血糖症(ペットボトル症候群)」の症状は、主に、ア)からだの細胞がエネルギー不足に陥ることでもたらされるもの、イ)低血糖時に分泌されるホルモンの変動に影響されてもたらされるものの2つに大別される。
ア)の主な症状は、異常な疲労感、起きられない、眠たい、集中力がない、めまい、ふらつき、物忘れがひどい、目のかすみ、呼吸が浅い、目が眩しい、甘いものが無性に食べたい、胃腸が弱い、ため息をつく、生あくび、偏頭痛などである。
一方、イ)の症状は、精神症状と身体症状にわけられる。
精神症状としては、睨んでいるような表情、暴力をふるったり、奇声をあげたりする、考え方がバランスを欠いている、うつ症状をおこす、幻覚をおこす、不眠に陥る、怒りだすと止まらないなどである。
身体症状は、手足の冷え、目の奥の痛み、動悸、頻脈、狭心痛、偏頭痛、筋肉の麻痺、発汗、体重減少、便秘、立眩みなどである。
これらの低血糖症(ペットボトル症候群)の症状と精神疾患の症状は、なにが違うというのだろうかと思うほど酷似している。
実は、精神疾患ではなく、ADHDでもなく、「低血糖症(ペットボトル症候群)」を見逃していることが少なくない。
「ドーパミン」が過剰に放出されると過覚醒の状態になり、「統合失調症(精神分裂病)」の幻覚や興奮などの症状をひきおこすが、低血糖は、ドーパミンの放出を促す。
ドーパミンの放出は、アドレナリンやノルアドレナリンを放出し、アドレノクロムをつくりだし、幻覚症状をもたらす。
また、「低血糖症(ペットボトル症候群)」を生じさせかねない食生活は、「腸内環境」を悪化させる、つまり、「腸内細菌」の劣化をもたらす。
つまり、セロトニンの合成不全をもたらす。
e) 消化器系の問題を抱える自閉スペクトラム症。腸内細菌との関係
自閉スペクトラム症の子どもの多くには、慢性的な腹痛、消化不良、下痢、便秘など、消化器系の問題があることがよく知られている。
毎日のように襲われる痛みや不快感は、より強く過敏症状をもたらす。
結果、注意力が散漫になり、学習能力、行動に悪影響を及ぼす。
つまり、慢性的な消化器疾患のある自閉スペクトラム症の子どもは、より重い自閉スペクトラム症関連の症状をもたらす。
こうした「慢性的な消化器疾患のある自閉スペクトラム症の患者に対し、腸内微生物の移植を施した結果、消化器系の問題に改善が認められただけではなく、自閉スペクトラム症の特徴的な症状である「社会的ふるまい」が45%改善された」、「その症状は、治療後もゆっくりと改善し、長く続いた」とする論文が、オンラインジャーナル『Scientific Reports』に発表された。
このことは、腸内細菌の質が向上したことで、セロトニンの形成、分泌が促進されたことを意味する。
そして、⑤-c)で述べる「ネオニコチノイド系農薬」は、②-d)で述べた「低血糖症(ペットボトル症候群)」をもたらす食品の摂取と同様に、腸内細菌叢をも変える。
腸内には、1000兆個といわれる細菌が存在し、免疫細胞の70%は腸の消化管にいる。
この免疫細胞を活性化させるのが、腸内細菌である。
ところが、ネオニコチノイド系農薬は、炎症を抑える菌など善玉菌を減らし、悪玉菌を増やす。
このことが、自己免疫疾患、アレルギー疾患につながっている。
⑤ 発達障害の発症原因となる大気汚染、ネオニコチノイド系農薬
胎児期を含む子どもの後発性の発達障害発症、不妊の原因として、大気汚染、農薬などの化学物質があげられる。
大気汚染について、WHOは、世界108カ国の約4300都市について、環境大気汚染の状況を調べ、「世界の人口の9割は高濃度の汚染物質を含む空気を吸っており、大気汚染で命を落とす人は年間700万人に上る」と報告している。
大気中に含まれる微小粒子状物質(PM2.5など)を構成する硫酸塩、硝酸、黒色炭素は、乗用車やトラック、工場、発電所、農場、そして、森林火災などから排出される。
PMとは、「Particulate Matter(粒子状物質)」のことで、1μm(マイクロメートル)=1mmの1000分の1)以下の非常に小さな粒子である。
この大気汚染物質「PM2.5」は、ADHDなどの発達障害を発症させる要因となり、大気中に高水準の微小粒子物質(PM2.5)が存在するとき、胎児の脳に破壊的影響がもたらされる可能性が指摘されている。
その指摘は、「妊娠中にPM2.5に曝露した人は、妊娠期間の短縮、子宮内胎児発育不全(FGR)を経験する危険性が高まり、結果、乳幼児の脳の通常発達が損なわれたり、生涯にわたる障害がひき起こされたりする。」というものである。
一方で、モンゴルとカナダを主に拠点とする研究者の調査により、「HEPAフィルター付き空気清浄機を使用することで、妊娠中の粒子への曝露を減らし、結果、子どもの神経発達の影響を減少させることができる」ことが明らかになっている。
全身の1/5という大量の血液が流れている大脳では、脳に害をもたらす薬物やウイルスなどが簡単に入り込めないように、脳の血管は「血液脳関門」と呼ばれる構造でブロックしている。
同様に、胎児の発育環境を守るために、胎盤の血管は「胎盤関門」という構造でブロックしている。
つまり、精神疾患、発達障害などを発症させ得る胎児期の脳の発育に影響を与える環境因子となる物質は、この「胎盤関門」「血液脳関門」で守られた血管を通過できない。
この「血液脳関門」「胎盤関門」を通過できる物質は、低分子、しかも脂溶性で電荷のない物質、つまり、PCB、ダイオキシンなどの化学物質、アルコール、カフェイン、ニコチン、大麻、覚醒剤、抑うつ薬、白砂糖などの薬品物質であり、妊娠している女性が暴力を受けるなど強いストレスで分泌されるコルチゾール、アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの脳内物質である。
そのため、妊娠期には、アルコール、コーヒー・紅茶・緑茶などを飲んだり、タバコを吸ったり、風邪薬をはじめ、幾つかの薬を服薬しないように指導される。
a) 喫煙・受動喫煙(ニコチン)
血液脳関門で守られた脳の血管を通過する物質ニコチンを含むタバコの喫煙・受動喫煙は、子ども(胎児期を含む)の成長に大きな影響を及ぼす。
例えば、「妊娠期に母親が喫煙していた子どもは、3歳児健診時、喫煙していない母親の子どもに比べて1.75倍の頻度で聴覚障害の判定を受けていた」、「母親の喫煙に加えて、出生後4ヶ月月の段階で、近くに喫煙する同居者がいると、2.35倍の頻度で聴覚障害と判定されていた」、「妊娠中に喫煙していた母親の子どもや喫煙者がいる家に生まれた子どもは、平均年齢約10歳の小学生での行為障害の発症リスクが実質的に倍増する」、「胎内や生後の早い段階でニコチンにさらされた子どもは、不安に陥りがちになるなどの気分障害を発症するリスクが高くなる」といった研究・調査結果が報告されている。
喫煙者は減ったといえ、身近なタバコの喫煙は、多くの障害をもたらすが、その中でも、驚愕なのは、「行為障害の高い発症リスク」である。
高い発症率として示された「行為障害」は、『別紙2』の「3-(14)反応性愛着障害(RAD)」の「*3」で、122文「DSM(アメリカ精神医学会の「精神障害の分類と診断の手引き」)のような発達障害の精神医学概念を用いずに、これらの特徴を持つ子どもをいい表すときには、「行為障害」の少年は、<非行少年(犯罪少年・触法少年・虞犯少年)>いわれることが多く、また、「反抗挑戦性障害」の少年は、危険な犯罪性はほとんどないが、学級崩壊や授業の混乱をひきおこす<問題児>といわれる。」、同126文「「行為障害」とは、反抗的で攻撃的な非行行為を繰り返す状態をいう。」、同127文「この非行行為は、年齢相応に必要な社会的規範や規則から著しく逸脱している。」、同128文「その非行行為をひきおこす原因としては、脳の障害、精神的な障害、人格発達の歪み、家庭環境や社会的環境の影響などがある。」、同129文「そして、「行為障害」の主な症状としては、いじめ、喧嘩、脅迫、その他人を傷つけるような行為や、ひったくりや強盗などの犯罪行為などがある。」などと説明している。
「行為障害」「反抗挑戦性障害」の背景には、反応性愛着障害があることから、被虐待体験(逆境的小児期体験)が発症の主な要因となるが、受動喫煙により高い発症リスクが生じることは驚愕する。
この背景にあるのも、胎児期と生後6ヶ月辺りまで「血液脳関門」が未発達であることから、コルチゾール同様に、汚染科学に直接曝露するからである。
なお、DSM(アメリカ精神医学会の「精神障害の分類と診断の手引き」)の診断基準は、同じく同3-(14)「*3」の中で記述している。
同様に、高い発症リスクとしてあげられている「気分障害」には、「うつ病」「双極性障害(躁うつ病)」が該当する。
児童・青年期のうつ病性障害は、行為障害(破壊的行動障害)、ADHD、不安障害、物質関連障害(薬物やアルコールなど依存症)、摂食障害が併発しやすい。
特に、「行為障害」を合併している児童・青年期のうつ病性障害は、薬物依存、アルコール依存、反社会的人格障害(サイコパス)の併発が多く認められ、自殺行動、犯罪などのより広範な社会機能障害が認められる。
また、子どもの双極性障害者の少なくとも4分の3には、「ADHD」、「反抗挑戦性障害」、「行為障害(破壊的行動障害)」の併存障害が認められ、他に、「不安障害」、「物質乱用障害」の併存障害があげられる。
同128文にある「その非行行為をひきおこす原因」としてあげられている「脳の障害、精神的な障害、人格発達の歪み、家庭環境や社会的環境の影響」は、主に、乳幼児期の被虐待体験(逆境的小児期体験)によりもたらされ、「うつ病」、「双極性障害(躁うつ病)」の発症においても、乳幼児期の被虐待体験(逆境的小児期体験)が深くかかわっている。
このように、その乳幼児期の被虐待体験(逆境的小児期体験)が発症の主要因である「行為障害(破壊的行動障害)」の発症、発症に深くかかわりのある「気分障害(うつ病、双極性障害)」の発症として、「受動喫煙」が示されている。
この「喫煙」は、インスタントコーヒーと同様に、第1次世界大戦の戦地で、前線の兵士の間で広がり、帰還後も吸うようになったことに起因する。
古来、戦場で戦う兵士の恐怖心を麻薬でとり除くために、麻薬(たばこを含む)の精製と配布(販売)は、国が担ってきた。
そして、重要が拡大した戦争が終わると、軍(国)の需要が減り、余った麻薬は一般社会に流れ、麻薬汚染が進むという構図が繰り返されてきた。
WHO(世界保健機関)は、タバコの主成分であるニコチンは、アヘン類、大麻、コカインと同列の依存性薬物と位置づけ、その依存性は、ヘロイン、コカインに次ぐ高さで、アルコール、覚醒剤よりも強力である。
現喫煙者の70%は「ニコチン依存症」で、依存している薬物=ニコチンを断つと禁断症状が表れ、疲労感、イライラに襲われる。
加えて、喫煙は、喫煙者と周囲の健康も危険にさらし、脳卒中、口腔・咽頭がん、喉頭がん、食道がん、喘息、肺がん、COPD(肺気腫、慢性気管支炎)、胃潰瘍、膵臓がん、膀胱がん、全身病として、高血圧、動脈硬化との因果関係は証明されている。
近距離路線バスが禁煙となったのは、いまから46年前の昭和50年(1975年)ころで、国鉄(現JR)は、その5年後の昭和55年(1980年)に国鉄車両内の禁煙化を求める「嫌煙権訴訟」が起こされたことを契機に禁煙車(両)が設置されはじめた(令和4年(2022年)4月現在)。
「受動喫煙の防止」を目的として、喫煙場所となる空間とそれ以外の非喫煙場所となる空間に分割する方法(空間分煙)があるが、メディアで「分煙」ということばがはじめて使われたのは、国鉄(現JR)が禁煙車(両)を設置しはじめてから5年後の昭和60年(1985年)3月17日の朝日新聞である。
つまり、それ以前の日本社会には、職場や飲食店で「分煙」という概念はなかった。
その後、昭和61年(1987年)4月に国鉄は分割民営化され、1990年代(平成2年-11年)以降、概ね優等列車全車両の50-70%が禁煙化され、JR各社が大幅禁煙化に踏み切ったのは平成19年(2007年)である。
それは、昭和55年(1980年)に禁煙車両を設置してから39年を要した。
この間、平成15年(2003年)、世界保健機関(WHO)は、タバコの規制に関する『世界保健機関枠組条約』を採択し、同条約は、平成17年(2005年)2月27日に発効した。
WHOの政策勧告では「完全禁煙を実施し、汚染物質であるタバコ煙を完全に除去すること。屋内のタバコ煙濃度を安全なレベルまで下げ、受動喫煙被害を受けないようにする上で、これ以外の方策はない。換気系統が別であろうとなかろうと、換気と喫煙区域設置によって受動喫煙をなくすることはできないし、行うべきでない。」とし、「分煙では、受動喫煙の問題を十分解決できない」としている。
日本において、「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では敷地内が禁煙となったのは、同条約が発効してから14年後の令和元年(2019年)7月1日で、「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用する様々な施設」が原則屋内禁煙となったのは、東京オリンピックの開幕直前、令和2年(2020年)4月1日である。
b) ダイオキシン、PCB、PM2.5
黄砂は、タクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、オルドス高原、黄土高原などの広大な乾燥地域から偏西風を通じて日本に到着する。
その間、中華人民共和国内で発生した「硝酸イオン」「硫酸イオン」、「アンモニウムイオン」などの大気汚染物質をとり込む。
日本で観測される「SOx(硫黄酸化物)」の49%が、中国起源のものである。
北九州地域で頻繁に観測される光化学スモッグも、「SOxNOx(窒素酸化物)」が原因とされる。
「NOx」や「炭化水素(揮発性有機化合物)」が、日光に含まれる紫外線の影響で光化学反応がおこり生成される有害な「光化学オキシダント(オゾンやアルデヒトなど)」や「エアロゾル」が空中に停留し、スモッグ状になり発生する光化学スモッグは、陽射が強く、風の弱い日が特に発生しやすい。
また、西日本の日本海沿岸での森林における樹木の立枯れも、偏西風が運んでくる黄砂に付着した「二酸化硫黄(SO2)」や「窒素酸化物(NOx)」による酸性雨が原因である。
昭和58年(1983年)以降、日本全国の平均はph4.7とヨーロッパを超える酸性雨(ph5.6以下)の状況で、日本海沿岸は全国平均より高く、降りはじめのパラパラ雨ではph3.9を記録するほど高い水準だった。
約40年経過したいまでは、「酸性雨」をメディアなどでとりあげることはないが、各県のHP(ホームページ)では「酸性雨」に関する情報を掲載し、平成31年/令和元年(2019年)の全国平均値はph5.24、日本海沿岸の福岡市ではph4.71、同新潟市ではph4.96、これは、約40年前の全国平均値と変わらない高い数値である。
問題は、偏西風によって運ばれる(黄砂)大気汚染物質、つまり、ダイオキシンやPCB、PM2.5などの化学物質に加え、散布される農薬や除草剤、家材に使用される薬剤は、甲状線ホルモンを撹乱したり、胎盤関門、血液脳関門で守られた脳の血管を通過してしまうことで、神経伝達組織を撹乱させたりすることである。
特に、「胎盤関門、血液脳関門で守られた脳の血管を通過してしまうことで、神経伝達組織を撹乱させる」ことは、「多動性障害(発達障害)」などのさまざまな障害を発症させる原因となっている。
これまで、発達障害の発症は、遺伝的要因が大きくかかわっていると考えられてきたが、その考えは正しくなく、エピジェネティックな(遺伝子の設計図に影響する遺伝子以外の)環境因子がより重大な因子であることを明らかになっている。
胎児期、約千億の神経細胞が他の神経細胞とシナプス結合という形でつながり、脳が形成されていく過程では、膨大な遺伝子が関与している。
このシナプス結合は、生育環境や化学物質の環境によって調節されることから、一人ひとり異なった個性(人格)がつくられる。
この中で、脳の発達をマイナス側に調節してしまうのが、暴力(戦争や紛争を含む)のある生活環境に加え、大気汚染、ネオニコチノイド系農薬など有害な化学物質である。
c) ネオニコチノイド系農薬
1990年(平成2年)ころから急速に広まった「ネオニコチノイド系農薬」が、子どもの脳の発達に悪影響を及ぼし、発達障害発症の原因となっている。
「ネオニコチノイド」は、「ニコチンに似た化学構造」を有する各種薬剤の総称である。
このニコチンに似た化学構造を有することは、ネオニコチノイドが、「血液脳関門」で守られた脳の血管、「胎盤関門」で守られた血管を通過することを意味する。
つまり、ネオニコチノイド系農薬は、胎児の発育環境、脳の発達を阻害する。
ネオニコチノイド系農薬は、農業にだけでなく、松枯れの防止剤、家庭用の殺虫剤、シロアリの駆除剤、住宅建材の中などにも使われている。
ネオニコチノイド系農薬の特徴は、植物の細胞内に入り込んで作用することから、洗っても除去し難いことである。
つまり、家庭で料理前に洗っても、体内に摂取される。
2012年-2013年(平成24年-同25年)の国内でのサンプル調査で、3歳児(223人)の尿中に、有機リン系、ピレスロイド系農薬の代謝物が100%、ネオニコチノイド系農薬の代謝物が79.8%の割合で検出された。
子どもの脳の発達に悪影響を及ぼし、発達障害発症の原因となり、さまざまな環境問題につながることから、2018年(平成30年)4月27日、ネオニコチノイドと呼ばれる農薬のうちの3種、「クロチアニジン」、「イミダクロプリド」、「チアメトキサム」を主成分とする薬剤(以下、対象薬剤)は、すべての作物に対して屋外での使用を禁止した。
もともとは、オランダと韓国が2014年(平成26年)、ブラジルが2015年(平成27年)、フランスと台湾が2016年(平成28年)に、これらの対象薬剤を禁止した。
一方で、日本はその流れに反し、安倍政権の下で、ネオニコチノイド系農薬の食品の残留基準を緩和した。
イチゴの日本の残留基準(アセタミプリド)は3ppmで、これは、EUの60倍、アメリカの5倍、緩い基準である。
同様に、ブドウの5ppmはEUの10倍、アメリカの14倍、トマトの2ppmはEUの4倍、アメリカの10倍、お茶の30ppmは、EUの600倍、緩い基準となっている。
こうしたネオニコチノイド系農薬、除草剤、大気汚染などの化学物質は、直接子どもが摂取するだけでなく、母体を通して、胎児期の脳発達に影響を及ぼす。
それだけではなく、農薬や除草剤、大気汚染などの化学物質を吸引することは、暴力のひとつの原因となり得る。
人工(精製加工品を含む)のあらゆる化学物質は、そもそも人体にとって異物、毒物でしかなく、微量でも体内に侵入すると、からだは毒物が入ったことを強烈なストレスとして感知する。
その結果、アドレナリンが分泌され、敵を排除しようとし、イライラ感や不快感といった症状を表す。
このイライラ感や不快感を他者にぶつけてしまうと、それは、暴力になる。
また、血液脳関門で守られた脳の血管を通過する薬、つまり、頭痛薬にはカフェイン、精神治療薬には覚醒剤の“類似した分子構造”に似させたものが使われる。
なぜなら、類似した分子構造にしないと血液脳関門で守られた脳の血管を通過しないからである。
「脱法ハーブ(脱法ドラッグ・危険ドラッグ)」についても、覚醒剤や大麻などの成分と“類似した分子構造”をしたものをハーブに沁み込ませたものだ。
化学物質は微量でも遺伝子傷つけ、発ガン性や催奇形性を伴うもの、アレルギーなどを引起す免疫毒性のあるもの、時には、急性毒性のあるもとと接すると死に至る。
化学物質汚染は、身近なところに存在し、その化学物質は、胎盤関門で守られた胎盤の血管、血液脳関門で守られた脳の血管を通過し、胎児の脳に深刻な影響を及ぼす。
d) 子宮内で、内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)に曝露した胎児
「内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)」は、「シシリー宣言(1995年11月5日-10日))」で、「子宮内で曝露した胎児の神経学的、行動発達と、それにもとづく潜在能力を損なう」と報告している。
「環境ホルモン」とは、環境中に存在し、生物に対して、ホルモンのような影響(内分泌かく乱作用)をもたらす化学物質のことである。
つまり、「内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)」を子宮内で曝露すると、脳や行動上の「発達障害」、「脳性まひ」、「精神遅滞」、「学習障害」、「注意力散漫」、「多動症」などをおこすと警告され続けている。
現在、人工化学物質は10万種を超え、環境ホルモン作用のあるものは2000種ではきかないとされ、それは、女性ホルモンと一部構造が酷似していることから、生体が誤認し、オスのメス化を生じさせ生殖能力を失うなど生殖系を侵したり、脳や神経の発達をも脅かし、暴力など異常行動を発生させたりする。
また、「化学物質過敏症」をひき起す原因物質は、化学建材、食品添加物、歯科金属、合成洗剤、車の排気ガスなど。建築に使われている化学物資は459種類に及ぶ(2009年(平成21年)3月18日現在)。
異物の侵入によって健常な細胞は傷つき、呼吸困難に陥る。
幾つかの細胞が壊死する。
建物内でのペンキ塗りやワックスがけに遭遇したり、いつもより多めの合成洗剤を使ったりする大掃除のときなど、目の痛み、頭痛、灼熱感、めまい、吐き気、嘔吐、意識喪失などの症状は、中枢神経系への影響が表れたものである。
例えば、次亜塩素酸ナトリウムを主成分としている塩素系漂白剤(浴槽のカビ取り剤、台所用の漂白剤、排水口クリーナーなど)と酸性の物質(トイレ用黄ばみ落とし洗剤、キッチン用洗剤など)が混ざりあうと猛毒の塩素ガスが発生し、その塩素ガスを吸引すると死に至るほど危険である。
こういった身近な化学物質の摂取が長期化すると生殖機能への影響がでたり、発ガン性が確認されたりする。
残留農薬や食品添加物、環境ホルモンなどの化学物質を体内に摂り込むと、生体細胞は活性酸素(フリーラジカル)やストレスの影響を受ける。
活性酸素やストレス受けた細胞は傷つき、ときには呼吸困難に陥る。
細胞のあるものは死滅する。
中でも、神経細胞に与える影響は大きく、シンナー、マリファナ、睡眠薬、覚醒剤等の薬物を摂るのと同様に正常な判断力を失い、精神障害を起こす。
なぜなら、有害物質を摂ると、脳内の酸素量が減少してしまうからである。
脳内の酸素量が極端に減ると死にいたる。
活性酸素は、体内に侵入してきた異物(殺菌、ウイルス)を撃破する働きも当然ある。
一方で、残留農薬や食品添加物などの化学物質、農薬や除草剤の散布など汚染された空気を吸収することで、悪玉の活性酸素が大量につくられる。
その結果、細胞は健康を疎外され、生活習慣病などを誘発するなどの悪さをする。
e) マイクロプラスチックと内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)
加えて、「内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)」の胎児、乳幼児の影響が懸念されているのが、マイクロプラスチックの問題である。
1835年(天保6年)、フランス人化学者・物理学者のルニョーが塩化ビニルとポリ塩化ビニルの粉末を作成したのが、史上初のプラスチックといわれているが、商品化されたのは1869年(明治2年)、アメリカの印刷工が、ビリヤードの球を「セルロイド(それまでは象牙)」でつくったのが最初である。
1907年(明治40年)、ニューヨーク在住のベルギー人ベークランドが、石炭から炭化水素物質を抽出し、合成高分子プラスチックを発明し、その素材(フェノール樹脂)は、のちに、家電や自動車といった工業製品にも広く使用されていく。
1926年(大正15年)に「可塑化ポリ塩化ビニル(手袋、コード、フィルム)、1938年(昭和13年)に「ポリスチレン(コンピューター、テレビの外枠)」、「ポリテトラルフオロエチレン(フライパンの表面のコーティング)」、1939年(昭和14年)に「ナイロン(衣類)」、1941年(昭和16年)に「ポリエチレンテレフタレート(飲料用ペットボトル)」、1951年(昭和26年)に「高密度ポリエチレン(バケツ、パイプ、漁網)」、「ポリプロピレン(台所用品、車の部品)」、1954年に「発泡スチレン(包装)」と次々と開発された。
プラスチックが大量生産されるようになり60年、この60年で、劇的に環境汚染は進んだ。
プラスチックの生産量は年々増加し、1975年(昭和50年)に5000万トンだった生産量は、2015年(平成27年)には4億トンに達した。
そのうち、もっとも大きい割合を占めているのが「包装用プラスチック(1.5億トン)」で、そのほとんどがリサイクルされずに使い捨てされ、燃やすと大気汚染につながり、埋め立て廃棄されるプラスチックは、土壌や海洋の汚染をひき起こした。
プラスチック袋やペットボトルは、劣化すると必ず微小なかけらへと崩壊し、環境のありとあらゆる場所へと入り込む。
クルマを運転するたび、タイヤやブレーキからプラスチックの破片が飛散し、風に乗り、エベレストなどの山頂、北極に到達したり、合成繊維の衣類を洗濯すると、プラスチックの微小な繊維が分離し、下水道を経て海へと流れ込み、深い海底の底に堆積したりするなどの環境汚染が問題になっている。
そして、人の体内からもマイクロプラスチックが見つかっている。
「マイクロプラスチック」は、長さ5mm未満の合成素材の総称である。
2022年(令和4年)3月、オランダのアムステルダム自由大学の研究者らは、「健康なボランティア22人から提供を受けた血液サンプルを調べたところ、17人(77.27%)の血液からマイクロプラスチックが検出された」と調査結果を発表した。
2023年(令和5年)3月には、精液と精巣から0.02-0.287mmのマイクロプラスチックが検出されている。
精液から検出されたマイクロプラスチックは、ポリエチレンとポリ塩化ビニルが多く、精巣内にはポリスチレンが多く検出された。
ポリエチレンもポリスチレンも食品の容器包装などによく使われている樹脂である。
マイクロプラスチックの体内への侵入経路は、例えば、食品や水と一緒に摂取したものは、小腸から血管やリンパ管に侵入する。
胎盤、肺、肝臓、腎臓などの内臓から検出されているマイクロプラスチックは、同年8月、中国の病院で心臓手術を受けた15人の患者の心臓組織と術前・術後の血液からマイクロプラスチックを検出されたと米学術誌『Environmental Science and Technology』に発表された。
5種類の心臓組織から9種類のマイクロプラスチックが検出され、その大きさは、最大で0.469mmで、もっとも多く見つかった樹脂はポリエチレンテレフタレート(77%)で、次いで、ポリウレタン(12%)だった。
ポリエチレンテレフタレートは、ペットボトルやポリエステル繊維などに、ポリウレタンは、自動車シートや伸縮性に富んだ繊維などに日常的に使われている。
また、2020年(令和2年)10月、アイルランドのダブリン大学トリニティカレッジの研究チームによる「ポリプロピレン製の哺乳瓶で授乳される乳児は、1日あたり100万個以上のマイクロプラスチック粒子を摂取している可能性がある。」との論文が、英科学誌「ネイチャー(Nature)」の関連誌「ネイチャー・フード(Nature Food)」に掲載された。
そして、乳児の使用済みおむつを調べた結果、1gの糞便につき平均36,000ナノグラムのポリエチレンテレフタレート(PET)が見つかっているが、これは、成人の糞便に含まれる量の10倍にあたる。
しかも、PETは、新生児の最初の糞便(胎便)からも見つかっている。
これは、既に、誕生の時点で、新生児の消化器内にはプラスチック粒子が存在することを意味する。
この結果は、先行研究において、「人の胎盤と胎便からマイクロプラスチックが見つかっている」ことと一致する。
そして、「乳児の便からマイクロプラスチックが見つかった」ことは、食べ物に含まれる栄養と同じように、一部の粒子は、消化管から吸収される可能性がある。
この現象は、転移と呼ばれる。
非常に小さい粒子は、腸壁を通過し、脳などの他の器官に転移する可能性が指摘されている。
スイス連邦工科大学チューリッヒ校のチームの研究は、「さまざまな種類のプラスチックに含まれる化学物質は、合計で10,000種を上回り、このうち4種に1種は、人体に悪影響を及ぼす怖れがある。」と指摘している。
これらの化学物質は、プラスチックの製造過程で柔軟性や強度をアップしたり、素材を劣化させる紫外線から防護したりするなどのさまざまな目的で添加される。
マイクロプラスチックには鉛などの重金属が含まれたり、環境中を浮遊するうちに、重金属やその他の汚染物質を蓄積したり、プラスチック粒子上に形成される微生物コミュニティに、人に対する病原性をもつウイルスや細菌、菌類が含まれたりする傾向がある。
特に問題となるのが、内分泌攪乱物質(EDC)と呼ばれる化学物質の一群である。
これらは、生体内のホルモンを撹乱し、生殖、神経、代謝に悪影響を及ぼす。
プラスチックの原料であるビスフェノールA(BPA)は、内分泌攪乱物質の一種で、数種類のがんとの関連が指摘されている。
そして、乳児の身体発達は、健全な内分泌系に依存することから、内分泌攪乱物質にとりわけ敏感で、乳児期は影響を受けやすい。
一般家庭の屋内の床には、毎日、1平方メートルあたり10,000本のマイクロファイバーが降り積もり、室内の空気はマイクロプラスチックだらけで、誰もが年に数十万個の粒子を吸い込んでいる。
その多くは、衣類、ソファー、ベッドのシーツ、カーペットから飛散している。
硬材のフローリングでは、ポリマーのコーティングからマイクロプラスチックが剥離する。
乳児は、かなりの時間をこうした環境でハイハイして過ごし、蓄積した繊維をかき乱し、空気中に巻きあげる。
このように、乳幼児は、日常生活のさまざまな経路で生じた微小な粒子を吸い込んだり、飲み込んだりする。
f) 人工香料「合成ムスク」
また最近、問題になっている人工香料「合成ムスク」は、乳児が母乳を通して摂取している。
「合成ムスク」とは、人工的に合成された香料の総称のことである。
もともとジャコウジカの分泌物から作られていた香料「ムスク(ジャコウ)」を人工的に合成したもので、主に、柔軟剤、芳香剤、脱臭剤などに使われ、さまざまな健康被害との関連が指摘されている。
例えば、「柔軟仕上げ剤を使用して室内干ししたところ、においがきつく咳がでるようになった。」、「隣人の洗濯物のにおいがきつくて頭痛や吐き気があり、窓を開けられず換気扇も回せない。」といった健康被害である。
においを不快と感じると、「セロトニン」が分泌され、血管が拡張する、つまり、脳血管内の血流が急激に変化することで片頭痛を発生させる。
片頭痛は、なんらかの原因で脳の血管が拡張し、その拍動にともない血管周囲をとり巻く知覚神経である三叉神経が刺激され、頭がズキンズキンと割れるように痛む症状を示す。
「セロトニン」は大脳深部の中脳で産生され、近接した「視床下部」により、セロトニンの分泌が調節される。
「視床下部」は、セロトニンだけでなく、自律神経、睡眠と覚醒、情緒、女性ホルモンなどのホルモン調節に深く関与し、満腹・空腹の中枢である。
人の感じる感覚のほとんどは、大脳深部の脳の「視床」に向かい、その情報は直下の「視床下部」に送られる。
この「視床下部」が敏感に反応し、興奮した「視床下部」の刺激を受けた「中脳」からセロトニンが大量に放出される。
セロトニンは知覚神経である三叉神経をコントロールし、三叉神経終末にはCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)が存在し、このCGRPは、血管の受容体を介して血管を拡張させ、同時に、炎症を起こす。
結果、脳血管は過剰に拡張し、拡張した隙間から炎症物質が漏出し、血管周囲に生じた炎症を悪化させ、血管周囲をとり巻いている三叉神経を刺激し、痛みが増強することで、「脈打つ頭痛」、つまり、片頭痛がおきる。
また、慢性反復的(常態的、日常的)にストレスにさらされていると、「視床下部」が頻繁に興奮し、頻繁にセロトニンを分泌することから、脳内のセロトニンは枯渇し、セロトニンの欠乏をもたらす。
つまり、毎日、洗濯したり、食器などの洗い物をしたりする状況は、慢性反復的(常態的、日常的)に、DV被害にさらされている被害者と同様に、脳内のセロトニンの欠乏をもたらし、耐え難い「片頭痛」に悩まされることになる。
シャンプー、合成洗剤、化粧品の中には、香料、防腐剤、界面活性剤、保湿剤、色素、染毛剤など、多数の化学物質が含まれている。
人工香料の分子は、呼吸や皮膚から体内に入り、アレルギーをひき起こす原因となり、子どもの喘息、接触性皮膚炎、一次性刺激皮膚炎、アレルギー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)、接触性じんましんをひき起こす。
喘息の発症原因として、大気汚染の他、香料もあげられる。
また、喘息症状の悪化をもたらす物質は、人工香料だけではなく、カバ、スズラン、ユリ、ヒナギク、ヒヤシンスなどの天然の香料も該当する。
柑橘系の人工香料「シトラール」は、自律神経に影響を及ぼす。
懸念されているのは、マウス実験で、「骨盤神経節の神経細胞の壊死」が認められていることである。
「骨盤神経節」は、人の膀胱、結腸、卵巣、精巣、子宮、前立腺などを支配している自律神経を指し、これら部位、中・高齢者に多い疾患である。
そして、人工香料は、「内分泌攪乱」をもたらす。
合成ムスクの「トナライド」、「ガラクソライド」には、エストロゲン受容体β、アンドロゲン受容体、プロゲステロン受容体で拮抗作用がある、つまり、ホルモンなどの作用を弱める。
例えば、女性ホルモン「エストロゲン」のバランスが崩れると乳がん、子宮がん、卵巣がんを発症する原因となる。
ドイツの研究で、合成ムスクの血中濃度が高いとホルモンバランスに影響を及ぼす、つまり、人の間脳にある「視床下部」がコントロールしている卵巣の機能に異常をもたらすことが明らかになっている。
食品添加物として使われる人工香料「ジアセチル」は、高齢者の血液、母親の母乳から検出されている。
これらの人口香料は、「血液脳関門」「胎盤関門」を通過する。
しかも、人工香料の「合成ムスク」は、からだの中で分解され難く、脂肪に溜まりやすい特性がある。
2005-2007年(平成17年-同19年)、熊本大学と佐賀大学が実施した共同研究において、日本人の母乳や脂肪組織に合成ムスクが蓄積されていることが判明している。
つまり、母親の母乳を介し、子どもが人工香料「合成ムスク」を摂取することになる。
g) 週数別胎児の成長と薬の影響
なお、「週数別の胎児の成長と薬の影響」は、以下のとおりである。
・0-4週(2週で受精し、3週で着床)
薬の影響と注意点:まだ、胎児のからだはつくられていないので、この時期に飲んだ薬の影響はほとんどない。
・5-8週(器官形成期)
胎児の中枢神経、心臓、目、手足など、重要な器官が形成される時期で、もっとも薬の影響を受けやすい時期である。
・9-12週(手足などの形成期)
重要な器官の形成は終了しているが、手足の指、耳、口などこまかい部分を形成しているので、ひき続き注意が必要な時期である。
・13-16週(器官形成はほぼ完了)
器官形成はほぼ終了するが、外性器などはまだ形成される。
新生児の先天的な病気の発生率は2-3%で、このうち、薬が胎児の器官形成に与える影響はごく僅かとはいえ、薬の使用には注意が必要となる。
例えば、ヨードを含んだうがい薬や噴霧薬で予防するのは、胎児の甲状腺機能に異常をきたす可能性がある。
抗不安薬は、新生児に震えなどの離脱症状がでることがある。
解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンは影響がないと考えられ、妊娠中期以降は、ロキソニンなどの非ステロイド性抗炎症薬は、胎児の動脈管収縮などの報告があり、使用が制限されている。
抗生物質は、ニューキノロン系以外は安全といわれているが、同じ名前でも含有成分が異なる場合があるので、市販薬は避ける必要がある。
・17週以降(器官形成が終わり機能が発達)
薬が、胎児の器官形態に影響を及ぼす(催奇形性)時期は過ぎたが、機能の発達に影響を与える薬に対する注意が必要となる。
⑥ 長時間のテレビゲームなど、前頭前野の発達不全に
脳の中枢神経系の発達に関連する疾患として該当するのは、「②妊娠中のDV被害、胎児虐待と胎児の脳形成への影響」の中で述べているように、「神経発達症(発達障害)」、「自閉症」、「双極性障害」、「統合失調症」、「学習障害」、「脳性麻痺」などである。
後発的に、この脳の中枢神経系の発達、特に、前頭前野の発達不全をもたらすのが、長時間のテレビゲームや携帯ゲーム、スマートフォンの使用である。
a) 乳幼児期にテレビ・スマートフォンなどの長時間の使用、高いADHDの発症率
後天的に器質的障害を招き、発達障害発症のリスクがあるのが、幼児期に1日2時間以上テレビ、タブレットやスマートフォンのスクリーンを見ることである。
カナダのアルバータ大学の研究チームが、カナダ国内の約2400家族を対象におこなった調査で、「3歳から5歳までの間に、1日2時間以上タブレットやスマートフォン、テレビなどのスクリーンを見て育った子どもは、ADHDと診断される確率が、30分以下の子どもに比べ7倍以上高い。」、「3歳から5歳までのスクリーンタイムが長いほど、5歳になってからの注意能力に影響する。」と調査結果を発表している。
シリコンバレーで働く親たちの多くは、タブレットなどの強い中毒性やコミュニケーション能力に与える影響を危惧し、自分たちの子どもには、小学校に入るくらいまで、タブレットやスマートフォンに一切触れさせない。
これは、ネオニコチノイド系などの農薬を使用している農家が、自分たち家族・親族で消費(摂取)する作物に対しては、ネオニコチノイド系農薬などの農薬を使用しないのと同じである。
『別紙2』の2-(1)で、以下のような、人の脳形成において重要な指摘をしている。
人間の脳は、生存している環境にあった脳の機能がつくられる(38文)。
人類は、脳や身体を進化させてきた一方で、必要のなくなった機能、つまり、必要のない生存環境では、進化させてきた脳やからだの機能を捨て去るだけでなく、生存のために異常を示すことがある(39文)。
「生存のために異常を示す」とは、正常な脳機能を守るために、別の正常な脳機能を破壊し異常をおこすということ、あるいは、異常な脳機能を補う(正そうとする)ために、新たな異常を生みだすということである(40文)。
つまり、「脳が脆弱な乳幼児期に、ある特定の入力(インプット)が欠けたり、過剰に入ってきたりすると、そのインプットに関連する情報を感じ、気づき、理解し、判断し、それに従って行動するという脳のシステムの発達に異常(問題・障害)が生じる」のである(41文)。
「人類の歴史」には存在しなかったテレビ(映像)、ゲーム機、スマートフォン、タブレットを通して、乳幼児期に強烈な“光の刺激”を脳に与えることなども、人の脳が、一度覚えた中毒性のある物質や刺激を得られなくなると快楽を求める渇望(中毒症状)をひきおこす。
そして、テレビ(映像)、テレビゲーム、携帯ゲーム、スマートフォン、タブレット、VR(仮想現実)に合った脳がつくられる。
つまり、脳は変質する。
b) ゲーム依存(ゲーム脳)
①-a)-イ)の冒頭で述べているとおり、脳は、大きく大脳、小脳、脳幹の3つに分けられ、人では、特に大脳が発達し、その重量は、脳全体の約80%を占め、思考や判断し行動する機能などを司る「前頭葉」、知覚や感覚などを司る「頭頂葉」、視覚を司る「後頭葉」、聴覚や記憶などを司る「側頭葉」の4つの領域がある。
「前頭葉」の大部分を占めるのが「前頭前野」で、「考える」「記憶する」「アイデアをだす」「判断する」「応用する」「行動や感情をコントロールする」「コミュニケーションをする」「集中する」「やる気をだす」など、人にとって重要な働きを担っている。
この「前頭前野」の働きである「想像的にものごとを認知し、仲間に伝え、行動に移す能力」は、7万年前を境にサピエンスに劇的な変化が生じ、脳の構造が変わり、獲得したとされている。
つまり、この「前頭前野」の働きこそが、サピエンスと人類(ホモサピエンス)の決定的な違いをもたらし、「人が人らしくある」ためにもっとも重要な部位といえる。
人と遺伝子の98%を同じくするチンパンジーの「前頭前野」は大脳の7-10%であるのに対し、人の「前頭前野」は、大脳の約30%を占める。
この「人が人らしくある」ためにもっとも重要な「前頭前野」に深刻な変異をもたらすのが、ゲーム・ネット依存、テレビゲームや携帯ゲームを長時間使用することである。
ゲーム・ネット依存状態の期間が長くなればなるほど、感情や感覚、欲望を制御する脳神経細胞の死滅が進む、つまり、萎縮する。
この状況は、ギャンブル依存症者にも同様に認められ、また、慢性反復的に虐待を受け、その後、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を症状に苦しむ子どもたちに見られる脳の障害と酷似する。
幼児・児童期からテレビゲームを長時間していると、「攻撃的になる」、「ひきこもりになる」、「虚構と現実の区別がつかなくなる」など、子どもに悪影響が及ぶことが報告されている。
ゲームの仮想世界では人や怪物などが死んでも、リセットすると、再びゲームがスタートすることから、現実世界においても、「人は一度死んでも、再び生き返る」と思い込んでいる子どもたちが多数いる。
この要因として、テレビゲームを長時間していることで、「前頭前野の機能が低下している」ことが考えられる。
大脳皮質の前頭前野は、特定の感覚や運動と対応した活動を示すことはなく、複雑な運動を組み立てたり、ものごとの順序や注意の方向を決定したりしている。
また、前頭前野はワーキングメモリ(作業記憶)、理性、創造性、思考などに密接にかかわり、認知機能として極めて重要な領域であり、常時、扁桃体に対して抑制をかけている。
つまり、前頭前野は、扁桃体で感情を爆発するのをコントロールしている。
前頭前野が機能不全(未発達)となると、「行為障害」「反抗挑戦性障害」のように、扁桃体で感情を抑制できないので、感情を爆発させ、暴力的な行動を伴いやすい。
テレビゲーム依存傾向のある子どもの特徴は、「笑わない」、「しゃべらない」、「しゃべるのが非常に遅い」、「忘れ物が多い」、「テレビゲーム以外では、集中力はない」、「時間にルーズである」、「キレやすい」、「自己主張が強い」、「人の話をきちんと聞けない」、「疲労感が強い」、「眼に力がない」などである。
これらの特徴を見ると、前頭前野の活動は低下していると考えられる。
これは、テレビゲームは、視覚系神経回路を活発させる一方で、前頭前野の細胞は働かないことを意味する。
前頭前野は発達不全となり、扁桃体を抑制できないので、視覚情報がダイレクトに扁桃体を興奮させる。
その興奮は、ゲーム中に、「死ね!」「消えろ!」などと過激なことばを吐くなど、言動、態度に表れる。
通常、脳幹から辺縁系、そして、前頭前野へとドーパミン神経線維が伸びていて、ドーパミンにより前頭前野の脳細胞が活性され、結果、創造性、理性、的確な意思決定ができるようになる。
ところが、テレビゲームや携帯型ゲームでは、視覚系から運動野への神経回路が強く働く。
これまで視覚からの情報は、「視床」を経由し、「視覚野」、そして、「扁桃体」に伝達されると考えられていたが、最近では、「視床」から直接、「扁桃体」に興奮が伝達される別の経路が存在することが明らかになった。
これは、『別紙2』の「1-(1)-②自己防衛システム(自己防衛反応)の断片化 」、「同-(2)-①覚醒亢進(過覚醒)」、「2-(1)虐待は、子どもの脳を委縮させる」で述べているように、闘争、または、逃避という動きに瞬時に反応できるように準備されていると考えられている。
前頭前野は、ドーパミンの働きが抑制されると機能が低下する。
テレビゲームや携帯型ゲームとしているとき、ドーパミンが分泌され、快楽的な状態をもたらす。
ドーパミンが分泌されることでセロトニンが低下し、前頭前野はセロトニン欠乏状態に陥り、前頭前野の機能低下をもたらす。
つまり、ドーパミンの働き(快楽的な状態)を抑制できない状態となる。
過激的テレビゲームや異常な緊張をひき起こすテレビゲームでは、脳の興奮性を高めるために、ノルアドレナリン神経やドーパミン神経の活動が非常に高まる。
ノルアドレナリン神経が高まるとセロトニン神経は抑制され、前頭前野は活動低下となる。
この前頭前野の神経細胞の活動が低下し、扁桃体に対する抑制が効かなくなると、直接、扁桃体に興奮情報が入り、攻撃的な行動が生じる。
これが、いわゆる「キレる」状態である。
また、長時間、テレビを見たり、スマートフォン、テレビゲームや携帯ゲームを使用したり、ネットを利用したりしているとき、人は歩かず、座っている。
この「歩かずに、座っている」ことは、脳の血流量に影響を及ぼす。
歩行中、記憶や意欲を形成する「海馬」の血流量は増加し、その海馬のアセチルコリン量も増加する。
アセチルコリン神経が活発になると、「大脳皮質」や「海馬」のアセチルコリンが増え、脳の内部の血管が広がり、血液の流れがよくなる。
脳内組織のリン脂質の「アセチルコリン(K.リゾレシチン)」は、神経伝達に関わる神経伝達物質のひとつで、快・不快などの情動行動を司る線条体・側坐核にもっとも多く存在し、記憶や意欲を形成する「海馬」、血圧、脈拍、睡眠にかかわり、「アルツハイマー型認知症」「パーキンソン病」の発症とかかわる。
「アセチルコリン」が減少したり、機能が低下したりすると、正常なものの考え方や判断、感情や言語などを司る「前頭葉(前頭前野)」に障害でてくる。
なぜなら、神経細胞からでている神経線維の鞘は、アセチルコリンによって保護されているからである。
アセチルコリンが減少すると、神経が疲れ、集中力や記憶力、学習意欲が減退し、イライラしてくる。
精神を患う人の脳内細胞のアセチルコリン濃度は、患っていない人の50%程度しかないとされている。
逆に、アルチルコリンに満たされていると心が落ち着き、穏やかになり、集中力は増し、よく眠れるようになり、食欲もでて、気分も爽快になる。
つまり、脳の発達期にある子どもが、座ったままで、長時間、テレビを見たり、スマートフォン、テレビゲームや携帯ゲームを使用したり、ネットを利用したりして、歩いたり、走り回るなどからだを動かさずにいると、記憶や意欲を形成する「海馬」の血流量は増えず、結果、大脳皮質や海馬のアセチルコリンは減少したり、機能が低下したりする。
そして、ホルモンの代謝が異常をおこし、イライラしたり、怒りっぽくなったり、キレたり暴れたり、「どうにでもなれ」といった自暴自棄になったり、死にたくなったりする。
『別紙2』の2-(1)11文前段では、「つまり、a)身体的虐待(体罰など)により「前頭前野」が萎縮すると、感情や理性、思考をコントロールし難く、犯罪抑止力が低くなり、「右前帯状回」が萎縮すると、集中力が欠け、自分で決めたり、共感したりでき難くなり、「左前頭前野背外側部」が萎縮すると、ものごとを認知し難くなり、「感覚野」への神経回路が細くなると、痛みに対して鈍感になり、…」と記し、同51文で、「感情や理性を司る「前頭前野」の萎縮など、前頭前野に一番影響を与えるのは、親や学校の教師による頬の平手打ちや(棒で)尻を叩くなどの体罰(身体的虐待)、同級生からのいじめを長期にわたる体験など、14-16歳(中学2年-高校1年)時、つまり、思春期後期(12-15歳)・青年期前期(15-18歳)の対人関係といわれている。」と記しているが、前頭前野に深刻なダメージを及ぼすのは、しつけと称する体罰を含む「身体的虐待」である。
加えて、同3-(6)-③191文-197文で、「人のすべての行動の背後にあるのは、中枢神経の変化、つまり、脳の変化だ。」、「5-6歳から大脳の「新皮質(合理的で、分析的な思考や言語機能を司る)」が活発に動くようになり、特に、「前頭葉(前頭前野)」の機能が高まる。」、「前頭葉(前頭前野)は、「旧皮質」を抑制する機能を持つが、旧皮質は食欲や性欲といった本能や情緒を司るので、欲望や感情のコントロールができるようになる。」、「前頭葉(前頭前野)は、人の意思や創造性、推論などの機能を司るので、5-6歳から精神活動がおこなわれる準備が整ってくるとされている。」、「しかし、親や近親者から暴力を受け続けて育つ(成長する/脳が発達する)と、「旧皮質」が司る食欲や性欲といった本能や情緒を「前頭葉(前頭前野)」はコントロールでき難くなる。」、「つまり、衝動的な欲求をコントロールすることができ難くなる。」、「その結果、成長過程において、「反応性愛着障害」「行為障害/反抗挑戦性障害」を発症する。」と記述しているように、しつけと称する体罰を含む「身体的虐待」による症状として、反応性愛着障害の症状と酷似し、診断時に見落とされやすい「ADHD」の症状のひとつ「衝動的な欲求をコントロールでき難くなる」を示す。
しつけと称する体罰を含む「身体的虐待」と同様に、人の意思や創造性、推論などの機能を司る「前頭前野(前頭葉)」の発達を著しく阻害するのが、幼児期に、長時間、テレビゲームや携帯ゲームの使用である。
つまり、長時間、テレビゲームや携帯ゲームをし、依存状態に陥った人の脳の活動は、被虐待体験(逆境的小児期体験)、特に、「身体的虐待(しつけ(教育)と称する体罰を含む)」を受け、のちに、「行為障害」「反抗挑戦性障害」と診断された少年とほぼ同じ状態をもたらす。
c) VR(仮想現実)
さらに、日常的に、五感を含む感覚を刺激する技術を利用した「VRゲーム」を行うようになると、人は、「仮想現実(バーチャルリアリティ:Virtual Reality;VR)」に順応した脳をつくってしまうだけでなく、現実と仮想現実との区別がつかなくなるリスクも高くなる。
人は、自分が「本当だとイメージしたこと」をもとに思考し、行動している。
梅干しを想像して口の中に入れるところを想像すると、口の中が酸っぱい感じがしてきて、唾液がでてくるように、人は、「イメージ」での体験と「現実」での体験の区別がつかない。
この人の脳の特性から、意図的につくられるVR(仮想現実)はとても危険である。
人が、VR(仮想現実)による深い没入感を体験すると、「ファントム・タイムライン症候群」と呼ばれるような心理に大きな影響を及ぼすリスクが指摘されている。
「ファントム・タイムライン症候群」とは、バーチャル世界と現実世界の区別がつかなくなる感覚のことを指す。
バーチャル世界でしばらく時間を過ごし、現実世界に戻ったとき、しばらくバーチャル世界にいる感覚が残ってしまう状態で、特に、若年層への影響が懸念されている。
なぜなら、脳や思考能力が発達段階にある若年層は、メタバースにおける偽情報やプロパガンダに対して脆弱で、思想をコントロールされてしまうリスクが高いからである。
2021年(令和3年)2月、イギリスのグラスゴー大学の研究者らによる調査で、「14歳前後から陰謀論を信じる傾向が強くなる」と示唆された。
脳科学者の明和政子京都大学教授は、「前頭前野が未成熟な段階にある子どものとき、物事を感覚的に捉え、ネット情報の強い刺激に影響されやすい」と指摘する。
周囲の環境に影響されやすい思春期(前期10-12歳/後期12-15歳)の子どもは、居心地の良さを現実世界よりもネット空間に感じると、脳に快楽をもたらす「報酬系」が活発化し、自分が知りたい偏った情報を集めたがる。
その偏った情報が、陰謀論であったり、スピリチュアルであったり、過激思想であったりする。
こうした前頭前野が未成熟なとき、親や養育者が、大脳辺縁系(本能や感情を司り、思春期に急激に成熟)が暴走するのを抑制する役割を果たす。
しかし、その親や養育者が率先して、テレビゲームや携帯ゲーム、VRゲームに興じ、スマートフォンを使用する状況にあるときには、その大脳辺縁系は暴走し続ける。
d) ネット利用
東北大学で、子どもたちの脳をMRI画像診断で解析した結果、「ネットを毎日のように使った子どもの脳では、「灰白質」や「白質」と呼ばれる部位の容積が増加していない」ことが判明した。
「灰白質」は、大脳や小脳の神経細胞層で、大脳は思考や記憶、小脳は運動の制御を司り、灰白質の体積(脳細胞の総数にあたる)は、7歳頃にピークに達する。
この神経の高次中枢、つまり、神経細胞同士が接続した大規模なネットワークを介して働く「錐体細胞」は、感情や欲求、習慣を制御する脳領域とも接続している。
発達期にあるはずの子どもの「灰白質」が増えていないことは、「脳の中で、あらゆる命令をだす神経細胞そのものが発達していない」ことを意味する。
「白質(脳の各領域において迅速な伝達を可能にする神経細胞間の結合から構成される)」は神経線維といい、神経細胞から情報を送る電線のようなもので、30歳頃に最大のボリュームに達し、成人後期に減少しはじめる。
この「白質」が増えていないと、脳の神経細胞を繋ぐ電線が発達せず、ネットワークが劣化してしまう。
スマートフォンを長時間使用している子どもの脳では、「灰白質」「白質」が未発達で、その状態が続くと、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている子どもと同様に、脳神経細胞は死滅し、萎縮する。
つまり、子どもが、スマートフォンを長時間使用すると、脳の中であらゆる命令をだす神経細胞(灰白質)の発達を阻害し、しかも、脳の神経細胞をつなぐ(白質)は発達せず、劣化し、萎縮する。
結果、ものごとを深く考えることができず、学校などの授業を理解したり、問題を解いたりすることができない。
e) アレキシサイミア
多くの子どもたちが、長時間、テレビゲームや携帯ゲームをしたり、スマートフォンなどのマルチタスクを使用したりしていることで、危惧されるのは、小学校の現場で、『別紙2』の「3-(13)失感情言語症(アレキシサイミア)と高次神経系のトラブル」で述べているような傾向を示す子どもが増えていることである。
「アレキシサイミア」の子どもは、ケガをしても、あまりに感覚がマヒしていて痛みを感じないなど、自分のからだにもかかわらず、異常に気づき難い、自分のからだと向き合えないという傾向を示す。
「アレキシサイミア」の子どもは、怒り、哀しみなどの感情を感じとることも、ことばで表現することができず、外のできごとのこと細かい部分に関心が限定され、自分の感情を認知することも、自分のことばとして相手に伝えることもできない。
そのため、「どう感じる?」と訊かれると、困惑する。
突然怒ったり、泣きだしたりするが、そのとき、なにを感じているかを説明することはできない。
なぜなら、そのときそのときの感情を、自分の中で区別することが難しいからである。
これは、感情、思考、意志、創造の座である大脳新皮質の前頭葉(前頭前野)の発達の異変と関係が深くかかわっている。
人の意思や創造性、推論などの機能を司るのは、「前頭前野(前頭葉)」である。
f) スマートフォン
スマートフォンなどのマルチタスクをずっと続けていると、人の脳は環境に順応してしまい、脳は、常に新たな情報という刺激を求めるようになり、依存状態がつくられるだけではなく、脳そのものが変質する。
ア) 睡眠障害など
また、スマートフォンが提供するさまざまなコンテンツに脳が刺激されていると、脳は興奮状態になることから、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなり、目が醒めやすくなったり(中途覚醒による断眠)するなど、睡眠障害を招くリスクが高くなる。
③-a)で述べているとおり、中途覚醒による断眠を伴う「睡眠障害」は、ADHDなどの発達障害を発症させる原因となる。
2023年(平成5年)、アメリカのVivek Murthy医務総監は、「ソーシャルメディアが、アメリカの若者のメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす懸念がある。」との公式勧告を発行したが、この報告書では、「ソーシャルメディアの問題ある使用、強迫観念にとらわれた使用、過剰な使用が原因で、10歳代の若者の睡眠が減少している。」、「深夜やそれ以降にまで及ぶソーシャルメディアの使用は、睡眠の質の低下、注意力の低下をもたらし、気分障害(うつ病、双極性障害)の発症と関連している。」、「1日に3時間以上ソーシャルメディアを利用する12歳-15歳のアメリカの子どもは、気分の落ち込みや不安の症状を体験しやすく、時に、若い少女により顕著である。」、「若い少女は特に、ソーシャルメディアの使用が原因で、体型に関する問題、摂食障害の行動を経験している。」と結論づけた調査を引用している。
イ) 浅い本読みで、深い思考不全に
スマートフォンのゲームに熱中している状態も、能動的にゲームをしているわけではなく、実際は、与えられたルールの範囲の中で一生懸命やっているだけである。
常に受け身で情報を与えられるのに慣れてしまうと、行動全般にその影響がでる、つまり、行動や判断が遅くなる。
そして、与えられたルールの範囲の中で、受動的(受け身)な行動習慣が身につくことは、本を読んだり、ものごとを考えたりするとき、「浅く」なる。
“深く”本を読んだり、“深く”ものごとを考えたりするとは、「単に受動的に知識を吸収するだけではなく、内容や状況をしっかり理解し、既に蓄えられている知識や経験と結びつけて新たな洞察を生みだす行為」を指す。
一方の“浅く”本を読んだり、“浅く”ものごとを考えたりすることは、「ザァーと表面的に中身を理解する行為」である。
スマートフォンで画面を忙しくスクロールしながら読んでいる状態は、まさに「ザァーと表面的に中身を理解する」ための読み方をしているにすぎない。
“浅い”本読みは、『別紙2』の冒頭などで、ストレス(脅威、恐怖)などが「海馬」に及ぼす影響(被虐待体験などで萎縮し、後遺症としてのPTSDなどを発症する)などを詳述しているが、短期記憶を司る「海馬」に読んだ内容が納められるだけで、いずれその内容を忘れてしまうことになるのに対し、“深い”本読みは、読んだ内容(短期記憶)と蓄えられた記憶と結びつけられていることから、そのまま短期記憶ではなく長期記憶を司る部位に移行されことになる。
つまり、“深い”本読みは、同時進行で、“深く”ものごとを考える行為そのものであることから、その人にとっての知識として蓄積されていく。
スマートフォンで浅い読み方が習慣になっていると、脳はその状況(環境)に順応してしまうことから、本を読む(勉強する)ときも同じように浅い本読み、すなわち、ものごとを浅く考えることになる。
ウ) メンタル統合(前頭前野統合)と文章理解
長年、「言語」と「想像力」の脳神経プロセスを研究してきたボストン大学の神経学者アンドレイ・ヴィシェドスキー博士が、『Research Ideas and Outcomes』に発表した論文では、「脳の外側前頭前野には、「記憶にあるもの」と「単語」や「文法」を統合し、まったく新しいものを頭の中で想像することを可能にする機能がある。」、つまり、「人は、外側前頭前野に損傷があるとき、モノとモノの関係や、相対性を表す文章が理解できなくなる。」ことが示している。
例えば、「Aは背が高い」というシンプルな文章は理解できても、「AはBより背が高い」となると、どちらが高いのか理解できなかったり、「円のうえに三角を描く」、「春は夏の前にくる」なども同様に、物事の上下関係、前後関係の理解がなくなったりする。
記憶の中の複数の単語を意味のあるメンタルイメージとして構成するプロセスは、「前頭前野統合(Prefrontal Synthesis)」、あるいは、「メンタル統合(Mental Synthesis)」と呼ばれる。
つまり、「メンタル統合(前頭前野統合)」は、複数の単語とそれらの関係を脳内で統合し、想像することを可能にするプロセスである。
そして、「入れ子構造(再帰構造)」になっている文章の理解には、メンタル統合能力が必須となる。
「入れ子構造(再帰構造)」は、主語-動詞関係を基盤とした生成文法の基本である。
一番単純な文は「私は、うれしい(楽しい、哀しい)。」と主語と動詞との基本構造からなる。
また、典型的な単純な句として、「私の子ども」といった所有格-名詞関係の基本構造もある。
こうした基本構造を理解できると、同様の構造を繰り返して無限に文をつくることができる。
例えば、上記の「私は、うれしい。」という文の中に、「私の子どもが合格した。」という文を差し込むと、「私は、子どもが合格したのがうれしい。」となる。
同じような構造を繰り返し適用することができるので、「入れ子構造(再帰構造)」と呼ばれる。
人は、ことばの「入れ子構造(再帰構造)」が理解できるようになると、次々に文をつなげて永遠にイメージを膨らませることができる。
この「単語の柔軟な組み合わせと入れ子構造」は、人の言語に共通する特徴的な機能といえるが、複数の単語が複雑に組み合わされた「入れ子構造(再帰構造)」の文章の理解には、受け手の「前頭前野外側」での“統合力”にかかっている。
親が「入れ子構造(再帰構造)」の文章で話すとき、受け手である子どもの「メンタル統合力」が育っていなければ、「入れ子構造(再帰構造)」の文章を理解することができない。
重要なことは、この「メンタル統合力」の発達には、就学前の5歳までの幼児期に、再帰構造のあることばに触れ、学んでいることが必要で、この臨界期(感受期)を超えると、以降の習得は困難となる。
特異な例として、13歳までいっさいのことばに触れることがなく成長した少女をはじめとする10人の子どもたちは、何年も言語トレーニングを経ても、英語の「in」「on」「at」などの空間的前置詞、動詞の時制、文章の再帰構造を完全に理解することはなかった。
この傾向は、社会的サポートがままならない途上国で、再帰構造のある手話に触れる機会のなかった聴覚障害のある子どもたちにも認められている。
あとから補聴器をつけたり、徹底した言語療法を受けたりしても、「緑の箱を青い箱に入れる」などの簡単な指示をこなすことができない。
このような子どもたちに特徴的なのは、トライ・アンド・エラーを繰り返す行動である。
例えは、子どもたちは、正しく緑色と青色の箱を持ち上げ、合っているかどうかのヒントを得るために、実験者の顔色を見ながら、2つの箱を空間移動させて、トライ・アンド・エラーを繰り返す。
この実験で示されるのが、「再帰言語」と「メンタル統合能力」との深い関係性である。
こういった指示を頭の中で創造して理解するには、5歳までに、難しい再帰言語にさらされることで鍛えられる「メンタル統合力(前頭前野統合力)」が必要不可欠となる。
この「メンタル統合力(前頭前野統合力)」は、『別紙2』の2-(2)で詳述している子どもの「語彙数の獲得」と深く関係する。
家庭内での会話で、獲得した語彙数が少ないと、就学後、教科書や本などの文章に書かれていたり、教師が話したりすることばを知らない(身につけていない)ことになる。
このとき、子どもは、文字(ことば)を会話のようなひとつのまとまりとして捉えられないので、文字を一語一語読む、つまり、途切れ途切れに文字を読む。
これは、「逐次読み」と呼ばれる。
つまり、文字(ことば)のまとまりと捉える(単語や文節)ことができず、意味の理解ができない。
いま、こうした「書いてある文字の意味を理解しながら読んでいない、つまり、字面だけを追って読んでいる(声を発している)」、「活字の羅列に対して目を移動させ、その文字を意味もわからずことばを発しているに過ぎない。つまり、なにをいっているのか意味がわからない」状況の子どもが増えている。
また、同2-(2)-②47文で、「自分の気持ちや考えを表すことば(心情語)の語彙数が少ない子どもの特徴は、「知るか!」「バカ(アホ)!」「死ね!」「勝手にしろ!」「キモい」「ウザい」「ヤバい」「ムカつく」…といった「ワンフレーズの決まり文句」を、吐き捨てるようなことば遣いで、そのあとのことばが続かないことである。」と記している。
その原因は、同48文「こうした「ワンフレーズの決まり文句」を吐き捨てるようなことば遣いは、幼児期に、親の使っていることばを真似て身につけたものである。」と記している。
加えて、その家庭で、親子が、テレビゲームや携帯ゲームに興じ、「扁桃体」の興奮そのままに、ゲーム中に、「死ね!」「消えろ!」などと過激なことばを吐く環境では、子どもの語彙数は増えない。
問題は、あらゆることを「ヤバイ」「キモい」「ウザい」「エグイ」で表現する語彙数の少ない子どもたち、自分の感情を上手くことば(言語)にすることができないことである。
なぜなら、論理的な思考ができず、双方向の話し合いができず、困ったことが起きた瞬間にフリーズ(思考停止)したり、「死ね!」「殺すぞ!」「消えろ!」と暴力的なことばで排除しようとしたりする。
このワンフレーズの心情語は、は、いうまでもなく、複数の単語が複雑に組み合わさった「入れ子構造(再帰構造)」の文章ではない。
こうした「ワンフレーズの決まり文句」を吐き捨てるように使うのは、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた一部の子ども、特に、非行行為で補導、少年院で過ごす子どもに顕著に認められる特徴のひとつである。
児童精神科医である宮口幸治氏は、『ケーキの切れない非行少年たち(新ケーキ潮新書)』の中で、少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことができない非行少年が大勢いたことなどを紹介している。
親が「ワンフレーズの決まり文句」で話す家庭環境では、難しい再帰言語にさらされる機会は少なく、結果、「メンタル統合力(前頭前野統合力)」は発達せず、就学後、教師の話す複数の単語が複雑に組み合わさった「入れ子構造(再帰構造)」の文章(話/支持)を理解できない状況に陥る。
毎日、ゲーム機で長時間遊ぶ中で、前頭前野(前頭葉)の発達が阻害され、ほぼ同時に、就学前の5歳まで、難しい再帰言語にさらされない家庭環境に育った子どもは、十分(完全)な「メンタル統合力(前頭前野統合力)」を習得できず、しかも、スマートフォンを長時間使用することで、脳の中であらゆる命令をだす神経細胞(灰白質)の発達は阻害され、しかも、脳の神経細胞をつなぐ(白質)は発達せず、劣化し、萎縮する。
そして、5歳までに「メンタル統合力」を十分(完全)に獲得できずに就学したとき、その子どもは、主語-動詞関係を基盤とした生成文法の基本となる「入れ子構造(再帰構造)」を理解できず、発達障害のひとつ「学習障害(LD)」と扱われたり、診断されたりすることになる。
「入れ子構造(再帰構造)」を理解できない子どもが、教師に「・・をやってみて。」と指示されたとき、周りの子どもたちがどうやるのかをうかがう(周りをきょろきょろと見続ける)、つまり、トライ・アンド・エラーを繰り返していると、落ち着きがないとADHD扱いされることもある。
いま、小学校の現場では、こうした主語-動詞関係を基盤とした生成文法の基本となる「入れ子構造(再帰構造)」を理解できない子どもがとても増えている。
これは、サピエンスが、7万年前、この「メンタル統合(前頭前野統合)」と「再帰言語」を獲得したことで、本質的に行動が異なる新たな種としてホモサピエンス(人類)が誕生し、以降、「メンタル統合(前頭前野統合)」と「再帰言語」はさまざまな文化をつくりあげてきた。
しかし、テレビが日常生活に組み込まれて約60年、1980年代-1990年代に、家庭用ゲーム機が普及し、直近の15年で、スマートフォン、タブレットなど普及してきたが、このわずかな期間で、子どもの脳、人の脳を変質させてしまったといえる。
日本では、「SNSなどによる短文のやりとりの増加した」ことで、長文を読み書きする機会が著しく減少し、高校生、大学生、新卒採用者の読解力が低くなっていることが指摘されている。
このことは、OECD(経済協力開発機構)の加盟国を中心に実施される国際的な学習到達度調査「PISA(Programme for International Student Assessment)」では、読解力・数学的リテラシー・科学的リテラシーの3分野で、義務教育終了段階の15歳3ヶ月以上16歳2ヶ月以下の学校に通う生徒(日本では高等学校1年生)が対象に生徒に実施しているが、その結果にも明確に表れている。
日本は、2012年(平成24年)は65ヶ国中で科学的リテラシーが4位、数学的リテラシーが7位、読解力が4位だったが、2015年(平成27年)は72ヶ国中で科学的リテラシーが2位、数学的リテラシーが5位、読解力が8位、2018年(平成30年)は、数学的リテラシーが6位、科学的リテラシーが5位、読解力は15位と、「読解力」に限り、順位を大きく下げ続けている。
さらなる懸念材料である。
DV被害支援室poco a poco
無断転載・転用厳禁(他案件での使用・引用を含む)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
