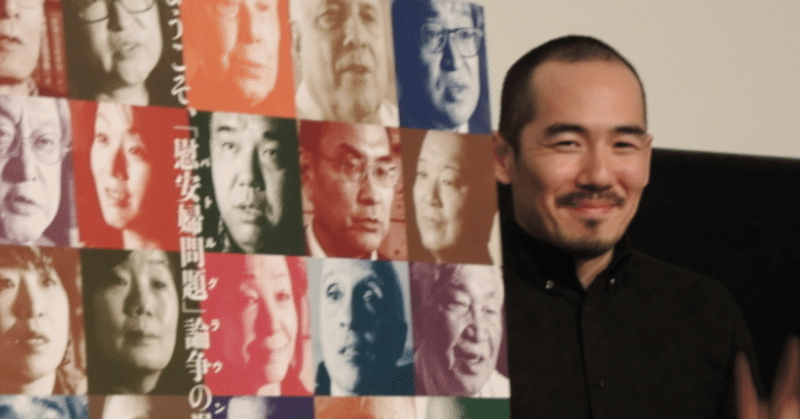
「主戦場」裁判 傍聴記(後編)
いよいよデザキの尋問です。先週の原告側尋問に続き、9月16日(木)13:10~、運良く傍聴できました。
傍聴席は先週とおなじ21席のみ。先週は何名かがアブれたのを目撃したので余裕をもって1時間前に到着したもののすでに長蛇の列だった。なんとかギリでセーフ。並んでしばらくすると、山本優美子氏が目の前を颯爽と通り過ぎて行かれた。今日は紺色に白の花柄のボディフィットなワンピでした。続き、藤木俊一氏が黒のボタンダウンとストーンウォッシュ風のデニムで登場、デキる男は今日は早めの到着です。さらに藤岡信勝氏や白髪長身の荒木田弁護士らが通過してゆき、まるで芸能人の出待ちのよう。はすみとしこ先生も傍聴に来られました!
法廷の様子は、9/17-18の「ワールド親父サテライト」の番組で当事者が詳しくレポート下さっていますので是非、こちらもご覧ください。
(25:00頃~1:22:00頃)
番組→https://youtu.be/B6LO2EmGaYo
番組と重なる部分もありつつ、以下は傍聴席からタス記者が詳細をレポートします。
■ 尋問の要領
当初の予定では、主尋問(原告側の質問時間)40分+通訳付で80分、反対尋問(被告側の質問時間)30分+通訳付で60分、計140分の予定でスタートした。ところが、以下にお伝えするようなハプニングが生じて、持ち時間をめぐって被告側は怒りだし、原告側も怒り・・・もうハチャメチャ。終わってみたら17時をまわっており、裁判官たちも残業でした。終わる頃には裁判長の顔は紅潮し、スダレ髪が額の脂汗に張り付つく始末、嗚呼。
■ 通訳のハプニング
最初の一声から「聞き取りにくい」とデザキ側弁護士よりダメ出しが入る。これには「ほんそれ!」と同意した。70歳を超えている?と見える老婦人の眼鏡は明らかに老眼鏡だ。マイクのセットを数名でチェックした後、気を取り直してリ再スタートするも、その後もすさまじい誤訳と聞き落としの連続。ルーマニアもウイーンもヒアリングできず、上映と一般公開を混同する。four hundred thousand を20万と訳す。フレーズの意味まで取り違えて、デザキが同じ内容を3度繰り返した場面もあった。耳が遠かったせいもあるのかもしれない。
ただでさえ逐次通訳だと時間が倍かかるのに、何度も被告側から訂正が入ってタイムマネジメントどころの騒ぎではない。法廷内にストレスが溜まってゆく・・・。

↑イメージです
通訳者は利用者側の帯同ではなく裁判所の手配だが、このシステムには大きな問題がありそうだ。地裁では裁判手続や法律用語のレクチャーはなされるものの、会議通訳の場合とは異なり専門用語の洗い出しはおろか、事前のブリーフィングすらなかったようだ。キーッ、重要な裁判なんですよ!!
最終盤には被告側代理人が「通訳」への苦情を裁判長に申し立て、(デザキの)英語の原文提出の許諾を求めるとともに、(裁判官交代や控訴審を見越してか)「抗議した旨」を記録を残すことを強く求めた。しかし原告側は通訳を介した日本語に対して答えているという矛盾も残る。そのため裁判官たちが一旦退出して別室で協議するという珍しい一幕もあった。
以下、デザキの答弁は昨日のたかまつなな氏のレビューと比較しながら読まれたい。
■ デザキ答弁の詳細
(被告側代理人(岩井氏)の誘導により、デザキは次のことを答弁した)
・上智の終了プロジェクトは柔軟で自由度があり、文書による論文形式に限定されず映像でも可能だ。はじめはPh.D.を取得するため論文を検討していたが、ドキュメンタリーフィルムが可能だったので、そちらを選んだ。慰安婦問題に興味を持ったのは一学期の頃で、最初は「平和学」を希望していたが上智には存在せず、代わりにGlobal Studies を専攻することにしたのだが、日韓両国に友人を持つ自分は両国間の衝突に関心が向いた。
・中野晃一氏は自らが指導教授として選択したものではなく、オリエンテーションで彼が担当となったためであり、理由は不知。映画には中野教授も登場するが、出演させるべきか迷いはあったが、教授は日本のナショナリズムや政治等が専門であり、なおかつ多くの学生が自身の研究に指導教授を登場させているのを見て大丈夫と思った。中野教授から映画を作るようにとの指示は受けていない。藤岡氏は月間hanadaであたかも中野の指示であるかのように述べておられたが事実ではない。
・出演者の選考は自分自身と、あと友人の助けで行った。友人のコリンとはカタリンのことである(ルーマニア人の彼は復数の呼称を有している)。出演者の選考基準は、主に最も活発に活動している方々を選んだ。歴史を変えたり、歴史を否定したり・・・。秦郁彦氏、高橋史朗氏、目良浩一氏ら、取材を辞退した方々もあった。秦先生の場合には何度か依頼を試み、はじめは拒否されたが、戸塚氏と吉見氏を取材した後なら検討可と仰ったので両氏の取材後にFAXで提案した。(faxの後で電話するように言われていたが夜間だったため遠慮して)翌日連絡すると、すぐに電話しないと憤慨された。
つまり、秦氏に限っては”両氏の取材内容を知った上で返答する”と回答されたわけだが、氏は特別な存在であったため特別な配慮をした。
(岩井代理人)原告らは、原告らを先に取材し、その後で(左派に)反論させているとの主張だが・・・。
*ここで原告側尾崎代理人より「それは映画における登場順序のことだ」と訂正の指摘が入る。
・左右の(人数の)バランスはある程度考慮したが、人数よりも最も活発な論者に登場してもらうことが重要であり、原告側は8:18と主張するが、キムやエリック・マール(?)やフランク・インテロ(?)、韓国人の看護師等はちょい役にすぎず、逆に征矢清(?)、目良浩一、中山成彬等を原告はカウントしていない。
*注:藤木氏によればパンフに記載された人数を比較したとのこと。
・最初から結論ありきではなく、映画で述べた結論は最終的な編集段階で固まったもの。自分が把握する「慰安婦」問題の主な論点とは、①20万人という数字、②リクルート方法(=強制連行)、③性奴隷説、の3点であり、自分の結論は、①は推定数なので慎重であるべきと考えており、②は国際法上では「騙した」という要素があれば強制連行にあたる。多くの「騙し」があったと思う。③金銭を受け取ろうが受け取るまいが、支配下に置かれた場合は「性奴隷」といえる、と考える。

・原告らに(文書で)取材を依頼したのは、岡本アキコかハタ・モモコかのどちらか。作品のアイデアは自分(デザキ)であり、撮影時に特に気をつけたのは照明、音響や2台のカメラのホワイトバランス、露出のチェック等だた。これら設営には25分ほどかかる。設営や取材対象者について何らかの指示を受けたりしたことはなく、自分はある種の完全主義者であり支配欲もあるため、(機材のセットアップを)誰にも触らせることはなかった。取材内容についても揉めたこともない。
*注:岡本明子とは、中野晃一教授がSEALDs奥田愛基らと設立したシンクタンク「ReDEMOS」(リデモス)のメンバー。
・撮影終了後に、映像を「使うな」と言われた覚えもない。取材対象者には(原告らを含めて)メールを送付し、映画祭について通知した。上映についての抗議も誰からも受けていない。映画の公開(Public Viewing)のお知らせメールについても同様に送付したが、誰からも抗議はなく、藤木氏とケント氏に及んでは祝福メールを頂いたほど。
・山本優美子氏への初期の打診メールで「プラットフォーム~」とあるのは、自分のYouTUBEのPVは100万ほどあり、反響が大きいことに加え、自分は(上智の院という)学術の領域にも属している。そのため、作品については彼らが声を届けられる”視聴者層が自分にはついている”ことをアピールしたもの。
・上智の学内だけの上映に限らない旨は、「もし出来が良ければ映画祭や映画館で~」と「承諾書」において事前にお伝えしている。藤岡氏にも(自分は機材の設営に専念していたが)取材前に「承諾書」を岡本氏が示しており、取材後に承諾書の話も出ている。取材の数日後にメールで藤岡氏とは、一文を加筆する旨の話が出ている。すでに取材時に受け取っているので、同メールに「承諾書」を添付することはしていない。
・取材には1.5時間ほど要し、岡本氏が日本語で行った。時々自分が付け加えることはあったが岡本氏に英語で伝え、それを岡本氏が藤岡氏に日本語で伝えた。
*注:どちらが何語で喋っていたかについては原告との間で重要な争点となっている。デザキは日本語が流暢ではないかという疑惑があり、尋問の中で裁判長が(うっかり?)「日本語ができないという設定ですよね?」と言ってしまうコントのような場面もあった。
・藤岡氏には2018年5月に映像のクリップをお送りしたが、見てから返事すると言われたきり返事はなかった。一方の藤木氏とは「承諾書」を巡って電話やメールでのやりとりがあった。全体の編集権を求める藤木氏の要望を呑むことはできず、したがって藤木氏の出演部分のみをお送りすることとした。(発話者の)発言の切り取りや捻じ曲げがないかの確認と、もし何か異論あればクレジットにメッセージを掲載することとなった。それに基づき、藤木氏に2018年5月にクリップを送付した。氏の要望で再送も。しかし返事がなかったので合意と解釈した。藤木氏に対しては過去「完成したドキュメンタリーをお送りする」と書いた事実はある。しかしその後、電話で条件を変更しており、2016年9月16日に協議の結果、合意に至っている。
・映画の中で「歴史修正主義者」「否定論者」の表現を使った意図は、あくまで”They are known as~(~として知られる)"、 "So called"(いわゆる)の意であり、メディアや学術界で彼らがそのように呼ばれているためであり、私(デザキ)自身がそのように見做しているという訳ではない。
・フェアユース(アメリカにおける著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ)の権威であるピーター・ヤーシー(?)にも確認をとり、全クリップにつき問題なしとの回答を得ている。
・原告らは上智大学に対して研究不正を巡る調査を求めたが、上智大では委員会を設置して約1年間ほど調査した。(自身も)資料を提出し、3時間の事情聴取を受けたが、結果的に何の違反も発見されなかった。原告らは異議を申し立てたが大学側は棄却した。
・靖国神社の行進の場面を巡って、過去に菊守青年同盟が配給会社である「東風」を訴えたことはある。一審判決は被告におとがめなく、控訴審は最終的に原告側が請求を棄却した。
・『主戦場』の作品は、ハーバード、スタンフォードをはじめ、バークレー、NY大、ストックホルム大、ウイーン大など、日本と韓国を除く世界50校以上の大学で上映されたほか、2019年アジア地域学会でも上映された。フィルムは良く出来ており、バランスがとれ、学術的にも高いレベルに達していると高い評価を得ている。広く世界で上映されるべきとの評価も受けた。
■ 原告からの質問に答えるデザキ
(↓原告代理人 中野による質問)
Q:指導教授からの指示はなく、共謀していないとの由。「承諾書がないとマズい」との指導教員のコメントが存在しており、指示を受けているにもかかわらず「共謀」ではないと言うのは何故か。
A:藤岡氏が署名を拒否されたので、他の教員(シュレイダー?)に相談したところサインが必要と言われたもの。指導というより自分から尋ねたものであり、実際、自分自身もそのように思っていた。
Q:パンフにはCo-Directorとしてハタ・モモコの名があり、パンフには彼女が自分の名を見つけて驚いたとの記載がある。任命は誰が決めたことなのか。
A:自分(デザキ)が決めた。
Q:答弁書のP3にはクラウドファンディングしたとの記載があるが、指導教官は何と言ったか
A:彼(中野晃一)には聞かずにやった
Q:予告編の制作はいつ頃か、また、卒業制作版と劇場版に(内容の)違いはあるのか
A:予告編は2018年の1月か2月だったと思うが定かでない。両バージョンで音楽やアニメーションなど見てくれの違いはあるが、コンテンツは同じである。卒業制作版で「MG」と残したのは、追ってアニメを挿入したいと思っていたため。
Q:トニー・マラーノ氏のYouTUBE映像を使用しているが、なぜ(使用の許可について)トニー氏本人ではなく、専門家に問い合わせたのか。
A:フェアユース法では必要がなかったから。CNN等からもクリップを使用しており、他の誰の意見も求めていなかった。
*注:回答の意味が不明でした
(↓藤岡信勝氏、後半は藤木俊一氏が共同で質問)
Q:当初のデザキからの打診メールには、①卒業制作として、②他の学生と共に、③ビデオドキュメンタリーを製作しており~との自己紹介があり、これが取材の目的と書いている、YESかNOか。そしてここに商業目的と書いてあるか。
A:自己紹介はYES。ここには書いてないが・・・(と言い書けてYES/NOの返答を迫られ)ここには書いていない。
Q:私は書かれた通りを信じて取材を受けたが、山本優美子氏へのメールにも「大学院生として私には・・・尊厳と・・・を以って・・・倫理的義務があります」また「これは、学術研究であるため・・・」とある。「商業映画」と書いてあるか。
A:いいえ、書いてありません。
Q:では、ここにある倫理的基準等を満たしていると思うか。
A:はい。
(ここで藤木俊一氏により動画の一部がモバイルPCで公開される)
修正主義者/否定論者の文字に挟まれた原告らのアップ部分と、日韓慰安婦合意(2017.12.28)に際し、これが「けしからん」として李容洙が怒鳴り込んでいる場面がイ氏の凄まじい怒声とともに公開される。
*李容洙(イ・ヨンス)とは、トランプ大統領に抱きついた自称慰安婦の女性。
Q:激しく怒る場面は強烈なインパクトをもたらすが、冒頭部は映画全体の基調を決めるものだ。これは冒頭部の字幕が終わって最初の場面であるが、貴方はイ・ヨンスが慰安婦ではなかったという説があるのはご存知か。
A:NO。
Q:イ・ヨンスが米軍の慰安婦だった有力な証拠が存在するのは知っているか?
A:(返答は)歴史家に確認しなければならないが、貴方も歴史の専門家ではない。
*注:ここで会場にざわめきと失笑が起きる。
Q:(TVの)アナウンサーが「20万人」と発言するが、その20万人という文字を、何度も繰り返し、また、「Sex Slave」についても何度も何度もSex Slave, Sex Slave, Sex Slave・・・と繰り返されるが、視聴者への刷り込みのある作り方だとは思いませんか
A:これは冒頭36秒の部分にあたるが、西欧のメデイアが頻繁にそう言っているということを伝えたものであり、実際のところ議論はより複雑であると本編では伝えている。
Q:上にRevisionist(歴史修正主義者)、下にDenialist(歴史否定論者)と書かれた文字に挟まれて、縦長の画面で原告らの顔が並べられ、アップで映し出されており、それぞれが独立して動くという非常に気味の悪い映像であるが、なぜそういう映像を作ったのか。
A:これは”欧米で”彼らがそう呼ばれていることを伝えたものであり、このような単純化とは裏腹に、実態はより複雑であり、彼らには意味のある議論が存在する、彼らにも道理があるのだ(how reasonable they are)という事を映画では伝えている。現に36秒に続いて9分間を(保守派に)充てている。
Q:いちばん単純化したのは貴方自身だと思われませんか? 5名の動く映像のどこに、(貴方が約束したような)尊厳や公正がありますか?
A:修正主義者、否定論者の箇所はわずか20秒ほどで、そのあと9分もの枠をとって、(原告らの)主張に道理があることを示した。
Q:5月9日に行われた私(藤岡)への取材時に、私は日本語で話しかけられたと記憶している。ところが(先週の)尋問では別のことを言っておられた。たしかに一部、そういう場面(注:岡本氏が質問している場面が前週の法廷で被告側より公開された)はあった。しかし、同じ原告の山本優美子氏も、日本語で取材を受けたと言っておられる。日本語か英語か、どちらだったか。
A:取材時には自分はカメラの背部に居て、取材対象者にはカメラの方向を見るのではなく、インタビュアーである彼女の方を見て下さいと言っている。
Q:取材時にどの言語を使用していたかは、冒頭部から全録画を公開すれば自ずと明らかになるが、その意思はあるか。
A:先週すでに(岡本氏の場面を提示したことで)証明済みだ。
Q:「合意書」の第五条には、「甲は、本映画公開前に乙に確認を求め、乙は、速やかに確認する」とあるが、これを貴方は履行していない。藤岡と藤木の両名に送付したか。
A:2018年の5月にクリップを送り、2週間以内の返答を求めたが返答なく、年内にも返答はなく、2019年4月まで何のコメントもなかった。返答がなかったので両者の解釈に齟齬はないと思った。ケント氏からは、PRの提案と祝意を頂いた。
*注:合意書とは「承諾書」とは別に藤木氏の配慮により、取材を受ける側についての権利が補完されたもので、藤岡氏と藤木氏の2名がデザキと交わしたもの。
(↓原告側 藤木俊一氏による質問)
Q:作中、「安倍政権」に触れた箇所があるが、指導教官の中野晃一教授がSEALDsや(・・・聞き取れず)をバックアップしていたのは知っているか。また、中野教授が2016年と2020年に、「しんぶん赤旗」にて新春対談を行ったことは知っているか。
A:SEALDsのイベントについて話しているのは知っているが、安倍叩きとは思わなかった。
Q:貴方は「漏洩や著作権侵害」という一方的な理由で、合意書の条項を反故にしましたか、していませんか。
A:していません。メールでクリップを送り、返事を受け取っていません。
(↓被告側 岩井代理人による質問)
Q:一般論として、冒頭部分で問題の所在を明らかし、分析がそれに続くものであるが、冒頭部分の表現はこのような「問題提起」にあたるのでは?A:そうです。
Q:つまり貴方は、冒頭の部分で、西欧では単純化されて紹介されているという「問題提起」をしたということですね?
A:そのとおりです。
Q:その結果、20万人説についても、概算の数値(estimate)を紹介したものであり、自身の結論として数値は出していませんね?
A:はい、そうです。
(↓原告側 荒木田代理人による質問)
Q:20万人は欧米メディアの概算数値と言われるが、では、貴方自身にとって慰安婦は何人なんですか?
A:最小値で2~3万人、最大値で40万人です。見積もりなので数値には注意深くあらねばならないというのが自分の持論です。
*注:通訳が40万人を20万人と誤訳した。
Q:貴方が結論付けた「強制的に募集した」という表現の、「強制」と「募集」は語義矛盾では?
A:強制は「騙すこと(deception)」を含みます。
Q:貴方は学術研究であると言った。では貴方の研究の「成果」とは何か。
A:(しばらくの沈黙ののち)世界中の大学で作品は上映された。
*注:ここで荒木田弁護士が「それをプロパガンダと言うんだよ」と間髪入れずに発言
■ 配給会社「東風」代表者・木下氏の答弁
(↓被告側 原田代理人の質問に答えて)

*イメージです
・ケント・ギルバート氏との会話は試写会のあった2019年3月18日のことではなく、差し止め会見の前日である5月29日の誤りで、この点を訂正する。ケント氏からは「ボクがキレたら怖いぞ」「ヤクザのようなやり方ではなく~」と言われた。3月18日にも電話はあったが、この時には櫻井よし子さんにも案内をしたいという内容だった。
・自社は2009年に設立したドキュメンタリー映画を専門とする配給会社であり、これまでに約80本の配給実績がある。映画の業界では①制作/②配給/③興行に分かれており、今回の件では①がノーマン・プロダクション、②が東風、③が各映画館や自主上映会の主催者となる。
・『主戦場』は2019年4月以降、各地のシアターやイメージフォーラム他で公開してきており、終了時期というのは特定できない。自主上映会とは、ミニシアターとは異なり、特定分野のものを特別な場所で主催者が開催するものであり、配給会社が素材を貸し出すやり方である。
・『主戦場』については、最初は順調に進んだが、今回のような裁判や妨害行為があると萎縮につながる。上映のために会場を貸さないようにといった申入書が原告らのHP上で公開されている。これらも萎縮効果につながる。
・今回は2018年10月の釜山映画祭に大矢英代氏の『沖縄スパイ戦史』が招待されており、その方が『主戦場』を観たことで東風を紹介した。その後、デザキ氏より東風にメールがあり配給の運びとなった。
・配給にあたって注意したのは主に、①対象者との関係-取材の許諾や合意書の存在の有無と、②アーカイブ映像の取り扱いの2点であり、①については実際に全員分を確認した。②については、米国のフェアユース専門家の了承を得ているとの回答を受けている。
・2019年4月の試写会へのご案内は、東風より原告全員および全出演者にお送りする了解を得ている。特定の人物には送るなとの指示は受けていない。
・ドキュメンタリー映画という性質上、出演者からのクレームはままあることで、作品が表に出る前にボツになるケースもある。ケント氏については公開そのものに反対されていたわけではない。しんゆり映画祭では上映が中止になりかけたが、是枝監督や一般市民の支援によって上映が実現した。自分たちは圧力には絶対に負けないが、萎縮があれば結果的に負けたことになる。菊守青年同盟からは提訴されたが、一審では勝訴し、控訴審は原告側が請求を取り下げている。
(↓原告側 原田代理人による質問)
Q:これまでに上映した映画館の数、売上高、利益等について教えてください
A:上映館数はおそらく50館以上になると思う。興行収入はおそらく数千万円、1億近くになると思う。利益についてはちょっと分からない。
Q:アメリカのアマゾンでDVDが流通している事についてはどうお考えか
A:それについては、韓国のSBSも含めて関与しておらず、自分たちにあるのはあくまで日本国内での配給の権利である。
■ 両日を通しての所感
前回から一貫して、冒頭部のおどろおどろしい作りに憤慨されている藤岡先生が印象的だった。藤岡先生とは閉廷後にお話する機会を頂いたが、とても柔和な方であった。荒木田弁護士の簡潔にしてシャープなツッコミには毎々感心するばかり。映画を視聴していない筆者にとって、法廷で再生された場面は非常にショッキングで、大変参考になったし効果大だったと思う。目下、なんとか本編が見れないか模索中。
左右の弁護団が揉めるたびに、裁判長が右を向いたり左を向いたり「まあまあ」「まあまあ」ととりなす様子には苦笑した。頭の形から脳の容量も大きそうだし良識的な裁判官とお見受けするが、最後に「通訳」の件で被告側岩井弁護士が慇懃無礼なトーンで延々抗議した際の、裁判長のリアクションが面白かった。頭のよい人がストレートに言ってしまわないよう、気を遣って言葉を選ぶので、結果的に「余計なフレーズを挿入しまくるので、結果として何を言ってるか分からなくなる」状態に笑いがこみ上げた。判決文は「韜晦型」でないことを祈る。
昨日のnoteの、たかまつなな氏のレビューと比較すると、いかにデザキの答弁がオーディエンスの評価と異なるものであるか分かるだろう。左派芸人ですら、あの感想なのだ。要するに『主戦場』は(たかまつ氏のような)左派ウケするエンタメにすぎないことを、たかまつ氏自身がはしなくも露呈させてしまったのである。だが、たかまつ氏のお陰で慰安婦問題を巡る若いジェネレーションの左右対立の原因が筆者なりに理解できてしまった!要は「国家観」の違いである。これについてはいづれ稿を改めて述べたい。
しんゆり映画祭での上映に是枝監督が一役買っていたことに、あらためてがっかりだった。この裁判には復数の論点が含まれるが、一旦の結論は来年1月27日に出されるそうです。
以上、傍聴席からtassがお伝えしました。 (完)
【付録】
9/17ワー親の番組のチャット欄にて、全裸パヨクさんが有力情報をご提供されていたのでご紹介します。
*ミキ・デザキ tbsラジオ 荻上チキ インタビュー要約
1,日本での差別という動画を上げた、ネトウヨの攻撃を受けた
2,同時期、慰安婦問題で植村隆氏もネトウヨの攻撃を受けた
3,ネトウヨはなぜ私や植村氏を沈黙させようとするのか興味がわいた
4,しかし映画作成に関し慰安婦問題は先入観なし
5,取材先の言葉を曲げずにそのままで
6,両サイド取材する旨伝えた
7,出演者が商業公開にクレーム→卒論も一般公開OK、契約書あり
*中央日報1,デザキ氏は次の作品のテーマとして日本国内の性暴力被害、難民問題などを考えている。「慰安婦について調査する過程で日本国内で男性による性犯罪がいかに多く隠されているかを知った」とし「韓国は『#MeToo(ミートゥー)運動』で性戦争が起きているが、日本は不幸にも依然として被害者が話しにくいようだ。現職男性記者の性暴力を告発した伊藤詩織氏の勇気は社会に大きな波紋を起こすものだが・・・(以下略)
