フランク・ザッパ アルバムレビュー1(Freak Out - Chunga's Revenge)
閉鎖してしまったウェブサイトから、フランク・ザッパ(以下FZもしくはFZ御大)のアルバムレビューをサルベージします。これ最初に書いてからもう25年くらい経ちます…現時点での加筆も多少加えながら行きたいと思います。
アルバムの情報を書き連ねることはあまりしません。(全編英語ですが)現在ではThe Big Noteと言う完璧なデータベース本がありますし、アルバムレビューもそこら中にあるので、ここでは私の私的な感想を記すようにしたいと思います。
Freak Out! (1966)

Ray Collins(Vo.Harm,Tambourine) Jimmy Carl Black(Ds.Voice) Roy Estrada(Bs,Cho) Elliot Ingber(G)
本作がリリースされた1966年、当時のアメリカでは何が売れていたのかといえば、ビートルズで言うとリボルバー、あるいはシングル「We Can Work It Out」あたり。チャートを見るとまだまだオールディーズの香りがします。MGMレコードは、そんな時代に本作をリリースしてしまったのです。しかも2枚組で。
1曲目からなんか違うな、ひねくれた音楽だな…と聴いていくと、最初の山場は3曲目「Who Are The Brain Police?」に現れます。おそらく、既存のどんなロック・イディオムにも当てはまらない曲・演奏。さらにはサウンド・コラージュ満載だし。
アルバム全体を通じて同じリフ・動機が意図的に何度も繰り返して現れ、C面後半「Help I'm A Rock」あたりから、完全な無法地帯・どんちゃん騒ぎ状態になります。同時期において相当に先鋭的なことをやっていたビートルズに比べても、このアルバムの方法論は遥かに過激で、前例のないものでした。
アルバム発表から既に半世紀が過ぎ、FZ御大の仕事全体を見渡せる立場から後知恵的に言うと、「この時点でFZの音楽は完成している」としか言いようがないのです。御大の頭の中には、すでに表現すべき音楽は出来上がっており、制約条件は演奏者の技術的側面(及び機材の制約)だけでした。もしこの時点で御大がシンクラヴィアを手に入れていたら、いきなりThe Black Pageのような曲が出来上がっていたはずです。最終曲「The Return of The Monster Magnet」で既に完成しているサウンドコラージュを聴いてもそれは明らかです。FZが一生をかけて紡いでいく音楽は、すでに1966年にその全貌を現していたということです。
そして、本作の最大のポイントは「醜さ」であります。すべての楽曲において、意図的にアンサンブルが醜くなるようなアレンジが施されている。歌っているのもむさいオッサンたちだし、コーラスも意図して外した音を選択している。聴きやすい音楽と言うものをFZはハナから除外していました。
パーソネルをつくづく見返すと、ラストのどんちゃん騒ぎは別として、このアルバムは5人で作られているのですね。未だに信じられません。4トラックレコーダーで作られていることも含め、ロックの奇跡の一つでしょう。
Absolutely Free (1967)
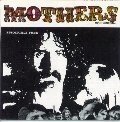
Ray Collins(Vo) Jimmy Carl Black(Ds.Voice) Roy Estrada(Bs,Cho) Billy Mundi,Don Preston,Bunk Gardner,Jim Sherwood
この作品は、ビートルズが「S'gt.Pepper's Lonely Hearts Club Band」でいくつかのアイデアをパクったことで有名です(少なくともFZファンの間では)。
筆者は「現在に通ずるFZのアイデアが全て集約されたアルバム」は、デビューアルバムではなくてむしろこっちではないかと思っています。もうちょっと言うと、Freak Outではまだ試行錯誤だったいくつかの方法論が、このアルバムでは大体確立されたということです。
アルバムの全ての曲をつないでいくSEGUEという手法、はっきりと現われている現代音楽への傾倒(ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」や「春の祭典」をそのまま使っています)、変拍子変連符ユニゾン、風刺に満ちた、またセックスを描写した歌詞と、長いギター・ソロ以外の要素は大体出尽くしています。
そして、これにR&Bも含めたミクスチャーミュージックを1曲で体現している「Brown shoes don't make it」は圧巻です。ただ、全体に猥雑感というか「すっきりしない感」が強いような気がします。テイストはFreak Out!とそんなに変わらないはずなのに、筆者としてはあまり回数を聴かないアルバムです。
なお、Louie Louieのパロディである「Plastic People」のモチーフは、最終作「Yellow Shark」に至るまでかたちを変えながら使われてゆくことになりました。
We're Only In It For The Money (1967)

Billy Mundi (dr, vo) Bunk Gardner (Reeds) Roy Estrada (Bs, Vo) Don Preston ,Jimmy Carl Black (Dr, Trp, Vo) Ian Underwood (Pf, woodwinds) Motorhead Sherwood (Sax) etc.
最近は上記のジャケにほぼ統一されているようですが、オリジナルジャケは「S'gt~」のをもろパクりだったのが本作(MGMがビビって上のジャケットに差し替えたんですな。CD再発の時はパクリバージョンでしたが)。大体このタイトルからして皮肉たっぷりですが、内容的にもヘビーなテーマを扱っていて、州知事だったロナルド・レーガンに対する痛烈な皮肉が入っていたり、カフカの「流刑地にて」を読んでからでないと聴いてはいけないとかいろんな事が書いてあり、日本盤のライナーにはこの「流刑地にて」までご丁寧に載っています。
筆者はこのカフカはちゃんと読まずに聴いています。カフカそのものがあまり好きではないこと、「流刑地にて」にはかなり残酷な描写が多く読むに堪えないこと、そして日本語文化圏の我々にはこの「カフカを読んでから聴く」ことにほとんど意義がないこと、などがその理由です(何も一から十までFZの指示に従うことはありません)。
このアルバムは、かなりポップです。全体に短く親しみやすい曲が多いのが特徴で、初心者にもお勧め。「Let's Make The Water Turn Black」など最近に至るまでのレパートリーもかなり含まれています。ただし、筆者個人として最も重要性の高い曲はラスト「クロムメッキの運命のメガフォン」であります。テープコラージュという手法を含め、ヴァレーズの影響がストレートに出たFZ史上初めての曲で、しかもそれをこういったポップなアルバムの最後に入れるセンス・構成力(というかムチャクチャ加減)には脱帽します。
ちなみに本アルバムにはオリジナルバージョンと、リズムセクション差し替えバージョン(ベースがアーサー・バーロウ、ドラムスがチャド・ワッカーマン)があります。後者はオールドファンからは非難轟々のようですが、私は両方とも結構好きで、両方保有してその時の気分で聴いています。
Lumpy Gravy (1968)

FZの初ソロ作。当時はアルバム両面1曲ずつで、針を落としてみたら全編大コラージュ大会、要するに前作の「クロムメッキの運命のメガフォン」をアルバム1枚に渡って延々とやっている。こりゃ売れまい。筆者も最初のうちは全く本作を聴けなかった覚えがあります。
むしろ、他のアルバムをいろいろ聴いてから本作を聴くほうが、よりその意味合いや値打ちが分かる気がします。序盤のメロディはランピーのテーマとされてますが、要するにOh No~Orange Countyに連なるいつものメロディ。直後の「いたち野郎」でも出てくるし、後年のMake A Jazz Noise Hereでもメドレーで演奏されるアレです。あるいはパート2の後半に印象的に表れるメロディ、言うまでもなくKing Kongです。
英語がネイティブで解らない我々にとっては、ベーゼンドルファー下のバカ話に耐えつつ、時々現れるこれらの美しいメロディを楽しむというのが正解でしょう。あ、筆者は最近ディクテーションのネタとして本作を聴いてますが(笑)。
もうひとつ。Civilization Phase IIIを聴いてから本作を聴くと、これは楽しいですよ。シビIIIを相当回数聴いていることが前提ですが。パート2のおおよそ4分辺り、「めりーごーらーん、めりーごーらーん」が聴こえてから「The thing is put a motor in yourself」と来る下り。ゾクゾクします。「タタタタタタタッター」と言うシンクラヴィアのモチーフが今にも聴こえてきそう。マニアックな楽しみ方やな~(苦笑)
Crusin' With Ruben And The Jets (1968)

Ray Collins(Vo) Roy Estrada(Bs) Jimmy Carl Black & Arthur Dyer Tripp III (Ds) Ian Underwood & Don Preston (piano) Jim Motorhead Sherwood (baritone sax & tambourine) Bunk Gardner & Ian Underwood (Sax)
今度は全編R&B(ドゥーワップ)と言う内容です。筆者は「FZ要素」の中で一番苦手なのがこのR&Bなので、実はこのアルバムはほとんど聴いていません。
FZ本人いわく「ストラヴィンスキーが新古典主義時代にやったことのR&B版」ということですが、当時の旧規範を用いて新しいものを作った意味では評価できるとしても、要するにジャズで言えばディキシーランドに対するバップみたいなもので、現在となってはその違いを云々する意味があるとは筆者には思えません。
ただ、評論家には衝撃的らしく、本作は非常に評論家受けのいい作品となっています。本アルバムも「We're~」同様リズムセクション差し替えバージョンが出ていますが、私は差し替え盤しか持っていません。
(追記)レコ評を機にもう一度聴くか…て言いながら聴いたら寝ちゃったし。結局このレコ評も差し替える気にならないし。ううむ。
Uncle Meat (1969)

Ray Collins (vo) Jimmy Carl Black (dr) Roy Estrada (b) Don Preston (electric piano) Billy Mundi (dr) Bunk Gardner (winds) Ian Underwood (various) Arthur Tripp (batterie) Motorhead Sherwood (tenor saxophone, tambourine)
Ruth Komanoff (marimba, vibes)
1969年、このときFZ御大は29歳。しかし、この時点で御大は完璧なFZ世界を確立してしまいました。いやはや、このアルバムの異様な完成度の高さ、何なんでしょう。
既に演奏形態はマザーズ初期の枠を大きく逸脱しており、クラリネットを中心とした管楽器やハープシコードのサウンドが全編を支配し、さらには1曲目からいきなりルース・ロマノフ(後のルース・アンダーウッド)のマリンバが響き渡ります。タイトル曲「Uncle Meat」を皮切りに「Dog Breath」「Pound For A Brown」「Mr.Green Genes」「Cruisin' For Burgers」そしてとどめの「King Kong」と、FZ活動の最後期まで演奏される名曲がずらりと並べられ、しかも全ての曲が密接に絡み合いながら音の万華鏡を構成していく。圧巻の一言に尽きます。
印象としては、フーガもしくは変奏曲といった所。つまり、このアルバムはトータル・アルバムどころか「全部で1曲」と言ってもいい緊密な構成を持っているわけです。最後のKing Kong組曲は、初出のこの時点で既にスタジオテイクとライブのコラージュになっています。ライブとスタジオ録音を素材として同等に扱いアルバムを構成する手法も、この作品が嚆矢なのではないでしょうか。何十回聴いても飽きることがない、御大の最高傑作のひとつ(御大の最高傑作は絶対一つではないので)と断言できます。
一つだけ苦言を。筆者が所有の1987年版CD2枚組には、空き時間を埋めるために映画「Uncle Meat」のシーンが40分近く挿入されています。これ、完全に余計。何でそんなことする必要があったんでしょうか。こいつのおかげで最後のKing Kongの感動がだいぶ薄れてしまっているではないですか。世の中の評価もほぼ同じみたいですね。
Hot Rats (1969)

Ian Underwood (p, org, clarinet, sax) Ron Selico (dr) Shuggy Otis (b) Captain Beefheart (vo) Don "Sugar Cane" Harris (vln) John Guerin (dr) Max Bennet (b) Paul Humphrey (dr) Jean-Luc Ponty (vln)
現在に至るまで非常に評判のいい作品です。英国で「クリムゾン・キングの宮殿」を抑えてアルバムチャート第一位になったというのも話題性十分ですが、特にCD化に伴う大幅なリミックスは多くのファンにとって衝撃的であったようです(私はオリジナルLPの内容を知らないので…)。曲的にも名曲「Peaches En Regaia」などいわゆる「名盤」の要素をしっかり持っています。また、カンタベリーファンからまさに絶大なる支持を受けているアルバムでもあります。
それを承知で言いますが、このアルバムは筆者は少々冗長だと思っています。その最大の理由は、FZ自身の長すぎるギター・ソロにあります。いわゆる一発もので5分以上もソロを弾き続けるには、残念ながらこの頃のFZは技量的に未熟だと言わざるを得ません(その点シュガー・ケーン・ハリスは凄い。本当に聴かせます)。※2020年追記。最近になってやっとFZ御大のギターが少し解ってきた気がするのですが、それでもWillieのソロは長すぎる…多分、一生理解できない気がします。
昔こういう趣旨のことをNiftyのフォーラムで書いて、カンタベリーファンの方々にかなりの集中砲火を受けたことがありますが…カンタベリーファンに大人気なのね、このアルバム。
ということで、一番強烈なのは何といっても②「Willie The Pimp」のキャプテン・ビーフハートのヴォーカル。この一曲だけでも十分に聴く価値があります(長いギターソロには耐えることを前提として)
Burnt Weeny Sandwich (1969)

Lowell George(g,vo) Roy Estrada(b,vo) Don Preston(kb) Ian Underwood(kb,clarinet,p) Buzz Gardner(tp) Bunk Gardner (woodwinds) Motorhead Sherwood(sax,vo) Jimmy Carl Black (dr, tp, vo) Art Tripp(dr, per) Sugar Cane Harris(vln)
本作は、各種の事故やトラブルでマザーズ継続不可能となった御大が、それまでのツアーやスタジオ録音から編集してリリースしたとされています(次作も同様)。まあしかし、活動の最初期から録音魔だった御大、既にこの時点で膨大な作品のストックがあったようで、その気になれば何枚でもリリースできたでしょう。アルバム枚数に関しては、むしろ契約の制約の方が大きかったのでしょうね。
で、このアルバム。自分の印象としては「ミニUncle Meat」と言った風情です。Holiday In BerlinとLittle House I Used To Live Inという二つの大曲が柱となって、アルバムの最初と最後にドゥーワップの曲を配し、チェンバー・ミュージック系の小品で脇を固める。うーん、この構成の妙。とても残り物編集盤とは思えません。長大なUncle Meatよりむしろ聴き易いかもしれないし。
当然、聴きどころは18分の大曲Little House、それも前半、それもシュガーケーンのヴァイオリン・ソロであるのは論を待たないのですが、いやいやどうして他の曲も実に捨てがたい。Holidayは御大らしい、叙情的でかつ前向きなメロディが素晴らしいですし、WPLJなんかも中毒性が高い。もちろん現代音楽フリークとしては、Igor's BoogieなんかのFZ節も実に楽しい。
地味なんで、FZ~マザーズファンも聴く回数がそんなにないアルバムかもしれませんが、2年に1回くらいは聴いて上げて下さい。何度聴いても飽きない、実に御大らしい作品です。
Weasels Ripped My Flesh (1970)

Ian Underwood (sax) Bunk Gardner (sax) Motorhead Sherwood (sax) Buzz Gardner (tp) Roy Estrada (b) Jimmy Carl Black (dr)
Arthur Tripp (dr) Don Preston (p, org) Don "Sugar Cane" Harris (vln) Lowell George (g, vo)
事実上第1期マザーズの最終作で、前作と同様に第1期マザーズの寄せ集めに近い作品なのですが、こちらの方が概して評価が高いようです。初期マザーズの代表作として、この作品を挙げる人も大変多いです。
本作は「アヴァンギャルド・ライブ・バンド」としてのマザーズの形がより前面に出されています。執拗に繰り出される5拍子・7拍子のシーケンス、あるいはFZ本人が解説を入れながら展開されるややお勉強的なポリリズム、あるいは集団即興、そして極めつけは、単音アナログ・ノイズのみで構成されたラストの表題曲。
上記の要素が好きになれるかどうかで、本作の評価は決まります。で、実を言うと筆者は得意ではない。だってそういうのは、実際にライブで目の前で観て初めて意味がありますからねえ。録音されたものを聴いても、面白さがあんまりよく解らないのですよ。
即興演奏部分にしても、メンバー個々人の技量差が結構出てしまっていてダレます。こういうのはヘンリー・カウあたりの百戦錬磨のメンバーでやらないと、作品として残せるレベルにならないのでしょうね。あるいはセシル・テイラーとか。
と言うことで、筆者の興味は「きちんと構築された楽曲群」に向かいます。キルユアママ→オーノー→オレンジカウンティのメドレーは、本作で最も安心して聴ける部分ですが、それ以上に「森のひきがえる」もしくは(よく聴くと超高速のUncle Meatテーマがこっそり演奏されている)Dwarf Nebula辺りが大好き。個人的に実に悔しいことに、これらの曲はすぐにライブ集団即興やコラージュに取って代られてしまう。もったいない!!
そして、筆者が最も好きな曲はThe Eric Dolphy Memorial Barbecueです。ただしこの曲は当時のマザーズには相当キツかったようで、余りちゃんとした演奏になっていません。この曲の正確な再現は20年後の「ザ・ベスト・バンド」での演奏までほぼおあずけになります。
Chunga's Revenge (1970)

Ian Underwood (org) Max Bennet (b) Aynsley Dunbar (dr) Jeff Simmons (b, vo) George Duke (org) Mark Volman(Vo) Howard Kaylan(Vo) John Guerin (dr) Don "Sugar Cane" Harris (organ)
1曲目「トランシルヴァニア・ブギー」の重厚なドラムが流れてきた瞬間、ゾクゾクします。ジミー・カール・ブラックのファンには大変申し訳ないですけど、ここでのエインズレイ・ダンバーのドラミングはやはりすごいというか別格。新生マザーズの幕開けにふさわしい、そんな感触でしょうか。
収録曲も表題曲やTell Me You Love Me、あるいはSharleenaなど、あとあとのレパートリーに続く重要なものが多い。ジャケットのFZの顔もこれ以上ないような独創的な表情でいうことなし。オススメアルバム…と誰もが思うでしょ。そうじゃないんですよ。私はこのアルバムを大した回数聴いていません。多分10回も聴いてないんじゃないかと思う。
その理由。今頃、FZ御大を聴き始めて20年以上を経てからようやく気付いたその理由は、「個人的にヒゲデブ(フロ&エディ)が嫌い」。これに尽きます。
フロ&エディ、上手いと思わないんだよね。基本的にがなっているだけ。ファルセットも綺麗に響かないし、ハーモニーで聴かせるわけでもない。彼らの真骨頂は歌ではなくて、要するにボードヴィル調の即興演劇部分なんです。だからステージングは実に楽しかったろうし、それを目当てに当時のファンはライブに足を運んでいたのでしょうが、ネイティブでない日本人にとっては(対訳を介してみても)全然面白くない。
ま、というのが本作にあまりのめり込めない理由でした。前述の通り、リズム体は強力だし良い曲が多いし、客観的な視点では十分お奨めですよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
