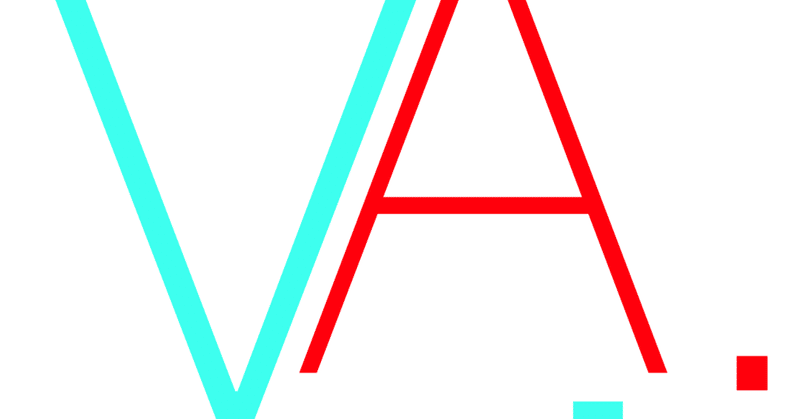
(連載)「ボカロアーカイブス一五一八」第0話 “ネット音楽の中のボカロ”
初めましての方は初めまして。
田沼ハルと申します。
今回から2015年〜2018年頃のニコニコ動画ボカロシーンを振り返り、その歴史や当時の雰囲気を紹介する連載を始めて行きたいと思います。
が、その前に。
今回は第0話という事で、私が筆を取るに至った経緯、本連載のねらいを説明させて頂きます。
part1.時代は何を求めた?
さて、現代日本音楽シーンにおけるインターネット発アーティストの大躍進は、皆さんもご存知の通りかと思います。
中でも元ボカロPという出自を持つ米津玄師氏やYOASOBIのAyase氏などは、もはや時代を代表する
と言っても差し支えないレベルの存在感を放っています。
また昨年の紅白歌合戦にて、前述の二人と同一の出自を持つキタニタツヤ氏が出演した事も記憶に新しいですが、私は今後このような流れがしばらく続き、インターネット発のアーティストがより存在感を増していくと考えています。
その理由を説明する上で重要な要素が、
若者文化とポピュラー音楽の関係です。
ヒットチャートと若者文化はいつの時代も太いパイプで繋がれ、一心同体の存在であり続けています。
そしてその歴史は常に「停滞と突破」の連続でもありました。
かつて冷戦下の鬱屈した世界で、愛と平和と快楽を求めた戦後生まれのヒッピー達。
その中で育まれたロックミュージック、その流れを破壊するべく放たれたパンクロック。
一方若き黒人達は自分たちの置かれた境遇への怒り、そして自由と誇りを胸に、ヒップホップという文化を創りました。
日本において例を挙げると、80年代以降のバンドブームは、旧来の音楽シーンからの脱皮を図る若者に支持を受けたムーブメントでした。
part2.時代はネット音楽を求めた
時代は移り、現代の日本。
ここでも若者文化における「停滞と突破」が発生しました。
つまり、長い間若者文化を発信するスピーカー的立場であったテレビが衰退し、SNSが大きく躍進した出来事です。
これによりSNSで手軽に自己発信する事が可能になり、動画サイトや各種サブスクリプションサービスを通じ、インターネット上で好きなカルチャーを共有し合うというのが当たり前の世界となった訳です。
そんな新しい価値観を持った若者達に支持されるに足る「新しい音楽」とは何か。
そう、ここでボカロを含む
「※インターネット発の音楽」に白羽の矢が立ったのです。
{※ここで言うインターネット発の音楽とは、動画投稿サイトにて発信される音楽(ボカロ曲、歌ってみた、その他オリジナル曲を含む)を指します。以下、「ネット音楽」。}
2006年のニコニコ動画サービス開始以来、長らくサブカルチャー、オタクカルチャーとしての立ち位置に居座っていたネット音楽。
近年の若者文化におけるSNSの全盛は情報の伝達速度を劇的に速めた為、インターネット上での拡散性に優れるこれらのネット音楽がメインストリームに躍り出ることは、むしろ必然的であったと言えます。
そして今後の若者文化をリスナー、そして表現者として担っていくであろう、所謂Z世代以降の若年層。
彼らはこういったネット音楽がヒットチャートを賑わしている現代を生きている訳ですから、冒頭で述べた先人達に倣いこの文化を更に加速、進化させていくでしょう。
part3.黎明
2024年現在、既にAdo氏を筆頭に、またボカロ界では原口佐輔氏やいよわ氏など、Z世代以降のアーティストが、日々ネット音楽の裾野を広げる活躍を見せています。
ただ、先に述べた「停滞と突破」のルールに従えば、10年以上先の音楽シーンがどうなっているかは正直想像できません。
ネット発の音楽は今後も発展を続けるでしょうが、ボカロカルチャー、ニコニコ動画を中心としたムーブメントという時代では無くなっているかもしれません。
しかし、間違いなくネット音楽の成り立ちに多大な影響を及ぼしたのは「ボカロとニコニコ動画」です。
ロックンロールに対してのブルースなのです。(?)
とにかくボカロとニコニコ動画は、今後ネット音楽の歴史を語る上で絶対避けられない存在になっています。
part4.ボカロアーカイブス
さて、長々と語ってまいりましたが、一度ここらで肩の力を抜かせて頂きまして。
改めましてこんにちは。或いはこんばんは。
わたくし、田沼ハルと申します。10年来(2014年末〜)のボカロリスナーであり、貴重な青春をボカロに費やしてまいりました。
人間、若い時に聞いた音楽を死ぬまで聴くことになるとよく言いますよね。
それに従うとおそらく私は60年後、老人ホームでこんにちは谷田さんのアルバムを聴きまくる異常独身後期高齢者になっているはずです。こわ。
ここまで「ネット音楽が今後も発展を続けるだろう」という話をしてきました。
長く続く文化はいずれ保存(アーカイブ)され、歴史として後世に残ります。
21世紀はネット音楽の時代になります。私が老人ホームでボカロを聴く頃になれば、既にネット音楽の歴史は通史として纏められていることでしょう。
ネット音楽評論家や様子のおかしいマニアが、2010年代のボカロコンピアルバムを収集し、その歴史を考察するような時代が来るのです。馬鹿らしい話に聞こえますが多分来ます。
私はそんな時代に向け、そんな人々に向け、今のうちに残しておきたいのです。
後世のネット音楽シーンに多大な影響を及ぼしたニコニコ動画ボカロシーンの歴史、当時の記憶を。
という訳で、題して「ボカロアーカイブス」。
当時のボカロシーン、その周辺で起こった出来事やリスナーの反応、空気感。そしてその時代の代表曲などを出来る範囲で紹介していきたいと思います。
ただ先ほど述べたように、私がボカロシーンをしっかり追うようになったのは2014年末頃からです。その後2018年後半頃よりボカロから少し離れていましたので、当時のボカロリスナーの反応を含め、まず今回の連載で紹介出来るのは2015年初頭〜2018年初頭までの時期になります事をお許しください。
理想を言えば初音ミク登場の2007年から現在まで、ぶっ通しで通史を語るのが理想なんですが、それはまたしっかりと情報を整理した上で考察するとして。
早速次回より2015年のボカロシーンを振り返って参ります。
n-buna氏(現在ヨルシカのメンバーとして活動)やorangestar氏を筆頭に、さまざまなボカロPが精力的に活動していた、魅力あふれるボカロの2015年。
拙い文章力ではありますが、皆さんが当時のボカロシーンの空気感に触れ、少しでも楽しんで読んでいただければ嬉しいです。
最後になりますが、次回以降の記事を読んで頂く際の注意事項を以下に記させて頂きます。
お読み頂く前にひと通り目を通して頂けると幸いです。
当連載における注意事項
当連載では、読者の方々に対し当時のボカロシーンの雰囲気を楽しく振り返って見て頂けるよう、ネガティブな表現は極力避けてお届けします。
ただし、当時ボカロシーンで実際に起こった出来事に関しては出来るだけ正確にお伝えする事も重要であると考えます。
執筆に置ける具体的な方針、当連載をお読み頂く上での注意点は以下の通りです。
①当時ボカロシーンに起こった具体的な出来事について紹介する際は、客観的な視点から事実に基づいた解説を心掛けます。その過程で特定の個人、クリエイター様を中傷する様な意図はいかなる場合もございません。
その上で、「特定の個人、クリエイター様に対する中傷であると受け止められかねない表現」を避けるため、細心の注意を払います。
②当時のボカロリスナーの反応やシーンの空気感を紹介する際は、動画コメントやSNS、ネット上の書き込みなどを参考にしつつ、私自身の見解や感想等、主観的な表現を用いる場面がございます。
そのような場合でも、①で述べたような個人を中傷する様な表現は使用しないよう注意致します。
③当時のボカロシーンを解説する上で、クリエイター様同士の人間トラブル、或いは金銭トラブル等、
個人間の問題、トラブルに踏み込んだ話題は一切取り上げません。
その他、記事にて取り上げた場合、クリエイター様側に不利益を生じさせる恐れのある事象についても同様です。
④当連載にて明らかに事実と異なる、または他者に不利益が生じる可能性のある解説(③の様な事例含む)を行っている箇所がありましたら、記事内コメント欄、筆者のX等を通じてご指摘頂けますと幸いです。早急に確認を行い、訂正致します。
⑤その他感想やご意見、ご質問等ございましたら、
お気軽に記事内コメント欄、筆者のXまでお寄せ下さい。
⑥当注意事項について、必要に応じて追記又は変更を行う場合がございます。予めご了承下さい。
-
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
