
【変化】中学校→高専での定期試験どう変わる? 7選
みなさん こんにちは!🙇
高専プロモーションチャンネル
【たにに】でございます。
今回は
中学校から高専での定期試験がどう変わるか
をまとめてご紹介させていただきます⏰
それでは早速
いってみましょう💨💨
YouTubeチャンネルでも
動画で説明していますので是非ご覧ください!
①年間テスト回数 科目数が変わります

中学校の時は中間5科目・期末9科目で年に5~6回
高専は中間も期末 10科目前後で年に4回

ケース1:明石高専 1年生 8科目
ケース2:徳山高専 1年生 11科目
ケース3:茨城高専 1年生 9科目
ケース4:
たにに 低学年 8-12科目
高学年 13-15科目
前期と後期で試験で行われる科目数が±2,3科目されることもあります。
なぜなら、半期(前期・後期)しかない科目もあるからです❗️

まとめると
中学は中間5科目 期末9科目 固定 年に5-6回
高専は毎回変動があるが平均して年に4回のテスト
少なくて8-12科目 多くて13-15科目です
②欠点ボーダーが設けられます

60点を切ると(俗にいうと欠点)になります😨

一部の高専では1-3年・低学年では
欠点ボーダーが50点の高専もあるようです👀
ここでよくある間違いなのですが
1回の試験で60点を切っても
単位や進級に問題はありません。

もう一度言います❗️
1回の試験で60点を切っても単位や進級に問題はありません。
結局 最終評価が60以上であれば単位は出ます。

しかし、皆さんには60切るかどうか 単位が出るかどうか
という低レベルな悩みに悩んでいただきたくはありません❗️
最終評価で80点を超えて優評価がもらえるかどうか。
こちらを前提として努力をしていただきたいと思います。
現在 1日20件 お申しこみをいただいている 新高専1年生
先取り学習差別化計画パックはその人たちへのプレゼントです。

概要欄・コメント欄からどうぞ👍
③過去問が通用する科目が出てきます
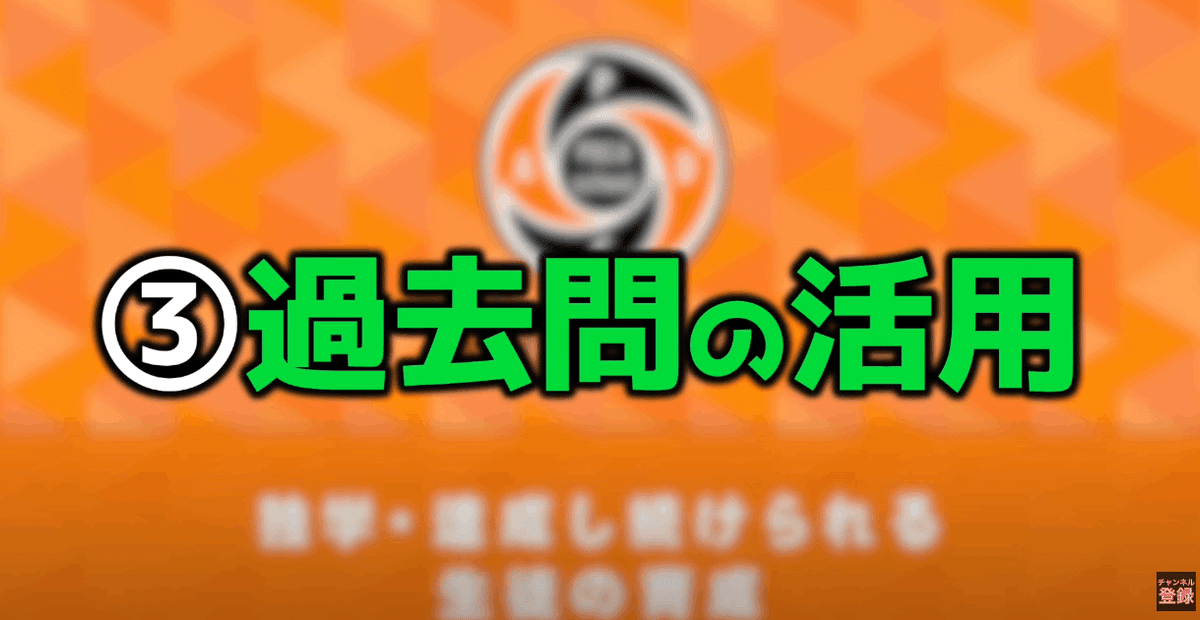
中学生で定期試験の過去問を使っている人は
半分もいないと思います。
私の塾では中学生の
定期試験の過去問が大量にストックされているので🗒
よく直前対策で4〜5通り
入念に行ってもらい 80-90点を得点していただいています。
高専に入ると 過去問がございます❗️
全体の科目の3~4割は使えるイメージです👍
高専や科によってピンキリとは思いますが
この過去問の使い方はすごく気をつけないといけません。

ある程度 試験の範囲は 教科書・ワークなどの公式・定理・概念は
自分で理解・取り組みをすべきでしょう。
過去問を使うのはその後の方がいいです。
なぜかというと、力がつかないからです😰
過去問だけを使って点数を取っても意味がないですし
そもそもそれで点数が取れる科目も少ないです❗️

最低限・本当に最低限 この科目だけはと言うのは
英語・数学・物理・専門科目です❗️
進学の場合、ペーパー試験で問われる科目だからです😊
最低でも英語・数学・物理・専門科目は
試験の範囲は 教科書・ワークなどの公式・定理・概念は
丸暗記せず理解・取り組みをすべきでしょう👍
どうしてこうなるのか、を徹底すべきです。

点取りのための過去問を使うのはその後❗️
長期的に自分の力を養いたい人はこれを徹底してください💪
目先の楽にとりついてしまって
公式やルール・構文をよくわからず丸暗記してしまうと
高専3,4,5年生で絶対にツケを払う必要が出ます。
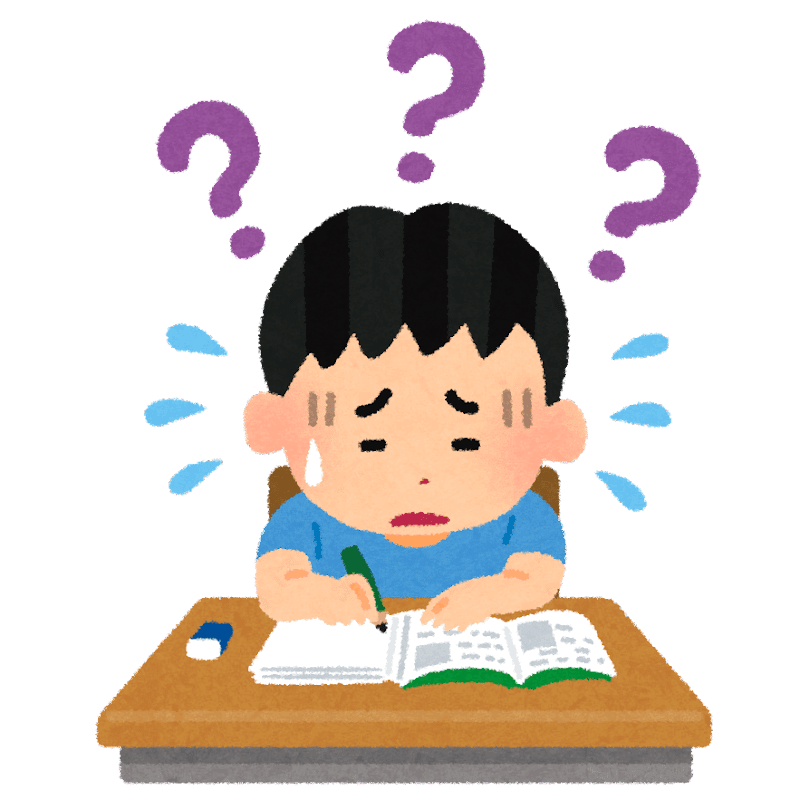
それを最大限防ぐように
現在 1日20件 お申しこみをいただいている 新高専1年生
先取り学習差別化計画パックを募集しており
それらを目指す人たちへのプレゼントです🎁

概要欄・コメント欄からどうぞ。
④より人との緊密な関係が成績を上げます

中学の時は、対策ワーク・プリント・YouTube動画
参考になる教材がたくさんありましたね

試験内容も”お決まり”な問題が多いです
当たり前ですね、教科書の内容・試験内容は
全国統一ですから❗️
高専では科目ではなく先生ごとの対策になります。
だから高専の学習塾は発展していません🥺
高専の数学ならこの対策をしておけばいい
と言うのがないのです🥺
先生によって教科書のB問題は出すのか?
教科書のどのレベルまで出すのか?
ワークからは出すのか?
過去問は使えるのか?
別途授業中に配布されるプリントから出るのか?
こう言うことを先輩・先生・友達から
よくよく良く聞いて対策すると効率的です。

部活・クラスメイトとの人間関係を大切にしてください❗️

友達が多く持たなくていいです、信頼できる人や
気軽に話しかけられる人を2~3人🗣️
2~3人いればそのテストに関する情報網に
詳しい人物の誰かにはつながっているでしょう😊
そこから先生のテストの癖・対策方法を聞くといいでしょう。
一番手っ取り早いのが
同じ学科の部活の先輩ですね。
いわば自分が今から歩む道を直近で
歩んだ生き写しのような存在なので
ゴロニャーンして上手く煽てて
先輩として立場を立てて
たくさんたくさん聞いてくださいw
⑤試験時間

中学の時は基本 試験時間は50分でしたね

高専では専門科目・数学・物理などで
試験時間が80分の科目が出現します。
80分です。1時間20分。
より多くの対策・勉強時間を必要とします。

専門科目・数学・物理であることが多いです。
⑥持ち込み可能物品 持ち込み科目が2〜3年生くらいから

関数電卓など電卓が持ち込み可能な試験が出てきます。
計算能力ではなく、公式や概念を使うテストをしたいからですね。

物理や専門で良く出てきました😊
数学で持ち込みokなのはあまり聞きません。
持ち込み資料が持ち込み可能というのが中学年〜高学年にかけて出てきます。
カンニングし放題!?と思われるかも知れません。カンニングし放題です。
それでも解きごたえのある試験ですw
あらかじめ自分が 決められた用紙や媒体に🗒
テスト範囲の内容をまとめてそれを持ち込むことができるんです👍👍
それで試験中それらを見ることができます❗️
しかし、あまりそれらの資料を見ることは少ないです。
資料をまとめる過程で、頭を使いますから、整理されて理解するんですね。
これは、大学などでは珍しくない試験形態で
大学に編入したら同じ用なテストを受けることがあるでしょう。
⑦逆に同じことは?


(1)カンニングしたら全科目0点 +停学
(2)試験期間は1週間前(2週間前からの高専もある) 部活原則禁止
(3)きつい
まとめ
いかがでしょうか?
今回は
中学校から高専での定期試験がどう変わるか
についてお伝えしました🎈🎈
これから高専に入学される方
高専に興味がある方
にとても参考になる動画🎬になっています❗️❗️
是非ご覧ください👀
閲覧ありがとうございます!
それではまた。
【高専チャンネル【公式】 高専入試・受験・大学編入】
【高専に関するメディア,まとめとリンク】
↑クリックすると色々なところへ行けます↑
【変化】中学校→高専での定期試験どう変わる? 7選

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
