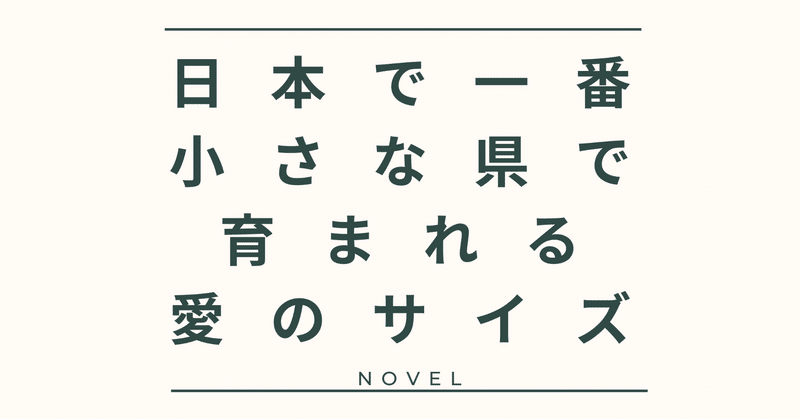
日本で一番小さな県で育まれる愛のサイズ【五話】【創作大賞用】
讃岐乃珈琲亭にはマスターと春子と幸助の他にも数名のスタッフが働いている。日本が好きで日本で働くことを夢見て来日した台湾出身の葉さん、マスターの珈琲に感動して勢いだけでここまできた元観光客でカナダ人のマシュー、朝はここで働いて昼からは近くのホテルで働いている明美さんと孝之くん、そして春子の8つ年の離れた妹、陽菜(ひな)。
陽菜は最年少でありながら讃岐乃珈琲亭のムードメーカーだ。いつも誰かと何かを楽しそうに話している。口を動かしながらも作業はてきぱきしているし、お客さんへの対応も明るい。事あるごとに写真や動画を撮っていて、マスターの許可を得てSNSに店の様子を投稿したりもしている。
そんな陽菜が鯉がまだ空を泳いでいる時に思い出したように言った。
「そういえば幸助さんの歓迎会ってしてないよね。歓迎会しようよ、マスター、姉ちゃん」
マスターは顎を触る。
「そうだな、忙しくてすっかり忘れてたわい。じゃあいつもの居酒屋の予約頼む春子」
春子は面倒くさげに
「また私が予約するの。仕方ないわね。あっ…」
そこで何かを思い出したようだ。
「そういえば幸助の誕生日って五月だったはずだから誕生日会も兼ねちゃおっか」
「いいね。姉ちゃんたまには良い事言うね。そうしよう、じゃあその時用の服買いにいかなきゃ」
「なんで歓迎会に新しい服が必要なのよ、それにこの前一緒に買ったじゃない」
「あれは、あれ。これはこれでしょ。姉ちゃんもせっかくだから久しぶりに服買いなよ」
春子はその時は適当に返事をしたが、幸助の歓迎会兼誕生会に現れた春子の服は全てが新調されていて、それをみて陽菜は姉ちゃんって単純だなあ、と思ったのである。
◇
讃岐乃珈琲亭では歓送迎会などがある度に五軒先にある居酒屋「吉田屋」を利用する。香川県の名物の一つである山賊が食べるような大きな骨付き鳥が美味しい居酒屋である。それ意外の食べものも総じて美味しいし、何より店員さんの活気が店中に広がっているので、居心地がよく、ついつい皆普段よりも呑みすぎてしまう。
この日も例外なく盛り上がった。その中で特に春子の機嫌が良さそうだった。飲むペースが速い。他の人がまだニ杯目なのに春子だけは五杯目のお代わりを注文しようとしている。春子も自身でペースが速いのは気づいていたが止められない。
幸助とこうやってお酒を一緒に飲むのは初めてだった。
幸助は少しだけ遅れてきて陽菜の隣が空いていたのに迷うことなくわざわざ春子の隣に座り、東京にいた時の話を沢山春子にした。その話は時折同じ日本だとは思えないものもあった。都会は夢も闇も同時に混在している場所なのだと思った。
そんな中で最初は一人だったはずなのに気づけば沢山の仲間に囲まれていたのは幸助らしいなとも思った。
たぶん彼女もいたはずなのにそういう話は一切しないのはなんなのだろうな、とも思った。
そんなことを考えている春子にさっきまで東京のことを話していた幸助が
「今日もお洒落だね。俺東京に行っても全くファッションセンスは向上しなかったからさ、今度服買いに行くの春子についてきてほしい」
と言った。
春子は驚いてとりあえずグラスの中のお酒を体に流しこんだ。それが幸助が飲んでいたものと間違えてしまっていたこともすぐには気づかない程に動揺していた。
(え、何言ってんの。今日もって言った?普段なんてそんなに服意識してないのに?私の服が全部新しいって気づいてくれたから、気を使ってそうやって言ってくれたの?お世辞でも嬉しいけど。あと幸助こそ今でも十分お洒落なんだけど。それに私今もしかしてデートに誘われてるの?そんなわけないよね?)
そんなことを考えていると幸助が続けて話し出した。
「けど二人で出かけるのはまずいよな。春子には洋一っていう素敵な彼氏がいるもんな」
「まあね、だから陽菜とかマシューと一緒に行こうよ」
「おう、そだね。また皆で休み合わせて行こう。近くでもいいから旅行にも行きたいな」
幸助がほんの一瞬だけ悲しそうな顔をしたのは見なかったことにした。
そこで陽菜が話に割り込んできた。
「えー私も旅行行きたい。次は旅行行こう。だからマスターシフト減らして」
マスターは子供をあやすかのように
「勝手なことばっかり言うな」
と陽菜をなだめた。
そのやりとりに一同が笑いに包まれた。
そんな中、春子は顔の火照りと酔いを醒ますためにトイレに向かった。
トイレに座るとぐらんと世界が廻った。やばい飲みすぎたと思った。
こんな時助けにきてくれるのが幸助だったらどうなっていたのだろうと春子は思う。
トイレの扉を叩く音がする。
その向こうから幸助の声で「春子、大丈夫か」という音がする。
春子は何も声には出さず、なんであの時は来てくれなかったのよと心の奥でつぶやいた。
扉の厚さはせいぜい五センチ。そんな五センチで世界は簡単に二つに分断される。
◇
春子と幸助は中学も同じ中学校だった。四クラスあったから同じクラスにはなれないと思っていたけど、一年の時は同じクラスだった。夏まではあっと言う間に過ぎていった。
事件が起きたのは秋の球技大会が終わった十月だ。
幸助はその容姿と明るさ、運動神経の良さで周りの女の子のアイドル的存在になっていった。そして女の子の間で幸助くんは皆のものだから誰も手を出してはならず、という謎の掟が出来上がった。そして何故か皆その掟を従順に守った。
同じクラスに神田という女がいた。神田は誰かが困っているとほっとけないんだよね、とよく言っていた。
そんな神田が球技大会が終わった二日後に急に春子にこう言ってきたのだ。
「春子のために幸助に春子の気持ち伝えてあげたよ。春子はどの女子たちよりも長く深く幸助のことを好きだって」
春子の表情が青ざめていくのにも気が付かずに神田は喋り続けた。
「そしたら幸助なんて言ったと思う。春子とはそんな関係じゃないからって言ったのよ。ひどいよね」
春子はこの日初めて学校を早退した。涙を止めようと思うのにどうしても止まらなかったからだ。こんな姿を幸助にだけは見られたくなかったからでもある。
通学路の河川敷の橋の下、影で暗くなってるところで春子は泣き続けた。色んな感情が押し寄せてきた。
怒り
勝手にそんな事を伝えた神田が信じられなかった。神田だって幸助のこと好きなのは見てたらわかる。なのに自分の気持ちじゃなくて、なんで私が幸助のことを好きだってことを伝えたんだ。あれは絶対善意じゃない、確信的な悪意だ。それなのに本人は善意でしてあげたんだと信じている。卑怯だ。
虚しさ
小学生の頃、恐れていたのはこれだ。自分の気持ちを誰かに勝手にバラされる。だから私は必死で幸助への気持ちを隠していたのに。神田のような対して仲の良い友達じゃない奴にまで自分の気持ちが筒抜けだったことも情けない。きっと幸助本人にだってずっと前から気づかれていたんだ。
悲しさ
そして幸助は私をそういう目で見ていないという事実。薄々分かってはいたけど、こうもはっきりと本人の口から(神田越しではあるが)伝えられたら、もう認めるしかない。私の初恋は気持ちを直接伝えることもできずに終わったんだ。なんて呆気ない。どうしてこうなる前に自分の口で想いを伝えなかったんだ。弱虫だ、私。このまま川に飛び込んでしまいたいとも思ってしまっている。弱い虫だ。虫なわたしのことなんて誰が好きになってくれるっつうんだよ。
橋の下で大声で泣いているはずなのに泣き声すらもトラックの騒音に掻き消される。
春子の存在が世界から消されようとしている。
◇
その日が絶望のピークだと思ったのに、追い討ちをかけるようなことが春子を取り巻く。翌日には春子が幸助に告白したという噂が学校中に広がっていた。
自分だけ抜け駆けだなんて引くわ、とか、そうまでして振られてるのだっさ、とか春子に聞こえるように言ってくる元友達たち。なにも言わず関わらないことを決めた元友達たち。一晩でこんなに人の態度って変わるのか、と春子はこのとき始めて人間を怖いと思った。
だけど学校には行き続けた。幸助がいたからだ。幸助にだけは心配をかけたくなくて、平気な顔して授業を受けた。涙を抑えきれなくならないように昼休みはずっと泣いた。誰にも見られないように聞こえないように声を殺して泣き続けて、そしてまた幸助の待つクラスに戻った。
心のどこかで、幸助気づいて、助けてと願い続けながら。
ある日、いつものように学校の隅にある誰も使わないトイレで泣いていたらトイレの扉をノックする音が聞こえてきた。
春子に嫌味を言ってきた奴らが来たのかもしれない、神田が謝りに来たのかもしれないと春子は一瞬思ったが、幸助が気づいて来てくれたのだと願った。
そしたら男の子の声で
「市川さん、そのままで良いから聞いてほしい」
と聞こえてきた。
その声の主は続けて
「俺は市川さんがいつも泣いているのが嫌だ。いや泣いているのが嫌なんじゃないな。ひとりでそうやって抱え込んでるのが嫌だ。いつも平気な顔してクラスに戻ってくるよね。けどよく見たら全然平気そうじゃない。じゃあ俺になにができるのかって、それは今はわからないけど、もうひとりでそうやって泣くのはやめてほしい」
春子はトイレの扉を開ける。
そこに立っていたのは幸助、ではなくて、幸助の友達の洋一だった。
洋一は春子と同じくらい涙で顔をくしゃくしゃにしている。
「こんな時になにを言っているんだって思うだろうけど、俺は市川さんのことが大好きです。だからいま市川さんが背負っているものを俺も一緒に背負いたい。そして図々しいけど市川さんの彼氏になりたいって本気で思ってる」
春子はいったい今何を言われているのか理解するのに時間がかかった。それでも洋一の真剣で誠実な態度にちゃんと向き合わないといけないことは理解できた。
「わたしは噂になっているとおり、幸助のことがまだ好きなの。だから、ごめんなさい。けどめちゃくちゃ嬉しい。ありがとう」
洋一は悲しい顔をしていたけど、すぐに笑顔を作り
「そうだよな。けど市川さんのこの状況を解決する手助けくらいはさせてもらうから」
と言った。
その言葉通り洋一はどうやったのかわからないけど春子が幸助に告白をしたというのが誤解だったんだと学校中の皆に広めてくれた。
そしたら元友達はまた友達になった。
友達は「噂をまにうけちゃって本当にごめんね」と配られてくるプリント用紙より軽い感じで謝ってきた。
許したくなかったけど、もう孤独はいやだったから許した。
そしてその次の年の球技大会のあと再度告白してきてくれた洋一と春子は付き合うことになった。
そしてその関係は今も続いている。
幸助とはそんな事件が起こっても普通に会話はしていたけど、なんとなく距離ができた。違う高校になってからは益々疎遠になっていった。
それでも時折春子はあの時トイレの扉を叩いてくれたのが幸助だったならどうなっていたのだろうかと考えてしまうのだ。
だからだろうか。洋一がプロポーズをしそうな雰囲気を醸し出すと春子はその状況を壊そうとしてしまっている。
幸せは頻繁に感じる。それなのに、孤独じゃないのか、と誰かに聞かれた時に即答で、はい、とは言えない。
孤独じゃないってなんなんだろう。孤独じゃないって心の底から思えた時の幸せってどんな感じなんだろう。
◇
幸助の歓迎会および誕生日会の翌日、春子はいつも通り幸助に、おはようと言ってきたから、幸助もおはようと返した。
やっぱり酔っていて覚えてないのかなと幸助は思った。
昨日、春子がトイレに向かう足取りが覚束なかったから心配になって幸助もトイレに向かった。幸助の大丈夫かの問いに春子は答えず、その代わりにトイレの扉を勢いよく開き、「幸助、やっぱり助けにきてくれたのね」と言いそのまま幸助に抱きついた。
そして「孤独じゃないってこういう瞬間瞬間のことを言うのかな」と幸助に顔を近づけて言ったかと思うとそのまま眠ってしまったのだ。その寝顔はかつて幸助が大好きだった子の面影そのままであった。
(さあ、気持ちを切り替えて仕事に取り組もう)
幸助は自分に鞭を打つように顔面を叩き、日常の業務に取り掛かった。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

