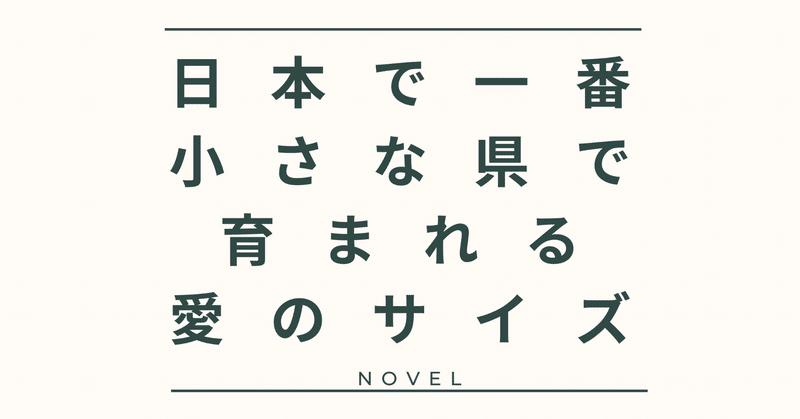
日本で一番小さな県で育まれる愛のサイズ【四話】【創作大賞用】
讃岐乃珈琲亭で幸助が働きだして早くも一か月が経過した。満開だった桜は散ってしまったが、その散った桜の花びらに魔法が込められていたかのように、世界に鮮やかさが宿り出している。空に鯉まで泳ぎ出しているから、地球人意外がこの光景を見たら、きっと魔法の力だと思うのだろうな、と幸助は狭い休憩スペースで妄想している。
讃岐乃珈琲亭は東京に比べれば田舎にあるぶん忙しくないと心の何処かで思っていた幸助だったが、その考えは完全に間違えていた。
讃岐乃珈琲亭は金比羅山の参道口に位置する喫茶店だ。
参拝目当ての観光客が大勢訪れる地域であり、その恩恵を受けて周辺には多くの宿泊施設や土産屋が点在している。
それらの宿泊施設のうち二つの小規模ホテルと三つのゲストハウスと讃岐乃珈琲亭は業務提携していて、各宿泊施設に宿泊したお客さんに讃岐乃珈琲亭での朝食券を渡していた。
マスター曰く春子が主導して地域の商工会や各宿泊施設に営業をかけもぎ取ったものらしい。
春子の奮闘のおかげで、朝の時間帯の讃岐乃珈琲亭は常に満席状態である。
そんな中で経験者である幸助が加わったことで業務が以前より円滑になると珈琲亭で働く同僚たちは期待していたが、実際にはその反対であった。
幸助の接客は柔らかく丁寧なのだが、お客さんと気が合うと長話を初めてしまうのだ。
幸助の接客のモットーは『ひとりひとりのお客様にかけがえのない時間を提供する』だから、ついつい接客時間が長くなってしまう。
この幸助の接客に対する考え方にかつての同僚桔介と度々口論となった。
「幸助、お前がお客さんに丁寧に接するのを攻めているんじゃない。ただ幸助がそうやって接客できるのも、周りがそのぶん効率よく作業してくれているからってことだけは覚えておいてほしいんだ」
と何度も言われた。
そして現在、春子にも同じようなことをよく言われている。幸助も言われるたびにもう少し効率的に仕事しようと考えるのだが、お客さんを目の前にすると、どうしても話に花が咲いてしまうのだ。
幸助の作業効率は期待されていたものほどではなかったが、幸助が淹れる珈琲の味には皆度肝を抜かされた。同じ豆を使っているはずなのに幸助の淹れる珈琲には旨味成分が何杯も入っているのではないかと思われるくらいに美味しかった。
更に凄いのはまだここで働きだして一か月しか経たないのに一度来店されたお客さんの顔を全て覚えており、各客の好みに合わせて豆の配分や珈琲の抽出の仕方、カップのデザインまで変えることができているのだ。これにはマスターも大いに感動した。
「春子と言い幸助と言い、かつてここでサービスを受ける側だった人間がこうやってサービスを提供できる側にまで成長している。時の流れは速いな」
マスターは各々の信念を持ちつつ、懸命に働く幸助たちを温かい眼差しで見守っている。
幸助の珈琲が素晴らしく美味しいように春子が作るお子様ランチは絶品だ。幸助も初めて春子のお子様ランチを食べた時、子供の頃の記憶が一気に蘇ってきた。あの時の味が再現されている。その上で春子にしか生み出せないようなほんのり優しいスパイスが効いている。マスターの味を伝承しつつも自分の個性も織り交ぜていて、幸助は純粋に春子を尊敬した。
「春子、いつの間にこんなに料理上手くなったんだよ。不器用だった印象だったのに、相当努力したんだな」
幸助に真正面から褒められて春子は頬を染めた。
「ここの助けになればと思って調理学校にも通ったし、マスターにも散々怒られながらも料理教えてもらったからね」
春子は幸助が淹れた珈琲を一口飲む。
「幸助だってこんな美味しい珈琲淹れられるだなんて、東京でただ遊んでたわけじゃないのね」
「なんだよそれ。当たり前だろ。珈琲の勉強を懸命にしつつ懸命に遊んでたんだよ」
二人は目を合わせそして笑う。
お子様ランチと珈琲の美味しい香りと春子と幸助の周りを漂う柔らかい空気。
その全てが本格的な夏を待つ空に浮かんでいく。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

