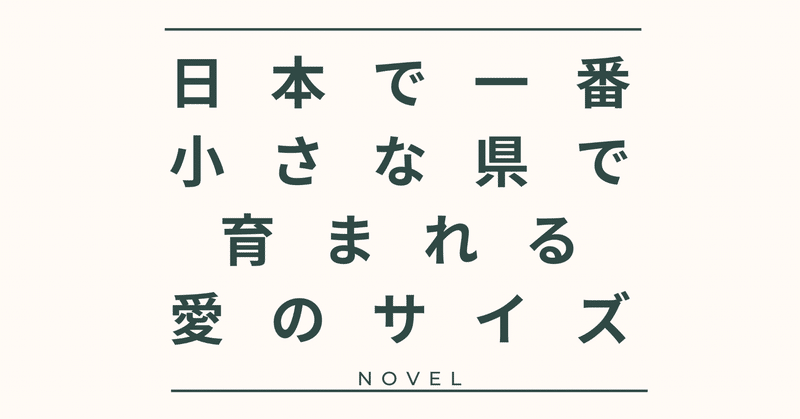
日本で一番小さな県で育まれる愛のサイズ【九話】【創作大賞用】
由紀と桔介の結婚式は七人で父母ヶ浜に旅行に行ってから二ヶ月後の九月の三連休の中日に行われた。
神前式は幸助の祖母が毎日参拝している金比羅の御本宮で両家の親族だけで厳かに進められた。
二人の門出を祝うかのように秋空はこれでもかと快晴で雲一つない。今日はあの日の旅行の時のようにうちわで雲を飛ばす必要も無さそうだ。
神前式の後、孝之が働いている金比羅山道沿いにあるホテルにて、披露宴が開催された。春子や幸助は披露宴から参加し、東京の珈琲屋でお世話になった店長や同僚たちとも久しぶりの再会を果たした。
披露宴のメイン席に座る由紀と桔介は終始幸せ全開なエネルギーを発していて、そんな二人の様子を見ていると普段結婚を意識しないような人たちでさえ、結婚って良いな、と思えるような、幸福感が会場を包み込んでいる。
披露宴は大いに盛り上がったが、その中でも余興は拍手喝采だった。
幸助、マシュー、孝之ら九人の男たちが最近話題のアイドルのダンスで会場を熱狂させたかと思うと、それに負けじと、陽菜のピアノに合わせて春子がプロ顔負けのバラードを熱唱したのだった。
歌っている当の本人である春子が一番号泣していて、その姿も合間って皆涙が止まらなかった。
披露宴の盛り上がりをそのまま引き継ぐようにしてカラオケ屋で開催された三次会でも皆それぞれにその時間を楽しんだ。
春子も笑顔で、この時間がずっと続けばいいのにと思っている様だった。しかし春子は意を決したように少し残っていた林檎サワーを飲み干し幸助の横に移動してきた。
「まだ三次会の途中で申し訳ないんだけど幸助に聞いてほしい話があるんだ」
春子の口調は真剣そのものだったので幸助は快くその申し出を受け入れた。
由紀と桔介に末永くお幸せに、また集まろうね、と挨拶し、春子は幸助を連れて近くの河川敷の橋の下まできた。
そこは春子が中学一年生の時、神田が幸助に春子の気持ちを勝手に伝えて、泣いた、あの時の橋と同じ場所だ。
その場所に春子と幸助は隣り合わせで座った。
最初に口を開いたのは幸助だった。
「なにかあった?」
幸助は春子の目をしっかりと見つめる。
「うん、あった。けどその前に言わせて、あの時わたしがいじめられなくなったのは幸助のおかげだっただね、ありがとう」
父母ヶ浜への旅行をしたあの日の夜。
幸助が寝てしまった後にキャンプファイヤーの前で春子は由紀と桔介と夜が明けかけるまで話込んだ。その日が終わってほしくなくて中々寝れそうになかったからだ。
その時、由紀と桔介が教えてくれた。
中学の時に春子が幸助に告白して振られたという噂が広がった。その噂は幸助の元にも届いていた。幸助はその噂が間違いであることを噂を流している人たち全員に直接伝えて回ったのだ。噂の大元である神田にももちろん伝えた。
幸助が誠実にひとりひとりに伝えたことで噂は間違いだったと皆が認めたのだった。
「ああ、そのことか。いいよ、あの時の俺にできることはあれくらいだったんだから」
幸助は春子から目を晒し橋を見上げた。
「あともしかして洋一をトイレに向かわせたのも幸助だったの?」
幸助は答えるか一瞬だけ躊躇し
「そうだよ」
と答えた。
あの時春子が一人でトイレで泣いていることに真っ先に気づいたのが幸助だった。何故気づけたかといえば、幸助は気がつけばいつも春子を目で追ってしまっていたからだ。今ならこの感情の正体がわかるが当時はなんなのかわからなかった。
そんな時に洋一から春子が好きなんだと告げられた。だから洋一に春子はトイレにいると教えたのだ。
そしてあの時自分が率先して春子のいるところに向かえなかったことを今でも後悔している。
「そうだったんだ。じゃあそれもありがとうだね」
「そしてごめんね、幸助」
「せっかく幸助がアシストしてくれたのに私この前洋一と別れちゃった」
幸助はそこでも
「そっか」
とだけ言い、その後はただ春子の横に居続けた。
何も聞かないことを選択した幸助の気遣いに春子は感謝の気持ちを抱いた。
父母ヶ浜への旅行へ一緒に行こうと洋一を誘った時、洋一からよくわからないことを春子は言われた。
「ごめん、旅行には行けない。できちゃったみたいなんだ」
なにができたのか、瞬時には理解できなかったが、ああ、子供ができたのか、と考えついた。洋一が他の女と遊んでいることは、なんとなく察していた。それでも定期的にプロポーズしてきてくれてたから、わたしへの愛はあるのだろうなと思ってしまい別れられなかった。だけどこんな気持ちのままじゃいけないから一度この旅行中にでも時間を設けて今後の二人について話してみようと思っていたのに、その矢先の出来事に驚いた。しかも相手が神田だなんて、世界はどうしてこうも狭いのだろう、と春子は思った。辛さや悲しみが襲ってくると思ったのに、自分に起こったことじゃないみたいで、何も感じなかった。きっとわたしも洋一への気持ちがとっくに無くなってしまっているのだと思っていた。だけど父母ヶ浜の旅行中に洋一がいたらもっと楽しいだろうな、とか、今日の結婚式だって、将来洋一と同じような状況になれていたのかもな、とか考えてしまっていた。自分の感情や考えのどれが正しいのかもうわからなくなっていた。もう一人では考えられないと思って、誰でもいいから側にいてほしいと思った。誰でもいいと思ったけど、誰でもよくなかった。幸助に側にいてほしいと思った。
そして今こうして幸助が側にいてくれている。
やっぱりこの人はわたしにはない優しさや温かさを持っている。
その時幸助の温度が手を通して伝わってきた。
幸助がわたしの手を握ってくれたのだと気づいた。
温かい。
あの日はひとりだった。
暗闇に紛れて消えてしまいたいとさえ思った。
けど今は同じ暗闇でも、もう暗くない。
これからどうなるかわからないけれどこの人と一歩ずつ歩んでいきたい。
ここまで読んでいただきありがとうございます。

