
【3分解説:そば】そばのルーツを探る
・年越しそばや駅前の立ち食い蕎麦など、おそばは私たちの食生活の大切なパートナーになっています。マクドナルドや吉野家もいいですが、そばはいわば日本の元祖ファーストフードとも言えるかもしれません。ですが、そばはいつ頃から今のように私たちの生活の一部になったのでしょうか。
・日本におけるそば自体の歴史は非常に古く、9000年以上前の高知県・佐川町の地層から蕎麦の花粉が発掘されていますから、縄文時代から食されていたようです。
・ただ、そばの実の殻は固く、脱穀が面倒なため、当時のそばはお米のように主食としては広く定着しませんでした。
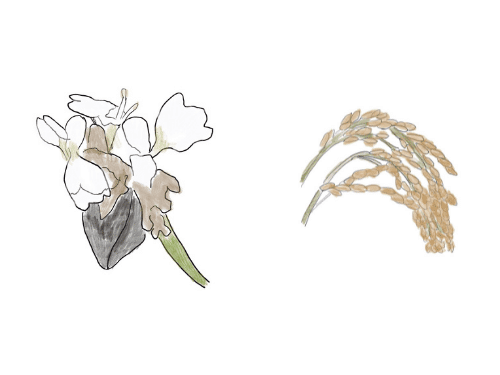
・797年の史記「続日本紀」(国家により編集された歴史書)には、「今年の夏は雨がなく、田からとれるものがみのらず、よろしく天下の国司をして、百姓を勧課し、晩禾、蕎麦及び小麦を植えしめ、たくわえおき、もって救荒に備えしむべし」との記載があり、そばは、お米がとれない凶作のときの代替食として栽培されていました。
・その後も、古今著聞集(平安から鎌倉までの貴族社会の様々な逸話を記録した本)には、歌人である道命(藤原道長の甥)が旅先で蕎麦を振舞われた際、来客向けに出すような食べ物ではないものを出された、として驚いた逸話が残されているくらいですので、鎌倉時代のあたりまでは凶作に備えた備蓄食として扱われていました。
・当時は粒のままおかゆのように茹でて食べていたようです。お国は違いますが、ロシアでは今でもそばの実をおかゆ(カーシャ)のようにして食べています。ちなみにロシアのそばの生産量は世界一(78万トン)で、日本の20倍です(日本は世界で7位(4.2万トン))。
・日本のように麺で食べるのは日本のほか、中国(ヘイロ)・朝鮮(冷麺)くらいのようです。

・その後、鎌倉時代には中国伝来の回転式の挽き石臼が普及し、面倒だったそばの実の脱穀が用意になったことで、そば粉の利用が増えていきました。
・ただ、食べ方としては、まだ麺ではなく、そば粉を練って団子形にして茹でたそばがき、焼いた焼きそばがきとして供されていました。
・麺状のそばが生まれたタイミングは不詳ですが、江戸時代には既に生まれていたようです。この頃は、そばがきと対比するために「そば切り」と呼ばれていましたが、滋賀・多賀大社の社僧であった慈性の「慈性日記」には、1614年の出来事として、江戸・常明寺で「そば切り」を食べたことが記されています。
・1643年に出版された料理書「料理物語」(日本で初めて材料やレシピを具体的に記した本)には、麺状のそば(そば切り)のレシピが記載されています。ただ、当初はお湯で茹でるのではなく、せいろで蒸していたようです。というのも、小麦粉のようなつなぎが普及しておらず、茹でるとそばが切れてしまいやすい事情があったようです。
・また、この頃は汁にそばをつけて食べる、つけ麺スタイルがスタンダードでした。
・そばつゆも今のような醤油ベースではなく、味噌仕立てでした。このつゆは室町時代には既にうどん用のつゆとして生まれていたもので、味噌を水で煮詰めたものを漉した「垂れ味噌」に、みかんの皮・大根汁・わさびを薬味に添えて食されていました。
・元禄(1688~1704年)の頃には、醤油の文化が上方から江戸に入り、醤油と出汁を合わせたつゆが広まり、今のぶっかけスタイルの「かけそば」も開発されました。
・当時の江戸の家屋は木製ですので、2~3年に一度は大火が度々起こり、その度に、都市再建のため地方から職人がかき集められました。こうして重労働で汗を流した労働者からは塩味の効いた味の濃い食べ物が好まれたため、そばの汁もまた、関東風の濃口醤油で仕立てられたつゆが愛されるようになりました。
・また、忙しい彼らにとって、一口ずつつゆにつけて食べるのは面倒ということで、素早く立ち食いできるよう、つゆを麺にぶっかけたかけそばもまた普及していきました。いわば、そばは当時の手軽なファーストフードだったわけです。

・一方で、つけめんスタイルも江戸時代の中頃(1750年代)には進化を遂げて、東京・深川の伊勢屋という蕎麦屋産により、竹ザル(食器や食べ物の水切り道具)にもった「ざるそば」が開発されました。お椀にそばをいれておくと、器の底にたまった水でそばがふやけてしまいますので、最後までそばをノびずに食べれるよう、ざるを器にして水を切る工夫がなされたようです。このざるそばは広く普及していくことになりました。
・また、同時期に、年越しそばの習慣も広がりました。「歳とりそば」「大年そば」「おおつごもりそば」とも呼ばれていました。なぜ年越しでそばを食べるようになったかというと、細く長いので寿命を伸ばすとか、切れやすいから1年の苦労・厄災を切り捨てるとか、いろいろ説があるようです。
・1751年には、そばの産地・レシピから有名店の蕎麦屋の様子まで記された「蕎麦全書」が発行されています。この頃には、江戸中に蕎麦屋やそばの屋台があちこちに出ていたようで、今私たちが食べるかけそば、ざるそばといったそば文化は、お江戸の市井の中で育まれていったことが伺えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
