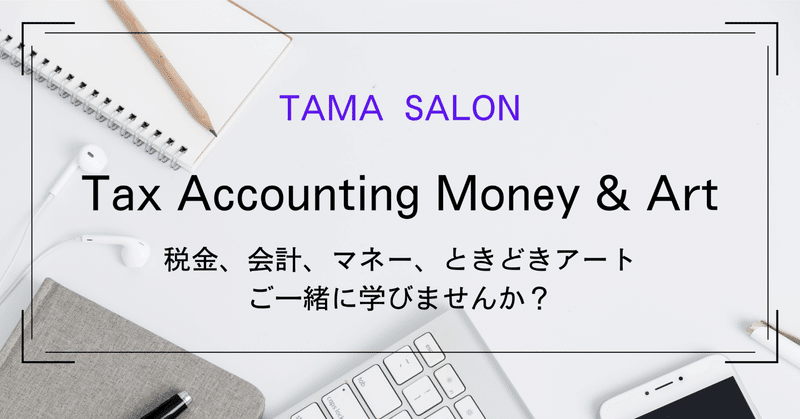
2.NISAの内容
皆さまは、すでに「NISA」を始めておられますか?
NISAのキホンと対策を整理しておきましょう!
年360万円まで非課税で投資可能
2024年からの新NISAには、投資信託を対象とした「つみたて投資枠」(年間投資上限額120万円)と上場株式等にも投資できる「成長投資枠」(年間投資上限額240万円)が設けられており、これらは併用可能です。
つみたて投資枠は「長期・分散・積立」に適した金融庁が定める一定の投資信託などから商品を選択します。
成長投資枠は投資信託だけでなく、国内・国外の個別株式、不動産投資信託(REIT)、上場投資信託(ETF)などにも投資できます。成長投資枠は購入方法に制限がなく、積立または一括投資のいずれも可能です。
2つの投資枠を合わせて、年間360万円まで非課税での投資が可能です。
もちろん、全ての非課税投資枠を投資信託の積立に充てても構いません。
(注)成長投資枠の対象商品から、整理・監理銘柄、信託20年未満、高レバレッジ型・毎月分配型の投資信託は除かれる
なお、口座内で売却があっても、売却分の非課税枠は再利用(再投資)できず年間投資上限額は増えません。購入に充てた投資枠は同じ年にその資産を売却しても復活せず、翌年になって、また新たな投資枠が発生します。
たとえば、成長投資枠で購入した上場株式100万円を年内に180万円で売却した場合には、売却益80万円が非課税となります。
購入に充てた100万円の成長投資枠は復活せず、年内の非課税投資枠は残り140万円(=240万円-100万円)となります。
また年間投資枠は、各年ごとの投資上限額ですので、その年に使用しなかった非課税投資枠は切り捨てられ、翌年に持ち越すことはできないので注意してください。
なお、分配金再投資を選択して投資信託に投資する場合は、最初の購入価額に加えて、その後の再投資に充当された分配金も投資枠を使用することになります。
たとえば、つみたて投資枠で毎月10万円、12か月の定期積立の指示をしている場合、12月の積立額は10万円から年間の再投資額を差し引いた金額で買い付け指示を行うことで投資枠120万円を使い切ることができます。
(自動調整してくれるネット証券会社もあります)

一生、常に1,800万円まで非課税
1人が生涯において非課税で保有できる最大限度額という意味合いで、「簿価残高方式」による「生涯非課税限度額」が設定されます。
生涯にわたる非課税限度額は1人当たり1,800万円(うち、成長投資枠1,200万円)とされ、常に最大1,800万円まで非課税投資を継続できます。
生涯非課税限度額は取得価額(帳簿価額=簿価)の合計額で判定し、口座内で売却があった場合は、その分の簿価が減少することで投資枠が復活し、新たな投資が可能となります。
たとえば、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて年間の非課税限度額360万円をフルに活用すると5年間で生涯の投資上限額を使い切りますが、保有資産のうち取得価額300万円の上場株式を売却すれば、その分だけ非課税限度額が復活することとなります。
「つみたて投資枠」に向いている商品
NISAのつみたて投資枠に向いてる商品は、基本的に、iDeCoの積立投資と同じ考え方になります。購入時の手数料が無料(ノーロード)で、運用管理費用(信託報酬)が低く、純資産額(規模)が大きいインデックスファンドが最適です。
各商品の目論見書または金融機関のウェブサイト、パンフレットに手数料が掲載されているので購入前にチェックしておきましょう。
信託財産留保額は、運用商品のスイッチング(変更)時に差し引かれる支出です。投資信託の解約(売却)によりファンド全体の資産が減少すると投資効率が悪化します。その補てんとして、解約者から保有者に対して支払うペナルティー的な支出で、ファンドの純資産に加算されます。
解約よりも新規購入による資金流入が大きい人気のファンドを別として、中規模のファンドで解約が増えて資産規模が小さくなると全体の運用成績が下がってしまいます。長期運用を前提とすると、必ずしも信託財産留保額の設定がない商品が有利だとは言いきれません。
ただ現状は、多くのファンドで信託財産留保額なしと設定されています。

★重要★ 購入時手数料が無料で、信託報酬率が低く設定され、純資産額が大きいファンドを選択しよう
「成長投資枠」に向いている商品
NISAの成長投資枠は、投資信託のほか、業績と財務状況が良好で株価の上昇が見込める上場株式、配当利回りの高い銘柄、不動産投資信託(REIT)、上場投資信託(ETF)などが向いています。
REITは少額資金で不動産投資ができる、現物不動産投資のような管理コス
トが不要、比較的高利回りであるというメリットがあります。
その反面で、金利情勢を反映して元本割りリスク(金利が上がると価格が下がる、金利が下がると価格が上がる)があり、また、投資物件(ホテル、住宅、オフィスビル等)により景気の影響を大きく受けます。
情報開示されている財務諸表に目を通しておくことが大切です。
通常の株式投資と同様に、価格変動・元本割れリスクがある点に注意し、投資先の財務諸表もチェックしたうえで投資判断を行いましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
