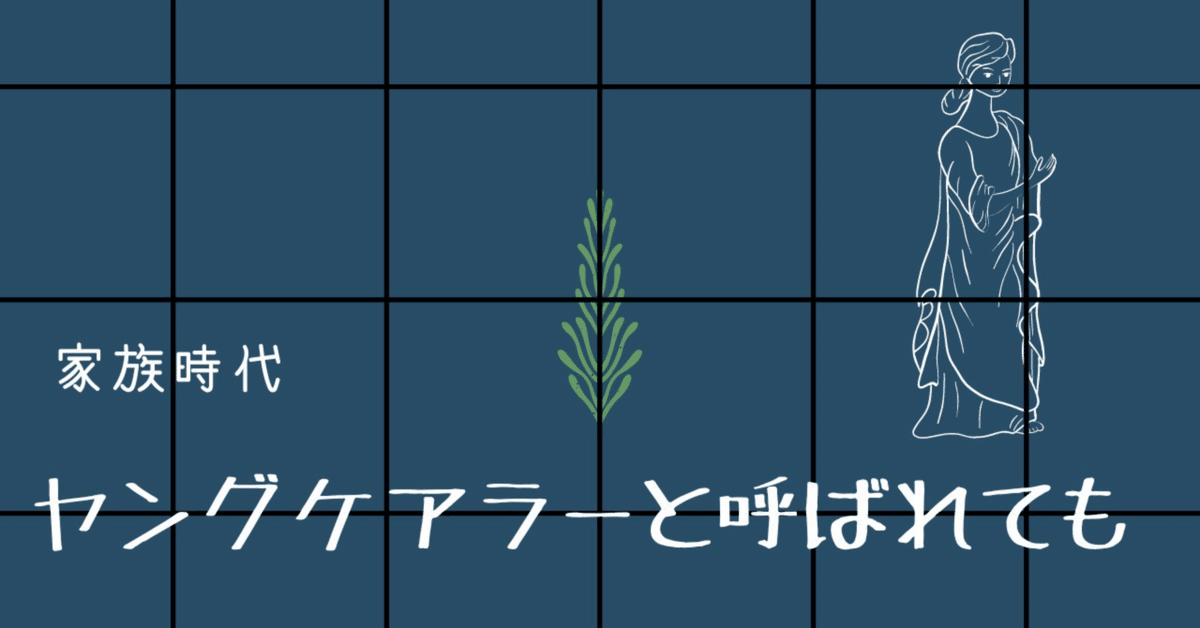
『ヤングケアラーと呼ばれても』
「最初の記憶」
ある言葉に大学3年生の時に出会った。Twitterを何となしに見いていた。すると、「ヤングケアラー」という言葉がタイムラインに流れてきた。
ヤングケアラー???
横文字で胡散臭くあまり良い印象ではなかった。気になってヤングケアラーを調べた。ヤングケアラーとは、病気や障害のある家族や親族の介護や面倒などの大人が担うようなケア責任を引き受け、家族の世話全般を行っている18歳未満の子どもを指す意味らしい。僕の母はパニック障害、父はギャンブル中毒だった。
僕は自分がヤングケアラーだと思った。
いや、そうじゃない、思いたかったんだ。
スマホを机に置いて僕はゆっくりと当時の母との記憶を思い出した。
あれは4歳か5歳とかだったと思う。僕と2つ下の妹と母と父と小さなアパートに暮らしていた。僕は同じアパートに住んでいる年上のお兄ちゃんの家に遊びに行っていた。その帰りである。僕はアパートの扉を「ただいま」と言いながら開けた。
玄関から真っ直ぐ伸びた廊下の先に蠢く塊があった。
その塊はジタバタ悶えていた。僕は怪物かと思った。恐怖で胸の鼓動がドクン、ドクンと音を立てたのがわかった。
その怪物は母であった。
母は痙攣して倒れていた。僕は急いでさっき遊んでいた家に戻り、年上のお兄ちゃんのお母さんに助けを求めた。その後、どういう処置になったか記憶はない。
僕は母を怪物のようだと思ってしまった。
「2つ目の記憶」
僕の母はパニック障害という病気を患っていた。
ヤングケアラーという言葉が今までの僕の記憶や経験を1つに束ねようとした。僕はそれに安堵したし、反発するかのように軽蔑した。
母によく抱っこしてもらった。「抱っこ」と言って母に抱きついた。それを1日に何回もする甘えたな子供だった。けれど母を怪物だと思った日から徐々に「抱っこ」と言えなくなった。身体的な触れ合いがなくなっていく。なんだろう、触れることができない、甘えることができなくなった。
その頃から僕は耳にタコができるくらい「家にはお金がない」「死にたい」と母に言われ続けた。別に屋根のある暮らしでご飯もあったし、母が自殺未遂をしたとかでもない、ただただ、僕は母のそういう話をとにかく聞いてきた。その当時の僕の力ではどうすることもできない話を聞いてきた。母の話を聞けるのは僕だけだと思っていた。僕がその役目なんだと思った。そしてなりより僕は母が大好きだった。
小1の時である。大事にしてたドラゴンボールの筆箱を母がパニックになって僕の目の前で床に叩きつけて壊した。僕がいるからこの環境から逃れられない、けれど僕に直接当たることはできない、だから母は僕の大事にしているものを壊した。そこには悲しさしかなかった。これで終わりなら、いつか僕は家を滅茶苦茶にして飛び出したのかもしれない。
けど、次の日の夜に壊れた筆箱を開くと紙が入っている。
紙にはお母さんの字で
「たいがごめんなさい。たいがにはいつも本当に悪いと思ってる。こんなお母さんでごめんなさい。たいがは心の優しい子、いつもありがとう」と書いてある。
胸が締め付けられるのが分かる。訳がわからなくなる。悲しいのか、嬉しいのか、わかんないけど、目に涙が溢れる。この涙の意味は知らない、今でもわからない。憎いのか、悔しいのか、わかんない、これが愛なのか、そうじゃないのか、よくわかんないけど、涙がボタボタ落ちたんだ。
「3つ目の記憶」
小1か小2ぐらいだったと思う。暴れ回る母があまりにもひどい日があった。母は下着姿で床を陸に打ち上げられた魚のようにのたうち回る。母は叫んでいる、言葉ではない何かを叫んでいる。
人は言葉にできないもの抱えているがそれを普段はないことにして生きている。けれど僕は言葉にできないものが叫びとして現れるのを何度も見てきた。この事が関係してか僕は後に現代思想の「差異」という言葉に惹かれる。僕の中では同一性より差異が日常だった。
母はさらに暴れ回り過呼吸になり息が出来ずに痙攣を起こして死に際の魚のようにピクピクしていた。その時、僕には何もできないことが自然と分かった。父が救急車を呼んで僕も初めて救急車に乗った。とにかく、母が死ぬと思った。ものすごく怖くて、悲しくて、どうしよもなかった。救急車の中でタンカーに乗った母の手を握りしめながら泣きまくっていたのを覚えている。
「お母さん死なないで」と何回も言っていた。
今思い返したら夢のような記憶だ。あんまり覚えてないし、その後の病院の感じもあまり覚えてない。
僕はただ母の手を握りしめて祈ることで精一杯だったんだと思う。
詳しくはいずれ書くと思うが、そんな母と再び手を握る日がある。それはずっと先の話で、僕が大学4年生の時になる。
今度は僕が叫び暴れて過呼吸になって痙攣して救急車で運ばれた。母も一緒に乗った。僕は病院のベットの上で泣き叫んだ後、弱々しく横たわっていた。僕の震える手を母は握った。
母もあの時の僕のように祈りながら握りしめたのだろうか。
僕らはどうしてこんなにも切ない触れ合いしかできないのだろうか。僕は母に手を握られながら泣いた。ボロボロ泣いた。
「4つ目の記憶」
僕には爪を剥ぐ癖がある。
母は僕にお金がないこと、将来の不安、父に対して、の話をよくした。単なる愚痴だったのかも知れないが、僕にはうんざりする話ばかりだった。僕はイライラしながら何度もため息をついた。聞きたくなかったが、そこで「もういい!聞きたくない!」って言って部屋に閉じこもったら母が暴れることは分かっていたから、いちおう、子供ながら出来る限り話を聞こうとした。母の話を聞いている感じを出しながら、その話から逃げるために自分の体で気を紛らわした。それで爪を剥いだ。母の話を聞いてるときに僕は爪を剥いだ。
それが癖になってしまって、小さい頃は手も足の爪も自分で剥いで取っていた。爪切りを使わなかった。けどもしかすると、まず癖が先にあったのかも知れない、なんでも家族の関係に結びつけるのは良くない。どっちか先かはわからない。
僕の父は爪を噛む癖があった。僕の父は父が小学2年生くらいの時にお父さんを亡くしている。母は父の不満を僕に言った後、たまに、お父さんはさびしい人だからと僕に言った。
考え過ぎてたのかもしれないが、僕は見えない流れみたいなのを感じた、こんな家族がずっと繰り返されているように思えた。僕はこのサイクルに吐き気がした。ここから抜け出したいと思いつつ、この流れを否定しきることもできなかった。
今はもう割と意識できているから爪切りは使う。けどたまに、無心で爪を剥ぐ時がある、少し落ち着くのである。気持ち悪いと言われるが、もうなかなか治るもんじゃない。
「5つ目の記憶」
母の気持ちの揺れで僕も揺れていた。母の大きな揺れで僕の小さい揺れは覆われた。僕は素直になれずに我慢することばかり覚えてしまった。
僕は母のことで何もしたくなくなる時があった。ため息もつく。ただでさえ母で大変なのに男のお前がため息なんてつくのかと父は嫌そうな顔をした。本当にそれが嫌だった。殺意すら湧くときもあった。「元はと言えばお前だろ、お前のせいだろ!僕は関係ないだろ」そう思う時もあった。憎くて仕方ない瞬間もあった。男だからが本当に嫌だった。お前はシャッキとしろ!ピシッとやれ!じゃないとどうすんだよ。そんな雰囲気が空気としてずっとあった。
だからかわからないけど、男同士の競争が苦手だった。興味が薄い気がする。どっちかというと、バランスを取る方に立ち位置を取りたくなる。あいつを負かすとか、圧倒時に勝つとか全然興味がなかった。そんな子供だったような気がする。それは勝ってこなかったから、勝つことの面白さを知らなかったからそうなったのかもしれない。言い訳にも聞こえる。けれど僕はサッカーをしてもいつもゴール前でパスを出す人だった。
そんな僕は父の目には優柔不断で女々しい奴に思えたんだと思う。
父にはよく「 お前はオカマか!」とか「お前は女か!」とか言われた。
そうなる背景には親の影響もあることを一切父は考慮に入れて話してはくれなかった。僕が勝手にこんな感じになったみたいな言い回しをされる。それもしんどかった。本当にしんどかった。それに反発して強く言い返してしまったら、母が傷ついてまたおかしくなったらどうしようと思って、言い返すことも出来なかった。僕は父のそういう言葉にヘラヘラすることしかできなかった。
父は「何やねんお前、男やったらちょっとは言い返さんかい」と言った。
おかしくなりそうなった。でもできるだけ穏便に済ませたくて我慢することになる。その我慢に本当に息が詰まりそうになる。胸がパンパンになる。何もしたくなくなる、何かが歪んでいくのが分かる。
「手紙 ①」
曖昧な記憶だが僕は中学3年生の卒業式の日に当時の校長先生に手紙を書いて渡した。
僕は中学3年生の時に人権作文で心の病についての作文を書いて学校の代表として全校生徒の前でスピーチをした。母のことを言わずに僕が心の病について普段思ってることを素直に書いた。代表に選ばれるなんて微塵たりとも思ってなかったがその作文は選ばれた。
僕は母を通じて心の病について自然と思考していた。意志とは関係なく思考してしまっていた。思考は侵入である。
人権作文の内容を校長先生は凄く褒めてくれた。内容への理解もあった。僕はこの1人じゃ抱えきれそうにもない家族のことを誰かに話したかった。友達に言える感じでもなかったし、その当時、学校以外の大人は存在しないように思えた。だから僕は校長先生に頼る他なかった。自分の状態を赤裸々に書いた手紙を卒業式の日に校長先生に渡した。
その時の記憶があまりない、もしかすると、結局渡せなかったのかもしれない、手紙の内容も全く覚えてない。
そもそも僕がもっと素直に気軽に人に話せていたら家族の状況は変わっていたのかもしれない。けれど、僕は手紙を渡して去ることで精一杯だった。住所なども書いてない、吐露をしただけの手紙。手紙が返ってこないことは分かっていた。
「手紙②」
中学3年生の時に返ってこない手紙を出した。
23歳の今日、僕は当時の僕に向かって手紙を返そうと思う。今なら言えること、書けることがある。
君は笑っているお母さんと適当に過ごす時間を取り戻したいだけなんだよね。そんな君に色々話したいとがあるんだ。
君はお母さんの医者になってる。まだ何も習ってないのに、ただ何も考えずに過ごしたいだけなのに、遊んで寝てたまに怒られたいだけなのに、いつのまにか医者としてお母さんを診てる。自分がどうにかしないとこの人は死んじゃうと思っているもんね。何もわからないで医者をするのは本当に大変だと思う。本当はさ、もっと適当でいいんだよ、大丈夫さ、なぜか医者と思われてるからそうなっているだけ、君は医者じゃない、君は適当でいいんだ。そうさ、一貫性はいらないよ、ずっと寄り添わなくても優しくなくてもいいんだよ、医者じゃないんだから。お母さんが叫び暴れまわり、部屋をぐちゃぐちゃにして何枚も茶碗を割り、死にたいと叫び、過呼吸になる姿は君のせいじゃないよ。君のせいじゃないよ。君はいるだけで支えとなってるし、君は何もしてないんだ。
君のお母さんは自分が精神病であることを強く思い過ぎて、目の前の息子を正常だと思い込んでいる。そらぁ、お母さん方が大変なことぐらいわかる。暴れるし叫ぶし、君はそんなことないから僕は別に大丈夫と思っているかもしれない。だけど、君もどんどん溜まっていってる、君の心は最強じゃない、揺れ動いているんだ。揺れを見せたらお母さんに影響すると思って我慢している。あと、言えないもう1つの理由は、お母さんに心配をかけたくないんだよね、お母さんがものすごく心配性なのを知ってるから、君は誰よりも知ってるから、簡単に自分の心が揺れ動いてることを言えないよね。お母さんが君のことを真剣に考えていることを君は知っているもんね、だから、こっそり寝るときにお母さんのことを考えて泣いたりしているだもんね。悲しくて悲しくて仕方なくなるよね。のたうちまわり、お金がないとずっと言ったり、死にたいとずっと言ったり、そんなお母さんが君のことをいつも大切にしてくれているから涙が出るんだよね。大丈夫。我慢しなくても良いんだよと君に言ってくれる人は後に現れる。こういうことも気軽に笑いながら話せる人にも出逢うんだ。その人は君の揺れを見てくれる存在だ。そんな人も現れる。君はいつもそういう人の前で泣いてきた。
君がふーっと、肩の力を抜いて息を吐けるのが大切な気がするんだ。君は優しいから、ずっとお母さんのことを考えると思う。考え過ぎて喧嘩もすると思う、言い合いもすると思う、けれど、その日々は材料だと思う、それをもとに君とお母さんに合った関係を創作していくんだ。それは別に一緒にやらなくてもいい。君がため息をついたり、泣いたりしなくてもいい関係を作るんだ。決してしたくないことはするべきじゃないと思うんだ。まず今の僕がやってみる。これもその1つなんだ。
届いたよ、君が出した手紙は確かに僕に届いたよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
