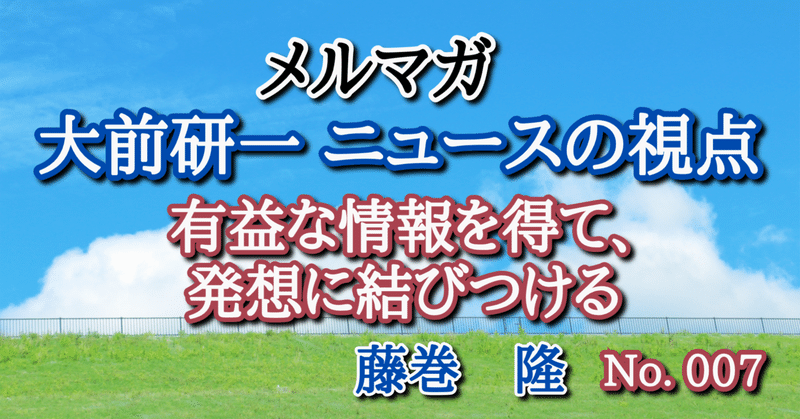
メルマガ 大前研一 ニュースの視点 有益な情報を得て、発想に結びつける No.007 KON477(2013/08/02)~ KON481(2013/08/30)
メルマガ 大前研一 ニュースの視点 有益な情報を得て、発想に結びつける No.007 KON477(2013/08/02)~ KON481(2013/08/30)
はじめに
私は30年ほど前から大前研一氏の著作を読み始め、読み続けています。
大前氏の著作や動画等から非常に有益な情報を得るだけでなく、考え方・発想法などを学んでいます。
大前氏のメルマガ購読を10年ほど前に開始し、今日も続けています。
ただし、すべての記事にきちんと目を通したわけではありません。
そこで、メルマガ購読の登録を開始した当時に遡って、読み直すことにしました。
そうすることで書籍との関連性によってより深く理解できたり、10年にわたる大前氏の考え方の変遷を感じ取ることができると考えました。
大前氏が頭脳明晰であることは異論がないと思います。
他にも頭が良い人たちは数多いますが、その人たちと大前氏が異なる点があります。
それは、大前氏は自分の考え方や発言に間違いがあった場合には、すぐに認め、訂正することです。他の頭が良いと言われる人たちは、プライドが高く、自分の間違いを認めたがらないだけではなく、訂正しようともしません。
🔶お知らせ
大前氏は私より年齢が一回り上です。大前氏は今年80歳になられました。
事情ははっきりしませんが、2023年6月29日に、BBT(ビジネス・ブレークスルー)の代表取締役を退任されました。
ビジネス・ブレークスルー大学の学長職に専念されるということです。社会人教育に対して情熱を注ぎ続ける姿に頭が下がります。
日本を再興するためには、社会人教育が不可欠であるという信念を持ち、今日でも社会人教育に励んでいます。
私は、他のところでも何度も書いていますが、30代の頃から大前氏に私淑しています。これからも変わりません。
KON477【消費増税・貿易統計・TPP~消費税引き上げの目的を考える】 ~大前研一ニュースの視点~ 2013/08/02 8:28
🔴メルマガ全文
┏━■ ~大前研一ニュースの視点~
┃1┃ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┗━┛『消費増税・貿易統計・TPP~消費税引き上げの目的を考える』 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
消費増税 消費増税による影響検討を指示
貿易統計 1-6月貿易赤字 4兆8438億円
TPP TPP交渉に正式参加
-------------------------------------------------------------
▼ 消費増税の再検討は危険な考え方/景気よりも財政問題が深刻
-------------------------------------------------------------
安倍首相が来年4月に予定する消費増税による景気や物価への影響を
再検証するよう指示したことが26日明らかになりました。
政府は法律で定めた通り消費税率を現行の5%から10%に
2段階で引き上げる場合を含め、増税の開始時期や引き上げ幅を変える
複数案を検討するとのこと。
デフレ脱却を重視し、増税が来春以降の景気腰折れを招かないよう、
追加的な景気対策の実施も視野に万全の準備で臨む考えのようですが、
これは「危険」な考え方だと私は思います。
消費増税については、民主党政権時に自民党も合意の上で
可決されています。
つまり、これは正式に「やらなければならない」ことです。
実施を2段階にした上、さらに繰延べとなってくると、
日本の財政規律の問題になるでしょう。
これは国債の暴落を招く危険性すらあります。
ゆえに、麻生財務相及び財務省は、何とか食い止めようとしています。
安倍総理は事情を理解していないのか、1年で1%ずつなどと
言っていますが、市場との対話という点で相当ハイリスクだと
思います。
消費増税を実施しても、きちんと3本目の成長戦略を描けば
問題ないはずです。
例えば、私が提案するような土地活用の規制撤廃などです。
また、消費増税について、景気にどのような影響が出るのか?
という議論があります。
安倍総理も、景気の数字を見ながら消費増税のタイミングを
秋に判断したい、などと述べていますが、根本的に間違っています。
というのは、今の日本の最大の問題は景気の悪さ(不況)
ではないからです。
この20年間日本はずっと不況でしたが、それでも餓死者が続出する
わけでもなく、失業率も4%台でスペインのような大きな数字には
なっていません。
つまり、日本という国は景気が悪くなっても、
つぶれることはないのです。
それよりも、GDPの2倍という歴史上類を見ない莫大な借金を抱えた
財政こそが、日本の最大の問題です。
約1000兆円の借金のうち、大半は自民党が生み出したものです。
だから、今の政府はなるべく手を付けたくないという心理が
働いているのでしょう。
飛行機に例えるなら、不況というのは
「乱気流になって揺れますのでご注意ください」程度の話ですが、
財政問題は「墜落します」と同義です。
かつて今の日本ほどの借金を抱えた国もなければ、
そこから回復した国もありません。
さらには、毎年80万人ずつ就労人口が減っていく日本では、
借金を返す人がいなくなる時代が、すぐそこに迫っています。
まず、この重要性を認識して欲しいと思います。
-------------------------------------------------------------
▼ 日本は米国化し、輸入国になった
-------------------------------------------------------------
財務省が24日発表した貿易統計によると、1~6月期の貿易収支は
4兆8438億円の赤字でした。
上期ベースでは3年連続の貿易赤字。
赤字額は前年同期(2兆9168億円)を上回り、比較可能な
1979年以降で最大となったとのことです。
原発稼働を停止したため、燃料の輸入が増加したことが
大きな要因になった、という報道もあるようですが、
これは本質的な問題を指摘していません。
確かに、直近の数字で輸入が大きく伸びていることは確かですが、
貿易収支のグラフを長期スパンで見れば、
右肩下がりの傾向にあるのは明らかです。
増加したという鉱物燃料の輸入額も2008年と同レベルであり、
突出して大きな数字だったというわけではありません。
日本の貿易収支には、反転の兆しは全く感じられません。
これは日本が米国化したことを意味しています。
すなわち、日本は輸入国になったということです。
今、日本企業は海外でモノを作って日本国内の販売網で販売する、
という形態に変化しています。
かつて米国が経験した「3つ子の赤字」問題のうち、2つの赤字を
日本も抱えてしまっている状況なのです。
-------------------------------------------------------------
▼ 安易に「国益」という言葉をつかって、ごまかすな
-------------------------------------------------------------
日本政府は23日午後、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に
正式参加しました。
日米両国を軸とする巨大な貿易圏作りが動き出し、
アジア太平洋を巡る経済や安全保障の枠組みに大きな影響を
与える見通しとのこと。
私が気になったのは、交渉担当官がしきりに「国益」を
強調していたことです。
私に言わせれば、彼らが言う「国益」は「少数利益団体の利益」
であって、本当の意味での「国益」ではありません。
国民消費者から見れば、良いモノが安く購入できることは
非常にいいことです。
そうした観点を無視して、自分たちの都合だけで「国益」を
語るのはおかしな話です。
安易に「国益」などという言葉を使わずに、
正直に言えば良いのです。
自民党には「国益」と称して、利益を守るべき団体があって、
そういう存在が自民党を支えているとも言えます。
ただ、そのような事情は米国でも同じでしょう。
オバマ大統領にしても理解できるでしょうから、
「お手柔らかに」と言えば良いのです。
こうしたことさえ理解できずに、安易に「国益」という言葉を
使うのは、明らかに新聞記者の認識不足だと思います。
==================================================
この大前研一のメッセージは7月28日にBBT Chで放映された
大前研一ライブの内容を抜粋・編集し、本メールマガジン向けに
再構成しております。
==================================================
✅KON477のキーワード・キーセンテンス
1「消費増税」
10年前の話ですが、消費増税論議が活発化していた時期です。
10年前はデフレで不景気の真っただ中で消費増税をしたことが、その後の景気回復を遅らせたことが明らかになっています。
モノの値段が上がらないだけでなく、賃金もずっと横ばい状況で消費増税をすれば消費が増えるはずがありません。
デフレは2013年時点で20年間続いていて、さらに10年間続き、結局30年間に及びました。
消費増税をするならインフレで賃金も上昇し、景気が良い時です。
消費増税のタイミングを間違えました。
2「貿易赤字」
日本は戦後、1ドル=360円という固定相場制でしたが、ニクソンショックで変動相場制へ移行しました。
以後、急速にドル安円高となりました。急激に円高が進み、一時1ドルが80円を割ることもありました。
1ドルが360円の時代以降に、日本は輸出立国し大いに稼ぎました。
しかし、その後、円高が進みドル建ての取引では赤字になりましたが、企業努力によって企業業績を改善するところもありました。
ニクソン・ショック(ドル・ショック)とは、1971年8月15日(日本標準時1971年(昭和46年)8月16日)にアメリカ合衆国連邦政府が、それまでの固定比率(1オンス=35ドル)による米ドル紙幣と金の兌換を一時停止 したことによる、世界経済の枠組みの大幅な変化を指す。当時のリチャード・ニクソン大統領がこの政策転換を発表したことにより、ニクソンの名を冠する。
「日本は輸入国になったということです」という大前氏の言葉通り、日本は天然資源が乏しいだけでなく、食糧までも足りないため、海外に頼らざるを得ない状況に陥っています。6割を輸入に頼っているのが現状です。
つまり、日本は自給自足ができないのです。
令和4年度の食料自給率
カロリーベースの食料自給率については、前年豊作だった小麦が平年並みの単収へ減少(作付面積は増加)、魚介類の生産量が減少した一方で、原料の多くを輸入に頼る油脂類の消費減少等により、前年度と同じ38%となりました。また、カロリーベースの食料国産率(飼料自給率を反映しない)についても、前年度と同じ47%となりました。なお、飼料自給率も前年度と同じ26%となりました。
2023年11月14日現在、ドル円相場は150.97 円(11月14日 14:30)です。
「円安が進行している」と報道されますが、50年前の360円と比較すると半額以下ですから円高です。
KON478【中国経済格差と香港金融市場~中国の参考モデルとなる日本のM型社会】 ~大前研一ニュースの視点~ 2013/08/09 8:28
🔴メルマガ全文
┏━■ ~大前研一ニュースの視点~
┃1┃ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┗━┛ 『中国経済格差と香港金融市場~中国の参考モデルとなる日本のM
型社会』――――――――――――――――――――――――――――――――――
中国格差問題 中国都市部の貧富の差 242倍
香港金融市場 融資の急拡大に警戒
中国経済改革 中小・零細企業の付加価値税を免除
-------------------------------------------------------------
▼ 共産党革命以降、中国の貧富の格差はさらに広がった。
-------------------------------------------------------------
北京大学の調査によると、中国都市部の最富裕層(上位5%)と
最貧困層(下位5%)の世帯年収を比較したところ242倍もの格差が存在
し、格差の幅も急速に拡大していることが明らかになりました。
かつて鄧小平は「貧しい人は後から追いつけばいい」と述べていました
が、今の中国社会は「持てる者がさらに持つ」という米国型になってしま
いました。
格差のない社会を実現するはずの共産主義にもかかわらず、
改革以降、所得格差の矛盾が大きく開いてしまったという状況です。
このままいけば、劣位に置かれている人達のフラストレーションがたま
り、再びボルシェビキ革命のようなことが起こる可能性があると私は思い
ます。
胡錦濤前国家主席の頃は、所得格差問題の是正は1つの大きなスローガン
になっていましたが、現在の習近平政府は所得格差問題よりも、
腐敗の撲滅などに力を注ぐこととで貧しい人達の怒りを抑えようとしてい
ます。
貧富の格差が広がっている中国ですが、統計手法によっては、
世界「最悪」の部類にはまだ入っていません。
所得上位10%の層の総所得に占める割合を見ると、
南アフリカなどは上位10%で全体の50%を占めています。
中国はまだ30%程度です。
また所得下位10%の層の総所得に占める割合を見ても、
中国は最低ではありません。(いずれも世界銀行による統計)
この種の統計には日本は登場しません。
M型社会になりつつある日本ですが、
まだまだ貧富の格差が少ない北欧型の分布になっています。
ゆえに、中国に比べて日本の田舎は綺麗だし、
安全で安心していられるというメリットがあります。
今、中国でも日本のように地方に温泉を作ろうという動きがありますが、
日本は大いに参考になるということです。
-------------------------------------------------------------
▼ シャドーバンキング→破綻という、日本がたどった道。
-------------------------------------------------------------
香港金融管理局(HKMA)の報道官は、香港での融資の伸び率が5月は
20%だったのに対し、6月に年率にして約40%に加速したことを明らかに
しました。
これは非常に注目すべきニュースだと私は感じました。
すなわち、いよいよ中国の金融当局が「蛇口を閉め始めた」のでは
ないかと思います。
だから中国本土の企業が、香港の銀行から借りるという
流れになったのでしょう。
これはかつての日本における「住専」と全く同じ流れであり、警戒するべ
きです。
総量規制と窓口規制の結果、ノンバンクへ資金が流れるという構図です。
中国でもメインバンクが絞ったために、シャドーバンキング、
さらに香港へ行き着いているのだと思います。
中国国務院(政府)は24日、李克強首相が主宰する常務会議を開き、
中小・零細企業約600万社に対して、商品の販売やサービスにかかる付加
価値税を8月1日から免除すると決めました。
中国に進出する日本企業が免税対象になるかどうかは不明です。
また一報で、中国国家審計署(監査院)は国務院(内閣)の要請により
全ての政府債務について監査を行うことを明らかにしています。
今の中国当局は、監査と免除が日替わりメニューで入れ替わっている印象
で、まるで落ち着きがありません。
かつて日本でも同じような状況がありました。
不幸にも厳しいタイミングに当ってしまった山一證券は破綻しましたが、
その後は救済に方針転換したため、破綻する企業はありませんでした。
今中国ではシャドーバンキングとして約350兆円の資金が裏口で動いてい
ます。
個人レベルで見ると預金した際の金利が3%から7%になるというのは
嬉しいことですが、借り手が5%~10%の金利を返済できるのかというと、
難しいでしょう。
どこかのタイミングで方程式が崩れて、日本と同じように破綻するしかあ
りません。
おそらく、今さら監査したところでもう間に合いません。
すでに「飛び降りても助からない高さ」に達していると私は思います。
まさに90年代なかばの日本と同じ状況です。
==================================================
この大前研一のメッセージは8月4日にBBT Chで放映された
大前研一ライブの内容を抜粋・編集し、本メールマガジン向けに
再構成しております。
==================================================
✅KON478のキーワード・キーセンテンス
1「貧富の格差」
中国は共産主義でしたが、習近平氏が国家主席に就任してからは資本主義を前面に出した政策を実行してきました。
その結果、中国は貧富の格差が大きくなりました。
2「シャドーバンキング」
中国は、過去日本がシャドーバンキングを使い破綻した二の舞を演じようとしています。
シャドーバンキングの問題点
シャドーバンキングは、これまでに世界において、深刻な事態が起きる度に注目されてきましたが、免許制等で金融当局から厳しく監督される通常の銀行と比べて規制が緩く、金融当局も実態をよく把握しきれていません。
一方で、その仕組み面において、多額の資金を集めてレバレッジをかけられること、情報開示が不足していること(情報開示をしていないこと)、金融当局等が効果的に規制や介入ができないことなどが問題点として挙げられます。
中国のシャドーバンキング
2010年代になると、今度は中国の金融システムの問題として「シャドーバンキング」が世界的に再注目されるようになりました。具体的な対象としては、信託会社やファンド、貸金業者、質屋などが該当します。
その中でも、特に問題なのが、信託会社などが組成し、主に銀行の窓口で販売されている「理財商品(高利回りの資産運用商品)」で、集められた巨額の資金が代替金融(場外融資)で主に地方政府の投資プロジェクト(不動産開発・インフラ整備等)に流れ、リスクが拡散しているとのことです。
仮に、その投資プロジェクトが行き詰った場合、誰が損失リスクを負うのかが曖昧になっており(幅広い関係者が損失リスクを負う可能性があり)、最悪の場合、中国の金融システムを大きく揺るがす恐れがあると言われています。
不良債権問題は今後白日の下に晒される日が来ると考えられます。
中国の不動産バブルはすでに弾けています。
中国恒大グループが返済も利払いもできなくなっています。
【解説】 中国恒大集団の破綻の恐れ、どれほど心配すべきなのか
恒大は積極的に事業を拡大。3000億ドル以上を借り入れ、中国最大の企業の一つとなった。
中国政府は2020年、大手不動産開発業者の負債額を管理する新たな規制を導入した。
この措置を受け、恒大は運転資金を捻出するために、物件を大幅に値引きして売ることになった。
現在では負債の利払いに苦しんでいる。
恒大の問題が深刻な理由はいくつかある。
まず、多くの人が同社の不動産を購入しており、中には工事が始まる前に買った人もいる。それらの人たちは手付金を支払っているが、同社が破綻すればそれを失う可能性がある。
恒大には取引企業が多いこともある。建設会社や設計会事務所、資材サプライヤーなどは、大きな損失を被り、倒産に追い込まれるリスクに直面している。
さらに、中国の金融システムに及ぼす潜在的な影響もある。恒大が破綻すれば、銀行などの金融機関は貸し出しを減らすようになるかもしれない。
そうなると「信用収縮」の状態となり、企業は無理のない金利で借金をするのが難しくなる。
信用収縮は、世界2位の経済大国の中国にとって非常に悪いニュースとなる。借り入れをできない企業は成長が難しく、事業継続すらできなくなることもあるからだ。
そのうえ、外国人投資家が不安を覚え、中国での投資に魅力を感じなくなる恐れもある。
KON479【東南アジア自動車市場とフォード・モーター~見直されるフォードの経営哲学】 ~大前研一ニュースの視点~ 2013/08/16 8:29
🔴メルマガ全文
┏━■ ~大前研一ニュースの視点~
┃1┃ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┗━┛ 『東南アジア自動車市場とフォード・モーター~見直されるフォー
ドの経営哲学』――――――――――――――――――――――――――――――――――
東南アジア自動車 1-6月新車販売台数 182万332台
国内自動車大手 スズキ インドネシアに乗用車新工場を建設へ
米フォード・モーター 日本とフォード、スレ違いの歴史
-------------------------------------------------------------
▼ 再び見直されるヘンリー・フォードの経営哲学とは?
-------------------------------------------------------------
東南アジア主要6カ国の1~6月の新車販売台数は
前年同期に比べ15%増の182万332台。
2013年通年では過去最高だった昨年と同水準となる見込みで、
日本車のシェアは80%を突破したとのことです。
日本車(トヨタ)の生産台数の全体で見れば、
未だに米国が強いですが、タイが大きく伸びて
2位になっています。
また中国市場、欧州市場が伸び悩む中、インドネシア市場が
欧州を抜く日も近いと思います。
タイ、インドネシアといった東南アジアの持つウエートが
重要になってきていると言えるでしょう。
スズキは2014年を目処にインドネシアに乗用車工場を
新設すると発表しました。
投資額は約1000億円と言われていますが、
これも東南アジア重視の流れでしょう。
現在、インドネシア市場におけるシェアは、
トヨタ、ダイハツ、三菱、スズキの順ですが、
今回の投資によってスズキが2位に上がってくると思います。
日本の自動車メーカーの目が東南アジアへ向き始めている中、
先日、日経新聞は「日本とフォード、すれ違いの歴史」
と題する記事を掲載しました。
最近、日本とフォード・モーターには不協和音が多いとし、
トヨタ自動車との提携を2年で解消することや、
TPP交渉への日本の参加を反対していることを紹介。
フォードのアラン・ムラーリー最高経営責任者(CEO)は、
トヨタ生産方式を導入するなど親日派で知られることから、
フォード創業家一族の影響力が働いていると分析しています。
ちょうどヘンリー・フォード生誕150周年ということもあって、
米国ではノスタルジックな雰囲気が強くなっています。
今こそ、ヘンリー・フォードの時代に戻るべきじゃないか、
という論調が強まっています。
ヘンリー・フォードはT型フォードを大量生産し、同時に従業員に
「高賃金」を支払うことを何回も演説したことで有名です。
従業員が高い給料を手にすれば消費が拡大し、
国全体が豊かになるという考えでした。
当時においても、他の搾取的な資本主義者とは違う
「経営者の鑑」だと言われていました。
実際、米国の労働分配率を見ると、ヘンリー・フォードの時代から
悪化の一途を辿っています。
ヘンリー・フォードの時代には、資本家と労働者の分配率の差は
今よりも小さかったのですが、両社の格差は段々拡大し、
現在では資本家に傾いています。
これは株式市場の優勢により、配当を行い、貯めた資産を海外に移す
という流れがあり、労働者が重視されていないことが原因です。
-------------------------------------------------------------
▼ デトロイト市の悲惨な状況は他人事ではない
-------------------------------------------------------------
フォードと日本の不協和音という意味を考える時には、
米国の自動車産業の「聖地」とも言える「デトロイト」という
街のことを念頭に置いておく必要があると思います。
フォードのアラン・ムラーリー最高経営責任者(CEO)は評判が良く、
優秀な経営者です。
そのムラーリー氏が考えていることの1つは、
「デトロイトを守る」ということです。
ゆえに、TPPに対する日本の農業のごとく、
デトロイトを守るために「ハンディキャップ」を獲得しようと
画策しているのだと思います。
ご存知の通り、先日デトロイト市は財政破綻しました。
その結果、今のデトロイト市はどうなっているか?というと、
1日のうちに十数件の放火や犯罪がある状況です。
街灯も40%しか行き届いておらず、ますます犯罪が増えるという
悪循環に陥っています。
米経済誌フォーブス電子版が今年2月に発表した「惨めな米都市番付」
でも、暴力犯罪の多さや高い失業率、人口の減少や金融危機の
影響などにより、デトロイトがワースト1位になっています。
日本はこれを他人事だと思っている余裕はありません。
代表的な例を言えば、夕張市です。
今日、同市の人口は最盛期と比較すると、10分の1以下に減りました。
夕張市だけでなく、一昔前には「3割自治」と言われた
日本の地方財政はさらに悪化しており、国の補助がなければ
「1割自治」のレベルに落ちているところもあります。
このような地域では、当然のことながら人口は減っていきますし、
サービスレベルも下がっていきます。
日本全体の人口が減っていく中、地方のオフィス空室率は
高まる一方です。
おそらく、今のままでは存続できない市町村が
多く出てくると思います。
デトロイト市の事例が、まさに日本の地方都市の明日の姿に
なってしまうかも知れません。
==================================================
この大前研一のメッセージは8月4日にBBT Chで放映された
大前研一ライブの内容を抜粋・編集し、本メールマガジン向けに
再構成しております。
==================================================
✅KON479のキーワード・キーセンテンス
1「労働分配率」
労働分配率とは、企業活動で得た付加価値に占める人件費の割合です。適切な人件費かどうかを把握できる指標の一つといえます。
スマカン Smart Company 2023.08.17
労働分配率が低い原因は人件費が増えにくいためであり、昨今の物価高なども相まってさらに低下する可能性も否定できません。十分な人件費が分配できていない場合は、今後の適切な分配が課題の一つともいえるでしょう。
スマカン Smart Company 2023.08.17
資本家と労働者で労働分配率が乖離したのは、資本家は株式を保有し、自社株が上昇すれば、純金融資産は天文学的な額に達します。労働者は給与の他に一時金(ボーナス)があっても資本家の収入にはとても追いつきません。
2「デトロイト」
デトロイトといえば自動車の町だということです。
先日、UAW(全米自動車労連)のストライキが行われましたね。
2024年11月に大統領選挙が行われますが、UAWは大統領選挙にも大きな影響力を持つと言われています。
バイデン氏、トヨタとテスラの労働者に対するUAWの組織化を支持

(UAW)がトヨタ自動車とテスラの労働者を
組織化する取り組みを後押しする姿勢を
表明した(2023年 ロイター/Leah Millis)
KON480【銀行検査・大学発ベンチャー・地下鉄新線計画・信用金庫~日本の役人が主導する政策の特徴】 ~大前研一ニュースの視点~ 2013/08/23 8:29
🔴メルマガ全文
┏━■ ~大前研一ニュースの視点~
┃1┃ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┗━┛ 『銀行検査・大学発ベンチャー・地下鉄新線計画・信用金庫~日本
の役人が主導する政策の特徴』――――――――――――――――――――――――――――――――――
銀行検査 画一的な銀行検査を見なおし
大学発ベンチャー 536社の67%が売上高1億円届かず
地下鉄新線計画 開業29年で累積収支黒字の試算
信用金庫 アジアへの事業展開が急拡大
-------------------------------------------------------------
▼ 今の銀行には、まともな融資判断をするスキルがない
-------------------------------------------------------------
金融庁は独自の基準に基づいた画一的な銀行検査を見直す方針を
明らかにしました。
1990年代はじめのバブル崩壊後の不良債権処理を目的としてきた
検査を転換し、融資先が健全かどうかの判断は銀行に大部分を
ゆだねる方針とのこと。
銀行がリスクをとりやすくなり、技術力はあるのに決算上は赤字に
なっている中小・ベンチャー企業がお金を借りやすくなるということ
ですが、これは全く実現性のない「嘘」だと私は思います。
なぜなら銀行には「査定」するスキルがないからです。
バブル崩壊以降、金融庁が作成したマニュアルにのみ
従ってきた銀行には、「経営者を見て、事業計画を見て」融資を
判断することができる人は育っていません。
今、銀行は融資の際、必ず「抵当」を前提とします。
かつて赤字で苦しんでいた松下幸之助氏に、銀行が
「経営者としての松下幸之助を見込んで」融資してくれたという
話は有名ですが、今では無理でしょう。
金融庁も都合が良すぎる発表をしたものだと思います。
自ら作成したマニュアルのせいで、融資判断ができない人材を
育てておいて、今頃になって銀行にまともな融資判断を求めるとは
支離滅裂です。
さらに似たような事例を挙げれば、金融庁は3月、
各財務局の認可を得た信金に対し、取引先企業が海外に作った
現地法人に直接融資できるという政策を打ち出しています。
愛知県瀬戸市の瀬戸信金や大阪府八尾市の大阪東信金が認可を得た他、
およそ20の信金が準備に入ったそうですが、
これも「本当に大丈夫か?」と疑いたくなります。
国内で運用先がないからと言って、そのスキルもないのに
海外直接投資を促すというのは、金融庁による規制緩和によって
ノンバンクに投資して失敗した住専を思い起こさせます。
役人が主導することというのは、基本的に同じパターンであり、
全く進歩が見られません。
-------------------------------------------------------------
▼ 大学発ベンチャーも聞こえはいいが、仕掛けそのものが間違っている
-------------------------------------------------------------
日本には、このような役人主導の辻褄の合わない政策が多すぎます。
帝国データバンクが15日発表した大学発ベンチャー企業の
2012年の売上高は、約7割は売上高が1億円を下回ったと言います。
約半数は5000万円未満で、有望技術や特許を強みに設立しても、
事業が軌道に乗らず苦戦が目立つとのことですが、
これも日本の大学の先生の実態を知っていれば「当たり前」の結果です。
小泉元首相が実施した「大学発ベンチャー1000社計画」をピークに、
東大発バイオベンチャーなどがいくつか出てきた程度で、
ジリ貧になっています。
それでも、安倍政権下では、2012年度の補正予算で、
産学共同研究や大学発ベンチャーへの出資金などの用途1800億円を
割り当てていますが、この資金はどこに消えていくのでしょうか?
大学の先生がベンチャーを起業したいなら、
自由にやるのは良いことです。
ただし、実行するなら、授業料の3分の1は配当金で賄うくらいの
気合が必要でしょう。
スタンフォードやMITとは異なり、日本の大学の先生には
「起業意欲」そのものが低いと感じます。
また資金を出すのは国ではなく、高齢者がエンジェル(投資家)に
なるほうが良いと私は思います。
そうすることで、高齢者が抱えている預貯金の流動性も
高くなりますし、意義も大いにあります。
これも役人主導の「仕掛け」そのものがよろしくない政策の
代表例だと言えるでしょう。
さらには、次のような事例もあります。
東京都江東区は区内を南北に通る豊洲―住吉間の
地下鉄新線計画について、70円の加算運賃を設定すれば開業から
29年で累積収支を黒字にできるとの試算をまとめたそうです。
しかし、これは建設費に国の補助を受けるには30年以内の黒字化が
義務付けられているため、それに合わせて「29年」と
言っているだけでしょう。
実際に黒字になる確率は極めて低いと思います。
これまでにも、飛行場を始め同じような試算をして建設された多くが
採算割れしています。
「基準ありきで、そこに合わせる政策」
それが日本の役人が主導する政策にはよく見られます。
結果として、不必要なものまで作ってしまうのです。
このような事例は枚挙に暇がありません。
それにも関わらず、その虚像のままを報道している新聞にも大いに
問題があると私は感じます。
上手く行っていない施策であれば、それは事実として
しっかり書くべきです。
役人が発表するままに報道しているだけでは、
脳天気に過ぎると言わざるを得ないでしょう。
==================================================
この大前研一のメッセージは8月18日にBBT Chで放映された
大前研一ライブの内容を抜粋・編集し、本メールマガジン向けに
再構成しております。
==================================================
✅KON480のキーワード・キーセンテンス
1「銀行は融資の際、必ず『抵当』を前提とします」
日本の銀行は、融資の際、「抵当」を要求するだけでなく、中小企業の場合には経営者に「個人保証」も要求します。
そのため、企業が破綻した場合には、経営者は破産するだけでなく、抵当もすべて持っていかれます。再起することができません。
また、中小やベンチャー企業はそもそも十分な「抵当」や「担保」がありません。融資を依頼しても、門前払いとなることが多くありました。
何が言いたいかと言えば、日本の銀行はリスクを負わないのです。
米国では、「個人保証」はつきません。そのため、破産しても再生することができます。
つまり、敗者復活ができます。
融資して後、融資先が破綻したら融資した者の責任という考え方です。
このような状況が長らく続きましたが、岸田首相がスタートアップ企業育成のため、個人保証がなく、無担保で融資する制度を新設しましたね。
経営者保証いりません!「スタートアップ創出促進保証制度」は起業家・創業者の味方
日本経済の潜在成長力が低下している中で、経済活性化の起爆剤としてスタートアップと呼ばれる創業間もない企業を後押しする政策が動き出しています。2023年3月15日に始まった創業期の資金調達を支援する「スタートアップ創出促進保証制度」です。


2「エンジェル(投資家)」
日本にはまだその存在が目立たないですが、エンジェル投資家は確実にいます。
手元に「エンジェル投資家」を理解するためにうってつけの本があります。
その名も『エンジェル投資家』(ジェイソン・カラカニス 滑川海彦・高橋信夫 訳 孫泰蔵 日本語版序文 2018年7月16日 第1版1刷発行 日経BP社)があります。
著者のジェイソン・カラカリスはビジネス書の作家ではなく、「1000万円を100億円にしたカリスマ投資家」(帯の表記)です。
さらに言えば、まさにエンジェル投資家です。
この中からごく一部を引用します。
エンジェル投資というのは立ち上げ最初期の非公開企業に投資し、投資した以上のリターン(利益)を得る。一般的かつ安全な投資に比べてはるかにリスクが高く、それだけ期待するリターンも大きい。
ほとんどの場合、エンジェル投資の期間は3年以内だ。投資相手の会社は実績が少ない、あるいはゼロだ。そしてプロダクト・マーケット・フィットのために切実に資金を必要としている。彼らが考え出したビジネスが完全にクレイジーでない場合、投資家にはこと欠かない。つまりエンジェル投資家の出る幕はない。実際、われわれが「エンジェル投資家」と呼ばれるのは、スタートアップの創業者のビジネスモデルを信じる者がひとりもおらず、絶体絶命となったとき天使よろしく窮地から救い出す役割から名付けられたのだ。
pp. 32-33
プロダクト・マーケット・フィットというのは、スタートアップの創業者が考え出したコンセプト(ウーバーならライドシェリング、インスタグラムならフィルターと呼ばれる写真加工機能)に対して、それを実際に使ってエンジョイするユーザーを見つけるプロセスを指す。大勢の人々があるプロダクトを使い、それを楽しんでいるなら、成功が保証されたわけではないとしても、そのビジネスには成功のチャンスが十分ある。
p. 33
KON481【ルネサスエレクトロニクス・シャープ・ソニー~ビッグデータ分析事業の課題を考える】 ~大前研一ニュースの視点~ 2013/08/30 8:28
🔴メルマガ全文
┏━■ ~大前研一ニュースの視点~
┃1┃ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┗━┛ 『ルネサスエレクトロニクス・シャープ・ソニー~ビッグデータ分
析事業の課題を考える』――――――――――――――――――――――――――――――――――
ルネサスエレクトロニクス 鶴岡、甲府工場を閉鎖へ
シャープ マキタがシャープへの出資を決定
ソニー ビッグデータ分析に参入
-------------------------------------------------------------
▼ ルネサスエレクトロニクスもシャープも、経営方針が曖昧になっている
-------------------------------------------------------------
経営再建中の半導体大手、ルネサスエレクトロニクスは2日、
生産体制を見直し、新たに鶴岡工場を3年以内に閉鎖、甲府工場を
2年以内に閉鎖すると発表しました。
6月のトップ就任後、初の会見に望んだ作田会長は、
再度の追加リストラの可能性を示唆するとともに、車載機器と
産業機器向け半導体に注力分野を絞り、再建を目指す考えを示しました。
官民が出資し、何とかルネサスエレクトロニクスを救済しようと
していますが、現状を見ると経営体制も定まっておらず、
非常に難しい状況です。
ルネサスエレクトロニクスは、NEC、日立製作所、三菱電機の3社が
出身母体になっているわけですが、未だに合併して1つの会社として
「体をなしていない」のが大きな問題だと思います。
工場1つ1つがバラバラですし、それぞれにお客さんも異なります。
地場との関係性もありますから、工場を閉鎖するといっても一筋縄では
いきません。
出身母体同士でのせめぎ合いもあるでしょう。
これだけそれぞれの意見が異なる工場がある状況をまとめつつ、
経営再建していくというのは、よほどの経営能力がないと難しいと思います。
ルネサスエレクトロニクスと、ある意味、似たような状況に陥っていると
感じるのが経営再建中のシャープです。
シャープから出資の要請を受けている電動工具大手のマキタは
20日までに出資する方針を決定しました。
両社は5月に業務提携し、マキタが主力の電動工具で培ったハード技術
と、シャープの電子制御技術を組み合わせてロボット事業への参入などを
目指す考えで合意しており、報道によると出資額は数十億から
100億円規模になる見込みとのことです。
シャープは現預金がどんどん減り続けていて、鴻海との提携で一時的に
上昇した株価も下落し、今では完全に低迷している状況です。
そのような中、シャープは、クアルコム、サムスン電子から出資を受け、
デンソーなど様々な企業からも出資を受ける予定と報道されています。
しかし、これほど多くの企業から出資を受けてしまうと、シャープが
どこに向かって舵をきるのか?というのは、非常に難しいと思います。
出資している企業は、全て違う目的・思惑を持っているからです。
このシャープの状況は、ある意味、ルネサスエレクトロニクスと同じで
す。
私からすると、マキタがシャープと組んでロボット事業を展開できる
イメージが湧かないのですが、それでもマキタは堅調な経営を
していますから良いでしょう。
問題なのは、このような形での出資が、結局シャープの経営再建の
解決策につながらないのではないか、ということです。
-------------------------------------------------------------
▼ フェリカの活用を今さら考え始めても、もう手遅れ
-------------------------------------------------------------
ソニーは19日、電子マネーに使われる自社開発の非接触ICカード技術
「フェリカ」で、ビッグデータ分析事業に参入すると発表しました。
フェリカはJR東日本のスイカなど国内商用ICカードのほとんどに
使われており、累計発行枚数は6億6千万枚を超えています。
この技術基盤を持つソニーが情報漏洩リスクを減らす新技術を開発、
事業化することでビッグデータの国内利用に弾みがつく可能性もある、
とニュースでは報じられていますが、私は無理だと思っています。
そもそも、このような事業展開については10年前に
私がすでにソニーに提案していることです。
例えば、ある個人の行動についてICカードの移動データから、
仕事帰りの移動だと分析できれば、帰りに立ち寄れる家の近くの
デパートの特別ディスカウントをオファーすることが可能になるでしょ
う。
フェリカの機能を使えば、さらに様々な「仕掛け」が考えられますが、
当時のソニー経営陣は私の提案には興味を示さずに、フェリカを
部品にしてバラ売りしてしまいました。
当時から、ソニーが主導権を握って「仕掛け」を構築していれば
良かったのですが、今となっては発行枚数6億枚といっても、
それぞれデータの所有者が違っていて、統一されていません。
あるデータはJR東日本で、あるデータはJR西日本、あるいは
決済データはJCBといった状況です。
これを共有化することは、今さら不可能でしょう。
もし当時から、ソニーがフェリカをバラ売りせずに、
最初から「仕掛け」を作って全体像を描いたビジネスを展開していれば、
世界制覇も可能だったと私は思います。非常に残念です。
世間ではビッグデータという言葉が、一人歩きしている節があります。
そもそもスモールデータの分析すらできていないのに、
ビッグデータの分析はできません。
スモールデータで発想を固めて、それをビッグデータに
活用していくから上手くいくのであって、最初から闇雲に
ビッグデータをかき回しても、何も生まれません。
今のソニーは、ビッグデータという言葉に踊らされている
だけだと感じます。
==================================================
この大前研一のメッセージは8月25日にBBT Chで放映された
大前研一ライブの内容を抜粋・編集し、本メールマガジン向けに
再構成しております。
==================================================
✅KON481のキーワード・キーセンテンス
1「ルネサスエレクトロニクス」
ルネサスエレクトロニクスの基本情報は次の図表をご覧ください(2023/11/16 終値)。

「半導体大手。ルネサスとNECエレが統合。車載マイコン世界トップ級」であることが分かります。
ただし、気にかかることがあります。
下記の記述をご覧ください。大株主に大きな異動があります。

(株)INCJ<旧産業革新機構>が段階的に売却している一方で、「米ブラックロックは保有割合が5%を超えたと報告」(2023/1106 16:44)という記載があります。
日本では保有割合が5%を超えると報告しなくてはならないという、5%ルールがあります。そのルールに則って報告したことになります。
トヨタ自動車の保有割合(3.83%)より多くなります。
実際にこの記事を見てみましょう。

今後、同様な外国企業による株式取得が増加することが予想されます。
このような事実を、日本企業の成長性に期待した外国企業による株式保有と捉えるべきなのでしょうか?
私はそのように解しています。
なぜなら、米ブラックロックは世界最大の資産運用会社だからです。
ブラックロック(BlackRock Inc.、NYSE: BLK)は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である。
2021年末における同社の運用資産残高(AUM)は10兆ドル(約1,153兆円)と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。日本ではブラックロック・ジャパン株式会社としてビジネスを展開しており、365名の社員が在籍している(2020年3月末時点)。
2「フェリカの機能を使えば、さらに様々な『仕掛け』が考えられますが、当時のソニー経営陣は私の提案には興味を示さずに、フェリカを部品にしてバラ売りしてしまいました」
ソニーが開発したフェリカの活用方法を大前氏が提案したのにも関わらず、当時のソニーの技術陣や経営陣は首を縦に振らなかったということですね。
フェリカのその後の経過を考えますと、戦略の失敗と言わざるを得ません。
ソニーの技術陣としては「専門外の人間が言うことなど聞けるか」という気持ちだったのでしょう。
残念なことです。
フェリカについて調べてみました。
FeliCa(フェリカ)は、ソニー(後のソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズを経て2代目ソニー=旧:ソニーモバイルコミュニケーション ズ)が開発した非接触型ICカードの技術方式、および同社の登録商標である。
駅の改札口で交通系ICカードをタッチしたり、コンビニエンスストアで電子マネーを利用したり。いまや、あちこちで見られる“かざす便利”をつくりだしたのが、ソニーの非接触ICカード技術方式「FeliCa」です。非接触だから、かざすだけで高速データ送受信。さらに、データは何度も書き換えられ、カード本体を再利用できるエコロジーなシステム。厳重なセキュリティーも実現し、公共交通機関の乗車券システムから、電子マネー、マンションの鍵まで幅広い用途で使われています。これからも、Felicity(至福)に由来する名前どおり、「FeliCa」は世の中をもっと便利に楽しく変えていきます。
どのようなところで使われているのでしょうか?

普段私たちが利用している改札機が挙げられます。
Felicaの特長

他にはこんなところで使われています。
下の画像および解説文は「"かざす便利"をつくりだす。ソニーのFeliCa」というタイトルのSONY公式ウェブサイトから借用しました。

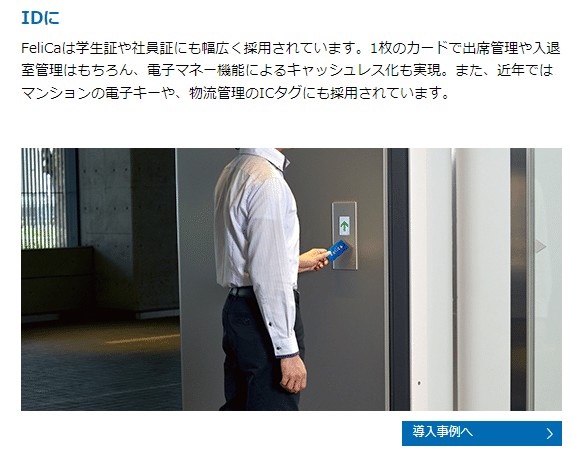



いろいろな場面でフェリカが使われていることが分かりましたが、残念なことに、フェリカという名称も機能も一般にはあまり知られていないことです。
✒ 編集後記
「メルマガ 大前研一 ニュースの視点」を読み返してみると、当時のことが断片的に思い出されてきました。10年という歳月が流れましたが、ところどころ記憶に残っていた個所があり、またその後の経過を確認することができています。
ちょうど10年前のメルマガですが、今読んでみても、学ぶことがたくさんあります。それは執筆当時の事情がどうであれ、普遍性のある考え方や、ものの見方、発想力、構想力、具体的な例を挙げて説明する方法、自ら実践することなど、そうしたものをすべて含んだプレゼンテーション能力の高さに圧倒されます。
ただし、私は大前氏を私淑していますので、あなたから見ると「傾倒しすぎだよ」と言われそうですが……。
栄枯盛衰は世の常です。
それは、企業においても、個人においてもしかりです。
以前であれば、一流企業は安泰で、そこに勤務していれば定年まで安心して働けるという共通認識がありましたが、現在では「一瞬先は闇」です。
大前研一氏の先を見通す力や発想力、構想力、分析力、発信力、その他にも多数ありますが、私には何一つ追いつけるものはありません。
それでも、大前氏をグル(「指導者」「教師」「尊敬すべき人物」「師匠」)と仰ぎ、書籍や動画などを通じて、これからも間接的に指導を受けたいと思っています。
(22,019文字)
✑ 大前研一氏の略歴
大前 研一(おおまえ けんいち、1943年2月21日 - )は、日本の経営コンサルタント、起業家。マサチューセッツ工科大学博士。マッキンゼー日本支社長を経て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校公共政策大学院教授やスタンフォード大学経営大学院客員教授を歴任。
現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長、韓国梨花女子大学国際大学院名誉教授、高麗大学名誉客員教授、(株)大前・アンド・アソシエーツ創業者兼取締役、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長等を務める。 (Wikipedia から)
大前研一氏の略歴補足
大前氏は日立製作所に勤務時、高速増殖炉もんじゅの設計を担当していましたが、原発の危険性を強く感じていたそうです。
MITで原子力工学の博士号を授与されています。原子力の専門家でもあり、世界的に著名な経営コンサルタントでもあります。
世界一の経営コンサルティングファームのマッキンゼーに転職。
マッキンゼー本社の常務、マッキンゼー・ジャパン代表を歴任。
都知事選に出馬しましたが、まったく選挙活動をしなかった青島幸男氏に敗れたことを機に、政治の世界で活躍することをキッパリ諦め、社会人のための教育機関を立ち上げました。BBT(ビジネス・ブレークスルー)を東京証券取引所に上場させました。
大前氏の書籍は、日本語と英語で出版されていて、米国の大学でテキストとして使われている書籍もあるそうです。
「大前研一 ニュースの視点」というメルマガに登録したのは10年前のことです。毎週金曜日に配信されています。
2013/03/03 0:28
〓〓「大前研一《ニュースの視点》」に登録いたしました!〓〓
この度は、無料メールマガジン「大前研一《ニュースの視点》」に
ご登録いただきありがとうございました。

🟡メルマガについて
メルマガに登録して、最初のメルマガが配信されたのは2013年3月8日(金)のことでした。
「大前研一 ニュースの視点」の通し番号にKON・・・となっています。
KO は Kenichi Ohmae です。N はナンバーです。
さて、私に最初に配信されたメルマガのタイトルは下記のようになっていました。
KON456【北方領土問題と韓国の新大統領~長期的な時間の流れで考える】 ~大前研一ニュースの視点~
通算で456件目だったのです。そのため、1~455のメルマガを読むことはできません。
ところが、調べてみたところ、2006年3月24日(当時は#106)以降であれば読めることがわかりました。

いずれの日にか、バックナンバーも取り上げます。
クリエイターのページ
メルマガ 大前研一 ニュースの視点
大前研一 名言集
堀紘一 名言集
カリスマコンサルタント 神田昌典
考え方
サポートしていただけると嬉しいです。 サポートしていただいたお金は、投稿のための資料購入代金に充てさせていただきます。
