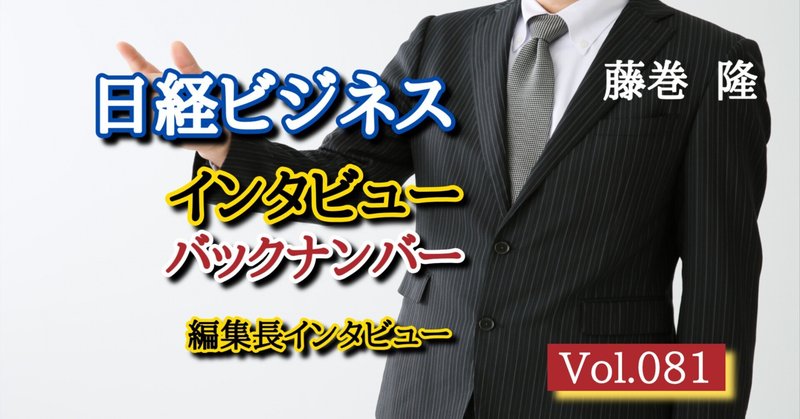
日経ビジネスのインタビュー バックナンバー Vol.081 2013.8.12-19
日経ビジネスのインタビュー バックナンバー Vol.081 2013.8.12-19

髙山 善司(たかやま・ぜんし)氏
1962年生まれ。長崎県出身。86年、西南学院大学商学部を卒業後、ゼンリンに入社。一貫して営業畑を歩み、住宅地図の販売と誌面広告の獲得でトップセールスを誇る。2006年、取締役兼営業本部長に就任。2008年、8人抜き、45歳で社長に就任。4代目、初めてのたたき上げ社長だ。2013年3月期は売上高549億9100万円、営業利益55億8500万円。前年同期比で増収、営業増益。スマートフォン向けの地図データ配信サービスが業績を牽引している。
2013.8.12・19
“地図出版社”から脱却する 2013.8.12-19
高山 善司(たかやま・ぜんし)氏
[ゼンリン社長]
2013年3月期、スマホ向けなどのデータ配信事業の売上高は141億円。
昨年同期比33%増でした。全体の売上高549億円に対して25%を占めるようになり、かつては稼ぎ頭だった地図出版事業を抜いて、今ではゼンリンの主力事業になっています。
グーグルとは2005年からライセンス契約を交わして地図データを提供しています。
今後は、付加価値を高めて有料でのサービスにも力を入れたい。今はどんなコンテンツにすれば利用者に納得してもらえるか模索しているところです。今までになかった斬新な機能を出す必要があります。
建物名だけでなく、その中にある設備や提供しているサービスまで地図で表そうと考えています。完成すれば、例えば「宅配便」を検索すれば、宅配便を扱っているすべての場所が地図上に表示されるという形です。
地図データは軍事的な問題から国によって管理が難しいため、これまではなかなか海外に進出を果たせませんでした。
ですが今後はインドを足がかりに、ゼンリン流の地図を世界に広めたいと考えています。
ゼンリンは地図情報はカネになる、ということに逸早く気づいた会社と言えるでしょう。
今までに熟練した技術者が作成してきた地図を、電子化することによって使い回しができ、いかようにも加工することができるようになりました。
1つのデータを何倍にも売ることができるのです。
コストを下げることができ、利益率を大幅に向上させることができます。
WindowsなどのOSやアプリケーションの販売と同じですね。
最初に作成するときにはコストがかかりますが、大量にコピーすることによって、売れば売るほどコストは小さくなっていきます。
ほとんどDVD1枚のハードウェアだけの値段になります。
書籍も同様です。初回の出版だけではあまり利益が出ません。もちろん、ブロックバスター(急激な莫大な売上)になれば話は別ですが、そんなことはあまりありません。
ですが、素早く重版になり、第2刷、3刷・・・となってくると印刷と製本だけがコストとなり、利益は爆増します。
さらに言えば、紙媒体ではなく、ネットからダウンロードできる電子書籍の場合には、印刷・製本が不要になりますから、ほとんどコストがかからず、利益が青天井になることさえあります。
🔷 編集後記
この元記事をアメブロに投稿したのは、10年前のことです(2014-02-14 23:21:52)。そして、オリジナル記事は11年前のものです。
読み直してみますと、「こんなことも書いていたのだな」「この個所に関心があったのだな」ということが思い出され、当時の自分の心境に思いを馳せています。
それだけ歳をとったのだと実感しています。
編集長インタビューの記事を読み返してみると、当時の経営者の心意気・信念・余裕・揺るぎない自信といったものが伝わってきます。
月日が経ち、自分だけでなく身の回りにも、環境にも変化があります。
しかし、経営に限らず、物事の本質は変わらないものです。
グーグルとは2005年からライセンス契約を交わして地図データを提供しています。
今後は、付加価値を高めて有料でのサービスにも力を入れたい。今はどんなコンテンツにすれば利用者に納得してもらえるか模索しているところです。今までになかった斬新な機能を出す必要があります。
🔴「グーグルとは2005年からライセンス契約を交わして地図データを提供しています」
このインタビューが行われたのは2013年8月9日のことです。
この日を基準にすれば8年も前に、今(2024年6月6日)から換算すれば、実に19年前からグーグルとライセンス契約を締結しています。
先見性がありました。行動力が素晴らしい。このプロジェクトは余程確信に満ちたものだったのでしょう。敢えてリスクを負ってビジネスを進めたのです。
✴️ もう少し、インタビューの内容をご紹介します。
ゼンリンのキラーコンテンツは住宅、建物1軒、1軒に居住者の名前が入っている住宅地図です。1948年の創業以来、足で調査する方法は基本的に変わっていません。アルバイトを含めた1000人の調査員が毎日、街を回って表札を確認して、情報を更新しています。
この蓄積は大きい。この膨大なデータを使っていかに見せ方を工夫するか、知恵を絞っています。
(中略)
1984年から始めた地図のデータベース化、つまり電子化です。
実は電子化を進めたのは販売目的ではなく、地図製作の合理化のためでした。それまでは手書きで地図を作っていました。専門の職人が道路を書くための製図用具など特殊な道具を使って、線を引き、手書きで居住者の名前を書いていたんです。そうした職人の方々も引退して数が減ってしまい、だんだんと地図が作れなくなるという兆候がありました。
(中略)
AR(拡張現実)技術もさることながら、今後、カーナビの一番大きいイノベーションは自動車の自動運転への対応です。
これは各自動車メーカーが取り組んでいますが、GPS(全地球測位システム)衛星による地図上の位置決めだけではなく、標識から何mで止まるか、どこにカーブがあるのか、そうした情報が別に必要になってきます。
つまり、従来の地図データだけでは足りない。新たな切り口で地図を捉えると全く別の情報を取り込む必要があるのです。
🔴AR(拡張現実)技術もさることながら、今後、カーナビの一番大きいイノベーションは自動車の自動運転への対応です。
この個所には正直驚きました。今でこそVR(仮想現実)ばかりか、AR(拡張現実)やMR(複合現実)という概念は一般的に広まってきていますが、10年前には専門家やごくわずかな人たちにしか認識されていなかったと考えられるからです。
自動運転についても同様です。自動運転は「そうなればいいな」という夢でしかなかったことが、現在では実現に向けて進んでいます。法制化の問題が関わるため、単なる技術面での対策だけでは解決しません。
では、ゼンリンの現在のビジネスはどうなっているでしょうか?
株探で見てみましょう。


PBR(株価純資産倍率=)は1倍割れしています。東証プライム銘柄なので、早く1倍を超えてもらいたいですね。

(ピービーアール/かぶかじゅんしさんばいりつ)
SMBC日興証券
1株あたり純資産は、いわば企業の(帳簿上の)解散価値といえますから、PBR=1倍は、株価とこの解散価値が同じ水準と判断されるのです。
(ピービーアール/かぶかじゅんしさんばいりつ)
SMBC日興証券
2024年3月期(第64期)決算

<Ameba blog (Ameblo) に投稿した当時の解説記事 2014-02-12 23:30:14>に触れてみます。
⭐️「はじめに」に書きましたように、携帯やスマホ版のサイトは、2007年1月から2013年7月まで毎週掲載してきました。
1ページに1カ月分(4回から5回)をまとめて掲載しています。
オリジナルの「編集長インタビュー」から特に印象に残った言葉を、ご紹介する形式を採っていますので、1週ごとの量は少なめです。
このため1カ月分のインタビュー内容を1ページに取りまとめています。
このブログでは、この形式を採用せず、毎週1回「編集長インタビュー」から一部を抜粋し、ご紹介していきます。
ブログの可能性を引き出せるように、いろいろな試みをしていきたい、と考えています。
例えば、互いのブログを紹介しあう「相互リンク」はその1つでしょうし、コメントやトラックバックもそうでしょう。
さらに、携帯やスマホ版のサイトでは、特に携帯ではデータ処理量が少ないために、表示できなかった画像データも、ブログ版では意識せずに扱うことができます。
掲載した記事に、私のコメントを追加することを考えています。
特に制約は設けず、自由に書いていきたい、と思っています。
インタビュイー(インタビューされる人)に関連した事柄や、業界の動向など書きたいことはたくさんあります。
たくさんのコメントをいただけると、とても嬉しいです。批判的なことでも構いません。
あなたがご存知の情報で公開することに問題がなければ、ぜひコメントをお書きください。お待ちしています。
『日経ビジネス』について付け加えることがあります。2つあります。
1つは、発行日付です。
普通、週刊誌の発行日付は発売日よりも1週間先の日付になっていますね。
今朝 (2013年8月1日) の新聞に掲載されていた、『週刊新潮』も『週刊文春』も8月8日号となっていました。これが普通ですね。
ところが、『日経ビジネス』は、毎週金曜日に指定した場所(主に自宅)に届けられ、発行日は翌週月曜日になっています。
つまり、最新号は8月2日に届き、8月5日号ということになります。
日経ビジネス編集部は、『日経ビジネス』の最新のホットな情報をできるだけ早く伝えたい、という方針を徹底しているからではないか、と考えられます。
もう1つは、サイトとの連動と独自コンテンツの配信です。
日経ビジネスオンライン (現在は日経ビジネス電子版)というサイトがあり、雑誌で掲載できなかったその後の進展に関する記事やサイト独自の記事を配信しています。
有料のスマホやタブレット、PCで閲覧できる独自配信の記事があります。
いろいろとお話してきましたが、当ブログは『日経ビジネス』の「編集長インタビュー」から特に印象に残った言葉をご紹介するブログです。
これからよろしくお願いします。
1回の投稿ごとに1カ月分にまとめたインタビューの概要を掲載します。
2007年1月8日号からスタートし、2013年7月までの6年7カ月分のバックナンバーだけで79件あります。
途中、数件記事が抜けている個所があります。
データを消失してしまったため現時点では再現できませんが、日経ビジネス電子版では「2011年10月から最新号まで」のバックナンバーが閲覧できるようですので、抜けている個所に該当する部分が見つかれば、追記します。
⭐ 『日経ビジネス』の電子版セット(雑誌+電子版)を「らくらく購読コース」で2022年9月12日号 No.2157 から定期購読をスタートしました。
⭐「日経ビジネス 電子版使い方ガイド」(全24ページ)を見ると
「雑誌『日経ビジネス』のバックナンバーの閲覧について」で、
閲覧できるのは2011年10月から最新号と書かれています。
そのため、2008年8月18日、25日分の記事は確認できません。
しかも紙の雑誌は、はるか昔に処分しています。
『日経ビジネス』の記事を再投稿することにした経緯
再編集して再投稿することにした理由は、次のとおりです。
自分が当時どんな記事に興味があり、どのような考え方をしていたのかを知りたいと思ったからです。
当時の自分を振り返ることで、当時と現在で考え方は変わったか否か、あるいは成長しているかを確認したいと思いました。
記事データは当然古くなっていますが、本質的な部分は必ずあるはずで、しかも普遍性があります。その個所を再度学んでみたかったのです。
さらに言えば、『日経ビジネス』のバックナンバーをご紹介することで、この記事に目を通していただいたあなたに何らかの有益なヒントを提供することができるかもしれない、と考えたからです。
「私にとって、noteは大切なアーカイブ(記録保管場所)です。人生の一部と言い換えても良いもの」だからでもあります。
(プロフィールから)
(5,184 文字)
クリエイターのページ
日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)
日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)
日経ビジネスの特集記事
サポートしていただけると嬉しいです。 サポートしていただいたお金は、投稿のための資料購入代金に充てさせていただきます。
