
対話考#2「対話を避ける文化」 【連載】
1 #1の補論
前回は、対話の要は「聴くこと」だと、音楽の例えを使ったりして考えてみました。
今後、「対話」に関して、筆者の中で知のアップデートは起こりうるでしょうが、この「聴く」原理だけは、変わらないかと思います。
西條剛央さんが提唱された「肯定ファースト」も、正に「聴く」原理だなぁと思います。
今のところ筆者は、「対話」とは大変広い概念だと思っており、明確に「コレ!」と指し示すことはできていません。
指し示せないというのは、
向かい合う者同士の「聴くという役割の自覚=心のあり方」を起点に、「対話っぽい雰囲気」が出現すると考えているからかもしれません。
では、実体のない雰囲気を作り出すには、どんなマインドセットになればいいのか。
解決をメインとするか、聴くことをメインとするか、それだけの違いです。とはいえ、そんな断言するように言われても、当の私たちは「現実的には難しいんだよな」と思ってしまいます。
たったそれだけの違いなのに、やっぱり心が乗らない。
ところで、「解決をメイン」とか「聴くことをメイン」とか区別するというのは、後天的な考え方です。つまり、意識して取り組もうとしているあらわれです。なぜ私たちは意識する必要があるのでしょうか。
少なくとも「モテない男」の筆者は意識することが必要ですね笑
2 なりたいのになれないのはどうして?
そこで今回は、なぜ私たちは意識しないと対話できないのかを、日本人の特質を探ることで考えていきたいと思っています。
一旦、以下のリンクを読んできてください
はい、お帰りなさい。
では、このエピソードを分析してみます。
筆者の認識構造(現象をこう捉えている)を説明すると、
・筆者のしてしまったクレームは「問題解決のための独白(モノローグ)」
・横入りされたその場面で意見を交流させるのが「対話(ダイアローグ)」
となりましょう。
筆者は、病院の予約受付時に横入りされ、その場では何も言えませんでした。そしてのちに、病院にクレームを入れたことに対して、「対話」を阻む日本人的な思考が邪魔をしたと解釈しています。
相手のことを「聴き」、自分の考えていることを「述べる」という「対話」が起こりづらいのは、本当に筆者だけなのか?
もしかすると、あのような場面が急に起こると「意見する前に、心に壁ができるんだよね。」と思う人は、案外たくさんいるのでは?
そしてその壁の正体は一体なんなのだろうか?
いろいろ突き詰めたくなります。
そして、もしかすると、当時の筆者、そして日本人全体として「対話」が起こりづらい状況にあるのは、なんらかの障壁が根底にあるのではないかとの仮説を立てました。
とはいえ、日本人は「真面目」「努力家」「謙虚」といった、テレビで毎年ひっきりなしに放映される愛国番組のようなステレオイメージで語る気はないです。
また、「筆者は争いを避ける気質だから口論を起こさなかった」そういう単純な話でもなさそうなのです。
そして筆者は、仮説検証の糸口を「民俗学」に求めることにしました。日本風土・文化というダイナミズムで捉えた方が、「なぜ筆者が対話を避けようとしたのか」に、より本質的に迫るかもしれないと直感があります。
民俗学的ということは、つまりは「日本人としての筆者」というアプローチです。
3 「ワタシ」と「私」を区別し、制する。
「病院」の一部始終をエピソードに持ってきたのは、高齢者と若者が物理的に近づく場(つまり異世代交流の場)にもなっていると考えているからです。
そういう、価値観の「対立」は両者で確実に起こっている状況下なのに、なかなか「対話」は起こらないのが日本なのです。
日本人って不思議です。
個人の意見を持ってるんだか、周りに合わせたいんだか、わからない。
どちらの思いも存在するのでしょうか。
それとも、愚痴やお酒でストレスを発散して、我慢しているのでしょうか。
さて今から、病院当時の気づきや感情を傍に置いて、文献を引用しながら自分に問うてみようと思うのです。
『日本的思考の原型/高取正男(2021)ちくま学芸文庫』では、日本の生活文化の伝承主体を問い、私たちの精神の特徴や課題がどこにあるのかを浮き彫りにしています。読みやすい文体で、民俗学の良い入門書だと感じます。
本書の軸は大きく3つあります。あとがきとしての阿満利麿さんの解説を参考にまとめています。
筆者エピソードの考察に関わるのは、特に②ないし①です。
①近代以前の日本人には、所属する家族や組織、地域に自分を一体化させて自分を認識する傾向が強かったこと(=「ワタシ」)。
→それが、日本人の「自我」を二重構造にし、「本音と建て前」を生んでいる。
②近代以後、家・ムラと対立しようとする西洋風「自我」を取り入れたこと(=「私」)。
→それを「接ぎ木」現象と称し、台木を「ワタシ」、接ぎ木を「私」とした。
→知識人の多くは、新たに身につけた「私(共同体から自立する自我))」だけで物事を理解しようとして、その意識下の「ワタシ(共同体と同一する自我)」には無関心を装いがちである。
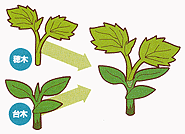
基本となる台木と、くっつける穂木を一体化させる方法である。
https://www.ja-m.iijan.or.jp/info/kouhou/kids/000079.html
③おのれを託した共同体から疎外された時、旅や漂泊の暮らしも確固とした形式だったこと。
→このような放浪者の自我「ワタシ」の依存先が、神仏の加護だったのかもしれないという考察。
→また、移住の暮らしの中から独自の神観念が生まれたのではないか、とし、それが日本人の神観念に対応して重層性を帯びているのではという考察。
特に、イラストまでつけている②ないし①の話にヒントを見出しています。「私」と「ワタシ」の接ぎ木比喩です。イラストでは穂木となっていますが、本稿では接ぎ木と呼びます。
「ワタシ」という台木
(=所属する共同体に自分を一体化させて自分を認識する自我)
と
「私」という接ぎ木
(=家・ムラと対立しようとする西洋風「自我」)
の構造を知って、なるほどと腑に落ちたのです。
そして、とどめの一手。
本書(日本的思考の原型)で一貫して協調されていることは、日本人の思考が世間の常識が是とする考え方、見方に尽きているのではなく、かならず、もう一つの思考や感覚がまるでその「影」のように付随しているという点である。
つまり、私たち日本人には、世間の常識(近代的な知識・言説)に、民俗としての共同体意識が影のように付随しているというのです。
面白いです。
病院エピソードを再考してみましょう。
あのエピソードの中で「対話した方が良かった」と嘆く自我は「私」です。つまり、これまでの西洋的な経験・西洋の知識から、「対話」状況に一定の価値を見出しています。近代的な論理の中で「意見を言ったほうがいいよ」と思う「私」。
一方で、郷に入っては郷に従え、を体現したのは「ワタシ」です。そういえば、別の感情を思い出しました。横入りされた直後感じた「ここで言い返して、住んでいる地域の人たちに村八分みたいなことをされたらどうしよう。」という疎外を恐れる気持ち。やはり筆者は、地方に在住している時大切なのは、まずその土地の文化を取り入れることと思っています。
上記の考察で筆者が感じていたモヤモヤは、「対話したいけど、したくない」といった、いわゆるアンビバレントな感情とはちょっと違うことがわかってきました。
「付随」しているんですね。
「従属したい日本人の台木」に、「対話したい西洋の論理」がくっついてきているんです。
筆者や筆者が育った言論環境(家、学校、本、職場)には近代以前、台木のように共同体としての感覚があった。そして、その言論環境に、近代化以後、西洋的な言説が取り入れられた。
150年前の近代化が、あまりに急だったために、私たちの言論環境は未だ整理できていないのです。整理というよりは、「ワタシ」が無意識下に押し込められた。そしてそれが、現代人の身体を脈々と流れている。
だから、たとえば古代ヘレニズムの「ソクラテス的、プラトン的「対話」が大事だ」と啓蒙されても、「面白い!」と思う一方で、「現実的には無理じゃない?」と思ってしまうのかもしれません。
この「現実的に」というのが、台木「ワタシ」の感覚です。自分の所属する共同体に「対話」を申し込むことは、なんか言いづらい。
同時に、この影の「ワタシ」の存在こそ、筆者のモヤモヤの正体ではないかと思うのです。2章で、「解決メイン」「聴くことメイン」の意識について述べました。
言い換えれば、日本的な「ワタシ」は「解決メイン」です。今ある共同体・集団は恒常的なものと捉え、変化とはトラブルです。解決して、元どおりになろうとします。
一方で、西洋の論理「私」は、「聴くことメイン」です。共同体の中にいる個人が大切なので、個人に合わせて流動的に進もうとします。本気で「聴く」というのは、聴いたことを取り入れるということです。つまり変化ありきだということです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
