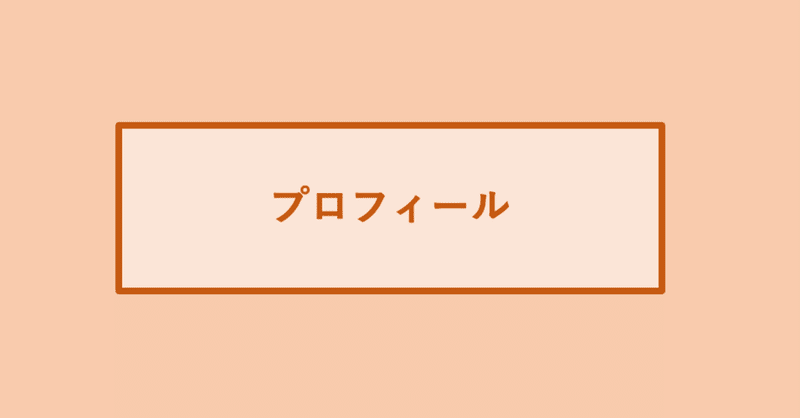
プロフィール
1.いろいろな法律の基礎的理解を向上したい
社内弁護士(会社員)をやっています。余暇をつかって、租税法の本を読んでいました。大学時代、「T字型」人間になりなさいと言われたことがあります。「T」の横の棒は広い知識を身につけなさいということ、縦の棒は専門領域を持ちなさいということ、と理解していました。これをまに受けて、社会人になってからも、「T」の横の棒の部分を広げるために、いろいろな法律を基礎から勉強してきました。ちなみに、専門領域は、金融法です。
「T型人材」とは、専門的な知識とスキルを蓄積し、特定の分野を究めた豊富な経験を軸に、専門外のあらゆるジャンルに関しても知見がある人材タイプのことです。
T型人材の「T」には、タテ棒が「専門性の深さ」、ヨコ棒が「知識の広さ」といった意味が込められており、ひとつの優れた専門知識やスキルをもつことから「シングルメジャー」と表現されることもあります。
専門性の高い技術と知識をもつスペシャリストであり、かつ幅広いジャンルの知見を豊富に持ったジェネラリストでもあるため、近年のグローバル化が進む社会やダイバーシティにおいて求められるニューノーマルな人材タイプともいえるでしょう。
資格試験というのは、基本的な知識を問うものなので、そのために準備をしてくれる予備校の講座、特に、入門講座は、短期間で基本的知識を叩き込む上で、便利であろうという短絡的な発想から、いろいろな、資格試験の講座を受講してきました。ティー字型人間になろうという努力のはじまりです。
2.学問への熱い想いをもった講師との出会い
そのようにして受講した資格試験の講師のなかでも記憶に強く残っているかたがいらっしゃいます。日商簿記1級の講師であった先生です。その先生は、工業簿記と原価計算を担当しておられました。郷ひろみさんのGOLDFINGER'99が流行っていたころで、「あちち」の話をされていて面白かったというのもありますが、郷ひろみさんの熱唱にこめられた熱い想いで、原価計算を愛しておられました。
予備校の講師の先生で、優秀で熱意のある講師は、たくさんいらっしゃいましたが、その先生は、一線を画されていました。テキストはすべて手作りで、1ページ、1ページが計算し尽くされていました。講義に沿ってテキストに掲載されている練習問題を解いて、次回の授業までに、問題集の問題を解くと、ほんとうによく分かるように計算して、問題集が作られていました。なによりも、その隅々から原価計算への愛情を感じることができました。
強い想いというものは伝染するもので、通信講座で受講していて、カセットテープでお声しか聴けなかったのですが、しまいには、岡本清先生の原価計算という1万円近い書籍を買って読んでいました。このような名著を読み解く能力はなく、勢いで買ってしまって後悔したのはいうまでもありません。結局、小林啓孝先生の現代原価計算講義を買って、なんとか理解して、満足したのは良い思い出です。試験には、無事合格しましたが、試験合格だけではない、なにかを感じ取ることのできる経験でした。ホーングレン教授がすごいというお話が、いまだに、想い起こされます。
簿記で、このような強烈な感情をうけとってしまい、それを法学に翻訳しようと、租税法をやってみました。簿記におもいっきり引っ張られてしまい、租税法は、法人税法が中心だと勘違いしていました。勉強しても、全然、理解が深まりません。苦しい思いをしながら、アドバイスを求めます。しかし、行政法(実体法)を理解していないとできないよ、と言われたり、行政救済法を理解できないとだめだよ、と言われたり、今となっては、いずれも的確なアドバイスなのですが、未熟なわたくしは、よくわからないまま、あきらめてしまいました。
3.大学院で研究者の熱意に触れる
その後、特許法を勉強しました。知的財産法の基本法であるところの特許法は、行政法(実体法・手続法)、私法、行政救済法が、からみ合っていて、興味深く、感じました。競争法もみてみました。発想が自由になる経験でした。ちょうど、そのころ、インターネットで、前述の先生のことを検索してみると、大学教授としてご活躍されていることを知りました。このころから、研究者と実務家の違いは、いったいなんなのだろうかと思うようになりました。大村敦志・小粥太郎「民法学を語る」(有斐閣・2015年)に出会ったのも、この頃です。荒木優太「在野研究ビギナーズ——勝手にはじめる研究生活」(明石書店・2019年)からは刺激と勇気をもらいました。勢いあまって、大学院の門を叩き、修士(法学)となりました。大学院の講義を受講して、試験ではなく、法律と対峙されている先生方に出会い、そして、その情熱の凝縮された論文というものを読む機会に恵まれるようになりました。
ところで、大学院の授業で、租税手続法、租税争訟法をとり、手続面と救済面は、なんとなくわかりました。また、国際課税法をとり、国内法と条約の適用関係を垣間みさせていただきました。しかしながら、租税実体法の授業はありませんでした。租税実体法への興味は、否応なく、膨らみます。また、研究者の先生方が精魂込めて書かれた、ご論文の端々から伝わる、豊富な勉強量、研究対象への熱意など、大学院で見聞きし、感じていることが、学習意欲を駆り立てました。
4.租税法に十数年ぶりに取り組んでみる
最近になって、土曜日、いつも立ち寄るカフェで、増井教授の租税法入門を読み、租税法の理論というものに触れ、面白いと感じました。この読書を通じて、債務負担については、純資産の増減がないので、所得はないという考え方も、そういうことかと思いました。借入金の利子は、消費ではないので、純資産の減少であるという説明は、理解するのに時間がかかりましたが、わかると面白いと感じるようになりました。簿記の経験から、資産のほうはわかりやすいのですが、消費のほうを理解するのに時間がかかりました(サイモンズの定式の話です)。むかし、いただいたアドバイスの意味が、手に取るようにわかりはじめました。そこで、いそいそと、Chapterのあとで紹介される論文を取り寄せて読んでみて、さらに、はまってしまいました。
たとえば、金子宏「租税法における所得概念の構成」同『所得概念の研究』(有斐閣、1995年〔初出1966年〜1975年〕)1頁、中里実「所得の構成要素としての消費––––市場価格の把握できない消費と課税の中立性」金子宏編『所得課税の研究』(有斐閣、1991年)35頁などです。
司法試験の問題を読んでみて、わかるようになってきたと感じたときは、嬉しかった。そこで、調子にのって、いろいろ調べてみて、ケースブック租税法というものが司法試験のネタになっていると知りました。ここでは、主に、その本に掲載された問題に取り組んでいます。すこしでも、研究者の方々の情熱にふれたいというきもちにあと押しされた取り組みですが、しんどい作業でもあります。一人で、取り組んでいると、いつのまにかやめてしまいそうなので、noteに掲載することにしました。
5.ケースブック租税法
著者のおひとりであられる増井教授によるケースブック租税法の紹介文が東京大学のウェブサイトに掲載されています。
この書籍の構想は、1980年代にまで遡るそうです。米国のロースクールのケースメソッドをとり入れるためのケースブックという明確な目的をもって創られたそうです。金子教授とそのお弟子さんであられる教授が熱い想いをもって著された書籍であることがわかりました。未公刊のteaching manualがあるそうですが、そこに掲載されている、金子教授を囲んだ著者による座談会は熱気に溢れているそうで、機会があれば読んでみたいと思いました。このような背景を知ると、本書の読み方もかわってきます。
(なお、座談会から20年が経過した2024年3月27日、弘文堂のウェブサイトで、teaching manualの座談会部分が好評されました。初版のケースブック租税法を前提とした内容なので、十分に、追い切れていない部分もありますが、熱気が伝わってくる内容です。じっくりと読んで、検討に役立てたいと思います。)
6.参考文献
回答で引用している文献は、次のとおりです。こちらは手元にあることを前提に書かせていただいております。
・佐藤英明「スタンダード所得税法〔第4版〕」(弘文堂・2024年)
・増井良啓「租税法入門〔第3版〕」(有斐閣・2023年)
間違いもあるとおもいますが、なにかの参考になれば、嬉しくおもいます。
なお、ケースブック租税法の所得税法の第2編は佐藤先生が担当されておられるので、佐藤先生のご著書と睨めっこしながら検討しております。
7.過去問の解答例の作成方針
ケースブック租税法を勉強したあとで、司法試験・予備試験の過去問を検討しております。これは、ケースブック租税法で勉強した知識を、教員の方々が、どのように応用することを期待されているのかを、体験するためにおこなっています。
このため、①出題意図あるいは採点実感において表明される試験委員の先生方の思いを、できるかぎり、汲み取ることと、②ケースブック租税法で勉強したことを、抜書き(コピー&ペースト)して作成するようにこころがけております。力不足で、うまくいかないことも多いのですが、大変、勉強になっております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
