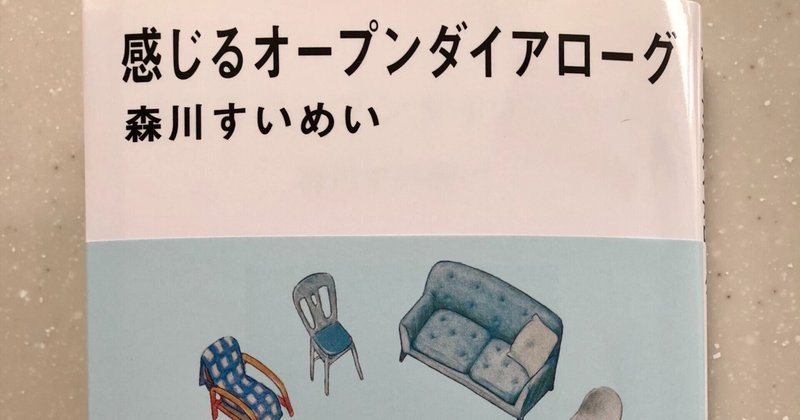
オープンダイアローグの手法も自分史の考え方と重なることに気がついた
「感じるオープンダイアローグ」というタイトルだけなら私は読まなかったでしょう。「ダイアログ」という言葉には、震災後、何度かふれており、対話の場にも何度か参加しているから、格別目新しい言葉ではなかったので。手に取りたいと思った理由は、先の投稿で取り上げた本の著者について、もっと知りたくなったからです。
オープンダイアローグ発祥の地フィンランドでは、精神を病む人の8割が投薬なしで回復しているという素晴らしい取り組みですが、冒頭で著者は「オープンダイアローグの手法を書いた本ではない」と断っています。むしろオープンダイアローグを行うことで人がどう変化したのか、その経過を書いたという。その経緯の一部が、私が考える自分史の取り組みと重なることを知り、嬉しくて心が震えたのでした。
この本の冒頭で、著者が患者さんと、その関係者を交えたオープンダイアログのシーンが描かれます。患者さんを気遣う家族、ヘルパーの方、そして言葉が出てこない患者さんを前に「私は、皆さんに幸せでいてほしいと思いました」と語る一文に心がぐいっと奪われました。その後に展開する対話。そして家族の一人がいったひとこと。解決に至るまでのシーンの切り取り方がとても上手で、先へ先へと読み進めたくなります。
その後は著者がダイアローグに出会うまでの体験記。ダイアローグの素晴らしさを知り、体得したいと学ぶ過程に、自分史めいた課題が出てくるのです。
あなたは誰なの?
困難を抱えた人たちと対話の場を持つものの責任?として、まず「自分は何者なのか」を仲間に伝え、理解してもらいます。何者なのかを伝えられない人に、見ず知らずの人が話す言葉を理解できないからという主旨だと思います。まず、自分にとって価値があるものについて語り、次に家族について語り、自分の原家族について語ります。自らが背負ったものがある人は、そこに言及することが難しい。言葉が出ない…という場面に陥ることもあるようですが、語り手の自己開示に併せて、聞き手たちはフォローの手をさしのべてくれます。この過程を綴ったやりとりがなんとも優しくて、読みながら私は付箋を貼りまくりました。
自分を語れない人に他者からの言葉は入っていかない
たとえ言葉にできなくてもいい。ただ、自分や家族に関する「鎧を着たままで」心が傷ついた人に寄り添うことはできない。そんなことを著者は書いていました。前著「その島のひとたちは、ひとの話を聞かない」を読んだあと、著者の持つ優しさに触れられたけれど、理解できなかったささやかなこと。たとえば「○○してもいいですか?」ではなく「○○します」という言葉に優しさを感じる…と書かれた、その意味が本書を読むことで理解できました。
うわべの言葉ではない。うわべの優しさではない。心からの優しさ、思い、愛が伝わる言葉遣い。弦楽器の弦をポロリとならしたような言葉遣い。それこそが人の心を揺り動かすのだと。
その本質部分で、自分史に通じるものを私は感じました。
#あなたのお話 、聞かせてください
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
