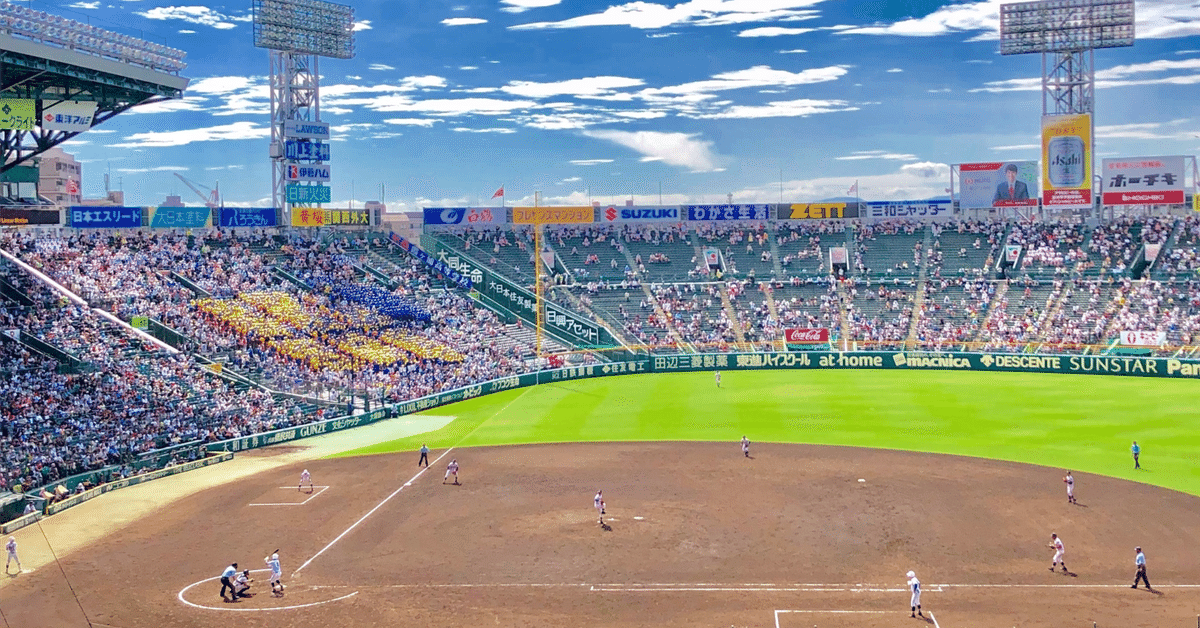
東筑 vs 九国 感想
3試合30得点と打で勝ち上がってきた東筑打線を2安打に抑え込んだ九州国際大付属が2年連続9回目の夏の甲子園出場を決めました。
福岡代表として少しでも上を目指して甲子園で暴れてきて欲しいです!!
さて今回は、本日行われた決勝戦を主に東筑に視点を置いて振り返りたいと思います。
※ここからの文章は個人の主観です。あくまで僕が感じたことであり非難や批判をするつもりはありません。
・試合前の展望
僕は戦前、決勝戦の展望としてこのようにツイートしました。
東筑が勝つ場合
— UEDA TAKENORI (@take_nr) July 26, 2023
→序盤、中盤にビッグイニングを作ってセーフティリードを作る
→3点以上の貯金を持って最終回に入る
九国が勝つ場合
→常にリードしたまま東筑打線をシャットアウト
→失点してもビッグイニングは防ぎ、2点差以内で終盤に持ち込み逆転
これまで打って勝ち上がってきた東筑と、接戦をモノにしてきた九国とでは強み・得意とする試合展開は真逆であり、東筑が勝つとするなら序盤から相手Pを攻め立てて貯金を作ったうえで終盤多少苦しみながらも貯金を切り崩しつつ逃げ切る展開が理想と考えていました。
対照的に九国が勝つ場合はロースコアの投手戦・失点したとしても大量失点を防いで終盤勝負に持ち込んだ場合、東筑打線を封じ込める力勝ちの場合だと考えました。
ですから東筑に勝って欲しい僕は得意の打撃でこれまでのような展開で勝利することを半ば祈りながら7-4というスコアを予想しました。
ということで東筑を応援する僕の福岡県大会決勝戦の予想スコアは
— UEDA TAKENORI (@take_nr) July 26, 2023
東筑7ー4九国
にします。
頑張れ東筑!
・試合結果
東筑は3回裏に三塁打で出塁を許したランナーをワイルドピッチで還してしまい1点を失うと、その後四球で出したランナーを次はセンターの打球判断ミスで長打にしてしまい2点目を失った。(結果的にこの点が決勝点になった)
4回表に2番関屋君の初球打ち二塁打で無死2塁のチャンスを作るとすかさず3番尾形君が送りバント。4番森木君の打席で相手キャッチャーのパスボールで1点を返すもその回以降ヒットが出ずに為す術もなかった。
・敗因について
敗因はなんといっても相手ピッチャーの田端投手を打ち崩せなかったことでしょう。序盤から得点を重ねて相手の打力では追いつけない所まで行き切るのが東筑の戦い方でしたが今回はこれまでのようには上手く行かず、ロースコアゲームとなってしまいました。そうなればやはり九国の方が上手で1点のリードを危なげなく守り切りました。
田端投手がとても良いピッチングをしたことも大きな要因ではあると思いますが、東筑打線にもまだできることはあったのではないかと観戦しながら思いました。
以下にそのできたのではないかと思うことを3つ挙げます。(もっとあると思いますが主なことを挙げます)
①打線としての狙い球の策定
②ハードコンタクトの徹底
③戦術の合理性について
①打線としての狙い球の策定
試合を見ていて東筑打線が狙っている球、振るべきではないとしている球がどれか分からなかったなあという印象を受けました。
これまでの試合から田端投手がどのような組み立てで打者を打ち取るのかある程度の傾向は知っていたはずでそこから打つべき球、手を出してはいけない球というのはそれなりに把握していたと思います。仮にそうしたものがなかったとしても試合中にイニング間のミーティングで球種・狙っていく球・割り切って見逃す球、の共有をすることで相手投手の攻略の方向性を定めるはずですが、今日の東筑にはそれが見受けられなかったように思いました。最後までボール球のチェンアップに手を出す、体勢を崩されるというのを繰り返していて、最終回に先頭の1番永田君がチェンジアップに当てるだけのファールフライを打ち上げて凡退したシーンは特にその象徴的なシーンでした。
左バッターは背中越しに入ってくる大きなスライダーと外角の直球の組み立てに最後まで対応しきれなかったように見えました。外角の直球とスライダーで早いカウントでストライクを重ねられて常に苦しいバッティングをしていたように僕の目に移りました。
こういう時は
「割り切って見逃し三振はOK」
「だからチェンジアップには反応しないようにしよう」
「低めの球は思い切って捨てよう」
「左バッターはインは捨てて思い切り体をぶつけるつもりで踏み込もう」
といった方針を定めることで「投手vs打者」の1対1の戦いから「打線vs投手」というチーム単位でピッチャーを攻め立てることができます。
おそらくこれまでの戦いは「投手vs打者」の単純な能力の戦いで勝てる投手と対戦してきたから打ち崩すことができたのではないかなと推察します。チーム単位での攻略が必要になったときにそれができるだけの徹底力・共有力があればなと感じる打撃内容でした。
②ハードコンタクトの徹底
初回の1番永田君の大きなレフトフライ、4回表の得点の口火となる2番関屋君のライト線二塁打くらいしか「強い」と感じる当たりはありませんでした。
中盤-終盤にかけてはなかなか打てない焦りもあってか、コンタクトに重きを置くようになってこれまでの東筑打線の怖さがなくなっていったように感じました。
なかなか出塁することができないときにはとにかくバットに当てて「何か」を起こしたくなる気持ちは分かりますが当てるバッティングは逆効果で相手を楽にしてしまいます。(カットし続けて粘るのとは別)そんなときこそ長打が必要になるのです。
なかでも「ホームラン」は打者一人で得点を完結させることができるため理想形です。相手ピッチャーが良いピッチャーであればあるほど「連打」の可能性は低くなり、複数打者での得点は難しくなります。そのため1人で完結するホームランは投手戦であるほど需要は高まると言えます。
東筑やっと長打出たけど久留米高専の外野が異常に前に出てる分頭超えたから実質センター前なんだよな。点は入ってるけど一点取るのに必要なヒット数が多い。やっぱりホームランを打って欲しい。
— UEDA TAKENORI (@take_nr) July 16, 2023
僕は常々ホームランを打って欲しいと言ってきました。今回1点差で負けたわけですがソロホームランが1本出れば同点に持ち込むことができる点差です。そんなの現実的でないと思うかもしれませんが全国的な強豪校は実際にどの打順からでも長打が出る選手を揃えてきます。
東筑もそんな打線を目指せるだけのポテンシャルは持っているので是非目指してほしいです。
③戦術の合理性について
2点先制された次の回に先頭が二塁打で出塁して次の尾形君にバントさせたがここが一つの分岐点だったと思う。「逆転」ではなく「まず1点」を取りに行ったところでこれまでの打ち勝つ野球から1点を争う思考に自ら切り替えた。これによって選手たちも打って複数点という所から目先の1点に囚われたのでは。 https://t.co/E1iz77Xmnp
— UEDA TAKENORI (@take_nr) July 27, 2023
今回の試合で一番の分岐点になったのはこの4回表のバントではないのかというのが僕の意見です。2点を先行された直後の回、東筑は先頭打者が二塁打で出塁するとすかさず「バント」を選択しました。
「バント」という戦術はアウトを1つ献上する代わりに走者を進めて「得点確率」を高める戦術です。野球のルール上3つアウトを取られる前に4つ塁を進まないと得点できないため「アウトを献上する」というのは攻撃にとても大きな影響を与えます。ランナーが本塁に近づくことで「得点する確率」は高まりますが「得点期待値(何点得点できるか)」は下がるためそのメリット・デメリット、試合状況を天秤に掛けた上で選択する必要があります。
無死ランナー単独2塁の状況で選択した「バント」には
「すぐに1点を取り返すことで主導権を引き戻したい」
という意図があったと推察します。しかし、中盤の2点という僅差と言えるビハインド(結果的には遠い2点だが)の中でまずは1点を取るという選択は些か早計、焦りがあるのではないかと感じました。県大会1試合平均10得点のチームが2点差の4回に3番打者にバントをさせるのは、東筑の試合戦略・チームスタイルからして合理性に欠けるのではないかと思いました。
結果的にパスボールで1点を返すことはできましたがランナーがいなくなったため落ち着いてその回を切られ、追いつくことはできませんでした。以降ヒットを出せず反撃の筋道を見つけられないまま試合を終えました。
この回に安易に1点を取りに行ったことで相手を楽にさせてしまった面は大いにあると考えます。
東筑打線の怖さは
「一気呵成の集中打」
「連打で一気に複数点を取る」
というところにあると考えます。先制点を取って0で抑えたい表の守備で先頭打者に狙い澄ましたように直球を弾き返されて二塁打を打たれた九国の守備陣は「ヤバい」「この回爆発するかもしれない」と脅威を感じたと思います。にも関わらず、自らアウトを献上してまず「1点」を取りに来た東筑を見て「良かった」と胸を撫で下ろしたのではないでしょうか。僕が守備者ならそう思います。
おそらく青野監督は自チームの打線に自信があり、打席を重ねれば打ち崩せるはずだ、という見立てがあってまず1点を取りに行ったのだろうなと思います。しかし結果的にはそれは誤算でしたし、例え打線に自信があるとしても2点差で3番打者にバントをさせるのは勿体ないなと感じました。
東筑は強打の打線というイメージが定着しつつありますが結構送りバントを多用するチームなんですよね。それは自分が高校生の時もそうでした。
「送りバント」という戦術は「手堅い」というイメージがあるかもしれませんが実際はそうでもなく状況によっては自ら得点のチャンスを手放すことになり得ます。下記に状況ごとの得点確率、得点期待値の表を乗せました。
これはプロ野球のデータですので一概にアマチュアカテゴリーに適用できるとは言い切れませんが参考になる部分は大いにあると思います。
東筑も今一度戦術や取り組みの見直しをしてもいいかもしれません。
・得点期待値

・得点確率

最後に
センターのミスが無ければ同点でまだ分からなかったという人もいるかもしれませんが4回以降打線が沈黙していたことを考えれば9回裏、延長TBでサヨナラで負けている可能性は高かったと思います。したがってそのifにあまり意味はないです。そもそも東筑は打って点差をつけて勝つというスタイルで勝ち上がってきたチームで、その裏には
「練習時間が短い分守備の細かいミスはしょうがないとしてそのミスが起きたとしても関係ないくらい点を取って勝つ」
という真意があると考えています。そのため打線が沈黙し、1点に抑えられた時点でチーム戦略として負けているに等しいと思います。
岡田君は素晴らしいファインプレーも見せていて良い選手だと思いました。もし1点を失った後のファインプレーが無ければ試合はより絶望的な展開になっていた可能性が高いと思います。是非高校で競技を引退せずに大学まで野球を続けて欲しいです。
また、決勝まで勝ち上がってOBや学校関係者の皆さんに夢を見させてくれた東筑野球部の皆さんありがとうございました。引退する3年生は次の目標に向けて頑張ってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
