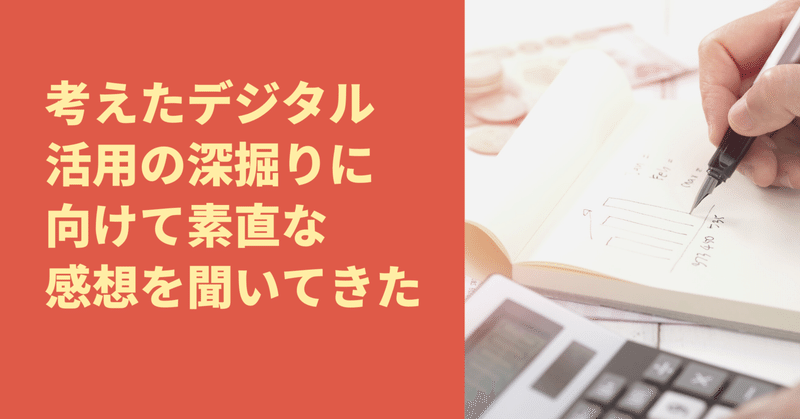
考えたデジタル活用の深掘りに向けて素直な感想を聞いてきた
取り組む対策は本当に課題解決になるのか?
デジタル技術を学習する機会が増え、今まで想像もしなかった取組みを学んだ事で誰がやっても同じ作業を削減できないかと思うようになり、実際に解決したいいくつかの課題とその対策について考えてきました。
*課題の洗い出しをしている前回記事はこちら。
今回は実際に解決を検討していくにあたり、取り組みたい課題を2つに絞った上でヒアリングとアンケート調査を実施してみました。
【課題1】投書制度のスピードを向上したい!
①自分が考えている課題感と対策
課題
改善提案に向けた確認や面談アポイントにタイムラグが生じることがある。
課題の関係者
制度を運営する事務局の担当スタッフ
会社への改善提案を希望する各部の社員
発生するタイミング
社員が課題を見つけ、グループウェアのアンケートに投稿したとき。
事務局が投稿内容を確認した後、担当者へアポイントを取得するとき。
発生要因
担当スタッフが人力でアンケート投稿を確認しているため。
投稿内容に応じた個別対応が求められる事例が有り、アポイント前に調査等で無駄に時間をかけてしまう事があるため。
考えた対策
RPA によるアンケート内容の取得と面談アポイントメールの自動化
②ヒアリング・アンケート内容
質問対象と理由
運用側と利用者側の感じる課題を把握するため、以下を実施。
事務局の上長と同僚へのヒアリング調査
各部に散っている同期社員15名への記述アンケート調査
質問項目(一部)
投書内容の確認とアポイント業務の自動化に対する印象。(ヒアリング)
制度を利用しやすい・しにくいと感じる要因。(アンケート)
事務局スタッフと連絡が取りやすい手段。(アンケート)
回答概要
好意的な回答
面談アポイントまでの自動化で投稿内容確認や対応漏れが削減できる点は良い。【事務局上長】
面談アポイントメールの発送が削減できるのは助かる。【担当スタッフ】
投稿してから時間が経つとめんどくさくなる。連絡がすぐ来るのは良いと思った。【営業担当】
否定的
投稿内容によっては面談前に事実確認をしておく必要がある案件もあるため、画一的にメール送付するのは問題ではないか。【事務局上長】
連絡ツールをメールに統一されると外回りしてるから不便。メール見るよりは電話のほうが手っ取り早い。【営業担当】
③調査を受けて
事務局スタッフからは感じている課題の方向性は賛同を得たものの、デリケートな対応が求められる点を考慮すべきとの指摘を受けた。
利用者からも相談のスピードが向上する点は評価されたが、利便性に関する興味関心のほうが高かった。
④今後の方針
投稿内容の自動収集についてはRPAツールを用いて実装を検討する。
アポイントメールについては。
【課題2】制作物の客観的な印象を知りたい!
①自分が考えている課題感と対策
課題
作成した制作物が制作コンセプトに準拠しているか、客観的な指標が無い。
課題の関係者
制作担当者
レビュー担当者(社内外問わず公開判断を下す人)
発生するタイミング
複数名への発信を予定している制作物を作成するとき。
完成した制作物の公開判断を下すとき。
発生要因
制作物のデザインは経験や勘で作成するという考えが一般的なため。
印象等を数値化するという考えが自社に無いため。
考えた対策
原稿案の色味や空白の取り方から読み手が持ちやすいイメージを数値化し、コンセプトとの乖離を評価する。
原稿案のレビュー時にレビュー対象者の表情を読み取ることで、制作物を読んでいる人の反応を 数値化する。
②ヒアリング内容
質問対象と理由
制作担当の課題感の把握と読み手が制作物を閲覧した際の反応を把握するため、以下を実施。
社内報作成をしている同僚へのヒアリング
社内報が配信されている同期社員15名への記述アンケート調査
質問項目(一部)
制作を行う際に注意している事と客観性を保つために実施している方法。(ヒアリング)
社内報等を読むときに感じる事(アンケート)
画像判別へのレビュー協力が依頼されたと仮定したときの印象。(アンケート)
回答概要
好意的な回答
社内報等を作るときは色味と字のバランスに注意している。【社内報担当者】
文章が多いものやイラストなどが無いものは正直見てないので有りかもしれない。【営業担当】
(見やすさは)文章が分かりやすいことが前提だけど、色合いやイラスト等でちゃんと読むか決めている。【オフィススタッフ】
否定的な回答
使用している色や文章量を数値化できると振り返り等の際に参考になるが、数値化できないなら厳しいのでは。【社内報担当者】
表情を読むレビュー補助ツールは認識精度を高める運用等も必要なため実用的ではないのでは。【社内報担当者】
(レビュー補助ツールについて)データが残らないとしても何となく嫌だ。【オフィススタッフ】
③調査を受けて
デザイン面への客観的なレビューへの需要が有り、実装にあたっては数値を用いたデータの蓄積と可視化が求められていることが分かった。
画像データ等を保持しない事が分かっていても表情を判別される事にマイナスイメージを持つ人が一定数見られた。
④今後の方針
色味や文章量の比率を取得するツールについては需要が見込まれたことから、画像判定を行った際の確信度を活用した補助ツールの作成を検討する。
表情を読む補助ツールについては運用面等の検討が不十分であったことが分かったため、再検討が必要。
ヒアリング等を実施してみて
自分の考えた課題に対して意見をもらえる楽しさを学ぶと共に思いついたアイデアを具体化する難しさを感じました。
いただいた回答のおかげで方針のズレや解決策に対する深掘りの甘さが少し見えたと感じます。自分のやりたいことが「本当に改善に繋がるのか?」という視点を再度持つよう心掛けつつ、ブラッシュアップに挑戦します。
もし、ご意見やご指摘ありましたらぜひお願いします。
閲覧ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
