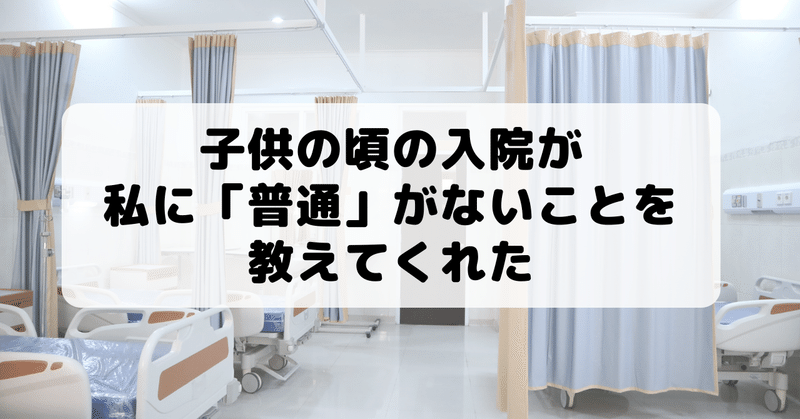
【多様性】子供の頃の入院が私に「普通」がないことを教えてくれた
私は「普通」って言葉を毛嫌いしている。
使うことを強く否定まではしないが、どうも「普通」という言葉を使われると違和感が拭えないから、やはり毛嫌いって感じ。自分ではあまり使わないようにしている。(いやまあ、そうは言っても普通に使うこともあるんだけど)
「普通は・・・でしょ」と、あたかもこの世の摂理のような、一般論みたいに使う人が多いが、すごくおかしいと思っている。
誰かひとりにとっての「普通」をそれぞれが持っているのであって、誰にも当てはまる「普通」なんて存在しない、という感覚が強いのだ。
その感覚は、自分の様々な経験の中で、「普通」に対する疑問や「普通」のせいで色々苦しんだ記憶があるからなのだが、最初にその疑問を感じた時を鮮明に覚えている。
それは、小学生時代、割と重い病気にかかって入院していた頃の父の何気ない言葉を聞いたときだった。
普通の小学生の生活が普通じゃなくなった日
小学6年の初夏の頃、学校の健康診断で検尿検査で引っかかった。血尿が検出され、かかりつけ医にいったがあまり状況が好転しないことから、大きな病院に診察に行ったところ、足のむくみを見ていた担当医が言ったのは、「今すぐ入院しましょう」だった。
そのまま家にも帰らずに入院。何の心構えもないまま突如ベッドで暮らすことになった。
慢性腎炎、腎臓病だった。原因などはよくわかっていない。今は治療法が変わっているかもしれないが、当時90年代初めの頃の治療法は、絶対安静。病状の進行が進まないよう、極力活動を制限するというものだった。
そこから、長期の入院生活が始まった。親はその時、一生病院で生活することになるのを覚悟してくれと言われたらしい。結果的には、幸いにも今こうしていわゆる普通の生活を送っている。しかし、私はこれは「普通ではないことを知っている」。そして、普通と言ってしまってはおかしいし、ある人にとってはとても失礼な表現だと思っている。なぜなら、私が過ごした、一見特殊に見えるであろう入院生活は、いたって普通な人間の営みの一部だってことを知っているからだ。
入院病棟と養護学校で出会った子供達
終わりの見えない入院生活が始まり、当然学校に行けなくなった私は、小児科の入院病棟に隣接されている養護学校に通うことになった。
つまり転校だ。
物心ついたころから一緒に遊んできた友達とも何も交わさず、先生にも会えず、学校を離れることになった。
正直、実感がわかない。よくわからないけど、時間がかかっても治れば元の生活に戻れるだろうと、わりと楽観していた。一方で、こういう運命なんだなと変に冷静になってる自分がいた。悲しいという気持ちは、あまりわかなかった気がする。でもなんか想像できない、よくわからない状況になったという、ふわっとした感覚だった。
転校はしたが、戻ってくることを願って、当時の元の学校のクラス担任は、クラスの友達に私宛の手紙を定期的に書いて、全員分を親に持たせてくれた。楽観していたとはいえ、もう戻れないという不安に潰されなかったのは、忘れられていないと確かめさせてくれた先生や友達のおかげだと思い、いまでも感謝しきれない。
入院病棟には、自分と同じ腎臓病にかかった子供達がいた。小さい子は小学2年生。小学5,6年生である自分と同年代が意外と多かった。中学生や高校生のお兄さんもいた。
腎臓病というのは痛いとか苦しいとかがあるものではない。ただ、腎機能は血液中の老廃物をろ過し、尿として排出するもので、これが衰えると、体に必要なたんぱく質が排出されたり、塩分を適切に排出できなくなり、水分が溜まったむくみや、だるさが伴う。細菌やウィルスが喉に感染した際、免疫に関するたんぱく質が、腎臓の組織に付着して傷つけることで尿に血液が混ざったりする。
そのため、走ったりする運動は禁止。食事は塩分を極端に抑え、極力風邪をひかないように気を付けることが治療の必須事項だった。
病状が進んだ子もおり、薬による副作用で体がぶくぶくに太ってしまったり、長期間のベッド生活で筋肉が衰え、自力で起き上がれない人もいた。ただ、見た目がどうであろうと、皆「普通」の子供だった。優しいお兄さんだった。
そういう人たちに交じって、私は養護学校に通い、5,6年生の子供達と、少人数クラスの授業を受けるようになった。人数が少ないから、2学年で1クラスなのだ。授業自体は通常の学校と同じ内容を受けることができたと思う。(よく覚えていないが、2学年をどうやって授業していたんだっけ?)
たまに、新しいメンバーが突如加わる。病気が予定通りに来るわけじゃないんだから当たり前だ。同じ病気の子もいれば、顔発疹ができる病気の子、歩いてるときに突然眠って倒れてしまう病気の子など、色んな病気と付き合って生きている同年代の子供達とともに暮らしていた。
喧嘩もしたりしたけど、昼夜ともに過ごす仲間でもあり、5,6年生が比較的多かったこともあって(2年生の子なんて同年代がいなかった)、それほど寂しいと感じたことはなかった。
1か月、2か月・・・半年たつ頃には、自分にとって、この世界が「普通」になっていた。
父が言った「かわいそう」が、どうしても受け入れられない
入院生活が自分の当たり前になった頃のこと。
親は、毎日のように様子を見に来てくれていた。家に帰れる、外泊できるのはひと月かふた月に一度だけ。家族と離れている時間の方が圧倒的に多かった。
ある日、いつものように見舞いにきてくれていた父が、同じ養護学校に通っている女の子を見て、言った。
「あんなに顔にぼつぼつができちゃって、かわいそうだな」
至極当然の感想だった。女の子の顔があんなになったら可哀想、誰もが思うだろう。病気が原因なのもわかっている、色々辛いこともあるだろう。
当然父としても、思いやったり気遣ったり、不憫に思ってのセリフだったに違いない。だから父を責めようとは全く思わない。
思わないのだが、即、心の中で叫びたくなったことがある。
「何言ってんだよ。あの子は全然可哀想な子なんかじゃないよ、普通の子だよ」
彼女は確かに顔の発疹がひどかった。でも、私は彼女とともに毎日を過ごしていて知っている。彼女は一つ上の中学生だったが、とても乙女チックで、その年ごろらしく、少しミステリアスな物語が好きで、私達弟妹分を集めては、不思議な話をさも真剣に話して、子供心の冒険心をくすぐる、楽しい話をしてくれる姉貴分だった。
根はとてもかわいらしい人なのだ。
本人が顔のことをどう感じているかはさすがに直接聞いたことはないが、私たちの前で隠そうとするでもなく、こっちも別に変に思うこともなく、ごく普通の友達として付き合っていたのだ。
俺達だって、病気で入院してるんだから、皆違うけど同じなのだ。
それを、その状況を知らない父が、いわゆる「普通の」生活をしている人が、ぱっと見た目で、可哀想だといった。
悪気はないだろうよ、悪気はないけど、悪気がないからこそ、そのセリフはおかしいし、残酷だ。
子供心にそう思った。
なぜ何も知らないくせに可哀想だと決めつける。
一体なんの優位性を感じて可哀想だと表現する。
可哀想じゃない貴方たちはなんだというのだ。
私は、父との間に、何か共有できない感覚の違いが自分の中に生まれていたことを知った。
父が、あっちの世界の人だ、と思った。
父だけではなく、母も妹も、元の学校の先生も友達も、みんなあっちの人だ。
そして、私自身が、今までこんなことも知らなかった、あっちの人だったんだと気づいた。
「人は、世の中のことを何も知らずに、自分の見えてる世界が普通だと思っているのだ。」
「ほとんどの人が普通で、たまに普通じゃない人がいると感じているのだ」
「私から見れば、その大勢の人の方が、こんな普通な状況があることを全く感じられていない、普通じゃない人に見えるのに」
「普通」が垣間見える世の中が辛い
色々割愛するが、親の努力のおかげで、私は完治しないものの、7か月で退院することを許された。当時異例の短さだった。その後、生活を制限しながらも徐々に他の人と同じ生活を送るようになり。20歳になるころには病気は完治したと診断された。なぜ治ったのか、本当に治ったのか、また再発するのか、それはわからない。
ただ、明らかに元に戻ったわけではないのは、私が、他の人と同じような生活以外の世の中があることを知ったという事だ。そこから、自分は周りとは違う、でも同じだ、でもやはり違うと、何度も人と違うことと同じことで悩んできた。
実に30代になってやっと、人と人はまず全く違うもので、人と同じであろうとすることに意味はなく、自分と違うことを敵視することも意味がないと考えるようになった。
この考えの根幹は、あの入院時の経験以来心に残っていたくすぶりであり、それがわかってからは、「○○するのが普通だろ」とかいうセリフを言う人が、どこかむなしく滑稽に見えてならない。自分の見えている世界が、他の人とは違うことに気づかず、あたかも周りも同じように見えている仲間だと思っている。
その仲間も、そいつが全く違うものを見ているにも関わらず、自分と同じものを見ていると思って、「それが普通だよな」と話が合っていると錯覚している。錯覚し合って、世の中に大勢を占める「普通」があると信じて、そこからあぶれまいと普通を目指そうとしている。
そして、「普通じゃない」と錯覚して見えた人を、敵視して攻撃するのだ。
何て不毛なことなのか。ないものを追い求め、ありもしない敵と敵対している。何がそうさせているのか。誰が「普通」が正しく目指すものだと教えたのか。
私は教育なんじゃないかと思っている。同類であることが成功の鍵だった時代は確かにあった。でも、私が子どもの頃、平成に入ったあたりから、日本社会は違う人間の見方を、教育すべきだったのではないか。そのずれのために、今私と同様何年も苦しんでいる人がいるのではないか。
今からでも、本当に必要だったことを学んでいくべきなんじゃないだろうか。伝えていくべきなんじゃないだろうか。
教育が私たちに教えたのだから、気づいていない人を責めることはできない。ただ、ちょっと考え方を変えれば、違いを怖れないようになり、自分は普通なんかじゃないし、隣の人も普通なんかじゃない。そう思えるようになれば、人を傷つけたり自分を傷つけることが無くなるのではないか。
一人ひとりが多様で多彩な一人で、自分もその異質で多彩な色の一つだと思えば、みんな同等の立場で、全く違う色合いの魅力を持つという事に気づけるのではないか。
そういう、違いに気づき、むしろ違いを活かせる生き方を身に着けていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
