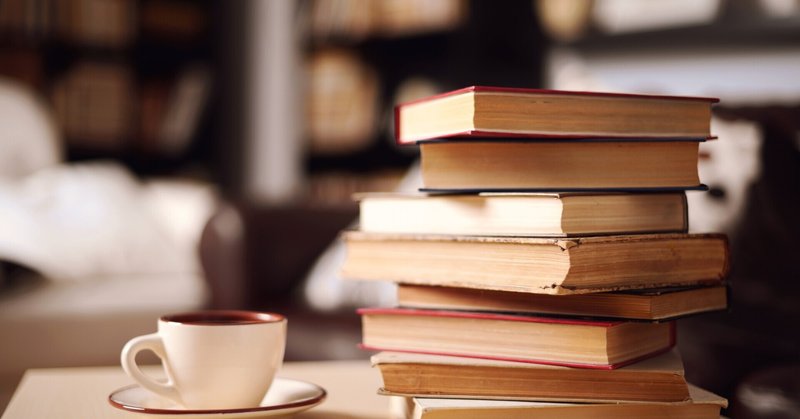
【書評】『新説の日本史 古代から 古代から近現代まで』
みなさんこんにちは。「定期的にnoteで文章を書くのだ!」と宣言しては長続きしないという生活を続けてはや2年近く。いったいなぜこうなのか?その理由は「何かのテーマについて内省して言語化するのが遅い!」というのに尽きる。
だったら本を読むたびにその内容をまとめて紹介すれば、内容も頭に定着するし、文章力も上がるし、記事も定期的に書ける。一石三鳥ではないか!と例のごとく単細胞的に思いついたので、まずはやってみようと思う。
本日の1冊は『最新研究 新説の日本史 古代から近現代まで』。歴史学という分野において日々様々な史料と格闘しながら研究をしている6人の若手・中堅の歴史学者が、それぞれの専門時代における重要な「最新学説」についてわかりやすく紹介している。著者の中には『観応の擾乱』で中世史ブームに拍車をかけた亀田俊和先生や、本格的な忍者研究でおなじみ高尾善希先生もいる。
ところでみなさんは「歴史学の新説」と聞いたら一体どのようなことを思い浮かべるだろうか?時折「歴史学を揺るがすような新しい史料が見つかった!」というようなニュースを聞くことも多い。
今年の頭にも「本能寺の変の時に明智光秀は本能寺から8キロ離れた鳥羽にいた」というような内容が記された新史料をきっかけに論争が起きたことをご存知の方もいるかもしれない。
過去にあった様々な出来事を復元しようというのが歴史学の営みと言える。だがこれは言うほど簡単なことではない。だって昨日の自分の行動でさえ正確に復元してくれと言われたら困るんじゃなかろうか?(少なくとも僕は全くできない。食べた飯すら復元不可能だ)。
しかも復元作業に必要な史料が豊富に揃っているとは限らない。過去に遡れば遡るほど史料の数は少なくなる(卑弥呼の時代に至っては日本に文字史料がないので中国の史料に依拠するほかない)し、客観的に歴史の姿を明らかにしようと思っても当事者全員が詳細な史料を書き残しているとも限らない。たいがい勝者が歴史を作りがちだし、敗者に対して歴史は冷たくなりがちだ。
ちなみに史料に基づかないで歴史を復元しようとすると、なんでもありの「トンデモ学説」となる。「源義経は大陸に渡ってチンギス・ハーンになった」「明智光秀は南光坊天海になった」「坂本龍馬はフリーメーソンだった」などなど。もはや伝説、神話の類だ。
昔師匠に大真面目な顔で「明治天皇は実は暗殺されていて、明治天皇とされているのは替え玉なんだ」と言われたことがある。史料という客観的な証拠を土台にしなければ言ったもの勝ちで、検証しようがない。なのでこれもトンデモ学説だ。当然そんなこと大真面目な師匠に言ってらどやされるので「ハハハ…」と軽く受け流してしまった。
そんな制約の中、歴史学者は残された史料を必死に解読・解釈しながら、史料に残されていない姿も想像・類推しながら、昔の世界の姿を再現していく。そして「新しい史料の発見」やそれに伴う「歴史解釈の変更」を絶えず行いながら、復元された姿をアップデートし続けるのが歴史学だ。
だが、歴史学者は常にそのアップデートをしていたとしても、学校でしか歴史に触れなかった大人にとっては「古い復元像」しか残っておらず、最新の学界の定説とのギャップが凄まじく大きくなることもよくある(実際歴史系の授業をするときに新説を混ぜながら話すと、保護者の方が子どもより驚くことも珍しくない)。
本書の中で触れられている新説を少しだけ紹介すると、
・応仁の乱の主な原因は将軍の後継者争いではなかった
・戦国大名は「上洛」を目指してはいなかった
・江戸時代の「士農工商」は身分ではない
・薩長同盟は軍事同盟ではなかった!?
・昭和天皇は戦後も政治・外交に影響力を持っていた
などなど、かつて中学・高校で習った日本史の内容と違うことにびっくりする人も多いのではないだろうかと思う。その一つをちょっと見てみよう。
例えば、一昔前のドラマや映画、小説では「戦国大名はことごとく京都へ上洛して天下統一に向けて号令しようとしていた」と語られることが多かったと思う(今は昔ほどではないにせよ、こうした説明の姿はよくいまだに耳にする)。
そして諸大名に先駆けて上洛を果たしたのが信長で、彼が天下統一に向かって歩みを進めていく、といった感じのストーリーが続く。信長を主人公にしたドラマなどでは、足利義昭を奉じて上洛を果たしたのに対し、越前の朝倉義景は義昭の上洛要請に応じず暗愚な様をさらした、みたいな描写もよくあった。

織田信長像(引用:wikipedia)
信長の偉業とセットになっている上洛だが、そもそも信長以前に上洛を果たした戦国大名は結構たくさんいる。三好長慶、斎藤義龍、六角義賢、有名どころでは上杉謙信も上洛経験がある。
何も信長が史上初ではないし、上洛は「天下人になって号令をかける!」といった大きな意味を持つことでもなく、もっと軽いハードルの低い行動だったと言える。逆に言えば「上洛して自分が国政に参加する!」と言う意識を持ったところが信長の特異なところ、と言い換えても良いかもしれない。
また信長と義景の対比にしても、この文脈に載せればまた違う評価が出てくるのではないだろうか?上洛して国政参画する意識を持った戦国大名が信長くらいしかいなかったのだから、義昭に要請に応じなかった義景が暗愚とこれで断じるのはあまりに酷だ。

朝倉義景像(引用:wikipedia)
また朝倉氏は、信長の上洛から遡ること約100年前の応仁の乱の時代には京都の政局に大きな影響を与えていた(時の当主・朝倉孝景が西軍から東軍に寝返ったことで乱は終結に近づいた)。決して中央政界について無知だったわけではない。
それに足利義昭を奉じて京都に入れば、現行政権である将軍・足利義栄とそれを支える三好氏を敵に回し、下手すれば応仁の乱のような戦乱に陥る可能性も高い。だからこそ義景はあえて上洛をしなかったのでは?という見解を、この本で戦国期のパートを担当している矢部健太郎先生は推測している。
このように最新の学説が1つ入るだけで、人物の評価も歴史事象の捉え方も大きく変わるのだ。もちろん新しい学説が常に定説になるとは限らない。様々な吟味の末に従来の定説がそのまま残ることもある。
でもこれほどダイナミックに歴史の見方を変えてくれる歴史学の新説を知らないで過ごすなんて勿体無い!!「歴史なんて久しく触れてない…」という大人の方にこそ読んで欲しい1冊である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
