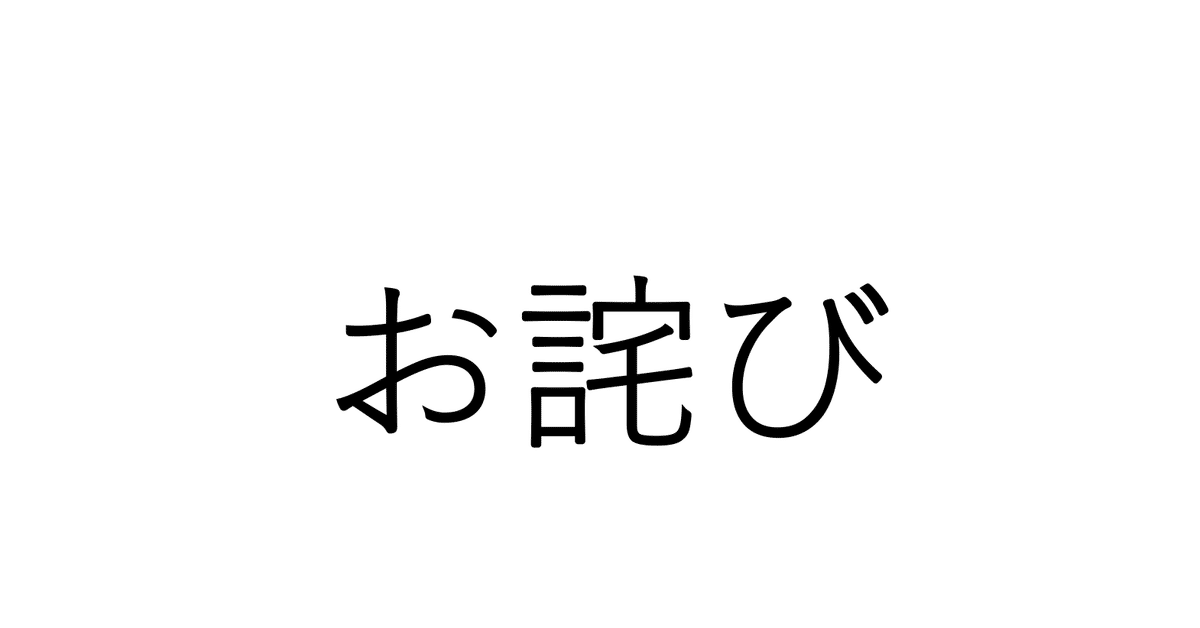
【お詫び】立憲民主党から1000万円もらっていた疑念のあるCLPに失望すると共に、出演者として反省しています
Choose Life Projectというテレビ、映画、ドキュメンタリーを制作している有志で始めた動画配信プロジェクトがある。代表の佐治洋さんは、TBSの報道番組を制作していたが、インターネット上に公共放送を作りたいと制作会社を退社した。
私は、佐治さんからTBSの番組で若者の投票率をあげるプロジェクトについて取材を受けたことがある。佐治さんは投票率をあげたいという思いの強い方だ。
CLPはクラファンで数千万円というお金を集め、マンスリーサポーターがおよそ2千人ほどいた。お金を特定のスポンサーからもらうのではなく、市民から集めることで中立性を担保しながらも、継続的なお金で持続可能な番組作りができる。NHKのディレクターで限界を感じ、社会問題解決型の番組を作りたいと時事YouTuberに転身した私にとっては、仲間であり、憧れるようなところもあった。
私は何度か番組に出演していた。そして、私のYouTubeに代表の佐治さんにでていただいたこともある。
だが、立憲民主党から代理店経由で1000万円もらっていた疑いがあり、よく出演していた小島慶子さん、津田大介さん、望月衣塑子さん、などが抗議声明をだした。
https://medium.com/@tsuda/7b7e65a79f2c?source=social.tw

もし、この抗議声明が本当であるならば、
あってはならないことだ。
まだどのような形でCLPが立憲民主党からお金をもらったかはたしかに分からない。そのお金の使い道の考えられる可能性は、立憲民主党内の広報物の制作or CLPの番組の制作などがある。どちらにしても問題があると私は考えており、私の元にも問い合わせがきているため、記事を書く。
メディアとして特定のところからお金をもらったら、それはわかるように表記する必要がある。わからないようにして番組をつくるのは、ステルスマーケティングだ。一時、芸能人がお金をもらいその商品を自分で買ったかのようにブログで絶賛したことはステマとして認知され、仕事を失ったこともあった。今回、CLPはこのステマが疑われる。
ちなみに、私自身はCLPには、最近出演していない。声がかからなくなったのもある。番組の色が当初私がイメージしていたよりも、左に傾いていったのが気になるところだった。是々非々を訴え、与野党問わず批判するときは批判する私のスタンスと違ったから声がかからなくなったのかもしれないが、これはあくまでも私の推測の域である。
私はステマにはかなりうるさく、SDGsの番組出演やタイアップに関しても、広告表記など細かく確認していることがおおく、特定の団体からのお金で、PR表記をつけないところとは当たり前だが丁重にお断りしている。
だが、この当たり前が当たり前でないことも、まだまだ残念ながら多い。雑誌やwebメディアなどは、仕事の依頼があった際に、私が勘づき、「これは@@からお金をもらいますよね?その場合、PR表記はつきますか?」と確認することもあり、いわば演者や事務所をだまそうとしているような媒体も、代理店もクライアントもいる。
騙されることは自業自得で、危機管理があまいと思い、注意深く確認してきたつもりだが、まさかCLPがそんなことをしてると思わず、きちんと確認してこなかった。
立憲民主党の代表選挙の公開討論会を主催している報道番組に対して、「立憲民主党からお金もらっていませんよね?」と、確認する必要があると思わなかった。
この点は、私の確認不足であり、私の出演によって番組をみてくださった方もいらっしゃると思います。そしてクラファンや支援をCLPにした人もいると思います。そのような方を裏切るようなことをしてしまい大変申し訳なく思います。
政治家や政党からお金をもらう際は、メディアとしては基本断るべきだと私は思うし、断らないのならそこのお金の流れを明確に記載すべきだ。CLPはただのメディアではなく、公共メディアをかかげていたのだ。お金をもらうのは悪いことではなく、お金をもらうことをわかるように記さないのが問題なのだ。政党のイベントや講演会の出演費や講師謝礼という形ならありだと思うが、CLPはメディアである。
完璧ではないが、多くのメディアの編集部がPR部門から独立していたり、既存のメディアは注意を払っている。メディア経営は本当に難しいが、スポンサー企業であっても批判できるように現場を守れないと、報道の価値がなくなる。
若者✖️政治参加を促す株式会社も、政治家からお金をもらう収益モデルでやっている団体がある。報道番組がそういう人たちを容易にキャスティングをしていることにも危機感を私は覚えている。知った上でも、その団体をだすなら、それはなぜ出すのか。そこじゃないと語れないことがあるのか、そのお金の流れを報道するときに説明しているのかなど疑念が残る。もちろん、いろんな考えがあり、政治家からお金をもらうビジネスにいきつくのは理解できなくはないが(私自身は絶対に選ばない)それをわかる形で明示しないのは倫理違反だと思う。ちなみにNHKではそのようなことがきちんと教育された。(一部政党からお金をもらっている団体が今回の衆院選でメディア出演しているのを見て残念に思ったが一応はそのような教育はされている。)
編集部が独立し、経営やお金にうとくなってしまいがちな現場の記者やディレクターはその団体の収益モデルなどに目をむけていないかもしれないが、そこに目をむけなければならないと思う。私も、数百回取材をうけているがそこを聞かれることって、ほぼない。
私自身本件で自戒をこめて、反省をしるすとともに、右も左も関係なく、視聴者からの信頼を損なうようなことはやめないと、この国の言論空間や強いては民主主義が衰退する。
1月1日の毎日新聞では、ロシアの政府系メディアがYahoo!ニュースの読者のコメントを改ざんし、日米の分断をあおっているのではないかという報道をした。今はまだ小さな影響しかないが、それが大きな影響がでる可能性を示唆した。
また私が現地に取材をしにいった2020年のアメリカ大統領選挙では、1つ前の2016年の選挙の際にケンブリッジアナリティカという代理店が、Facbeookからの情報で心理学者などをまじえ、有権者の投票行動を操作したということがおこった。
日本では、Dappiという17万人のフォロワーを誇るtwitterのアカウントが、野党議員の国会質疑を恣意的に編集しており、運営していたIT企業が自民党と取引していたことが分かった。
本案件はDappi問題を追求していた立憲民主党としても大問題であり、説明責任が求められる。CLPにも説明が求められるが、CLPに問題をおしつけるような形で終わってはならない。経緯説明とともに、再発防止策まで述べてもいたい。広告代理店にお願いしていたからではすまされない問題だ。
アメリカに比べて、まだ規模は大きくないように見えるものの、ネット空間を使い、世論操作が容易にしやすくなっている現状を注意深く見なければならない。
若者の政治参加をうながす団体は特定の政党に取り込まれやすい傾向にあるが、私の会社は、なんとしても、特定の政党に取り込まれることなく、若者を一番に考えていく。YouTubeたかまつななチャンネルでは、視聴者を裏切ることはしないようにします。そして見抜けなかった場合や間違った場合は、経緯説明や謝罪をします。
ちなみに、私はCLPからもらった報酬はおそらく数千円だと思う。ギャラがでなかったこともあるし、苦労されている姿を知ってギャラをお断りしたこともあるし、CLPのクラファンに支援もした。また本件については、佐治さん、CLPに抗議声明の真相を確かめる連絡もしているが、今現在はお返事をいただけていない。ちなみに、6日、CLPは経緯説明するとtwitterでは、のべていた。
本件が仮にステマではなく、1000万円のお金をCLPの製作費ではなく、立憲民主党内の動画制作に使っていたとしても、私はCLPの理念から見て、倫理的にどうかと思う。特定の政党と癒着しながら、番組を作ることはよほど困難であるからだ。実際、CLPは左派系メディアとして捉えられているし、野党に甘く与党に厳しいと見られても致し方ない。過去の出演者をみても明白であろう。番組制作が脅かされないように、PR案件をうける会社を独立した部門にしたり、子会社にしたり最大限の配慮が必要だと思うからだ。
私の会社も代理店経由で立憲民主党の広報の相談をもちかけられたことがあるが、そことはお仕事をしていない。特定の政党だけからお金をもらうことや、その政党のPRなどをすることなどは、私のやりたいことではないからだ。
近年は新聞社であっても、読者層にあわせた好みの記事を書いたり、結論ありきの取材をしていることが目立つが、それは自分たち自身で、自分たちの業界の首をしめることだと思う。
お金には色がある。ジャーナリズムは、お金になりなくい。右も左も両方批判するときは批判し、いい時は評価する。両方の支持者から叩かれる。時間がかかるわりに、そこが見えにくく、寄付なども集まりにくい。正直苦しい。だからこそ、お金の色や透明性には細心の注意をはらい、食いしばる必要がある。
ジャーナリストが独立するとお金がなく大変だ。だから、禁断の果実に手をだしたくなる気持ちはいかにも分かる。
私たちの会社はだから、日本政策金融公庫や地方銀行からお金をかりている。若手起業家を取材したときに、借金は悪いことだとおもい、色があるお金に手をだしたり、悪いVCに苦しめられる人を私はたくさん見てきた。起業家教育や金融教育がかけている結果だと思う。銀行からお金をかりることは悪いことというイメージがあるかもしれないが、銀行は使い道をうるさく指図しない。スポンサーもいなければ、お金を稼ぐように指南するVCもいない。自分たちで返せる見込みでかり、理念にそって経営し、返していくことができる。コロナで返済期間にも猶予があり、金利もすごく安い。私の講演会の収益をお金になりにくい報道や番組制作に赤字でもあてたりしている。
しんどいですが、耐えます。色があるお金には手を出さない。出すとしても(スポンサーがつくなど)、きちんと説明責任を果たす。それをお約束します。
この度は、本当に申し訳ございませんでした。以後気をつけます。
2021年1月5日 たかまつなな
※一部、誤字があったので、公開後訂正しました。
基本的にすべての記事は無料でご覧いただけます。もし有益だと思っていただけたらサポートいただけますと幸いです。「笑いで世直し」するための活動費(イベント代、取材費等)として大切に使わせていただきます。
